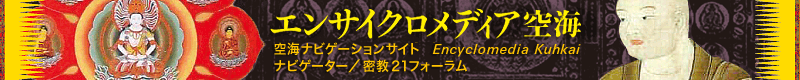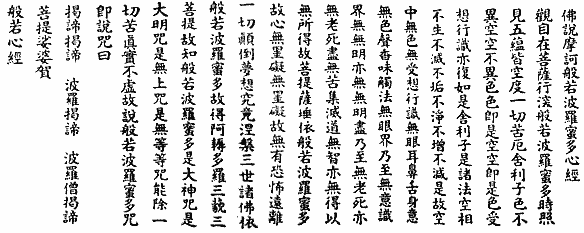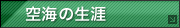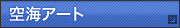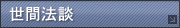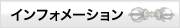★真実は二つある。般若心経による「色」と「空」
「般若心経」は、仏の真実の智慧が凝縮された功徳のあるありがたいお経である。経典に「真実であり虚ならず。故に般若波羅密多を説く」(真実不虚、故説般若波羅密多)とあるから、素直に受け入れればそういうことになる。問題は、この真実がどこから現れてくるかということである。
もし科学でこの世の全てを解明できるというのであれば、人間は最終的に神の認識をもち得るという前提に立つことになる。逆に人間の無明を認めるならば、科学の真実とは無明の真実かもしれないという不確実性がつきまとうことになる。
不思議なことに、万能の神と人間との絶対的な断絶を前提とした西洋から科学万能主義が生まれ、無明を自覚した東洋において人間は仏になれるという仏法が生まれた。とりわけ現世において生身のまま成仏できると断言した空海は、西洋合理主義との対極にあるかのようである。ところが、一方で空海ほど合理的な発想をした僧も珍しいのである。
例えば、満濃池で空海が行った築堤工法は水圧が計算されている。堤防の内側へ湾曲したアーチ型の堤を築いて水圧を分散したり、池内に溜まりすぎた余水のはけ口を設けたり、これまでの日本はない水の理にかなった新しい工法を用いている。綜芸種智院の発想も近代的である。入唐したとき大量の各種漢方薬を請来したことが『高野雑筆集』に記されてあるので、医学の知識もあったらしい。空海は筆の作り方まで唐で学んでいたことは、嵯峨天皇に贈った狸の毛の筆の話にも見られる通りである。その他、石油石炭の使用方法を民衆に伝えたとか、温泉の発見とか、空海にまつわる生活技術の伝承は限りがない。しかも、それらは当時一流のものばかりである。
護摩壇を築いて工事の安全と早期完成を祈願する神秘主義者空海と、水圧を計算する合理主義者空海に自己矛盾はなかったのだろうか。私は空海を知れば知るほど全くなかったと思うようになった。矛盾とは、二つの真実を一つの真実に整合させようとするときに生じるジレンマのことである。そのとき、人はある問題について「真実は一つでなければならない」と考えている。我々現代人が「最終的に真実は一つである」とどこかで信じているのは、哲学や近代科学が陥った罠に我々もまた呪縛されてきたからではないだろうか。
空海はどうも「真実は二つある」と覚っていたようである。二つの真実とは何か。それは「仏の真実」と「人間の真実」のことである。護摩を焚くときの空海は「仏の真実(仏法)」に、水圧を計算する空海は「人間の真実(科学)」に従っていたのである。神秘主義者空海と合理主義者空海が矛盾しないのは空海の中に「二つの真実」があったからである。
空海の築いた満濃池の堤は、江戸時代(寛永三年)のカサ上工事のためにもう見ることはできない。この世の全ては移り変わり、私たちは何一つ永久に留めることのできるものを持たない。万物は常に流転し一瞬たりとも同じ状態にはない。仏教ではこの真理を「諸行無常」という。生老病死は刻々と人間を襲う無常である。釈尊のいう「苦」とは、因と縁に支配されたままならぬ人間界の実相のことである。この世界を此岸「有為の世界」ともいう。
だが、もし諸行無常を生じる原因(因縁)が陽炎のようなものであれば、存在や現象は仮象にすぎない。自己も陽炎であり、本来不変なる自己などという本質はどこにも存在しないはずである。仏教はこの真実を「諸法無我」と呼ぶ。「無為の世界」ともいう。自己という本質が無我であれば執着心も幻にすぎない。執着心が幻であれば煩悩もない。煩悩が消えれば「苦」から救われる。このように「諸行無常」と「諸法無我」は仏教の根本とされている。
ゆえに「苦」から解放されるには、「諸法無我」を自覚することである。彼岸に渡ることが仏教の目的であるから、「諸法無我」とは彼岸の理法であり「仏の真実」だということになる。その実践の一つが「般若心経」という経典の存在理由なのである。そして、この経典の中心が「空」であるならば、「空」とは「仏の真実」だということになる。
さて、「般若心経」ではこの真理を簡潔に「色即是空」(色即ち是これ空なり)と言っている。「色」とは我々が日常的感覚で認知できるところの現象世界(有為の世界)の全てを表す。自己も自然も物質も意識も現象も因も縁も全て「色」である。いわゆる理屈でおおむね説明できる因果論の世界のことを想定すればよい。
次に「空」とは何か。これが問題である。「般若心経」の冒頭主文「観自在菩は深般若波羅密多を行ずるとき、五蘊(ごうん)は皆空なりと照見されて、一切の苦厄を度したまう」とある。極めて簡単にいえば観自在菩薩(お釈迦さん自身のことでもある)は深く瞑想されていたとき、人間の肉体も精神も(五蘊)全て空なりという仏の真理を悟られて、この世の一切の苦から解脱されたということである。
問題だと言ったのは、お釈迦さんが照見して解脱された「空」が凡人にはよくわからないことである。かくいう私にもよくわからない。だから、「仏の真実」だと言ったのである。何故なら、「仏の真実」は人間の頭ではとうてい測り知ることのできない深い真理だと思うからである。私は人間に分別できないものはこの世には必ずあり、そのことを謙虚に受け止める感性が人間や科学を間違いなく導く知恵の源泉だと思っている。だから、般若心経を素直に唱えても、「空の内容」まで理解しようとしない妻は理解していると言ったのである。
ところが、専門家が細かく解説することによって、実はある意味でこれほどわかりやすい仏教がかえって意味不明になってきたのではないかと思う。「色即是空」について、例えば専門家はこのような説明をする。
「この世においては、物質的現象には実体がないのであり、実体がないからこそ、物質的現象である。実体がないといっても、それは物質的現象を離れていない。また、物質的現象は、実体がないことを離れて物質的現象であるのではない」
このような極めて難解な説明が多い。難解ではあるが、物質的現象(色)とは実体がない(空)と言っていることはわかるだろう。ここで指摘しておきたい点は、「空」を「実体がない」という「意味として解釈」している点である。あとはどうでもよいことである。
次に、このような解釈にもとづく別な日本の代表的な仏教学者の文章を紹介しよう。
「仏教は一方無我説を主張する。無我とは、我々が常識的に自己と考えているもの(我)は何ら実体のあるものではない(空)ということであった。我がないのにあるかのように思い、執着するところに苦の原因がある(集諦)ともいわれていた」
この学者も述べるように、仏教ではどうやら「空」とは「無い」という意味らしい。なるほど「空」とは何も無い状態を表す「カラ」とも読む。だから、現存する「色」(我・物体)は本当は「空」であり実在しないというのである。だが、もし「自己の実体はない」のだと本当にお釈迦さんが考えたというのなら、お釈迦さんはただ発狂していただけである。では、常識的に存在する坊さんは、ありゃ幽霊か? 私も幽霊だったのか?
「自分は実体としてここに存在する」と断言できなければ仏教ではないと私は考えている。お釈迦さんもそう思っていたはずである。自己が存在しないところに「苦」が生じるわけはなく、あるとすれば、その自己とは死体である。それは小学生にでもわかる「人間の真実」である。
★わけのわからぬ仏教学者の「般若心経」
次に、お釈迦さんは「空即是色」(空即ち是色なり)と言い換える。専門家によると「実在しないということは実在する」ということになるらしい。最初の専門家の「実体がないからこそ物質的現象である」というのはこのことである。何のことだかサッパリわからぬ。だから、「無我」だったはずの「我」が再び存在を主張し始めるのである。「無我」を否定した「有我」である。したがって、先ほどの学者は続けて「この無我説と、仏教が一方で説く主体性の強調とは、理論的に明らかに矛盾である」と書いている。
この仏教学者が正しければ仏教は矛盾に陥っていることになる。どうしてこのようになるのだろうか。それは「真実は一つでなければならない」と思い込んでいるからである。「仏の真実」は人間の知恵では測り知ることができないがゆえに「仏の真実」なのである。「人間の真実」で説明できれば、それは「科学の真実」というものである。
「仏の真実」と「人間の真実」とは別であるという当たり前の感覚があれば、何も矛盾するところはない。彼らの間違いは「人間の真実」で整合させようとするから自分でもわからない説明になるのである。最初にボタンを掛け違えると、あとは限りなく観念論の世界で格闘するしかない。その結果、先ほどの学者の頭の中はこのような苦しみを生じる。
「ところで、我がないのにあるかのように思い、執着すると言ったが、では、その思い、執着する者は何か、誰なのか。ほかでもない自らである。悟りに向けて実践する主体と同じ自己である。無我説の立場からいうと、私が思うという思い、私が悟ったという思いも、どちらも間違いであろう。悟りのあかつきには、そのような思いは捨てなければならないし、捨てられるであろう。しかし、そこに、捨てられた自己が残り、悟った仏がいる。あるいは、悟りとは自己が法と一体になること、その法そのものになりきることだといっても、そこに、法と一体になった自己(それを仏、如来という)が残る。この問題は、言葉を通じてどんなに追求していっても、結局は解決がつかないだろう」
一般の人がこのような論述についていけるだろうか。少なくとも私にとっては全くリアリティーのない空論でしかない。仏教の解説書にはこのような難解極まりないものが少なくない。結局、この無我説(空)を説く彼の論述は「これは仏教がその教理体系を理論の平面上で矛盾なく説こうとしたときに生じた最大の難問であった」という袋小路に入っているのである。
★瀬戸内寂聴さんは仏教を語っているのか?
核心部分に"最大の難問"を抱えたような「仏教」をお釈迦さんの教えだと思っている人の法話を聞くと、聞いている方がわけがわからなくなる。今度は極めて平易な言葉で「空」の講義を聴いてみよう。現在日本中で最も人気がある天台寺の瀬戸内寂聴さんの「般若心経」の講義である。『寂聴・般若心経』より「空」について語った部分を抜粋してみる。
「物というのはあったって、それを見る者がいなければ、ないと同じ。物があっても、それを認める心がなければ、ないと同じじゃないか。物も心もないところには何の悩みもない。すべては空だということ。これは、仏教で見つけた、非常にユニークで素晴らしい認識だと思います」
「要するに物体があっても、現象があっても、それを感じる心がなければ、ないのと同じだということです」
「ものがあっても、それはないのと同じで、ないということも、あると同じだ。それを繰り返しています。そういうふうに反対側、裏側から繰り返し言うところが仏教の非常にうまいところだと思います」
「ない、ない、ないづくし。すべてがない。それが空の姿だと(お釈迦さんは)言っているんです」
「これで空相ということが、だいたいわかったでしょう。空というのは無に通じます。空と無は同じだと思ってもいいですね」(・・・だいたいわかるどころかチンプンカンプンである)
彼女がここで「空は無と同じだ」と語っているのは、先ほどの学者と同様である。つまり、仏教の専門家が「空」を「無」だと解釈していることがここでもわかる。それで寂聴さんは「色即是空」を心の持ち方や、思い込みしだいで「現実はないのと同じだ」と言い、これで悩みは解決すると言うのである。
馬鹿馬鹿しくて話にもならない。そんな簡単なことで苦悩が解消するようなものを、お釈迦さんが生涯賭けて悟った非常にユニークで素晴らしい認識だと言うのである。本当は甘いのだが、酸っぱいと思うことにしてあきらめたのはイソップ物語のキツネぐらいなものである。それを自己欺瞞と言う。お釈迦さんは、人々に自分を偽って生きなさいなどとは一言も教えていない。
「あると思っている私は錯覚であり、私というものは本来どこにも実在しないのである」という屁理屈が一般に素直に理解できるはずがない。私に言わせると私は明らかに「ここに実在している」のである。この瞬間は明らかに自分も彼女もこの世に存在しているからこそ、私は失恋に悩むのである。それがこの世の実相であり人間界の真実である。美しい彼女もいずれしわくちゃバアサンになることは誰でも知っている。時が経てば人はみなこの世から消えて行くこともわかっている。
それは「空」というものではなく、ただの諸行無常である。諸行無常という人間界の真実で執着心を捨てられるのであれば「仏の真実」は必要ない。悩み事は虚無主義でこと足りる。諸法無我という必要はない。「仏教はとはあきらめの心」だとはっきり言えばどうだ。
「見て見ぬふり」や「思い込み」や、単なる「時間論」で現実を忘れさせるのは、仏教ではなくその場しのぎの慰めというものである。バーのママにでもグチって酒でも飲めばおおかた解消することだ。お釈迦さんは昨今ブームの癒し屋セラピストではない。
★「般若心経」は「否定の論理」か? 西田哲学への疑問
このように「色即是空」を現実否定だと考えた坊さんは、「空即是色」と逆転したときに再びとまどうのである。「ないというのも、あると同じだ」(???)と言うしかない。だから、「空即是色」で「無」が「有」に、陽炎が実体になったとき、学者は「色即是空」をここで再度否定していると言うのである。つまり、否定の否定である。否定の否定は肯定であるから、やっぱり現実を肯定しているのだと訳のわからぬことを言う。それなら最初から否定などしなければよい。
彼らの説明によれば、現世を否定すると全てが空しくなり、努力して生きるのも馬鹿々々しくなるので、否定をさらに否定して虚無主義から人々を救い上げたのだなどと言う。お前は癌であと三ヶ月の命だと宣告しておいて、実は嘘だよ。オマエサンは健康体だよ。どうだ命のありがたさがわかったか。これが仏教だと言われているようなものである。ならば、仏教はほとんど心の詐術である。
こういう屁理屈をこねている本人も、おそらく首を傾げながら言っているにちがいない。寂聴さんも作家なら自分の感性を信じればよさそうなものだが、得度したとき天台宗からそのように学んだのかもしれぬ。あるいは日本の哲学界の権威が言うことなのだから正しいとでも思ったのかもしれぬ。
『般若心経の真義』の著者・重松昭春氏は、「色即是空・空即是色」について、これを二重否定の論理であるとした哲学界の誤解を見抜いている。その誤解を「即非の論理」という。「即非の論理」とは、「Aは即ち非AでありこれこそAである」という論法である。「自己は即ち非自己でありこれこそ自己なり」ということである。これは「即非の弁証法」という西田(幾多郎)哲学から考えられたものである。わかりやすくいうと「自我に死んで真我に生きよ」ということである。鈴木禅学流にいえば「死んで生きるが禅の道」なのである。
「色即是空と、自分の生き方を一つひとつ否定していって、何にもなくなってしまった極点でくるりと引っくり返って、思いもかけなかった人生が展開してくる」などと仏教学者は言うが(例えば『般若心経を読む』紀野一義氏)。ひっくり返らなかった場合はどうなる? 保証はどこにもあるまい。ひっくり返らなかった哲学青年の行き着く先は真っ逆さまの華厳の滝だった。「人生不可解なり」と絶望した藤村操にしろ、「生まれてきてすみません」と言い残して自殺した太宰治にしろ、自分の生き方を否定した結果、ひっくり返りそこなって自死を招いた。
★「般若心経」は「相互肯定の理法」
自我否定ののち自己肯定が生まれるというのは必ずしも間違いではないが、これと仏の教えとは別であると私は思っている。仏の教えとは西田流にいえば「即非」ではなく「即是」の理法である。「Aは即ちAでありこれこそAである」という論法である。
お釈迦さん自身がそう言っているのだから間違いない。「色即ち空であり」「空即ち色である」と言っている。「色は空に異ならず」(色不異空)「空は色に異ならず」(空不異色)とも言っている。これは日本語のわかる人なら誰が読んでも同一の論理であり「相互肯定の理」である。
もし「色」即ち「無」であるなら、お釈迦さんは当然「色即是無」と言われたはずである。人がせっかく「空」と言ったものを、勝手に「無」だの「カラッポ」だの「否定の否定」だのと決めつけることはお釈迦さんに対して失礼である。これは仏教否定ともいえる恐るべき誤謬ではないか。お釈迦さんはもとより「即非の弁証法」や「絶対矛盾的自己同一」などと訳のわからぬ弁証法など語ってはいない。ただただ「仏の真実」を説かれているだけである。
現世は一瞬一瞬は常に移り変わり、子どもはみるみる成長していき、親は刻々と老化していく。恒久不変な自己など存在しないことぐらい言われなくともわかっている。とはいえ、諸行無常の移りゆく時の流れのままに、少なくとも人間は七、八十年は実在しているのである。だから「苦」が生じるのである。そして「空」を悟られた瞬間お釈迦さんが解脱されたのであれば、「空」とは「仏の真実」であろうことぐらい素人の私にでも理解できることである。
すなわち、「色」は「空」とイコールであるという意味である。「空」とは「色」(人間や万物)を生み出し包摂している根源的世界のことであろう。ちょうど子宮の中の胎児と母親のような関係である。胎児は母親自身でもある。だから、般若心経では「色即ち是れ空なり」と説く。別言すれば「人間の世界」は「仏の世界」の中にあるということである。「有為の世界」は「無為の世界」とつながっているということである。
しかし、胎児であるわれわれ人間が認識できる世界は、あくまで「人間界の真実」までである。なぜなら、母体は胎児にとって認識の次元を超えているからである。次に、同じ真実を「空即ち是れ色なり」と説く。別言すれば「仏の真実」は即ち「人間界の真実」を包み込んでいるということである。一体なのである。否定の論理どころかまさに「相互肯定の理法」なのである。
私は素人であるから間違っているのかもしれないが、そのぶん学識に惑わされることのない内なるリアリティーで考えることができる。寂聴さんも西田哲学もおそらく仏教学的には正しいのであろう。何故なら天台宗の最澄がそのように学んでいるからだ。最澄のお師匠さんは唐の天台大師である。天台智顗は、この問題を「三諦」(空諦・仮諦・中諦)から説明している。ちょっと専門的になるので紀野博士の言葉でごく簡単に説明する。
三諦の第一である「空諦」とは「この世のことはすべてがあてにならない。雲をつかむように空しいものである。これが人生の大前提である」大体こういう意味である。諸行無常といえばすむことであるが、これを「色即是空」ととらえるのである。すでにこの段階で色(存在)は幻(空)だとされている。
第二の「仮諦」は「しかしこの世の現象や自分の存在は否定できないのだから、一応仮に在ると認めよう」というのが「仮諦」である。「仮に在る」という認識が私には納得がいかぬが、紀野博士はこの部分を「色不異空」「空不異色」であると解説している。
第三の「中諦」とは第一と第二の重なった世界であるという。これを博士は「あてにならないからこそ、そして人の命はまことにはかないものであるからこそ、今生きていることがたとえようもなく素晴らしいと感じるのではないか。そのとき空しかった空は少しも空しいものではなく、仏の命に抱かれた豊かな世界となる。これが真実であり空即是色というのである」と解説している。(???)
つまり、ここでくるりとひっくり返るそうである。偉い坊さんはひっくり返るのだろうが、私のような凡人は逆さまになったままである。これは一大事である。何とかしなければならない。で、考えるのであるが、申し訳ないがこれは観念の遊びではないか。それは「空」を「空しい」と解釈しているからではないか。まるで正、反、合の弁証法のようである。だから「即非の弁証法」が考案されたのではないか。これは哲学である。神仏は一体どこに存在するのか!
「この世は空しく虚無である」と言ったのはニーチェである。彼はこの認識を受動的ニヒリズムと言った。次にその虚無を克服する積極的な力を能動的ニヒリズムと言った。そこから運命愛と超人の思想が生まれた。しかし、ニーチェは神を殺して発狂した。だが、お釈迦さんは涅槃寂静に入られた。ならば、釈迦は哲学をやったのではなく、神仏と出会ったのであろうと素直に想像すべきである。お釈迦さんは観念の三段論法など語ってはいない。まさに「仏の真実」を語ったのである。
逆さまになったままの私はとにかく起き上がらなければならない。そのためには自己の内なる知恵に聴くしかない。さて、空海には「二つの真実があった」と語ったが、「空」はあくまで「仏の真実」であり、「色」は「人間の真実」である。もともと次元が異なるものである。次元の異なる真理を低次元の人間の理屈で整合しようとするから、あの京都学派のような苦しい理屈になるのだろう。次元の異なる世界は言葉や思考で理解しようとせず、素直に感じとればよいことである。
素直に感じ取れば、私にとって「空」は「意味論」ではなく、「実体論」となってしまう。つまり、根本的なところで既成仏教と決定的な相違をもって立ち上がるのである。これは傲慢ではなく、自らの知恵に従えと教えられた釈尊と空海に、すなわち仏法に従ったまでのことである。
★「色」と「空」は実在している
例えば、もし一次元の世界(点と線だけの世界)に生物がいれば、二次元(平面だけの世界)に住む生物がそばにいても絶対に見えないだろう。もし横から直線上に現れたり、横にそれたりすれば、見えない世界から突然現れたり消えたりしたとしか思えないだろう。だが、二次元の世界に住む生き物にとっては平面だけが真実である。高さをもつ三次元の世界の生き物は知覚できない。上下に移動するものは突然現れたり消えたりするはずである。
これは、真実は次元の数ほどあるという単純な例である。我々は四次元の世界までは認識できるが、経典が語る「仏の世界」はいわばN次元である。人間界のでつじつまを合わそうとすること自体、すでに仏を知らぬ証拠だともいえるのである。
直線は平面に包括され、平面は立体に包括されているように、「色」の真実は「空」というN次元に包括されてはいるが「空」の真実の一部でもある。だから「色即是空」なのであろう。また、「空」は「色」という下位次元を構成する全体ではあるが、「空」も「色」によって構成されているともいえる。だから「空」から見れば「空即是色」となる。これは「空」から見た真実である。「色即是空」も「空即是色」も次元を変えた相互肯定の論理になっており、否定の否定などという論理が出てきようもないのである。
おそらくこれを否定の論理にしたのは、先ほども述べたように「空」を「無、カラッポ」と解釈したためであろう。有為の世界をカラッポと観じれば、どうしても現実否定の論理しか導き出せないからである。これは、「空は空として実在している」ということを読み落としているからではないだろうか。「色」という人間の世界の外に、(あるいは内に)「空」という「仏の真実」が実在していることをお釈迦さんは実感されたのである。そのリアティーと一体化されたからこそ解脱されたのだと思う。
「空」という「仏の実在世界」を信じなければ、そもそも仏教が成り立つまい。「空は無と同じだ」と言う瀬戸内寂聴さんや、否定の論理を唱える仏教学者は、いったい仏の実在を否定することが仏教だと主張したいのだろうか。だから、「仏教がその教理体系を矛盾なく説こうとしたときに生じた最大の難問になる」という自家憧着に陥ってしまうのではないか。
私は少しも難問だとは思わないが、お釈迦さんが弟子の舎利子にあまりにも「無」とか「不」とか否定的な言葉を語られたので、仏教学者は「現実」(色)が本当に「無」(空)だと思ったのかもしれない。しかし、これは驚くべき国語力不足であり、恐るべき仏教の誤解である。
手元に般若心経があれば確認してもらいたい。お釈迦さんの説法はこのようにして始まっている。
「舎利子よ、色は空に異ならず、空は色に異ならず。色即ちこれ空、空即ちこれ色である。私たちの目に映る世界で感じ、思ったこと、行い、知り得たと思うことも亦すべてかくの如し」
(舎利子、色不異空、空不異色、色即是空、空即是色、受想行識、亦復如是)
多くの解説書はこの部分を、「常に移り変わる現実には実体がない。空なのだ。それが私たちの生きる世界の本質である」と説明している。これが誤解のもとである。次にお釈迦さんは「この諸法の空相は不生にして不滅であり、不垢にして不浄、不増にして不減なり」と教える。
(是諸法空相、不生不滅、不垢不浄、不増不減)
続いて「無」のオンパレードである。
「是故空中、無色無受想行識、無眼耳鼻舌意、無色声香味触法、無眼界乃至無意識界、無無明亦無無明尽、乃至無老死亦無老死尽、無苦集滅道、無智亦無得」と"ないないづくし"が始まる。
口語訳すると、
「この故に空の中には、色もなく、受、想、行、識もなく、色、声、香、味、触、法もなく、眼界もなく、乃至意識界もなく、無明もなく、亦無明の尽きることもなく、乃至老死もなく、老死の尽きることもなし。苦、集、滅、道もなく、智もなく、また得もなし」となる。ここまでが「空」のレクチャーで、あとは「般若心経」の功徳と実践方法を語っている。さて一体どこに現実否定があるというのだろうか。
先ほど私は専門家とは全く正反対に「相互肯定の理法」だと語ったが、お経にそのように書かれているのだから事実である。ここで注意すべきは"ないないづくし"を語る前に、あらかじめちゃんと「是故空中」(この故に空の中には)と前置きしていることである。この故に現実(色)の中には、すなわち「是故色中」とはどこにも書かれていない。
「この故に」というのは、先の「生ぜす、滅せず、垢がつかず、浄くもなく、増えもせず、減りもしない」ということを指しているが、そこでも冒頭わざわざ「是諸法空相」(この諸法の空相は)とハッキリと断っている。「空相は」とは「空の実相は」という意味である。あくまで「色の実相」ではない。
だから、お釈迦さんの「ないないづくし」は「仏の世界の実相」を語っているのであり、私たちの「現実の実相」を語っているのではないことぐらいまともな国語力があればわかりそうなものである。実在する私が無いなどとアホなことをお釈迦さんが言うわけがあるまい。なぜ、こうも強調するかというと、ボタンの掛け違いは仏教を根底から否定することになるからである。
例えば「空」を「無」ととらえる仏教解説では、「最終的に空の究極は空そのものも消えるのである。結局残ったものは現実だけである」などと、ペテンにかけたようなことを言い出すからである。無常も四苦八苦も苦集滅道(四諦)も八正道も、即ち仏教そのものが消えてしまうのは、解脱した者にとってそれらの方便は不要であるから正しいとしても、「空も無い」と言ってしまえば、救われる世界がないということになる。この理屈に合わぬ物言いが人を惑わすのである。「空という概念すら消える空の世界(仏の世界)が実在する」と確信をもって明言しなければ仏教になるまい。
ところで、インド人の最大の発見はゼロの発見だといわれる。実数はゼロから無数に現れ、突然ゼロに戻ることもある。ちょうど低次元の世界の生物には、高次元の生物が突然出現したり消滅したりして見えるのと似ている。さて、ゼロ(零)は「無」であろうか。ゼロこそが無限大を生じさせる最も基層にある豊穣な世界だとインド人が考えたとするなら、「空」とはそれに近い概念ではなかろうか。
物理学的な例で考えれば「空」は空間に、「色」は物質に置き換えられる。固体を加熱すると溶けて液体となり、沸点を超えると気体になる。さらに加熱すると、原子は壊れて電子と原子核になる。最後は原子核よりも小さい素粒子が溶けてエネルギーとなる。このように、物質の一部が消滅すると莫大なエネルギーに変わることは、原子爆弾や原子力発電の原理として私たちは知っている。
相対論の認識では、物質はエネルギーの一形態にすぎないから、この逆をやれば反対の現象が起きる。これが非物質と物質との相互転換である。つまり、空間はカラッポの無の世界ではなく、消滅した物質のエネルギーが満ち満ち、またいつでも物質を生み出すことのできる「空」の世界(空間)なのである。今日いわれる波動に近いもので古人はこれを霊性と言った。
これは、物質も非物質も同じであると同時に「実在している」という一例である。「色」と「空」は連続した実在の世界である。「色即是空・空即是色」は相互肯定の実在論である。ただし、これは時間、空間、物質が密接に結びついた相対論の解釈であり、あくまでも人間の次元での真実であるから、N次元の仏の真実である「空」の一部でしかないと考えなければなるまい。要するに、全容は説明できないから私は「仏の真実」としか言わなかったのである。
では、なぜ「空」を自覚すれば解脱できるのか。「空」は永遠不滅なる「仏の真実」であり「諸行無常」なる縁起の世界を生み出す母体でもあるから、「空」から見ればこの世は「空の一形態」(極めて短い物質的現象的世界)ということになる。私という存在は「空」より現れたものであるから、死ねばまた「空」に帰っていくだけである。そちらの方は永遠不滅の仏の世界(彼岸)であるから、そちら側に生きる(往生する)私の方が本来の「私」でもある。とすれば、この世の私が「我思う故に我有り」などとデカルトが執着するような「我」とは、空から見れば陽炎のようなものである。「我有り」と思うが故に「苦」もまた生じるのである。不変なる我を所得していないことを覚れば(無所得)我を苦しめる煩悩もあるわけがない(心無罫礙)、すなわち煩悩もまた陽炎である(顛倒夢想)。
これが「色とは即ち空なり」と悟った釈尊の教えであろう。
これは、私なりに「仏の真実」の一部を解釈したにすぎず、本当は言葉で説明しないほうがよい。ただ「空さえも無くなる」という仏教研究家がいるので、空は実体であることを言いたいために多弁を弄した。もう一つの理由は科学主義者には、面倒だがこのような唯物論で説明すれば少しは仏教を理解できるかと思ったからである。
相対理論まで引き合いに出さなくても、空海はすでに千二百年前に物質と非物質の実在性は把握していた。空海には、あの屁理屈学者のような矛盾も混濁もない。親鸞のような苦悩の自己否定も、憧れの阿弥陀浄土もない。あるのは、今、ここにおける自己と仏との連動のみである。
「自心即ち実相なり。実相は即ち本尊なり。本尊即ち自心なり」『秘蔵記』
空海はまたこうも言う。
「空は色を生成消滅させる根源であるから、空から見れば色は仮有(仮の実体)であるが、しかし有為の世界にあっては歴然として存在する有形の森羅万象である」と言い切っている。
「一は百千の母なり。空は即ち仮有の根。仮有は有に非れども有有として森羅たり」
「空」が森羅万象の根源であれば当然のことである。ならば、「空は空としてそっくりそのまま実在」していなければならない。
空海は言う。
「空は色に異ならざれば、諸相を泯(ほろぼ)して宛然として有なり」(宛然とはそっくりそのままの意)「諸相を泯して有なり」とは、「空」の世界では物質は非物質に転化され、しかもそれが無形の実体としてそのまま実在しているということである。つまり、「仏の真理」では人間界の現象は全て消えてはいるが、「人間界の真理」においては有るものは有ると明確に二つの真理を語っているのである。空海のほうがよほどわかりやすい。
空海は「是の故に色即是空、空即是色なり」と語ったあとで、「空」を語る僧侶が「空」を覚らないので、この真理に矛盾を覚えたり"仏教の最大の難問だ"などと騒ぐ者が後を絶たないと嘆いている。
「衆生は此の理に迷うて転々として絶えることなし」(以上『十住心論』)
おそらくこれが空海密教と天台法華教の根本的な相違ではないだろうか。親鸞が「真言法華は行じ難しなり」と嘆いた気持ちもわかるような気がする。
では、「空」はどのようにして感得すればよいのか。先ほどの理論物理学的な解釈でよいのか。実は、あれは単なる方便にすぎない。あのような理屈で納得したと思うのなら誰でも解脱できる。科学では肝心なものが欠如しているのだ。それは「仏の意志」である。空の世界に充満する「仏の智慧」が抜けているのである。サイエンスは精巧な仏を彫っても魂を入れることはできないのである。だから我々は、いかに理論物理学の知識を詰め込んでも解脱できないようになっているのだ。
お釈迦さんは「空」を覚ったのみならず、その世界に満ち満ちている「仏の声」を聴かれたから解脱されたのであろう。初期、釈尊がそのあまりにも神秘的な体験を語ることを断念されたのは、言語の領域を超えた世界だったからである。それは、私たち凡人には説明し難い超常的なものだったろうと想像するしかない。だから仏教家は屁理屈をこねるよりも、謙虚に仏の言葉に耳を傾けることのほうが仏の意志にかなっているのである。
空海はその行為を「行」と言った。しかも「仏の声」は森羅万象に遍在し、法身大日如来は人語を超えた密語として常に人々に語りかけていることを実感したのである。これが智慧である。
「五大に響きあり、十界に言語を具す。六塵は文字なり、法身は実相なり」『念持真言理観啓白文』
その智慧は仏が生み出した人間の奥底にもあることを知っていた。最澄に語ったように「理趣は自分の中にあり、書物の中にはない」とい 、言葉がそうである。
「法身いずくにか在る。遠からずして即ち我が心なり」『性霊集』
「諸仏も法界なれば我が身中に在り、我が身も法界なれば、諸仏中に在り」『念持真言理観啓白文』
「我が自心の中に浄菩提心清浄の理あり」『秘蔵記』
「五蘊皆空とは真実の法、法界と心とは異説なし」『十住心論』
などの言説がそうであろう。
法界(仏)と心(人間)とは異説なしとは、仏は本来人間の心の中にあるということである。つまり、「空」即ち仏は、「色」即ち人間であり、それが「色即是空、空即是色」の真義であると語っているのである。「空」と同化するということは、おそらく生きながら生命の永遠性のようなものを実感する喜びだったのではないだろうか。
ここまでくれば、仏教が本来目指したものは、極楽浄土やあの世の話ではなく、現世における即身成仏にしかないことがわかるであろう。私が密教こそ仏教中の仏教であるというゆえんはここにある。密教を顕教(仏教)の究極に置いた空海が、生涯釈尊を崇拝した理由も、まさに釈迦こそが即身成仏の姿であったからにほかなるまい。
ゆえに私は、仏教の「相互肯定の理法」を正しく伝えたのは真言密教の空海ただ一人であると思っている。空海密教を国家権力と結びついた俗物宗教であるとか、禁欲の釈迦教に対する欲望肯定の反動宗教だとか、現世利益の神秘的ヒンディズムなどと浅はかな見方をする仏教研究家が多いが、そのいずれもが仏教と空海について無知である。
それは京都学派が華厳にまで到達しながらも、ついに密教が理解できなかったように、明治以降の仏教アカデミズムが密教を異端視してきたことにも原因があると思っている。日本は近代化とともに、深いところで仏教を捨ててきたように私には思えてならない。
以上は「般若心経」を私の実感をもとに言葉にしてみた素人の解釈である。それも、言葉にするとどうしても実感とは遠のいてしまう。真のコミュニケーションは実存の深まりのうちに自ずと共鳴するものであろう。とりわけ、神仏との共振は、やはりある種の「行」によってしか得られないのかもしれない。生きることに忙しい私たちの「行」は、しかし実存の深まりのなかで実践されるにちがいない。その中で静かに耳を澄まして仏の声に耳を傾けたいものである。そのような感性を大切にして生きることが、空海の私たち庶民に教える「行」のような気がする。
つまるところ、仏の世界と人間の世界との波長の一致を、日常の中から感得する生活をせよということではあるまいか。この波長が一致したとき、何事も全ては計算されたかのごとくうまくいく。人生の中で人は何度かそういう体験をするものである。空海の生涯は、奇跡の連続によって、まるで計算されたかの如く導かれて運いる。
おそらく仏神は全ての人間に智慧を発信し続けているのであり、それを受信できるか否かは受信機の問題である。その感度こそ私は「聖性」であると思う。最近は何かといえば感性、感性と騒ぐが、真の感性とは「仏の声を聴きとる感度」のことである。
道を誤るとすれば、エゴにまみれた私たちの"感性"が真の感度を鈍化させているのであり、受信不能にしたときである。日本のインテリが論理の鬼と化すことや、「生命分断史観」を自国の子どもに刷り込むことは、自国の「仏の声」を捨てることであり、ついにはこの国に「仏の智慧」が届かなくなるということである。
「自ら観ぜよ。我が心は無色無形なりといえども、本来清浄にして潔白なることなお満月の如し。客塵煩悩のために覆弊せられて明らかに見ることを得ず」(空海)