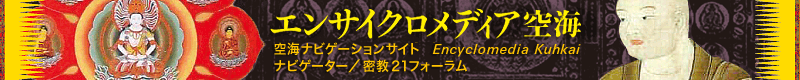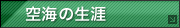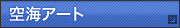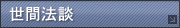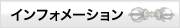★まんだら四国のお礼参り
結願寺からひと山越えれば阿波の第十番札所・切幡寺は近い。そこから数珠つなぎのように点在する札所を逆打ちしていけば、元の一番札所・霊山寺に戻る。そんなところから、結願した遍路はいつのころからか《お礼参り》と称して霊山寺まで遍路を続けるようになった。元の出発点に戻るのである。
私はこの巡礼形態を生命循環思想などというえらく形而上学的な視点でとらえたが、別に遍路ガイトブックにそのような説明があったわけではない。先達を派遣したり遍路講を組んだりする組織団体もいろいろあるらしいが、私たちはそういう団体があることすら知らないままに全くの自己流で回ってきた。したがって、私の考えが正しいかどうかは別問題である。
本式の遍路のやり方は、まず高野山の奥の院で弘法大師にお参りして、最後に再び高野山に詣でるということになっているが、これとても単なる習慣である。「四国八十八ヶ所霊場会」という組織があるので問い合わせてみたが、四国霊場がそういうことを奨励していることはないという。八十八ヶ所霊場は宗派も形式も超えた自由意志の世界である。
にもかかわらず、遍路は《お礼参り》をし、あるいは高野を出発して高野に戻るのである。何を根拠にそうしているのか本人たちにもわからないのだろうが、不思議なことに日本人は循環運動をしたがるのである。私たちが《お礼参り》をしたくなったのも、結局そういう内発的な衝動だった。
いずれにしろ《お礼参り》をすれば起点に戻るしかない。あえて理屈をつければ胎蔵曼荼羅の図象学の完成になる。胎蔵界曼荼羅が教えるところによれば、大日如来を中央にして、発心とされる東方の宝幢如来から右回りに発して、南方(修行)の開敷華王如来、西方(菩提)の無量寿如来、北方(涅槃)の天鼓雷音如来と順繰りに観想して中央(方便具足)の大日如来に到達するようになっている。
ということは、「まんだら四国」は八十八ヶ所を結願してもまだ大日如来の「方便具足」が残っていることになる。方便具足とは、大日如来がある方便をもって人々に悟りの世界を知らしめるということである。とすると、《お礼参り》もしくは《高野山詣》が方便具足に相当するのかもしれない。つまり、大日如来の説法に触れるという山場が残されているとも考えられる。
いずれにせよ、東方(徳島の発心道場)からスタートする遍路は、曼荼羅の理にかなっていることは確かである。そんなことを考えて四国を回ったわけではないが、どこかしら空海に近づいているような気がしないでもない。自然に湧き上がるそのような感覚が、《お礼参り》という信仰的な行為を私たちにとらせた。
結願の日が父の命日に当たっていたことは不思議といえば不思議だが、単に偶然かもしれない。空海は「この真言誦持すれば、法界曼荼羅に入ることを得しめたもう」などと盛んに神仏の意志が人間に入って何かを発現するようなことを言っている。「医王の眼には途に触れてみな薬なり、解宝の人は砿石を宝と見る」と、密教眼から見ればただの現象も背後に仏の意志が働いていることに気がつくと言っている。
とはいってもそれはそれ、私たちは夫婦で愉しむ道草遍路である。「お礼参り」はまだ見残した四国の秘境を訪ねるのが目的でもある。
第一日目は四国霊場番外札所・箸倉寺を参拝した。弘法大師が金比羅神の神託を受けて七堂伽藍を建立し、御神像を刻んだと伝わる神仏習合の山岳寺院である。同時に金比羅宮の奥の院でもあり、一種独特の雰囲気をもつ修験の霊山である。本殿の大天狗とカラス天狗の巨大な面には度肝を抜かれた。山頂から見る吉野川の眺めも雄大である。
二日目は吉野川をさらに上へ、上へと登って行った。吉野川の上流が四国山脈を横切るところに千態万様の渓谷がある。西日本随一の奇岩の景勝地「大歩危・小歩危」である。大股で歩いても小股で歩いても危険というところからこの名が付いたと言われる約8キロの名勝は、二億余年の太古から結晶岩や含礫片岩で奇岩の渓谷を形づくっている。エメラルド色の神秘的な清流を遊覧船に乗って川下りをしながら眺める断崖絶壁はまさに圧巻であった。
渓谷に沿ってさらに四国山脈を奥深く分け入ると「祖谷」(いや)に至る。日本三大秘境に数えられてきたこの地方は、ひと昔前は鳥も通わぬ陸の孤島であったそうだ。今では「かずら橋」で全国的に有名になっており、多くの観光客で賑わっている。祖谷には良質の秘湯もあり、その一つは傾斜角度42度、200メートル下の谷底までケーブルカーで下りて入る露天風呂がある。温泉愛好会の会長は、さっそく唯一の会員を連れて温泉を楽しんだ。秘境ムード満点。
私たちはその後さらに「奥祖谷」まで足を伸ばす。観光客もまばらな奥祖谷まで来ると、清流と原生林に囲まれた渓谷美が展開する。奥祖谷のかずら橋を渡ったり野猿(渓谷の空中を人力で渡る一種のロープウエー)に乗ったりして、しばし童心に帰った。
祖谷はまた平家の落人の里としても有名だ。平家滅亡後、一族がこの山中に落ちのびてきたため平家屋敷なども残っている。かずら橋には敵が攻めて来たときいつでも切り落とせる戦術上の目的があったそうだ。この地方の歴史はさらに古く、紀元2、3世紀にはすでに集落を成しており、ただの秘境ではなく日本のルーツにかかわる謎多き地域でもある。
車で走っていていつも思うことは、四国の山は実に深くて険しいということだ。空が覆い隠されるほど山がそそり立っている。そういう四国山地のさらに奥の、吉野川の源流の辺り、V字型に切れ込んだ谷を見下ろす山の頂上に集落がある。水田はどこにも見当たらず、稲作文化とは縁のない不思議な地方である。だから、祖谷は蕎麦が主食であったそうだ(今でも蕎麦の名産地である)。
山の頂上付近に住む土地の老人に、祖谷は平家の落人によって開かれた地域なのかと聞くと、「バカこけ、ワシらはずっと昔からここに住んでおった、平家は最近来た連中だ」と言われた。
山の上に住む民は大陸民族である。祖谷は文化的に長く取り残されていたのかもしれない。あるいは歴史好事家のいうイスラエルの「失われた十部族」と関係があるのかもしれないなどと妻と歴史話を面白がった。祖谷の遺跡には確かにそれを暗示するものは多い。そんな場所をいくつか探散しながら、アッシリアに滅ぼされた古代ユダヤ人のロスト・アーク(モーゼの失われた聖櫃)を秘匿しているという剣山説や高天原説など、歴史の謎解きに花を咲かせつつ、その晩私たちは祖谷の温泉に泊まった。
★大日如来の説法
第三日目、私たちは剣山に登ることにした。日頃の運動不足の解消も兼ねて山歩きを楽しむためである。標高1955メートルの剣山は石鎚山に次ぐ高峰である。妻が旅行雑誌で山の写真を見ており、頂上が草原のように開けていて、しかも山頂にヒュッテ(山小屋)があるのでそこに泊まってみたいと言っていた。どうやら彼女は、剣山でアルプスの少女ハイジの気分でも味わうつもりらしい。
だが、剣山は石鎚山と並ぶ四国の二大霊峰である。石鎚詣、剣山詣は古くから四国の二大霊峰信仰の山である。結願したとはいえ、私たちの空海を訪ねる旅は続いていた。
麓の剣神社の近くの駐車場に車を置くと、リュックを背負って私たちは鼻歌まじりに陽気に登って行った。七合目辺りまでくると、登山道から見えるはずの眺望は雲のため白く閉ざされてしまった。せっかくのハイキングも台無しである。八合目の大剣神社の辺りまで来ると、急に発生した濃霧に行く手を覆われてしまった。ビニールのカッパを着て頂上に着いたときは、横殴りの強風が猛烈な霧雨を浴びせるように私たちを襲った。雨雲の中に入ったと思った。
数メートル先は完全に視界のきかぬ白一色の世界である。山頂の様子は何がどうなっているのか全くわからない。ただ得体の知れぬ白い霊気が荒れ狂うばかりである。爽快なアルプスどころか、天地が渾然一体となった混沌たる世界にいるようである。私たちは、剣山の滝にでも打たれたかのようにすっかり濡れそぼって山頂ヒュッテに入った。
これまで本格的な登山経験のなかった妻は、ペンション風の洒落たヒュッテを想像していたようだが、山頂の厳しい天候に耐えうる山小屋は、文字通り頑丈な山小屋であった。濡れた衣服を着替えてストーブを囲みながら、その夜は吹きすさぶ風の音を聞くしかなかった。
夕食後ヒュッテのご主人が語るには、昨日の日曜日の朝は御来光を拝もうと80人もの登山客がこの山頂にひしめいていたそうである。ところが、あいにくの天候で御来光は拝めなかったそうである。今夜は私たちの他に一組の中年夫婦がいるだけで、山小屋は空しく夜の闇を吸収していた。
「ああ、御来光を見にみんなこの山に登るのか」
「今日の天気では明日もきっと無理ね」
日の出の眺めを目的に登山したわけではないので、二人とも格別落胆もせず、しかしその夜はなすすべもなくひたすら毛布にくるまるしかなかった。
翌朝、日の出の時刻は6時3分である。
40分前に、ご主人の新居さんが起こしに来てくれたので外へ出てみた。昨日の霧は嘘のように消えていた。仄暗い山頂は熊笹が一面を覆うなだらかな丘陵をなし、吹き渡る風の中に荒涼たる草原のようである。寂莫とした薄明の中を見渡せば、近くの黒い山影が剣山を拝するかのように雲に浮かんで寄り添っている。360度、足元の高さまで敷きつめられた雲の海が一望に広がっている。
新居さんによれば、日本晴れの日の出は味気なく、ほどよい雲の出現が御来光を際立たせるという。前日の空模様から全く予期もしていなかった私たちに、この朝、剣山は荘厳な美を見せてくれたのである。今朝のような素晴らしい御来光はめったにないと、長年山頂で暮らすご主人が感激したほどに、それは一生のうちに二度と見ることはあるまいと思われるほどに壮大な自然のドラマであった。
天地は混沌から徐々に姿を現していた。頭上の高層雲は累々とした黒い屋根をなして、日の出の方角に遠ざかるにつれて暗灰色の流れ雲となり、まだ明けやらぬ空と溶け合っている。胸元を発止と打ってくる凛然たる寒気に眠気は吹っ飛び意識は純化してくる。東の空がわずかに白みかけると、雲上の峰々は轟然と雄叫び、寒風は耳元で絶叫する。私たちは烈風吹きすさぶ風雲の狭間にいた。
山岳カメラマンの新居さんは三脚を立てて一眼レフを構えた。
剣山は暁暗(ぎょうあん)の眠りから今まさに醒めようとしている。雲々は山頂を包み込みながら、仄白く静かにうごめきはじめた。それらは、霊峰に蟠居する巨龍たちが幾重にも剣山を取り巻くさまにも似て、雲裏に隠された聖櫃(せいひつ)の光芒に、凶々(まがまが)しい相貌を浮かび上がらせているようだ。
私と妻は髪を逆立てて東方に向かって立った。
神事の刻限(とき)が迫ってきた。
灰色の空が茜色を帯びてくると、黄金の雲々が満天を覆い、剣山はこの世のものとも思われぬ金色の台(うてな)に神変した。辺りの山景は冷瀧に洗い出され、白龍は虹色の瑞雲に変貌しはじめた。やがて世界は黄薔薇(きばら)の澄明な光輝に包まれてくる。再び大空を振りさけ見れば、刻々と満ちてくる夜明けが不浄の闇を追放し、神の沙庭は広大な御空に拡散していった。
風は止み、たまゆらの空寂が辺りを支配した。妻と私は手を握り合ったまま息を飲んだ。
東の天辺が清明な水色に変じた! と思うや、遥かなる雲海の一点に閃光が煌めいた瞬間、天高く放たれた光の流矢は、凛烈な大気を引き裂いて剣山にとどいた。一瞬眼がくらんだ私たちは須臾に五体を神の光に射貫かれていた。
見れば、無窮の天壌に赫々たる神の矢を放射しつつ、大日如来はまさに燦然と昇った。
何たる神々しさ!
天地はあまねく照り輝き、生きとし生けるものは光放つ存在に蘇生った。私たちは一木一草とともに思わずその場に跪いていた。大自然が全ての命に語りかけた一瞬の説法。
日輪はただしんしんと万物の上に降りそそいでいる......。
★童塚と泥仏と空海の声
御来光のせいか、剣山の神霊か、何か神秘的な力に打たれたような気分をかみしめながら、私たちはその日《お礼参り》のために下山する。国道を香川県方向へと向かう途中で「一宇峡」や「土釜」「鳴滝」などの景勝を見学しつつ里へと降りて行ったが、いつものおしゃべりの妻が何か物思いに耽っているふうだった。
あとで彼女が話したことだが、剣山で新しい時代を告げる天地創造の説法を聴いたような感じがしたと言うのである。それは人類の結婚である。二組の男女の四極構造である。そういえば、あの大日如来が出現した瞬間、剣山頂にいた者は二組の夫婦と、それを見届ける山小屋の番人と、そして一匹の犬だけだった。劇的な場面構成が見事に準備されていたあの状況に、彼女は何事かの象徴を感じたそうである。
昼過ぎ、阿波の十番札所に着いた。
これから回る寺々は三年半ぶりである。ずっと身に着けてきた笈摺と輪袈裟も今回で最後かもしれない。そんなことを考えながら切幡寺の山門に向かうと、杖のないのもどこかもの淋しい気がした。
この日は十番から逆打ちで五番・地蔵寺まで回った。寺の様子は大体記憶していた。だが驚いたのは、この数年でいくつかの寺が全体的に観光化されていたことである。懐かしさと寂しさの入り混じった複雑な思いを感じながら、その夜は御所温泉に泊まった。三年前四十九歳の誕生日を迎えたあの鯉のぼりの温泉である。
五日目は第四番札所・大日寺から第一番札所・霊山寺まで打ち戻った。初めてこの寺に詣でたときは、もっと境内は広々としており古刹の感じがしたが、今は人々の生活の臭いに包まれた界隈のような空気を感じる。あのときは遍路の知識はほとんどなかったし関心もなかった。あの日形ばかりのお参りをした最初の大師堂で、携帯用の木魚を叩きながら力を込めて「般若心経」を唱えてみたが、しかし特別変わったことは何も起こらなかった。変わったことといえば、初心者のぎこちなさが今は遍路慣れした所作に変わったことぐらいである。
「真言は不思議なり、観誦すれば無明を除く、一字に千理を含み、即身に法如を証す」と空海は言う。この寺で空海に会おうと思い立って出発したが、八十八ヶ所を回ってみても、正直空海に会えたという自信はない。いや少しは会っていたような感じもするのだが、それは頭の中だけのことだったのかもしれない。
歩いて何度も回ってもお大師さんに会えないでいる遍路はたくさんいるというのに、遊びながら道草遍路をしてきたような者が空海に会えるわけがない。まして無明を除いたり即身に法如を証すことなどできるはずもない。だが、私はそれでも満足だった。《お礼参り》の最後の納経をすませると、これでやるべきことを全て果たしたような安堵感を覚えた。
空海は若いころ突き上げてくる激しい求道心を「還源の思い」と呼んだ。
「弟子空海、性薫我を勧めて、還源の思いと為す。径路未だ知らず、岐に望んで幾たびか泣く」『性霊集』空海の遍路行が家も故郷も地位も名も捨てて「仏の源に還る」旅であったのなら、故郷を捨てたと思って
いた私のほうは、空海を求めながらも父母の源に還る旅になった。それは、どこか空海に導かれつつ、自分が自分に還る旅でもあった。これも一人の人間の「還源の思い」ならば、そういう意味ではかすかにでも空海に触れていたのかもしれない。
遍路は終わった。私たちは寺を出ると遍路衣装を解いた。
第六日目。塩江温泉のホテルを出ると、父の命日を迎えた結願寺に寄ってみることにした。ここから大窪寺は近い。《お礼参り》を終えた私たちは、結願の日に納めた金剛杖に最後にもう一度会いたくなって行ってみたが、私たちの杖はもう見当たらなかった。
思えば、さほど乗り気でなかった私を妻が遍路に連れ出したのではあるが、妻を動かしたのは父のようでもあり、どこかしら空海の意志のようでもある。そんなことを漠然と考えながら、結願寺の大師堂で最後の経を上げてみたが、空海はやはり沈黙するばかりだった。
「このまま広島に帰ろうか。それとも、もう一度仏母院に行ってみようか」
「もちろん行きましょうよ」
広島に帰るにはまだ時間があったので、私たちは真魚の泥仏に魅かれてまた海のほとりの仏母院を訪ねた。参詣者で賑わう霊山寺とは打って変わって、周囲を田圃に囲まれた仏母院はひっそりと静まりかえっていた。
夏には青々とした稲田に包まれて近づけなかった童塚は、今は刈り田の中にぽつねんとその茂みをあからさまに見せている。刈り残した頭髪のように、そこだけがこんもりとした灌木の一群には、時折かすかに揺れる小笹が、もう冬近い秋風の名残を漂わせていた。
「ここで空海が泥仏を祀って無心に遊んでいたんだね」
直径3メートルほどの何の変哲もない茂みである。かつては子供守護の信仰が厚く供花が絶えなかったそうだが、今ではお参りに来る人もいないのか、白ペンキの角棒に「童塚」と書かれた立札が、朽ちかけて白骨のように枯草の中に倒れていた。
私は白木の泥を払うと草の中に立て直した。白い墓標のように見えた。
「真魚ちゃん...」
妻はわが子を偲ぶようにつぶやく。
遍路がお大師さんとしか呼ばない空海を、彼女はなぜか時々「真魚ちゃん」
と呼びかける。考えてみると、それは幼い空海の魂が宿る場所で、ごく自然に
出てくるようだ。
ご住職は私たちを覚えていて、すぐに本堂へ通して下さった。平服に戻っていた私たちはそのまま祭壇の前に正座した。正面には日輪を背負った大日如来像が見守っている。大窪寺で買っていたお菓子とお布施を供えて左右の燭台に灯明をともす。香を炊く。目の前には真魚のあの泥仏が安置されている。鐘を打つ。合掌。結んだ印は真言合掌である。
私は小さな声で「般若心経」を唱えた。うなだれたこうべに自分の声が静かに滲み入ってくる。それはいつしか言葉としては消えてゆき、「心経」は快い調べのように響いてきた。八十八ヶ所を回り、各霊場であれほど唱えてきたにもかかわらず、このようなことはかつて一度もなかった。なのにどうしたことか、私は自分の読経にひたすら聞き惚れていた。
「心経」は冥想の五体に沈静していく。そのうち真言の声は、時々、遥か彼方から風に乗って届いてくる声明のように聞こえてきた。私は自分の声がこんなにも格調高かったかと、ふと訝りながらも奇妙な恍惚感に包まれながら唱え続けた。やがて真言は自分の声であって自分の声ではなく、どこか遠くからでもあり、すぐ近くからでもあるような、声量のある静かな男性の声が重なっていることに気がついた。
(確か聞いたことのある声だ......)
私はそれが善通寺の暗闇の中で聞いた空海の声に似ていることに気がついたが、何故か驚きもせず、ただただ共鳴する空海とともに唱え続けた。それほどに声明の調べが心地良かったのである。
夢のような束の間が過ぎて目を開いたとき、目の前の泥仏が一瞬輝いて見えた。はっとした私はもう一度見ようとしたが、そのときはもう、溢れてくる涙の向こうに霞んでいた......。
私は屏風ヶ浦の砂浜に腰を下ろして惚(ほう)けたように海を眺めている。妻が渚で波と戯れている。あれは幻聴だったのだろうか......思い返せばほんの一瞬の出来事だったようでもあるが、全身に伝わったあの快感とあの空海の声は私の中にありありと残っている。
「涅槃とはああいうものなのだろうか。あのまま広島に帰らなくてよかった。妻が空海の声を聴かせてくれたような気がする)空海の生まれた場所で、私は神秘感に打たれたまま、この体験をまだ彼女にさえ口にできないでいた。
妻が私を呼んでいる。
我に帰ってその方を見ると、彼女が渚に立って砂浜を指さしている。砂の上には大きく「空」と「海」の二文字が書かれていた。私は腰を上げると彼女のそばに行き、その砂文字に続けて、力強く「風」と書き加えた。
ひときわ大きな波が打ち寄せて、その砂文字を吸い取っていくのを見届けた私たちは、西暦2000年、空海の待つ高野山へ向かったのである。