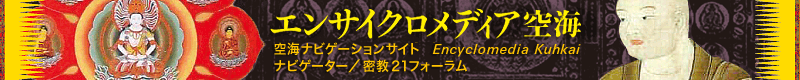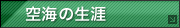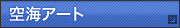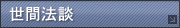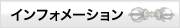昨日の雨はどうやら上がった。盆休みの続きは第四十四番札所からである。南予(南愛媛)は第四十三番札所・明石寺を最後に海辺回りの札所は一気に四国山
地へと入って行く。石鎚山系の懐深くに第四十四番、四十五番があり、それを打つと再び中予(中部愛媛)の里に向かって下りてくる。松山市に向かう途中に四
十六番、四十七番、四十八番と山里の札所が続き、さらに松山市北東部の札所を回って、「へんろ道」は再び海辺に出る。そこからまた四国の辺地の札所を今治
に向かって辿ることになる。
四国全図を見ながら考えた。四国霊場は時々山中深く入るが、札所間をつなげばおおむね四国の輪郭をなぞることになる。つまり、四国を縁取る辺地に霊場の多くが点在しているということである。これは、すなわち四国の霊場巡りは海洋信仰と関わりがあるということではないか。
室戸以来ずっとそんなことを考えてきた折もおり、私と全く同じ観点から四国遍路を研究した学者がいたことを最近知った。故五来重博士である。高野大学、
大谷大学教授を歴任し、日本の庶民信仰の歴史を解明するため、仏教民俗学を提唱された人である。なかでも、四国霊場の基層には古代日本人の海洋信仰がある
という画期的な発見をされ、これまでの四国遍路の概念を一新された学者である。そこでは、空海をずばり「海洋修験者」とまで呼んでいるのにはさすがに驚か
された。
私は海辺の土佐の霊場を訪ねながら、ただ直感的に感じたことである。自分が海辺育ちであり船乗りでもあったので、「海の空海」に親しみを感じるのだろう
と思っていたのだが、もう一つ気になっていたことが空海と海を連結させた理由である。それは、四国の文化とは異質な沖縄の文化で育った妻が、私を四国遍路
に誘ったことである。
むろん、本人に四国遍路と沖縄を結び付けようなどという大それた意図があったわけではない。妻はせっせと鶴を折りながら、まったく自由意志で「お遍路を
したい」と思っているだけである。だが、白衣のお遍路さんたちに交じって、ニューファッションのカラフルな妻が、いつも生彩を放っているのが、私には新鮮
だった。私の心象風景にある暗い遍路にはないものである。
妙に存在感がある妻を見るたびに、それは単に彼女のお洒落感覚という以上に、霊場における彼女の存在が何かを主張しているように感じていたのである。そ
れら諸々が私に四国遍路の行き着く果てが南の海を夢想させ、遍路信仰の底に古代日本人の海洋信仰を連想させていたのだ(むろん、五来博士に弘法大師信仰と
沖縄とを関連させるような飛躍はない)。
妻も私も、行動の原点は直感と実感である。教義というフィルターを通さずに直接法身の説法に耳を傾ける。論証は直感の確かさを証明する手立てにはなる
が、それは人生の主ではない。主ではないが、自分の直感が何であったかを専門家が解説してくれたような喜びはある。ともかく、私は「私の空海」を求めてい
きたい。
松山市から出発した私たちは、山中の第四十四番札所に向かう途中で、四十八番、四十七番、四十六番札所を通過することになる。これらの札所を順次逆打ち
して行ったほうが効率はいいが、正攻法でやりたがる私たちは、やはり順打ちで行こうと話合い、途中の寺は飛ばして第四十四番札所に直行した。
 歩き遍路は、明石寺(卯之町)から大洲、内子と通過して、峠越えの続く難路をたどって海抜490メートルに位置する久万町に入る。道程は約95キロ。札所間では岩本寺から金剛福寺(約120キロ)に次ぐ長さ。伊予の「遍路ころがし」は愛媛県中南部の山中まで続く。
歩き遍路は、明石寺(卯之町)から大洲、内子と通過して、峠越えの続く難路をたどって海抜490メートルに位置する久万町に入る。道程は約95キロ。札所間では岩本寺から金剛福寺(約120キロ)に次ぐ長さ。伊予の「遍路ころがし」は愛媛県中南部の山中まで続く。霊場に着いた私たちは、さっそく遍路姿に身を整えて、杉や檜が林立する初秋の参道を登る。樹齢280年の樹々から射し込む陽の光が清々しい。高地の朝の 澄んだ空気の中で、妻が胸に下げた鈴の音がチリーン、チリーンと鳴っている。いつしか遍路もすっかり馴染んだのか、心が静まるのも不思議である。私たちは また聖なる異次元の世界へと入って行った。
大宝寺は弘法大師が霊場と定めた時よりもさらに百年以上も古い寺である。杉木立の坂道を4、500メートルほど登ると豪壮な山門に着いた。仁王門の左右 の大草鞋は収まり切れずに天井まで這っている。山門を過ぎて坂道を登り、さらに石段を登ると、珍しいことに左右に二つの鐘楼があった。
鐘撞きの大好きな妻は、心躍らせて両方とも撞く。右側は古いもので、左側は太平洋戦争で亡くなった英霊の供養のために建てられた「平和の鐘」である。私も撞く。父を思い出す。深山の密教寺は朝露の潤いを残し、鐘の余韻は
《朝まいりはわたくし一人の銀杏ちりしく》
山頭火の詠んだ句が境内の石に刻まれていた。
●第四十五番札所・岩屋寺
 弘法大師空海は大宝寺で修行中、なお深山に霊気が立つのを感じてさらに奥へと分け行った。私たちも後を追う。森林が岩峰を
弘法大師空海は大宝寺で修行中、なお深山に霊気が立つのを感じてさらに奥へと分け行った。私たちも後を追う。森林が岩峰を歩き遍路は大宝寺の裏の峠を登って岩屋寺へ打ち越えるが、私たちドライブ遍路は国道33号線に戻って山を迂回する。面河川の支流に沿って山峡を走り、ようやく霊場の麓まで来た。
空き地の駐車場に車を駐めると、すでにお参りをすませた遍路のバアサンたちが数人ベンチで休んでいた。気さくなバアサンたちは何かと話しかけてくる。
「今日はええあんばいの天気や。あんた、お四国さんは何回目?」
「初めてですが、おばあちゃんはもう何度か回られたのですか」
「わたしゃ、まだたったの5回よ」
「えっ、5回も回ったの」
「あんた、5回なんかまだ序の口や。この人は10回、あの人は15回目やが」
そう言うと、もう一人のオバアサンが口を出して、
「そう、そう。40回や50回はザラにおいでるがな」
「そんなにオイデルんですか。どうして?」
「一遍回ったら、何でか知らんけどまた回りとうなるんよ。お四国病ゆうてなあ」
「そうや、そうや。お宅らもいんまお四国病にかかるけんナ。ホナ頑張って行っとおみ」
そう言ってバアサンたちは愉快そうに笑いながら、私たちを見送ってくれた。
山道を登りながら、「俺は一回でいいぞ。四国病なんかにはかからないぞ」と妻に宣言した。(後日談だが、このときの思いは見事に覆された。結願後、私たちはまた四国を回りたくなったのである)
急坂の参道は登るにしたがって霊域に入っていくのがわかる。つづら折の坂道には南無大聖不動明王と染め抜かれた赤や紺の旗が延々と立ち並んでいる。岩屋 寺の本尊号である。 苔むした森林の斜面には、賽の河原の石積みのようにビッシリと積み並んだ石仏の群れが次々と現われてくる。霊気に包まれながら登りきると、まもなく行く手 に巨大な岩山が天からのしかかるように頭上に迫ってきた。堂の屋根が岩場に抱かれるようにせりついている。私たちは仰天した。それはまさしく岩屋寺であっ た。
「岩のすがた
私は、不動堂の脇の梯子を伝って「仙人窟」に上ってみた。高い岩の天井をもつ窟そのものを本堂と見なせば、
本堂、大師堂をお参りしたあと、弘法大師が掘ったと伝えられる「
尻込みする妻を外に待たせて、私は一人で巌窟の中に入って行った。窟の中は一寸先も見えぬ闇である。ローソクの光を頼りに身をかがめながら入って行くと 予期せぬ奥の深さに驚いた。ところどころに石仏が祀ってあり、何とも不気味である。洞窟はさらに奥へと続く。先には大師が掘った独鈷の霊水が今でも湧いて いるそうだが、暗すぎてわからない。最も奥まったあたりにかすかに赤い灯明がほのめき、菩らしき影を見たときローソクが消えてしまった。しかたがないので まっ暗な中を手さぐりで出てきた。
他のお遍路さんは私のように岩壁に登ったり穴の中に入ったりしないで、お参りをすませるとさっさと次の札所を目指す。私たちはさらに「奥の院」へ行くことにした。
本坊で行場の鍵を借り、白山妙理大菩薩守護のお札をもらって古びた裏山門を抜ける。裏山の三十六童士行場を登ると、また仰天した。合掌したような双の岩峰が垂直にそそり立っている。どういうわけか前々から妻が来たいと言っていた「
絶壁の下には高さ4、5メートルの大きな不動明王が睨んでいる。妻が挨拶してこいと言うので近づいてみると、右手に宝剣を構えているのはいつものお不動さんだが、
「白山妙理大菩薩逼割行場」と書かれた木戸の扉を開いて中に入り、二人が逼割岩の割れ目を驚嘆して見上げていると、上から菅笠にぞうり履きの行者がロープを伝ってスイスイと下りてきた。
「帰りは木戸の鍵を掛けてください」と言われたその人は、霊場順拝は何と137回目だという。思わず合掌する私に錦の納札を下さった。裏には住所氏名年齢、順拝回数が書いてあった。年は66歳、少し願を掛けたいことがあって行場に来たという松山市の人だった。
話はそれるが、遍路の納札は順拝回数によって色が変わる。4回までは白、5回以上は青、7回以上は赤、25回以上は銀、50回以上は金、100回以上は 錦である。名刺代わりにお札を交わす習慣があり、また遍路をしたくてもできない人が錦札をお守りにすることもある。なにしろ、お遍路さんはお大師さんと同 行二人の聖なる旅人なのだ。私は金のお札も、銀のお札も旅の途中でもらった。
赤い金剛杖を持っている人は先達であり、50回以上は大先達といわれるらしいから、この人はきっと超大先達なのだろう。ちなみに、最高記録は中務茂兵衛 の280回だといわれている。弘化四年(1847)、周防国(山口県)生まれの人で、明治の廃仏毀釈の嵐が吹き荒れるなか、ひたすら霊場を巡って遍路の伝 灯を守った人物として伝えられている。「へんろ道」では、今も彼の事跡に触れることができる。一生を乞食と放浪で過ごしながら、遍路の道標に作った136 基の石標がそれである。
私たちの納札はもちろん白。序ノ口どころか新弟子テストの段階である。しかし、新弟子の妻は「奥の院」に行ってみたいと言うのだから見どころがある。
「落ちてきたら受け止めてよ」
軍手をつけた妻は、もうロープにしがみついて岩の裂け目を登り始めた。自転車すら乗れない運動神経の鈍い妻が、しかも穴グラに弱いくせに懸命に登っている。私は歯を食いしばった妻の必死の形相が目に浮かんで吹き出しそうになった。
ほとんど人一人しか通れないほどの岩の割れ目を20メートルあまり登って、やれやれと思ったら今度は鎖である。ぶら下がるようにして登る妻の足元に注意を払いながら、この物好きは一体何だろうと考えた。
弘法大師がこの山に来たとき、法華仙人という女性の仙人が出てきて「自分はこの山の主である」と名乗った。大師が「ならば、その法力を顕わしてみよ」と 言うと、女仙人は二十丈(約66メートル)の大磐石をかき分けて通った。その割れ目がこの「逼割禅定」である。妻がこの話を知っているとも思われぬのだ が......
言い出したらきかない。売られた喧嘩は受けて立つ。始めたらあとには引き退がらぬ性格である。彼女はとうとう登りきった。
「兄者よ、やったぜ」、妻は息を切らせながら満足気である。
「うむ、見事。だが本番はこれからだ」
「ギョ!」
見れば頂上にはさらにエボシのように屹立した岩峰があり、ほとんど垂直に梯子が掛けてある。今度はこれを登るのだ。これまでは予行演習であった。私はい よいよ血が騒ぐ。『一遍上人聖絵』にある菅生の岩屋は誇張ではない。全くそのままだ(中国の桂林に似た風景で、下に市女笠をかぶった上臈三人が顔を隠し、 頂上の白山神社に向かって二人の僧が梯子を登っているのを供侍が見上げている図)。
「これは俺が登ってみる」(これを登らねば白山権現には詣れないのだ)
天に昇る気分で梯子を登る。昔の修行者は一体どういう神経をしていたのか。時々墜落して怪我をする遍路もいたそうで、過去には頭を割って死んだ者もいたという。
妻が登って来る。やっぱり負けず嫌いだ。
「こわい!」
「上も下も見るな。梯子だけ見ろ」
テッペンは白山権現の小さな祠があるだけで、狭くて立つことすらできない。私たち二人は岩壁に身を寄せかけて合掌した。岩上の行場からの展望はもの凄い。すぐ足元は千仞の谷である。瀬戸内海が見えるはずだが、遠くは靄に閉ざされて雲海のようになっていた。
《山高き 谷の朝霧海に似て 松吹く風を波にたとへん》
大師はこの行場でそう詠んでいる。ゆえに岩屋寺は山にあるが山号は「海岸山」と付けられた。空海は山にあっても「海を見ていた」のである。
ここは太古の昔、海底の礫岩峰が林立していた場所である。岩壁の怪岩峨々は隆起した地層が数万年の間に侵食を繰り返してできたものである。空海はその窟に籠もって、大自然に抱かれるちっぽけな人間を考えたにちがいない。
「お大師さんは本当に穴グラが好きなのねえ」
「穴グラは自然の懐だもん。理知の塊のような空海には全く反対の自然児の血が脈々と流れていたんだよ。彼はきっと人間の根源にある母体回帰の本能を知っていたのさ」
「それがきっと胎蔵界曼荼羅の思想になるのね。お大師さんたらマザコンね」
「そうさ。すべからく男はマザコンさ。穴禅定はまっ暗な子宮だったよ」
「そして、いったん子宮から出てくるやいなや危険な岩山を登りたがる。"漢"よねえ」
「命を賭けるのが男だからな。だから、空海は山に籠ってばかりいないであれほどの社会的偉業をやったんだ」
(それにしてもわが空海をマザコンとは?)
私は妻のバチ当たりを詫びるべくそっと手を合わせる。
菅生の岩屋寺を打つと、遍路は大宝寺への打ち戻りコースで山里へ下りて行く。だが、私たちはそのままさらに奥へと前進する。四国山脈を縦走する石鎚スカイラインを飛ばして四国最大の渓谷「面河渓」に向かった。
4時頃、現地到着。
水の青、苔の緑、白い滑らかな岩肌、周囲の断崖を鏡のように映す緑の河底は、ため息の出る美しさである。遊歩道を深く入れば、断崖、滝、奇岩、樹海など変化に富んだ見事な自然美が展開する。
渓谷をひと巡りした後で河原に下りると、私はまた小石を拾いたくなった。私の妙な癖で旅に出るとよく小石を拾ってくる(実は方々で拾っているのだが妻には内緒にしている。別に理由はないのだが何となく隠しておきたいのだ)。ここには本当に形のいい石がたくさんある。
別段それをどうこうするわけでもないのだが、人知れず黙って転がっている小石を見ると、何かしら親しみを感じるのだ。石ころは一つひとつ表情がある。大 きさも色も異なり、それはそれで一つの個性である。しかも、彼らの個性の形成にかけた歳月は人の歴史の長さなどとてもかなわぬ。
面河渓谷で遊んだあと、再び石鎚スカイラインを登って行く。目指すは四国山脈の最高峰「
結構道のりは長い。行けども行けどもという感じで延々と登って行く。
「四国の山は高いのねえ」
「車でもこんなに時間がかかるのに、昔の行者は歩いて登ったんだ」
「空海も大変だったんでしょうね」
「道もない時代だもの。草鞋でよく登れたなあ。片手に杖を持ち、一方の手で鎌を持って薮を切り開きながら登ったそうだよ」
秋の斜陽は山々に映えわたり、ほのかな紅を融かし込んだ空は名残の青さに安らいでいる。長く尾を引き始めた山の影をいくつもカーブしたとき、左前方に石鎚山がくっきりとその姿を現した。
「石鎚山だ!」
「あれがそうなの? すごい!」
西陽を浴びた霊峰が決然と天を突き上げている。妻と私は思わず車を止めて外へ出た。高地の冷気にたちまち心身が引き締まる。
山並みの向こうに、ひときわ高い石鎚の連山が簡明な姿で聳え、両翼を広げた山の中央部は、剣の刃こぼれのような凹凸をなして固い稜線を描いている。灰褐色の山肌は堂々とせり上がり、ついには鋭い山頂が秋の天空を指し示すようにそそり立っている。
私も妻も息を飲んだ。
「あれが石鎚山か......」
「あれが石鎚山なのね......」
思わずひれ伏したくなるような山容である。まさに霊峰という名にふさわしいその高さは1982メートル。西日本最高を誇る山岳である。
「四国を放浪した空海は、あの山で修行したんだ」
「私たちも行きましょう!」
にわかに活気づいた私たちは石鎚山を目指して車を発進した。
石鎚山は室戸岬の御蔵洞とともに、空海自らが修行の聖地として『三教指帰』に書き記した山である。食を絶って言語に絶する修行に励んだ若き空海の求道の 山である。私たちが巡拝コースを離れてここへ来たのは、登山で足腰を鍛えると同時に、空海の古跡をこの目で確かめたいがためである。
石鎚山は古くから山岳信仰の道場であり、富士山、御岳山、立山、大山、大峯、釈ヶ岳とともに日本七霊場に数えられている。「
そこに歌われている聖とは山岳修行者のことである。石鎚山を開いたのも山岳修験者の元祖
ちなみに修験とは、山林で修練苦行して験力を得ること、すなわち修行得験のことである。彼ら山岳修験者は、平野にあっては呪力によって病気を治したり、
山野を跋渉しながら各地を遊行する彼らの信仰は、当時国家が独占していた宗教(奈良仏教)の埒外にあった。彼らの活躍の場は、主に民間信仰に深く根を下 ろしていた。その性格を一言でいえば、律令的な側面をもちつつも大いに反律令的であった。役小角が国家権力によって捕えられたのも、国家の統制外にある聖 たちの民衆の中における影響が恐れられたためである。現代風にいえばアウトローであり、反体制勢力でもあった。
少し当時の思想背景を覗いてみよう。
空海が生まれた時代は、すでに彼らが暗躍していた奈良時代の末期である。ちょうど長岡京から平安京に都が移転されようとしていた頃である。空海が大学受 験を目指して上京したのは、没落前の平城京であったといわれている。すでに廃都となりかけてはいたが、平城京は人口20万人を擁する日本最大の都市であ り、旧来のアカデミズムの中心はまだ奈良にあったからである。
空海が大学の明経科(今でいえば東大の法科)で高級官僚の道を目指していた頃、政治の舞台は遷都という改革期にあった。時代は新しい時を迎えようとしていた。実はこの頃、すでに山岳修験者のグループは中央仏教と対立していたといわれている。
新都造営のための地勢学を研究するのは宮内の陰陽寮という役所の一つであった。そこで陰陽師という学者たちが占地を研究するのであるが、その知識は百済 からもたらされた陰陽道であった。仏教が導入されてから聖徳太子によって儒、仏、道が習合し、行政倫理は儒教に、宗教倫理は仏教に、国家の盛衰は道が占う という役割分担が成立した。つまり、道は国家戦略の裏側を支えていた。
もともとは暦学や医学などと同様の博学として理解されていた陰陽道が、一方では日本古来の神々と習合した。習合させたのが、主に初期の修験者である。そ の結果、学術としての陰陽道が在野では高い宗教性を帯びることとなっていった。そして、朝廷側の陰陽道と小角など在野の陰陽道が対立するのである。それは また、国家宗教と民間宗教、宗教の中央集権化と地方分権化の対立、平野部と山間部の対立でもあった。見方を変えれば、アカデミズム対アンチ・アカデミズム の拮抗といってもよいか。
空海はこのような二大潮流を背景として出現した。そして、彼は後者を選択する。アカデミズムの頂点にいながら、自らドロップアウトをしたのである。その きっかけが虚空蔵求聞持法であった。空海に求聞持法を授けた「一人の沙門」とは、彼ら山岳修験者の中の誰かだといわれている。
ただし、それは空海ほどの青年に儒教や道教よりも仏教が優れていることを納得させるほどの人物でなければならなかった。すなわち、奈良仏教について相当 の学識があり、しかも山岳修行者が所有していた求聞持法を修した人物である(勤操ではないかとの説があるが定かではない)。
いずれにせよ、「一人の沙門」との出会いによって空海は山岳修行者のグループに入って行った。『三経義疏』の中で、あの聖徳太子にまで非難された律令外 のグループにである。空海が他の高僧と対照的なのは、仏教を学ぶにあたって、最初から正統なアカデミズムに進まなかった点である。例えば、鎌倉仏教の祖師 たちの多くは比叡山の天台教学で学んだ。空海は自然を師とした。
18歳でアウトローの仲間入りをしたこの青年は、以後十数年間、山林を駆け巡り各地を放浪する。空海が仏道を志すにあたって選択したこの時のスタートは、のちの彼の思想を方向づける重要なポイントである。その空海が修行した山が、あの石鎚山なのである。
6時過ぎ、「土小屋」に到着。
石鎚山は西条市方面と土小屋方面からの二つの登山コースがあるが、私たちは土小屋から登ることにしていたので、その夜はそこに一軒だけしかない「国民宿舎・石鎚」に泊まった。
ほとんど登山客しか利用しない宿舎は、山男の臭いがした。六畳一間の部屋には電気ゴタツがあり、早速もぐり込む。寒い。昨日の奥道後ではクーラーをかけ ていたのに、今日はコタツである。高地の気温はこうも差があるものか。今日は、一日崖を登ったり山や渓谷を歩き回ったので足がガクガクしている。だが、明 日のウォーミングアップは、これで十分だ。