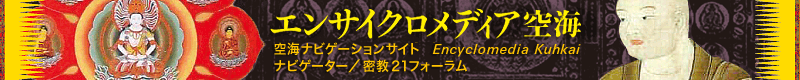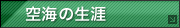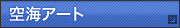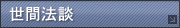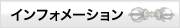物心合一の理念は、日本の思想においてさらにいっそう強力となり、ついには両概念の完全な融合が達せられるべき運命にあった。この融合の中心がむしろ物質的なるものに置かれ、そして象徴が現実と見なされ、凡俗なるいとなみがあたかも至福であるかのごとくに考えられ、この世そのものが理想的な世界と取られているということは、注目すべきことである。結局、幻夢ではないのである。インドにおいては、物質的具体的なるものを、精神性の光り輝く秘蹟と感ずるこの感じ方は、一方においてタントラ教と男根崇拝とに導くものであるといえると同時に、他方においては、われわれの忘れてならないことであるが、家庭と経験との生きた詩を形成しているのである。
(略)日本の歴史において平安時代として知られている時代――当時西暦七九四年に、奈良から平安、すなわち京都へ首府がふたたび移されたことからかく呼ばれる――において、われわれは密教と呼ばれる仏教発展の一つの新しい波を見出す。その哲学的基礎は、それに禁欲的苦行と肉体的歓楽の崇拝という、二つの極端を包含することを得しめるがごときものである。
この運動は、中国においては、まず南インドの金剛智三蔵(梵名ヴァジラボーディ)とその甥の不空三蔵(梵名アモーガヴァジラ)とによって代表された。このうち後者は、西暦七四一年に、かかる観念を求めてインドへ帰った。これは、仏教がヒンズー教のいっそう大きな流れに混入する合流点と考えることができ、かくしてこの時代におけるインドの影響は、宗教におけると同じく、芸術においても圧倒的である。
インドにおけるこの派の起源は明らかでない。非常に早い頃にさえ、その存在の痕跡と見られるものはあるが、しかしその体系はバラモンの教義と仏教の教義とを結合しようとする要求が起った七、八世紀になってはじめて完成されたもののように思われる。これは、ラーマーヤナが、生活の過度の僧院化に対する抗議として、その最後の形を与えられた時期であった。日本においては、この新しい哲学的立場は、物心の合一と、至高の精神の実現とを、具体的な形で教えてきた法相宗および華厳宗を、一歩進めたものであった。というのは、これら両思想家たちは、その理念を実践において証明しようとする努力において、かれらの先人たちよりも前進していたからである。そしてかれらは、自分たちが釈迦仏陀すらただその一顕現にすぎない至高の神性、毘盧遮那との直接の交わりから生れたものであると主張した。かれらは、あらゆる宗教、あらゆる教えの中に真理を見出すことを目ざし、それらのおのおのは最高なるものに到達するそれぞれ独自の方法であるとした。
瞑想における心と肉体と言葉との合一は、もっともすうようなるものと考えられた。ただし、これら三者のうちいずれの一つでも、その最大の可能性にまで持ちきたされるならば、最高の結果を生むものであるとされてはいた。かくして、かれらは、かれらが心と肉体との間の境界に横たわるものと考えたところの「言葉」、すなわち聖なる呪文を唱えることを、その結果を収めるもっとも重要な道としたのであり、かかるところから、この派は時に「真の言葉」、すなわち真言宗と呼ばれた。
芸術も自然もいまや新しい光に照らされて眺められることになった。すなわち、あらゆるものの中に、没個的普遍者たる毘盧遮那が含まれており、それの至上の実現こそが信者のたずね求むべきものとされたのである。罪業も、この超絶的一体性の見地よりすれば、自己犠牲と同じく神聖なものとなり、最下の悪魔も最高の神と同じように自然に、万神殿の中心となるのである。もっとも微々たる細部も、大事にされ保存されなければならない。目的は生の全体を神性の具現として見ることであるからである。
(略)この時代の芸術作品は、他のいかなる時代にも知られていないような、神々に対するこの強烈な熱意を近親感にみちている。われわれは、すでに、密教の教義が中国に入ってきたのは金剛智三蔵にはじまることを見てきた。この人は七一九年にかの国に来たり、瑜伽に関する経典を翻訳した。そして彼の後をついだのが不空金剛で、彼は七四六年にインドから帰ってきたとき、さらにいっそうの知識をもたらしたのであった。それが日本に入ってきたのも同じ頃で、空海からはじまるが、彼は不空金剛の弟子慧果の教えを受けた人であった。これらの教師たちは、魔法的な力を持つものと考えられ、非常な尊敬を受けたもので、日本仏教における最大の人物の一人である空海は、八三三年に彼が瑜伽の行者として三昧に入った地、高野山上に、いまでも瞑想に耽って坐していると思われている。空海の作品は多数あるが、彼の描いた「真言宗七祖の像」は、京都の東寺に、そこのいくたの貴重な宝物に伍して今日まで伝わり、この大師の偉大な心意の雄渾壮大さを深く偲ばせるものがある。彼の直弟子である実慧、智証などは、すべて中国においてこの教義を研究し、この運動をさらに推し進めた。奈良時代初期の信条も寺院も、大体においてこの新しい勢力に属したが、それはこの派の綜合的見解が、それ以前のいかなる教義とも衝突を起すものでなかったからである。
(『東洋の理想』「平安時代」抜粋、岡倉天心、講談社学術文庫、1986)
花の理想的な愛好者とは、破れた竹垣の前にすわって、野菊と話をかわした陶淵明のような、たそがれに西湖の梅花の間を逍遥しながら、不思議な香りに包まれて我を忘れた林和靖のような、花をその天然のすみかに訪ねる人である。周茂叔は、彼の夢が蓮の夢と混るように、小舟の中で眠ったと伝えられている。この精神こそ、奈良朝でもっとも名高い元首の一人、光明皇后の心を動かしたものであって、次のような歌を詠まれた。「おまえを折れば、花よ、私の手がおまえを汚してしまう。おまえと同じように、私も草原に立ったまま、過去、現在、未来の仏におまえを捧げる」。
しかしながら、あまり感傷的になるのはよそう。奢侈をいましめながらも、気宇を壮大にもとうではないか。老子は言った、「天と地は無慈悲である」(「天地不仁」『老子』第五)。弘法大師は言った「往く、往く、往く、往く、生命の潮流は停ることがない。逝く、逝く、逝く、逝く、死は万物におとずれる」(「生れ生れ生れ生れて生の始めに暗く、死に死に死に死んで死の終りに冥し」『秘蔵宝鑰』)。どこを向いても破壊と面とむかう。上を向いても下を見ても破壊、前も後も破壊。変化こそ唯一の永遠なるものである。ならば、なにゆえに「死」を「生」と同じように歓迎しないのか。生と死はたがいの片われにほかならず、梵天の「夜」と「昼」である。古いものの崩壊によって、再生が可能になる。われわれは容赦しない慈悲の神-「死」を、さまざまな多くの名のもとに崇拝している。拝火教徒が火の中に迎えたのは、「すべてを滅ぼすもの」の影であった。今日でも神道日本がその前にひれふすのは、剣の魂の氷のような純粋主義である。その神秘の火はわれわれの弱点を焼きほろぼし、聖なる剣は欲望の奴隷を斬る。われわれの屍体から天上の希望の不死鳥が翔び立ち、欲望から解き放たれた自由から、より高い人間らしさの自覚が生まれる。
花を切り、その手足を曲げることによって、世界観を昂める新しい型を展開させることができるならば、そうしてもよいではないか。われわれが花に求めるのは、美にたいするわれわれの奉仕に加わってもらうだけのことである。われわれは「純粋」と「簡素」に身を捧げることによって、この行為の償いをしよう。こういう論理で、茶人たちは生け花の法を定めたのである。
(『茶の本(英文収録)』「花」抜粋、岡倉天心、講談社学術文庫、1994)
【関連サイト】
【参考文献】
★『The ideals of East with special reference to the art of Japan』(岡倉天心、ジョン・マレー書店(ロンドン)、1903年)、日本誤訳『東洋の理想』(講談社学術文庫、1986年)
★『The awakening of Japan』(岡倉天心、センチュリー社(ニューヨーク)、ジョン・マレー書店、1904年)、日本誤訳『日本の目ざめ』
★『THE BOOK OF TEA』(岡倉天心、フォックス・ダフィールド社(ニューヨーク)、1906年)、日本誤訳『茶の本』(村岡博訳、岩波文庫)、『茶の本(英文収録)』(桶谷秀昭訳、講談社学術文庫、1994年)
★『岡倉天心全集』(平凡社、1980年)
★『岡倉天心-日本文化と世界戦略』(ワタリウム美術館編、平凡社、2005年)
★『茶の本の100年-岡倉天心国際シンポジウム』(松岡正剛・磯崎新・熊倉功夫ほか、小学館スクウェア、2007年)