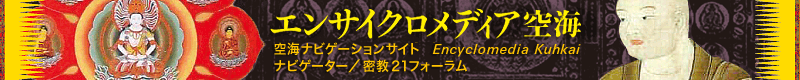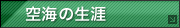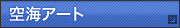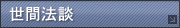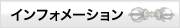宇多天皇は出家ののち、仁和寺伽藍の西南に「御室」という僧坊を建て、そこに住んだので仁和寺は別名「御室御所」といわれる。その旧地にはいま「仁和寺御殿」といわれる御所風の建物が建っている。
仁和寺は伝統として皇族や貴族の帰依や庇護を受け、明治期まで皇子や皇族方が門跡として住持をつとめた。江戸期寛永年間に京の旧御所が建て替えられた際、紫宸殿・清涼殿・常御殿などがこの仁和寺に下賜されている。今の金堂は旧紫宸殿の建物である。
旧清涼殿の用材を使って建てられたという御影堂には、真言宗の本山らしく弘法大師の像が祀られている。大きな総門をくぐると左手に本坊がある。ここに旧常御殿を移築したのだが、明治時代に焼失し大正初期までに再建された。「仁和寺御殿」である。
 |
 |
 |
そもそも、空海亡き後の高野山の経営を任された真然(空海の甥)が、師である東寺の真雅(空海の弟)から東寺の経蔵にあって「長者」以外は閲覧できない不文律にあった『三十帖策子』を借覧し、それを高野山にもち出して返さなかったことが事のはじまりである。
その後、真然の孫弟子の無空が高野山座主の時、東寺長者であった観賢が院宣をもってその返還を迫ったため、無空は延喜15年(915)近しい弟子らとともに高野山を離れるのだが、山に残った弟子らは返還を拒んだ。やむなく観賢は藤原仲平(藤原基経の三男、姉は宇多天皇の夫人、妹は醍醐天皇の皇后)の力を借り、東寺に取り戻した。その際に朝廷から「策子筥」が贈られている。
ところが東寺に宝物として厳重に保管されていた『三十帖策子』を、源氏平家相争う合戦もクライマックスの文治2年(1186)、仁和寺の守覚法親王が借覧して返却をしないまま今に至っている。まことに紆余曲折の珍宝といえる。
「策子筥」とは正しくは「宝相華迦陵頻伽蒔絵冊子箱(ほうそうげ・かりょうびんが・まきえ・さっしばこ)」といい、ふたの真ん中に「納真言根本阿闍梨空海入唐求得法文冊子之筥」の銘がある。金粉・銀粉を淡く蒔いた黒漆塗りの地に宝相華・瑞雲・鳥・蝶・迦陵頻伽(極楽に住む想像上の鳥)が左右に金・銀の研ぎ出し蒔絵で描かれている。
この『三十帖策子』には、空海が長安で梵字・悉曇つまりサンスクリット語を修得した時の師といわれる般若三蔵が訳出したばかりの『四十華厳』が第二帖に収められているほか、顕密両教の経典・儀軌が多数記録されているが、私はここで意図して梵字・悉曇に関する記述の端々から推し量れる空海渡唐の動機についてふれてみたいと思う。
夢告に従い、大和久米寺の東塔の下に『大日経』を発見し、経初の「住心品」第一は読解によってわかったのだが、「具縁品」第二以下の実修部分にあたるところは師資相承の秘伝のためよくわからなかった。ために空海は、唐の長安で密法の然るべき師に直接会いそれを教授してもらうために命がけの渡唐を決心した、という話は『御遺告』にもとづく今日でも有力な空海渡唐の動機話であるが、私にはもはやおもしろくない。
華厳経あるいは華厳思想への強い関心を空海渡唐の理由にあげる人もいる。たしかに空海は、東大寺で『八十華厳』や『六十華厳』を比較対照しながら徹底して修めたにちがいない。法蔵の『(華厳経)探玄記』や『(華厳)五教章』をそのわきに置いて何度も熟読したであろう。いわゆる空白の七年、空海は東大寺の学僧に従い相当深く華厳思想の研究をしていたと思ってさしつかえない。そして、唐に渡り、『四十華厳』を訳出した般若三蔵のもとで『四十華厳』のほか澄観の「四種法界」説も聞いた。しかし、どうも空海にはそれで満足した形跡がない。
当時遣唐使船がとっていた航路は危険度の高い東シナ海横断航路で、佐伯今毛人が遣唐大使に任じられながらとうとう仮病まで使って辞退に及び、その代理が海の藻くずとなったことは有名な話である。空海にとって華厳はそれほどに命がけのものであっただろうか。
また、「請来目録」には『大日経』の名がなく『金剛頂経』系の経軌類が数多くあったことから、空海渡唐の動機は、当時の日本ではその全容がわからなかった密典で、しかも『大日経』よりも新しい『金剛頂経』への強い関心だった、という説もある。しかしこれには、いつどこで『金剛頂経』を空海が知ったか、その証左が明らかにされていないため説得力に乏しい。
ところで私は、空海渡唐の動機を「虚しく往ひて実ちて帰る」と両立させて考えている。その観点から、梵字・悉曇すなわちサンスクリットの修得と真言・陀羅尼の勉強、そしてそれをもとにした儀軌類の理解や作法の伝授に至る期待こそが渡唐の動機の一番であった、と言うことに躊躇しない。
あの時代に東シナ海を渡るリスクを思うと、「長安へ渡らなければ、どうしても解決しない」というせっぱつまった動機がなければなるまい。この点、空海にとってサンスクリットの習得は明確な必然性がある。
幼少から言葉に異能の才をもっていた空海は、雑密の陀羅尼や、求聞持法の際の虚空蔵菩薩の真言などから、言霊言語としてのサンスクリット、梵字としてのサンスクリット、悉曇としてのサンスクリットを意識し、また真言・陀羅尼の言葉の意味やイメージやそれらを多用する行法、とくにそれが行者と仏とが一体になる大事な秘儀のカギをもにぎっていることについて強い関心をもちながらも、おそらくよくわからずに悶々としていたのではないか。
また、サンスクリットの修得は唐の長安にいる然るべき師について習わらなければならないこと、サンスクリットができなければ密教の言語哲学的本質が会得できないことも察していたにちがいない。だから、空白の七年の間空海は大安寺に出入りする渡来僧をつかまえては悉曇・梵字・真言・陀羅尼を少しづつでも学び、不首尾ながら多少の参考文献を手に入れ、読み・書きのほか唐語や和語への変換を徹底して習ったのではないだろうか。しかし、これがきちんと会得できなければ自分が向おうとしている密教世界が不備に終る、そういう危機感やあせりがつのるばかりであったと思う。
だから、長安における空海のサンスクリットの勉強は、日に夜を徹して行われたと思われる。たった2年足らずであそこまで、と思わせることが『三十帖策子』や後の『声字実相義』に見える。今、大学などで学べるサンスクリットにしても、入門から2年で空海のレベルに達するのは無理である。空海とてさすがにサンスクリットには時間がかかったはずで、空白の七年はちょうどよい時間である。
しかし般若三蔵らの特訓によって空海のサンスクリットの力は急成長し、意外にも破天荒な結果を招来した。青龍寺の恵果和尚に会ったとたん「お前を久しく待っていた、すぐ私の密法をすべて授けるから、これを東国(日本)に弘めなさい」ということになった。恵果は言った通り、空海を伝法潅頂の壇に入れ次々と金胎両部の大法を授けた。自らの密教を付法する継承者は、金胎両部の大法を即座に理解できる根機に恵まれていなければならなかった。その象徴は、真言の発音からその意味やイメージをインド僧並みに解するということである。秘密語たる真言・陀羅尼の伝授には、発音すればその意味がすぐわかるサンスクリット語学力がなければならなかったのである。空海のサンスクリットの実力は、般若三蔵から聞いて知っていたであろう。恵果のもとにいた幾千の弟子たちのサンスクリット語学力を凌いでいたにちがいない。だから、恵果は迷うことなく空海をえらんだのである。
『三十帖策子』のなかに、梵字・悉曇にかかわる資料がある。諸処、行外に空海の書き入れ(赤字)がある。それらを注意深く見ていくと空海のサンスクリット力のレベルが見えてくる。それは、相当な実力がなければ書けない注記である。さらに、『声字実相義』のサンスクリット複合語(六離合釈)の正確な捉え方や、その概念をメタファーにして声字とのかかわりを説く発想からしても、並々ならぬものがうかがえる。
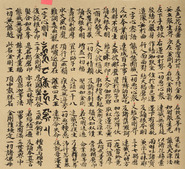 |
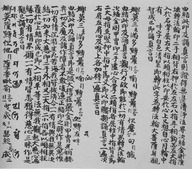 |