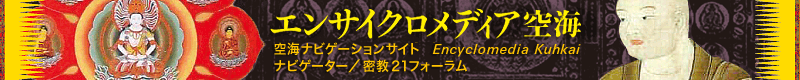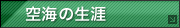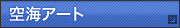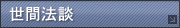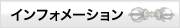◆親鸞の布教の不徹底さ
親鸞の苦悩は、世俗化した叡山を嫌う彼の潔癖性が、同じく世俗の煩悩をもつ自己を見つめるところから発しており、阿弥陀仏にすがったのは、煩悩を克服できない自己救済からであった。浄土教は梅原猛がいうように、個人の、つまり「私にとっての仏教」であるならば、自己の信仰が確立した段階で問題は解決したはずである。しかしここで自信を得たのか、親鸞はこれより布教活動に奔走するのである。関東一帯に親鸞が布教活動を行っていたのは、親鸞四十二歳の時から約二十年間であったらしい。この間、彼は多くの門徒をつくったばかりでなく、『教行信証』の執筆も手がけている。
『教行信証』は親鸞の信仰を理論化したもので浄土真宗の教理である。親鸞が布教活動に立ち上がったのは、大乗仏教の中の、わけても法華一乗の比叡山で学んだためであろう。『法華経』の眼目は菩薩行である。親鸞の主著『教行信証』には、彼の主張する菩薩の利他行の論理が二種回向として理論化されている。常陸の国で情熱的に布教した親鸞は、もっとも充実した時を過ごしていたにちがいない。
だが、私は親鸞の真意は必ずしも門徒に正しく伝わったとは思えない。その理由こそが、私のいう親鸞の、人としてのわかりにくさにあったように思うのだ。おそらく彼のこの資質が、後々浄土真宗の跡目相続争いや、財産や門徒の取り合いや破門など、教団内部の骨肉の争いにもつながったのではないかと思う。親鸞のもっとも望まなかったことではあるが、腹違いをあわせて七人の子をなしたことによって、浄土真宗の血脈争いや本家争いが起こったとしても、結局は自分の蒔いた種である。彼らが異説、邪宗を唱えたのも、やはり、親鸞の生き方のわかりにくさも一因ではなかったか。
そう思う理由の一つが、彼が六十歳を過ぎたころ突然常陸を離れて京都に帰ったことである。親鸞は妻や弟子たちと別れて飄然と都に帰っていった。門徒からすれば教祖が理由もなく信者を置き去りにして消えたのである。どうして親鸞は東国を去ったのか。これについても現在定かなことはわかっていない。そのころ関東においても盛んになった念仏弾圧のためとか、門人たちの信仰に愛想をつかしたとか、いろいろな説は語られるが真相は不明である。親鸞は思い立ったら決然と行動に移すが、内面が見えにくいため行動に謎が多い。
もし念仏弾圧なら、それを避けずに戦うべきである。問題解決の知恵を出すべきである。空海ならおそらくそのようにいうだろう。もし門徒の信仰に愛想をつかしたというなら、それは自分の責任である。布教したのは自分自身である、常陸の国に留まって、正しく門徒たちを導きなさい。それが伝道者の責任である。空海ならきっとそういうだろう。
梅原はしかしこのときの親鸞の心の中の悲しみに眼差しを向ける。『教行信証』にある「悲しきかな愚禿鸞、愛欲の広海に沈殿し、名利の太山に迷惑し」という言葉に、自己の心にある愛欲と名利の心を悲しげに凝視する親鸞を見る。だが私はこの告白から、親鸞がなぜ最後まで僧名を捨てなかったかわかったような気がした。もしかするとそれは、自分にも僧としての名利心があったのではないか。そのためにはたとえ愚禿であっても僧侶親鸞でなければならない。おそらく親鸞は密かに気づいていたはずである。あれほど厳しい内省の人である。かすかに残るそういう自分の名利心を悲しげに見つめていたのだろう。
愛欲と名利は人間にとって業のようなものである。そしてこの二つの業が親鸞を苦しめたとき、彼はこれを受け入れつつ、阿弥陀如来に業深い自己の救済を願った。梅原は親鸞の中のそういう悲しみを見る。だがそれだけでなく、梅原の鋭さはそこに宗教の本質を見る。親鸞からこの業の悲しみを取り外すとき、それは肉食妻帯の肯定どころか、肉食妻帯の賛美になる。悪人の救済どころか、悪行の肯定ともなるとした指摘である。
梅原はいう。「これは、むしろ宗教の名におけるあらゆる倫理の否定となる。親鸞は女を抱いてよいという。ではなぜ多くの女を抱いてはいけないのか。親鸞は肉を食べてよいという。ではなぜ殺人や、窃盗をしてはいけないのか。」実際、親鸞が常陸にいたとき、善乗坊という弟子がそういう教えを説いたが、親鸞は彼を遠ざけたという。きっとうんざりしたのだろう。愛想をつかしたのかもしれない。
しかし私は、このような誤解のもとは、やはり親鸞の倫理の否定にあったのではないかと思うのだ。彼の純粋だが逆説的な説法が果たして門徒に正しく伝わっていたか。悪人こそ極楽往生できるという教えによって、この頃、すすんで悪行をはたらく者が横行するという社会風潮が広がった。
法然は学なき人々に念仏易行を説いた。しかし彼自身は学者であり、一生不犯の高潔な清僧であった。それでは悪人の味方になりきっていない。弱者の側に立っていない。親鸞はここに一つの矛盾を感じたのであろう。彼は肉食妻帯によって、法然の教えの不徹底さを超えたつもりだった。しかし今、自ら超えた欲望の解放が、その教えの不徹底さゆえに信徒たちによって再び乗り超えられようとしている。
その考えは間違っている。もし親鸞がそう思ったとしたら、彼らの迷妄な信仰に絶望するより、常陸に留まっても信者を正しく導くべきではないか。空海なら間違いなくそういうだろう。私の知る空海の、清濁まとめて昇華していく統合的な性格からすれば、それ以外は考えられない。
もしも宗教の名における世俗倫理の否定であるならば、辺地の農民を地主の支配に縛りつける倫理的な束縛から解放すべきであろう。そのように解釈した弟子があったとしても不思議ではない。宗教的倫理をかざして領民から搾取する世俗化した大寺院や、朝廷や貴族らの荘園領主の搾取に反逆するなら、権力に対して正面から物申せ、民衆と共に支配者の弾圧と戦え、そのような現実論者が出てきても不思議ではない。
現実を否定して人間の救いがあるはずがない、現実の中にこそ浄土は存在していると考える日蓮が、念仏浄土教を激しく排撃するのは、浄土教のもつこの矛盾を見抜いたからである。親鸞没五十年後、日蓮は法然や親鸞を不戴天の敵と見て、当時日本中で絶大な力をもっていた念仏浄土の教えを敵に回し、これを真っ向から否定した。日蓮は念仏を無間地獄(四箇格言)とまでこき下ろす一方、時の政府(鎌倉幕府)に『法華経』にのっとった政治を行わなければ他国から侵略を受けると、命がけで権力に物申した現実主義者である。
ところが親鸞はそういう実践的な動きも見せぬままに東国を去っている。親鸞が常陸にいた時でさえ、善乗坊のような弟子もいたぐらいだ。宗祖のいなくなった東国では未曽有の混乱が生じた。弟子たちの間では教えの解釈をめぐって、困惑や混乱や、門徒の奪い合いまでも起きた。一方、京の都では、噂に名高い浄土真宗の親鸞上人が京都に戻られた。悪人こそが救われるそうである。そういう本願ぼこり、悪行肯定、悪行礼賛がはびこったのは、起こるべくして起こったことだといえまいか。
◆帰京の謎
さて、親鸞が晩年京に帰った謎について、梅原は、あれほど名利を嫌い山を慕った道元ですら、死ぬ前に「故郷恋し」の一念で京に帰って死んだことを考えると、親鸞にも「故郷恋し」の感情が隠れていたとしても不思議ではないという。出家主義の道元までもがなぜ晩年病をおしてまで都に帰りたがったのか。ひょっとしたら死処(しにどころ)を故郷に求める気持であったかもしれないともいう。梅原は空海の高野山入山についても「死に場所」を想定したが、空海の場合は全く違うだろうという私の見解は先に述べたので繰り返さない。(『空海の統合性(一) 』)
しかし親鸞の場合は梅原の考えに同意したい。道元や親鸞に「故郷恋し」の一念を見るのは、もしかするとそれは、生涯京都で活躍してきた梅原の京都に寄せる心の投影かもしれない。
だが空海には、親鸞のような郷里を恋しがる心情は当てはまらない。空海は少年時代を過ごした父母の故郷(四国讃岐)に帰ってはいない。しかも、大活躍をした京都にさえも帰っていない「吾れ永く山に帰らん」と宣言した通り、法身の里(高野山)で結跏趺坐したまま入定している。
空海にとってこの世の「死に場所」など問題ではなかった。生まれた場所も問題ではない。大日如来こそが彼の故郷であった。つまり空海は、人間は母親の胎盤を借りて宇宙から生まれ宇宙に帰って行くことを自覚しているのである(阿字の子が阿字のふる里立ちいでて、また立ち帰る阿字のふる里)。思想のとおりに生き、そのとおりに生涯を全うしている。そこに矛盾はなく、私にとって空海は実にわかりやすいのだ。
親鸞はなぜ二十年も布教し、多くの門徒を得た常陸をすてて京に帰ったのか。例えば念仏弾圧に抗議するために、朝廷に働きかけるための帰京なら、おそらく門徒衆も納得したであろう。しかし政治的運動をした痕跡はない。といって京都で積極的に布教もしていない。外からはただ故郷で余生をすごすための帰京に見える。
しかし親鸞はただ余生を京都で過ごしていたのではない。実は晩年になっても『教行信証』の後半部分を修正、補強、改訂するために、『大無量寿経』と最後の思索格闘をしていたのだ。だがそこまで理解できるのは後世の親鸞研究者ぐらいであり、当時の門徒にわかるはずもない。
伝統仏教の倫理に逆らい、その罪で天皇を恨むのであれば、京の都よりも草深い越後の貧しい民とともに生きればよいし、あるいは常陸の国の門徒たちと東国で生きるならわかる。なぜ京都に帰りたがるのか。門徒たちはそのように感じたであろう。
私はここに親鸞の屈折した帰属意識を感じるのである。道元もそうであったように、親鸞もまた貴族の出身である。越後の貧しい民でも、東国の荒くれ者の血を引く民衆の出身でもない。天皇に一番近い貴族の出身なのである。だから親鸞はあれほど聖徳太子を慕ったのではないだろうか。
かつて親鸞は、自分の詠んだ歌が後鳥羽上皇に褒められ、桧皮色の小袖を褒美として下賜されたこともあった。流罪という罰を与えた冷たい上皇を憎みつつも、最後は都を恋しがる。ちょうど虐待されている子どもがそれでも母親を求めるように。京都は天皇家の実家である。だが、実家の敷居はまたげない。かといって草の民とも生きられない。ただ怨み続けるしかない。私はここに親鸞の行き場のない孤独を感じる。
だがその孤独は、一方では越後や常陸での説法生活を通して、彼が初めて自覚したものでもあったろう。親鸞は悪人になり切れなかった法然を、肉食妻帯を公言実行することによって乗り越えたつもりでいた。在家の側に立ったつもりで民衆とかかわってきた。無知蒙昧な名主や村落民に念仏を説きまわった。だが彼自身は、民衆そのものになり切れなかったことに気づいていたはずである。彼らは念仏の同胞である。しかし自分とは異質の同胞であった。
村民はことのほか重い強固な存在である。したたかな我欲の群れでもある。教化、啓蒙のおこがましさを親鸞は骨身にしみて体得したはずである。自分は、所詮民衆という他者の根源に関わることはできない貴族の出身なのだ。親鸞は他者との関わりの中で、教化、救済、同化というような布教理念を放棄して、孤独な一人の念仏者に戻ったのではないか。親鸞の帰京の謎を解明する手立ては何もないが、私にはそう思えるのである。
◆信仰の混乱
親鸞は京では目立った布教活動をしていないのだが、東国の門弟たちは親を失った羊のごとく迷い、さまざまな異端、邪説が興っていた。弟子たちは狼狽し、疑問が起きるたびに京の親鸞に問いかける。それへの返事が今残る四十三通の親鸞の書簡である。
親鸞は書簡だけではなく、教団の混乱を収めるために我が子善鸞を東国に送った。だがあろうことか、この善鸞がいっそう事態を紛糾させたのである。自分は親から伝えられた往生の方法を知っている。今まで親鸞やその弟子たちが伝えてきた念仏の道は、真の極楽往生の道ではないといったからである。どうして善鸞が、そのように明らかに父親に背き、父親を裏切る行動に出たのか、これも現在もよくかっていない。この善鸞の行動は、東国の門弟たちにいっそう大きな動揺を与えた。
事実として確かなことは、名代として送った我が子にさえも親鸞の真意が伝わっていなかったか、もしくはあえて背かれたということである。親鸞は最晩年、遂に善鸞を義絶してしまう。我が子すら教化できない教祖が、他者を教化する浄土真宗とはどういうものか。素朴な疑問が湧きあがることがある。
親鸞の家系にはそのような骨肉の争いがときどき起きている。覚如上人(親鸞の末娘である覚信尼の子、覚恵の長男、親鸞の曾孫にあたる)も我が子存覚(長男)を勘当している。それも二度も義絶している。理由は、存覚が父母の追善供養を真宗の大事として考えていたからである。高森顕徹は、「これは先祖の追善供養を徹底排除した親鸞聖人の教えを明らかに破壊するものであり、破門されて当然だ」という。(『歎異抄をひらく』高森顕徹)
しかし親鸞は法然の教えを一生信じて、それを人に伝えていくという信仰の生活を送った人である。自ら教団を作ろうという意思もなかった。だが覚如は本願寺という後の大教団の実質的な創始者なのである。だとすれば、親鸞聖人の教えを継承しなかったことにおいてはどっちもどっちであろう。
『歎異抄』(第五条)に親鸞が先祖供養を否定する言葉がある。「親鸞は父母の孝養のためとて念仏、一返にても申したることいまだ候わず。」と端的に述べられている。覚如は「某(それがし) 閉眼せば賀茂川にいれて魚に与えるべし。」というの親鸞の遺言を『改邪鈔』に載せ、葬式、供養などはもっとも停止(ちょうじ)すべしと書いている。
ところが息子の存覚は、『報恩記』などに「父母の死後は、追善供養を根本とする仏事を大切にして、親の恩に報いるつとめをはたすべし」「追善のつとめには、念仏第一なり」と言い切っている。いったいこの宗門一族はどうなっているのか。しかも今日浄土真宗は盛んに葬儀や法事全般を執り行っている。これは法事を禁じた親鸞聖人や覚如上人の意志に背くことにはならないのか。
今日浄土真宗が説くように、法事に関して、故人の扱い方や霊魂の解釈など、宗教的な理屈はいかようにもつけられようが、それにしても何か布教の不徹底さ、根本的に筋の通らぬものを感じるのである。ちなみに覚如は妻を何度も替えた人だが、そのたびごとにいつも十九歳の女と結婚したそうだ。存覚の日記にはそのような父親、覚如上人の女性関係が書かれている。本願寺中興の祖蓮如も女性関係は盛んだが、女犯の思想だけはリアルに受け継いでいるようだ。
余談はさておいて、話を戻す。
東国の門弟たちは、ほかならぬ親鸞の息子、善鸞のいうことであるから、あるいは善鸞のいうように、親鸞が秘密の法門を隠していたのではないかと疑わしく思ったのであろう。そこで東国の門弟や信者たちはその旨をただそうとはるばる上京してきた。この東国の門弟や信者を前にして、親鸞は、自分は念仏以外の往生の道は知らないと、その理由を縷々語るのである。
『歎異抄』(第二条)に親鸞のこういう言葉がある(後半)。
「自分は法然聖人の念仏を信じた。もし法然聖人に騙されて、念仏したがために地獄に落ちても後悔しない。私は念仏以外に極楽往生する道を知らないからだ。私の信心はそれだけだ。皆さんが念仏を信じるのもいいし、念仏を捨てるのもよし。全く皆さんの自由勝手。みなさんが自分で決めることです。」
親鸞の言葉はそっけない。どこか突き放したような響きさえを感じる。はるばる十か国を命がけで超えてきた門徒衆に対して皆さんの勝手はないだろう。門弟の問いの答えにもなっていない。
だが、親鸞は論理で答えたのではなく心情で答えたともいえる。一人の念仏者として信仰の本質を語っているのだ。浄土教は「私にとっての仏教」であるように、信仰とは神と私の関係である。かけがえのない私を救い摂ってくれる神仏との関係である。それを信じるか否かは他人の支配の及ばざる世界である。だから信仰の道は自分で決め、自分で進む以外にないと当然のことをいったのである。
私は親鸞が「自分を灯り」にして生きよという釈尊の教えを真に理解したのはこの頃ではなかったかと思う。ふつう信仰者というものはこの段階で自己完結するものだが、しかし親鸞が完結していたかはどうも疑わしい。その理由は、彼は、「わが信仰」を「論証」しようとしたからである。それが『教行信証』という生涯を賭けた浄土真宗の教義書づくりであった。
親鸞はこの書の執筆に当たり、膨大な経典をテクストとして読み漁るのである。この辺りの事情は拙論後半の◆『教行信証』にみえる親鸞の矛盾との格闘以下で論じるが、すでに読者は矛盾に気がついていると思う。
『恵信尼文書』の親鸞を思い出してほしい(『空海の統合性(一)』)。彼は経典(学問知識)に頼っている自分に気がつき、名号(南無阿弥陀仏)以外に、何の不足があって経を読もうとするのかと思い返して、以後、経を読むことを止めたと妻に語った。名号すなわち「信」があれば学問知識(自力門)は不要だという、他力信仰の奥義を覚ったはずである。
名号一つが救いであったのなら、それは信仰者にとっての自己完結である。信仰という契機を感得し、一度学問知識を捨てた親鸞がなぜ再び諸々の経典を読もうとするのか。考えられるのは、親鸞は本当に「自分を灯り」に生きていたのかという疑問。もう一つは浄土真宗の教祖として親鸞なりの責任をとろうとしたか、あるいは著書をまとめることよって、自己に対する教義的決着をつけるためである。
だがその『教行信証』は、教義書というよりも膨大な経典の集合体という感が強い。そのような特異な著書のありようが、別な角度から見れば、私には学び続けなければならない親鸞の、宿痾のような資質が感じられ、また、生涯『教行信証』でわが信仰を論証しなければならないこと自体が、心の底の葛藤にさえ見えてくるのである。
釈尊の晩年、釈尊が三か月後に自分は涅槃に入る(入滅する)と予言した時、高弟の阿難は泣きながら訴えた。師がこの世からいなくなったら、自分たちはこれから何を拠り処にしていけばいいのかと問うた。それに対して釈尊の場合は正面から答えている。それが有名な自灯明、法灯明の教えである。釈尊は人に依るな、自らに依れ、法(真理)を依りどころにせよと教えた。「自己を島として住し、自己を帰依処として住せよ、他を帰依処とせざれ。法を島として住し、法を帰依処として住せよ、他を帰依処とせざれ。」(『涅槃経』)
つまり、いわば経典ばかり拠り所にせず、宇宙の真理と自分の関係を拠り所にせよときちんと答えている。このように釈尊は弟子の問いに対して、心情で答えるのではなく論理的に答えているのだ。私にはこういう文脈の方がわかりやすいのである。とにかく釈尊はたとえ愚問かと思われるような問いに対しても、懇切丁寧に答える人である。法を説くとき有効に方便は使うが、決して誤解を招くような逆説は使っていない。
であれば、親鸞のあの二十年間の布教活動は何だったのか、他者の心に教えを説いて回りながら、親鸞の教えを信じた門徒たちの迷いに対して、まるで他人事のように信じるも信じないもあなたがたの勝手だという。梅原はこれを、親鸞が強い言葉を語りながら、その信仰を他人に押しつけない、自由で確信にあふれた信仰の言葉だと評価する。親鸞自身にとってはそうだったのかもしれない。心情倫理においては梅原のいうとおりである。だが私は、これを個人的心情の問題としてすませるには疑問を感じる。
親鸞は多くの門弟に布教した。すなわち物理的(親鸞は信者の集まる場所を寺といわず道場という)にも、精神的にも、他者との交わりの中で阿弥陀の教えを説いたのである。それは、大乗仏教が他者との関わりを抜きにはありえないことを、親鸞自身が十分にわかっていたからだ。であれば、それは布教という名の社会的活動にあたる。
ならば社会性・公共性が問われることもわかっていたはずだ。当然そこに社会的責任性が生じるのは近代の法哲学の考え方でもある。時代は異なるにせよ、マックスウエーバーの責任倫理(成果主義=政治)と心情倫理(心情の純粋さ=宗教)を思い出すのである。親鸞にはこの二律背反をいっしょくたにして、責任倫理に対して心情倫理で答えるというような、ちぐはぐなものを感じるのだ。
『歎異抄』(第六条)に親鸞のこのような言葉が残されている(意訳)。
「もっぱら他力念仏をする仲間の中で、あいつはおれの弟子だ、こいつは他人の弟子だとかいって弟子を取り合いして争うことがあるようだが、もってのほかのことである。親鸞には、弟子など一人もいない。そうではないか。私自身の思い計らいで念仏を称えるようにしたのなら我が弟子ともいえよう。だが、まったく弥陀のお力によって念仏する人を、我が弟子というのは極めて傲慢不遜である」と語ったとある。この中の「親鸞は弟子一人(いちにん)ももたず候」という言葉は結構有名で、親鸞の布教姿勢の表れであると評価されるところである。
だが、親鸞に多くの弟子がいたことは歴史上の事実である。例えば高森顕徹は「『親鸞聖人門侶交名牒』や他の資料を重ねると、親鸞から親しく教えを受けた門弟は、六、七十名あったことが確認されている」という。ではなぜ「親鸞には、弟子など一人もいない」といったのか。これを高森は「それは聖人自身の、深い自覚以外なかったのである」という。「聖人はかの人々を、決して、わが弟子とは思われなかった。というよりも、毛頭、思えなかったからであろう」という。
おそらく親鸞自身の思いはそうであろう。しかし門弟からすれば勝手な言い草である。念仏は弥陀の力によっていただくものであり、おのずとはたらくものなら、法然や親鸞が教えずとも民衆の口から自然にほとばしるものではないか。一体だれがナムアミダブツを称えよと教えたのだ。それは宗祖であろう。その段階で門徒は弟子であると自覚したとしても責められるべきものではない。まるで宗祖に梯子をはずされたような心境であったろうと思う。
よしんば弟子など一人もいないというのが親鸞聖人の真意であるというのなら、あの大教団は何事か。それも親鸞没後、代々一族中心による世襲の教団経営は、親鸞聖人の真意を受け継いだことになるのだろうか。親鸞には弟子、門徒は一人もいなかったのではないか。とにかく親鸞教にはつじつまの合わぬものを感じることが多いのである。
政治は結果責任である。政策を実現すること、そしてその政策が国民のためになることが政治の責任倫理であり、政治家の人間性が一義的な問題とはされない。人間性がいかに清廉潔白であっても、政治力のない政治家に価値はない。宗教家は逆である。人間性が問われる。結果の成否より宗教者の心情の純粋さ、宗教的倫理性そのものに価値をおく。いかに崇高な教えであっても、布教者の人柄や生き方に矛盾や疑問を感じたまま、その人や教団の語る言葉だけを切り離して信仰できるものだろうか。
『慚愧和讃』では親鸞はこのように告白する。
是非しらずで
邪正もわからぬこの身なり
小慈小悲もなけれども
名利に人師をこのむなり
是非の正邪もわきまえぬ、わずかな慈悲もなく、上に立つ値などない身でありながら、師とかしずかれたい名誉欲と利益欲しかない親鸞、まことに情けない限りであるという意味である。
これを高森は名利を離れて動けない深い懺悔であるという。たしかにそのとおりである。親鸞は懺悔が最後に人を救いに導く契機であることを知っていた。しかもそれは発露(告白)しなければならないことも知っていた。しかし心から懺悔を発露ができる相手は唯一仏陀のみであろう。それほど懺愧の念は心の中で独り噛みしめる問題であって、『慚愧和讃』まで著わしてことあからさまに公表する類のものなのか。
弟子一人ももたないという自覚と、師と仰がれたい気持ちに矛盾はないか。むしろ多くの門弟に慕われたことを素直に感謝すべきで、懺悔する暇があれば師として、いや念仏仲間というなら、仲間のリーダーとしての責任を果たすべきではないか。自分にその資質のあるなしは仏に問いかける別問題である。
五木寛之が、「仏の教えは河原の石、つぶてのような民草のためにある」というのも、親鸞の布教に影響されたつぶてのような民草の立場の代弁なのである。つまり布教を前提にしているからである。梅原もまた、親鸞は信仰を他人に押しつけないといいながらも情熱的な布教活動を認めている。
ただ梅原の眼は、親鸞の信仰という内実にその価値を認めているのであり、五木の親鸞理解とは異なる。五木のような文化人の親鸞像の原型は、おそらく服部之総(はっとりしそう)あたりの影響ではないかと思う。つまり信者を貧農の民草に限定する見方である。
梅原は、親鸞の信者を貧農のみに見出そうとする服部之総以来の見方は、宗教というものをゆがんだ眼鏡で見るものだと指摘している。私も親鸞の信仰の内実よりも、信者層を特定化して、そこに階級性を付加する考え方は、親鸞を虚像の革命家に仕立てることになると思う。
親鸞自身は農民と共に権力闘争や階級闘争をした事実はない。どこまでも信仰による極楽往生を説いて、旧仏教と宗教上の問題闘争をした人である。第一、唯物論者が霊魂の再生を説く浄土真宗に関心をもつことは自己矛盾も甚だしい。親鸞の思想に強烈なアナーキズムの臭いを嗅ぎとるのは勝手だが、信仰の内実を欠いた親鸞像はもはや親鸞とはいえない。(服部之総1901~1956はマルクス主義歴史学者・歴史哲学者で、親鸞や蓮如に関する著作がある)。
親鸞は、人間にはどろどろとした醜い心があることを肉食妻帯によって露呈した。道徳は仮面である。倫理は偽善である。だが、叡山の慈円にとっては、偽善は最後の道徳のとりでであった。仮面でもよい。その仮面を捨てたら人間は野獣にかえる。仮面をかぶれ。道徳という虚偽の仮面をかぶることによって、人間社会の倫理はかろうじて保たれる。だが、叡山の堕落を嫌悪した親鸞にとって、それは二重に仮面をかぶることに思えたのであろう。悔いることも恥じることもない、無懺無愧の集団に見えたのである。
だから自分は僧の倫理を破った。しかしそれは、あくまでも自己の煩悩という個人的な問題から発露したもので、一般性をもって宣説すべき思想なのだろうか。親鸞は僧であっても愛欲を肯定した。ではなぜ多くの女を抱いてはいけないのか。蓮如は五人の妻と関係をもち、二十七人の子どもを産ませた。親鸞聖人は複数の妻を認めた。教祖様の記録を破って何が悪かろう!
真宗大谷派の宗務総長を務めた暁烏敏(あけがらす はや・1877~1954)などは、歳をとって目が見えなくなっても、まだ女好きがやめられなくて、あっちこっちに若い女がいた。それで懺悔し、阿弥陀様にわれらごとき煩悩多き者をお助け下さいと、熱い涙を流す。「それは甘えだ」と梅原に指摘されてもしかたあるまい(『宗教の自殺』梅原猛・山折哲雄共著)。まことに親鸞の思想の都合のいい部分を継承する人々である。門外漢からはそのように見えるのだから仕方がない。
天皇に反抗した浄土真宗が、親鸞な亡き後、なぜ天皇のお膝元に総本山を置くのか。これも合点がいかない。西本願寺、東本願寺は京都のど真ん中だ。権力の中心地である。無論、宗門内での本家争いや離合集散など複雑ないきさつは承知している。だが、天皇に反抗した親鸞教にあれほどシンパシーを感じるリベラル左翼文化人は、ここに矛盾を感じないのだろうか。
空海は確かに京都で大活躍をした。天皇に最も近い体制側の人間であったともいえる。しかし空海は京が恋しいからでも、華やかな京都を好んだからでもない。大日如来の密厳国土建設という明確な活動目的をもっていたからである。東寺を教王護国寺と改名したのもそういう大乗の使命感からであった。仏法を守る僧侶として、国家国民の救済と安寧という使命を果たすために、彼は一見、相矛盾するようにも見える八面六臂の活躍をした。
『空海の統合性(一)』の冒頭で列挙したように、その姿が人々には万華鏡のように映るが、空海の思想と行動は常に一貫し、実社会とも連動している。国家と民衆に尽くした事業の数々は今さら列挙するまでもなかろう。知らない人は『沙門空海』(渡辺照宏・宮坂宥勝・ちくま学芸文庫)を読むことをおすすめする。
空海の生涯をつぶさに見ると、彼がいかに自己愛的な煩悩や名利心から遠い存在であったかがわかる。あれほど権力の中枢(王法)に近づいた空海が、政治権力から遥か遠く離れた高野の山岳地に本拠地を置いたことはその証である。つまり仏法にスタンスを置く僧侶として、空海が全くブレていないことの証左である。
◆親鸞の慈悲心と伝統仏教の慈悲
空海も、その百年前の行基もそうであるが、旧仏教の祖師たちは常に民衆と連動していた。それは大乗仏教の慈悲を実践しようとしていたからである。菩薩道の実践である。菩薩の徳目は六つの行(六波羅蜜)であり、その第一は布施行である。布施とは他者に施し与えるということである。くだいていえば世のため人のために尽くすということだ。
とはいえ、菩薩のような高僧でなければできないことではない。布施の中にはだれにでもできることが書かれている。赤ん坊ですら、母親に抱かれてニコッと笑ったとき、母親に至上の幸福感を与えているのである。他者に笑顔を与える。これを布施の中の和願施というが、優しい言葉をかける言辞施など、日常凡夫にもできることはいくらでもある。伝統仏教は慈悲というものをそのようにとらえる。
親鸞は慈悲をどのように考えていたか。『歎異抄』(第四条)に親鸞の言葉が記録されている(本文意訳・高森顕徹)。≪≫内は私の心中の思い
「慈悲といっても、聖道仏教と浄土仏教では違いがある。聖道仏教の慈悲とは、一切のものを憐み、いとおしみ、大切に守り育てることをいう。≪そのとおり≫
しかしながら、どんなに努めても、思うように満足に助けることはほとんどありえないのである。≪当然だろう。人間は万能ではない。それでもゼロよりはましである≫ それに対して、浄土仏教で教える慈悲とは、はやく弥陀の本願に救われ念仏する身となり、浄土で仏のさとりを開き、大慈大悲心を持って思う存分人々を救うことをいうのである。
≪あの世で大慈大悲心を起こしても遅い。あの世の住人に何ができるというのか≫
この世で、かわいそう、何とかしてやりたいと、どんなに憐れんでも、心底から満足できるように助けることはできないから、聖道の慈悲は、いつも不満足のままで終わってしまう。≪いいじゃないか、この不満足の心があればこそ、人助けに奢ることなく、次はもっと相手の身になって力を尽くそうという反省と向上心につながるのだ≫
されば、弥陀の本願に救われ念仏する身になることのみが、徹底した大慈大悲心なのである、と聖人はおおせになりました。」
ということは、目の前に瀕死の人がいても、念仏する身になることのみが、徹底した大慈大悲心だということになる。瀕死の人に向かってナムアミダブツを称えるとは?・・・解せぬ、私にはどうにも解せぬ。大きな事故にでも遭遇して重傷を負ったとき、傍らで念仏を称えてもらうよりも、さっさと救命措置を施してくれる方がありがたいのではないか。
「四の五のいわずにさっさと救急車を呼べ!」空海なら必ずそういうだろう。真実の慈悲とは何か、聖道門か浄土門か、などという観念論の無意味さを、釈迦は毒矢の喩えで説いているではないか。理屈よりも、現実に民衆のために汗をかいてくれる行基や空海の慈悲心の方がよほどありがたい。
しかし親鸞はここで、神のごとく純粋で完全無欠な愛こそが本当の慈悲だといいたいのである。そのような大慈大悲心を得るために一度あの世で仏にならなければならないというのだ。だから現世の聖道門の慈悲はレベルが低いというのである。これは曇鸞の『浄土論註』で語られる往還廻向に依るものだが、親鸞は、いったい自分が神仏と同等の慈悲がもてないことを恥じているのか。だとすれば、これは謙虚さでも懺悔でもない。傲慢である。
結局、私が親鸞に矛盾を感じるのは、彼が他の力に依ろうとするように見えるからである。つまり自分で考えて、理想を立ててそれに向けて生きるというより、その時々の心情的状況に応じて、問題を克服するために経典などの他の力にすがるように見えるからである。禅定とはまた別の、思考の放棄を感じるのだ。
その第一が僧たる自分の愛欲を、聖徳太子によって自己肯定したことであった。その次が法然にすがったことである。法然の浄土三部経にすがったことである。究極は先師善導(613~681)の選択した「どんな悪人でも浄土に往ける」という『観無量寿経』にすがったことである。そして万人救済の阿弥陀仏(『大無量寿経』)にすがったことである。これが私には、先に行動を起し、あとから理論づけているように映るのである。自己正当化のために、自己の思想を担保する都合の良い経典を探してきては理論づけをする、そのように見えるときがあるのだ。『教行信証』の執筆形跡からもそのことを感じるので、最後に親鸞の代表作について感想を述べたい。
◆『教行信証』にみえる親鸞の矛盾との格闘
親鸞は浄土真宗の教義を『教行信証』に結実した。『教行信証』とは略称で、つぶさには『顯浄土眞實教行證文類』(けんじょうどしんじちきょうぎょうしょうもんるい)という。この『教行信証』は極めて難解である。というのは、経典の引用が多すぎて、梅原猛も何度読んでもほとんど理解できなかったといっている。『教行信証』を全部通読する人がいたらその人は大変根気のいい人で、たいていの人は途中で本を投げ出すという。
読み始めると経典、また経典の引用である。この九割近く経典の引用によってつくられている著書から、親鸞の生の声、独自の思想を読み取ることは至難である。国際日本文化研究センター所長を、初代の梅原猛のあとを継いだ山折哲雄も、この書物を本当に理解するのに半世紀もかかったそうである。このような難物を、とても素人の私に扱いきれるとは思わないが、浅学の謗りを覚悟の上で、これを最終章のつもりで続けたいと思う。
まず、第一にこの書名は何を主張したいのかわからない。山折哲雄によると、例えば空海の代表作『秘密曼荼羅十住心論』の主題は、そのタイトルを読み下せばただちに了解でき、「十住心」という心をテーマに論じられていることが一目瞭然だという。道元の著作『正法眼蔵』(しょうほうげんぞう)も、そこで論じられているのが「正法」という主題であることが、これまた誰の眼にも明らかである。日蓮の代表作『立正安国論』も例外ではない。そこには法華経を押し立てて国家を安んじるという思想(主題)が鮮明にされている。法然の著作『選択本願念仏集』(せんちゃくほんがんねんぶつしゅう)も「われは念仏を選択するのだ」という法然の意志がまぎれもない形で刻み込まれているという。このように、一般的に書名とは作品の主題が明確に表示されるものだ。
しかし『教行信証』は、教・行・信・証という目次の項目を並べたような題名である。何か主題はあるのだが、キーワードのみ提示しておき、ここでは明かさないとでもいうような題名である。序を読めば、確かに親鸞の気持ちでは主題は決まっている。だが、それをどのように導き出し証明するか、ここからがやたらと長い。よくよく読むと、論理の展開上矛盾に突き当たって、あっちこっち彷徨いながら、書きながら考えているようなものを感じる。
この浩瀚な書物は、さまざまな経典を引き合いに出すのだが、読者は方向の見えないままに引っ張りまわされているような気になり、途中でくたびれ果ててしまう。梅原や山折という大先達の道案内がなければ普通の人にはとても読めそうにない。つまりここでも、要旨が大まかにまとまったら筆を執るという行動が先だって、あとで調整するようなものを私は感じるのだ。先に女犯に踏み切って、あとで行動の意味と理屈をつける様な感じである。空海の著作や生き方からはとうてい感じられなかったことである。
ところでそもそも浄土信仰とは何か。浄土思想とは古代インド人が心に描いた理想郷が原点である。彼らはヴェーダに説かれるヤマの楽園、ウパニシャッドにおける梵天の楽土、さらにヒマラヤ山脈の北側のウッタラ(来世)などの楽土の存在を想像していた。いずれも金・銀・瑠璃・水晶でつくられた浴地の蓮華が浮かび,宝樹が生い茂り、すべての欲が満たされ、長寿を保つ美しい理想郷である。
仏教はこの考えを取り入れたようだ。浄土には東方・薬師浄土、南方・釈迦浄土、西方・阿弥陀浄土、北方・弥勒浄土(四方四仏)があると説く。そうのち一番人気が出たのが阿弥陀浄土で、西方十万億土のところに極楽浄土があるというものだ。楽土の極めつきが極楽浄土である。
余談だが、この西方楽土の水平思考が日本では垂直思考にかわって、極楽は天上界に存在することになったように思われる。おそらく日本古来の山岳信仰の影響であろう。亡くなった人の魂が肉体を離れて山に登って行くという表現が『万葉集』の挽歌にもある。その上、戦後のアメリカ文化の影響もあってか、現代人はいよいよ天上界を想像するようである。それはともかく、現代人はほとんどが地獄の反対は天国だという。黒沢明監督の名作も「天国と地獄」である。戦前までの日本の大人はみな「地獄極楽」といったものだ。「地獄天国」などという日本人はいなかった。
ともかく浄土関係の経典が編纂されたのは、釈尊入滅から数百年後だといわれている。よって実際の釈尊が浄土を説いたかは不明であるが、いずれの経典も仏説ということになっているから、親鸞をはじめ、浄土教の伝法者は極楽浄土を釈迦の説だと信じ込んでいる。
考えられることは、インドの既製宗教との折り合いである。釈尊は仏法(仏教という言葉は明治以降の翻訳語)という新しい教えを布教するにおいて、バラモンの伝統思想を全面的に排除するということはしなかった(似たように日本密教も古来の神道を吸収統合している)。釈尊はおそらくある程度取り入れながら説いたであろう。
しかしバラモンの輪廻転生をあえて否定はせぬが、輪廻と業報を結びつける積極的な態度はとっていない。人の価値は生まれや宿業(宿命論)によるものではなく、行為(業)によって決まるのだと説いて、できる限り現世に力点を置くという態度を示した。生まれながらにすべては決まっているという決定論に対して、因と縁と人間の自由意志とによる業のはたらきを説いている。
おそらくヴェーダやウパニシャッドにおける楽園楽土についても、弟子から質問を受けたであろう。経典では舎利子や阿難に対して、のちの浄土思想的な答え方をしているからだ。楽園楽土とは五濁(じょく)や悪道のない荘厳清浄の理想郷であると。つまり仏の世界=覚り・涅槃(浄土)である。私は、それは現世における解脱を意味しており、あえて死後の世界を指していたとは思えない。
いずれにせよ五世紀半ばまでに信仰の基礎となる浄土三部経が中国で訳出される。その後六世紀、曇鸞(476~542)が浄土信仰を説き、ついで道綽(562~645)に受け継がれ、善導(613~681)によって中国浄土教は大成される。日本では、上代における浄土信仰としては弥勒の兜率天上生の信仰が盛んで、それと並んで奈良時代にようやく阿弥陀に関する造像などが行われて阿弥陀信仰が広がった。
ちなみに平安時代は密教が花開いた時代ではあったが、一方では浄土への信仰がパラレルに浸透していた。しかしそれはまだ奈良時代の浄土図に見られるような観想的・情緒的な浄土信仰であり、地獄を強調して極楽と対置するような、鎌倉時代の生々しい浄土信仰とは質的に相違がある。時代背景の違いであろう。
平安時代の中頃、源信が地獄の思想を含む『往生要集』を著わし、厭うべき六道の穢土を詳説した。極楽浄土礼賛の源信以来、末法思想におおわれた中世からは日本の浄土教として広く隆盛した。人々が切実に死後の世界に関心を持つようになって、日本仏教は一気に浄土信仰に収斂し、その布教過程において、浄土宗における「行」の簡便化が進行した。
源信は極楽往生の道は念仏をおいて他にないが、極楽浄土には真実と方便の二種があり、機根(資質)に応じて区別されているという。しかし法然は機根には関係なく、ひたすら念仏を称えればだれでも極楽往生できると説いた。一般に専修念仏(せんじゅねんぶつ)といわれる。しかもその念仏はたった十回称えればいいのだ。
親鸞に至ってはその念仏さえも、一度称えるだけでいい、いや、正確にいえば、念仏しようと思い立っただけですでに阿弥陀に救い摂られていると、まさに「行」の簡便化の極に達している。いや「行」の簡便化というのも不正確である。親鸞は念仏を「行」とすら考えていない。彼は阿弥陀の本願を信じるか否かに往生の基準を置いているのである。すべての「行」を放棄して全身全霊阿弥陀にゆだねる「信」に基点を置く。この信心がもてるか否かが、いわば浄土真宗の(機根)なのである。したがって親鸞は、極楽往生には「信」という(機根)によって行き先に本物と偽物の区別があると、ある意味源信に回帰したようなことを主張するのである。
法然の教えでは、念仏さえ称えれば、たしかにこの世で地獄に落ちる人間は一人もいなくなる。地獄の閻魔が失業するならこの世はやりたい放題になる。だから親鸞はせめて極楽にランクをつけなければならないと考えたようである。これが真仏土と化真土の思想である。
死というものを身近に感じなくなった現代人からすれば、どうでもいいような観念論に思えるが、末法世を恐れるこの時代の仏者は、このような死後世界の判釈を切実に議論していたのである。人を殺すことが習いである武士の出現によって、当時の人々は生きること自体が死と隣り合わせであった。
極楽の実在を信じない現代人に向かって、あるとき浄土真宗の坊さんの、「親鸞聖人のいわれるお浄土とは、私たちの心の中のことなのです」という法話を聞いたことがある。これはまったく親鸞の浄土真宗を語っていない。いかにも死を忘れた現代人向けの説教である。
『歎異抄』を愛好する戦後知識人は、この書物には、死後世界が語られないからであろうと思われる。田辺元は西田幾多郎が禅を中心に哲学体系を打ち立てたのに対し、親鸞の浄土真宗の思想を中心に新しい哲学を打ち立てた。それが『懺悔の哲学』である。
そこで往相廻向、還相廻向を説いているが、いかにも現世的な解釈である。還相廻向とは死んでから生まれ変わってこの世に戻り、衆生を救うということであるのに対して、彼は、念仏によって生きたまま悟りを開いた人間が、また衆生のところに戻ってきて衆生を救うという。全部、現世のこととして解釈している。つまりお浄土は生きた人間の心の中にあることになる。
田辺はおそらく『歎異抄』(第一条)の「弥陀の誓願不思議に助けまひらせて往生をば遂ぐなりと信じて、念仏申さんと思い立つ心のおこるとき、すなわち摂取不捨の利益にあずけしめたまふなり」という親鸞の言葉を、「不思議な阿弥陀如来の誓願の力によって救われ、弥陀の極楽浄土へ往くことができると信じて、念仏を称えようと思い立つ心の起こった時、摂政(おさ)め取って捨てられぬ絶対の幸福に生かされる。」というように読み取ったのであろう。摂取不捨の利益とは絶対の幸福を指す。
つまり弥陀の救いはあくまで「今」であり、幸福を味わう現世であると。だから先の真宗の坊さんも、お浄土は私たちの心の中にあるというのだろう。しかしこれは浄土教の前提を無視している。弥陀の誓願によって、死後は必ず極楽に往けると保証されているから、現世も大安心で幸福に生きられるのである。死後の極楽の実在を抜きにしては成り立たない信仰なのである。もし浄土の視点を現世にすれば、これは真言密教になる。
繰り返すが、法然も親鸞も、死後の極楽浄土の実在を疑うべくもなく信じていた。これを抜きにしては親鸞の思想も浄土信仰も語ることはできない。当時の人々は極楽の実在を信じたからこそ救われたのである。現に法然は何度も極楽から生まれ変わって舞い戻ってきた人である。自分は極楽行きには慣れているから行きやすくなったと親鸞に語っているくらいだ。法然からそのように聞いたと親鸞は証言している。(『浄土和讃』)
すでに師匠は極楽行き列車のホームでも迷わない旅のベテランなのだ。だからこそ親鸞は、摂取不捨の利益にあずけしめたまふなりと言いつつも、自分のような凡愚悪人も、果たして本当に往生できるかという問題に切実に悩むのである。
ただ空海は、極楽のランクづけとか、行き方の方法論とかいった神学論争を「戯論」としてあっさりと退けるところがある。このあたりも、現代人にとって空海の方がわかりやすいところがある。空海は決して死後世界を否定しているのではないが、神学論争(経典・論書)に自縄自縛されてはならないというのである。空海は幻想のない人である。行き過ぎた思い込みは、自らを不安と恐怖に追い込むとしてこんなことをいっている。「無知のものは夜叉を画きて、みずから画き還つてみずから怖る。」(『五部陀羅尼問答偈讃宗秘論』)現代の認知心理学にも通じるところがある。
親鸞は自らの救済(往生)の可否に不安を抱いたが、密教では人はみな生まれたときから本質的に救われていると考える。無論悪人も同様である。顕教で異教の神とされたバラモンの神々も、密教では大日如来の世界で昇華されて仏の守護神となっている。大日如来とは凡愚も悪人も畜生も修羅も救い摂るオールマイティーの世界のことである。
胎蔵曼荼羅図を見るがよい。一番隅っこには死体を食らう餓鬼まで大日如来の視野に収まっている。親鸞のように、自分は悪人だというほど自省的な人間が救われないわけがないのだ。阿弥陀仏の万人救済の誓願は、主尊大日如来の心であることは密教僧なら常識である、親鸞は密教のこの奥義を、延暦寺の台密でどのように学んできたのだろう。私は親鸞が本質的に悩む必要のないことを悩んでいるように見えるときがある。親鸞も二十年の叡山体験という自力修行を経た後で、はじめて他力の世界が開けてきたのだと思う。なら密教の奥義についてどう思うか聞いてみたい気がする。
さて、『教行信証』は「教の巻」「行の巻」「信の巻」「証の巻」とあり、このあと、「真仏土の巻」、「仮真土の巻」という二巻が追加され、全体で六巻である。一巻から入ると結論にたどり着くまでにほとんどの人が音をあげるだろう。ほとんどが経典の引用で、親鸞は自分の抱えた教義的問題の矛盾を、さまざまな経典の言葉を拾い集めてその整合に格闘している。五巻、六巻までたどり着くのは並大抵ではない。しかしここにこそ親鸞の自己矛盾を止揚していく思想が姿を現す。
親鸞が浄土三部経の中から『大経』を浄土真宗の根本経典に撰択(せんちゃく)したことは先に述べた。浄土教の根本は本願という思想であり、親鸞の主張する阿弥陀の本願がそこに書かれているからである
阿弥陀仏はもともと法蔵菩薩というこの世の出家者であった。いうまでもなく歴史上の人物ではなく経典に登場する出家者である。彼は大衆の救済を願って四十八種の誓願(四十八願)をかけて難行苦行して、その願が成就して無量寿仏(阿弥陀仏)になられた。その四十八願中の第十八願こそが、いわゆる阿弥陀仏の本願というものである。
その願とは、要するに、心から極楽浄土に往生しようと思って十念すれば、どんな人間でも極楽浄土に往生できる。それでなければ自分は仏にならないという願である。こういう願をかけて法蔵菩薩は阿弥陀仏になられたのであるから、阿弥陀にすがって十念(心の中で阿弥陀仏を念じる)すれば全ての人は必ず極楽に往生できるというものである。つまり阿弥陀仏の第十八願こそが万人救済の特効薬なのである。
この十念を法然は「南無阿弥陀仏」を十回称えることと解釈したが、親鸞によれば念仏しようとする心が起こった時に、すでに阿弥陀によって救済されているとした。いずれにせよ法蔵菩薩の第十八願を本願の中の王として、四十八願の中心としたのは法然である。
これは法然の解釈のこじつけであり、この願が四十八願の中心をなす根拠はどこにもない。またこの願にみえる「十念」という言葉を十称(十回念仏を称えること)としなければならない理由もないのである。法然は後に伝統仏教僧からこの点を突かれて激しい批判に晒されている。(私はこの批判もあまり意味がないように思えるが)ともかく法然は「十念」=「十回」と解釈した上で、第十八願が阿弥陀仏の王本願であると強引に主張するのである。
しかし親鸞は法然の浄土教を疑念なく信じ、阿弥陀一仏信仰に傾倒していった。客観的に見れば「念仏以外のいろいろな行をも、往生の要因として認めるべきである」とする貞慶(1155~1213・法相宗)や高弁(1173~1232・華厳宗)ら伝統仏教の方が、経典そのものに対する素直な解釈といわざるをえない。
そもそも専修念仏は浄土門の中の一方便であるとともに、浄土門そのものが聖道門の中のひとつの方便にすぎない。仏教の長い歴史の中で、諸教間の優劣が論じられた教相判釈(きょうそうはんじゃく)は盛行しても、一つの行だけを正法とし、他の教行を公然と否定するという法然の論法は前代未聞であった。しかし親鸞は師の説く法蔵菩薩の第十八願こそが阿弥陀の本願だと信じ、そこから親鸞の絶対他力の思想が生まれるのだ。
但しである。私にいわせれば、法蔵菩薩の難行苦行はすでに自力である。自力ののちに仏になったという話である。親鸞はこのことをどのように考えたか、その形跡はない。いや、法蔵菩薩は難行苦行に耐え抜いた特別な人(聖道門)で、耐えられない凡夫を代表して阿弥陀仏になられたのかもしれぬ。だからといって愚凡悪人は一切の努力をせずとも阿弥陀仏に救い摂ってもらえるというのは、少し虫が良すぎはせぬか。この思想は一歩間違えれば向上心の放棄、そして人間の「甘え」を引き出す。
いや、全く努力をしないというのは言い過ぎかもしれない。法然の口称念仏とは心を阿弥陀一尊に集中して称えねばならない。心が少しでも乱れてはならないのだ。そのような精神統一に持っていこうとすること自体修行のいることで、これはすなわち自力ではないのか。何より親鸞は愛欲の雑念断ち切れず六角堂に籠っている。それでも集中できずに法然の専修念仏を超える独自の境地を切り開いた。たとえそれが肉食妻帯であったとしても、彼は真の他力念仏の境地を求める努力の連続ではなかったか。これが私には他力を得んとする自力に見えるのである。
空海はおそらくこういうだろう。「親鸞よ、お前が生まれてきたこと自体すでに他力である。死ぬことも他力である。生老病死ことごとく自力でままなるものはない。釈尊のいわれる苦とはその意味でもある。われわれは宇宙の大日如来から命を頂き、最後に命をお返しするように絶対他力によって決定づけられている。密教とはもともと壮大な他力の世界の自覚にあるのだ。それがわかれば今さら阿弥陀の他力本願もない。われわれは生まれる前から大日如来の懐に抱かれているのだ。だからこの世に生を受けたら、せめて自力の向上心をもつことが、命を頂いた大日如来への報恩ではないのか。だから私は『十住心論』を書いたのだ。向上門を否定した下向門というものはありえないのだ。」
オギュスタン・ベルク(フランスの地理学者)によれば、世界に意味があるとすれば、それはわれわれの世界への関係性の中にしか存在しえないという。つまり、われわれ人間を世界に存在させる諸々の関係は、そのこと自体によって、われわれを倫理的な存在として、その土台を据えるというのがベルク博士の考えである(『地球と存在の哲学』オギュスタン・ベルク)。
しかし僧侶として破戒してしまった親鸞にとっては、極悪人とよばれるような人間でさえも、阿弥陀の本願の力によって浄土に往生することができると主張する善導の説を信じた。そして法蔵菩薩(阿弥陀仏)の第十八願こそが、唯一のわが救いの根拠だと思った。親鸞の思想が『大経』に依拠するのは、このような阿弥陀仏の無差別の救済という絶対的な愛の誓願を信じたからであった。
道徳・倫理も守れない悪人や、社会からつまはじきされた棄民・罪人もすべて救済しようという阿弥陀仏の万人救済である。戦後の進歩的文化人の大好きなヒューマニスティクな弱者救済思想でもある。しかし親鸞は『歎異抄』を愛好する現代人が考えるような甘いものではない。
有名な悪人正機説は、もとは善導の思想であり、「善人なおもて往生をとぐ、いはんや悪人をや」というほぼ同様の言葉も、すでに法然によって語られているが(法然の伝記『醍醐本』)この思想を親鸞はさらに先鋭化した。
『歎異抄』(第三条)にあるこの言葉をその背景からいうと、法蔵菩薩(阿弥陀仏)は、智者や善人を対象にしてあのような願をかけられたわけではない。むしろ愚かな悪人を対象に、あのような願をかけられたのである。愚かな悪人は智慧や徳の力によって、つまり自力で極楽へ往生することはできない。ただ「南無阿弥陀仏」と称えることによってのみ、極楽へ往生することができるというものである。
ここで注意しなければならないことは、阿弥陀仏は善人を対象にして願をかけたのではなく、むしろ愚かな悪人を対象にして願をかけたという解釈である。その愚かな悪人の成仏は、阿弥陀仏が『大経』においてはっきりと保証しているというのだが、これは法然や親鸞の解釈にすぎない。
第十八願を現代語に訳すと、「自分が仏に成るとき、すべての人々が心から信じて、我が国(極楽)に生まれたいと願い、十念しても生まれることができないようなら、自分は決して悟りを開かない。ただし五逆の罪を犯したり、仏の教えを謗るものだけは除かれる」というものである。設我得仏 十方衆生 至心信楽 欲生我国 乃至十念 若不生者 不取正覚 唯除五逆 誹謗正法。
このように別に悪人に限定しているわけではない。この願を悪人成仏とすれば、阿弥陀の本願は悪人成仏のためであり、まさにほかの方法によっては成仏することができない悪人こそが往生の正因(しょういん)となる。だから、「悪人でも往生す、まして善行を積んだ善人が往生できないことはない」という常識はここでは通用せず、「善人なおもて往生をとぐ、いはんや悪人をや」という意味こそが真理となる。
これはまさに強烈な宗教のパラドックスである。悪人こそ優先的な救済の対象である。道徳の延長上に宗教はない。自己の善を否定しなければ阿弥陀仏にめぐり会えないということになる。この思想によれば、庶民だけでなく僧の倫理、三学(戒・定・慧)もすべて無意味となる。であれば、まさに無条件の成仏である。いや、阿弥陀救済の条件はあるのだ。それは徳を積む人より、むしろ悪を積む人だという条件がある、と凡夫愚者が誤解したのは無理からぬことである。
親鸞といえば『歎異抄』(第三条)の悪人正機説が中心に語られる。現在の浄土真宗の教義がそうである。多くの人は『歎異抄』の純粋な倫理観に打たれるが、そこに潜む危険性にまでは気がつかない。私は第三条が親鸞の真意とは思わない。第三条、悪人正機説には肝心なものがすっぽり抜け落ちている。それが『教行信証』で語られる信と懺悔である。
親鸞は常陸で書き始め、京都に帰っても再三再四推敲して『教行信証』を書いた。親鸞は浄土の本当の教え、つまり浄土真宗の真義を後世に残すために、老後を著作に全情熱を傾けるのである。『歎異抄』は親鸞の思想や人格を理解する入門書として位置づけるのはいいかもしれないが、これを浄土真宗の教学とするのは間違いで、本当の教学は『教行信証』だと思う。
私は宗門の立場から親鸞の思想を見ているのではない。真宗学者が宗門の立場で親鸞聖人を解説すると、実に見事な宗教、それも現代風の宗教に変わっているように思える。私はあくまで本人の著作から宗教家としての人間親鸞を理解しようと努めている。
親鸞が「われは大無量寿経を選択する」と決意した理由は、いうまでもなく悪人優先の往生思想をみたからであった。こうして教、行、信までは悪人の往相が述べられる。そして極楽往生して悟りを得たら、また現世に舞い戻るのである。これを還相という。
もともと往還浄土の思想は親鸞のオリジナルではなく中国浄土教の善導の発想である。還相論の中心は曇鸞の『浄土論註』である。そもそも往還二廻向というテーマを最初に取り上げたのは中国の曇鸞だった。親鸞はこのテーマにひらめいて、この命題に導かれながら『教行信証』を書き始めたようである。
親鸞は第一巻「教の巻」冒頭で「浄土真宗を案ずるに、二種の廻向あり。一には往相、二には還相なり」と宣言をしている。その宣言の真義こそ、極楽往生して悟りを得た者は、大慈大悲心をもって再びこの世に還るところにある。つまり往還二廻向とは万人救済の菩薩行がその神髄なのである。往還には目的がなければならない。それが阿弥陀本願の救済論であるからこそ、それを説く経典は真実なのである.ゆえに冒頭で「それ眞實の教をあらはさば、すなわち大無量寿經これなり」と続けるのである。
『歎異抄』にあるような、悪人こそ往生できるというふてぶてしさはここにはない。親鸞の死後二十年たって他人が書いた『歎異抄』は二次資料と見るべきであり、一次資料としては、本人の著書『教行信証』に耳を傾けるべきではないか。
往還二廻向は、これすべて弥陀の大悲による不可思議な力によるものである。一切の自力を捨ててこそ弥陀の本願にかなうということを教・行・信・の三巻までは繰り返し説く。
往還二廻向するには、まずは極楽に往生しなければならない。その浄土行きの極楽列車には浄土門(他力念仏者)しか乗れないという論証である。悪人も、他力念仏者であるかぎりはこぞって乗車できる、いや、むしろ悪人こそ優先的に乗車できるはずである。
ところが、『教行信証』を読むと、親鸞は還相廻向どころか、悪人が往生できるかという「往相の問題」に悩み苦しむのだ。あれ?悪人こそが往生の正因ではなかったのか?また矛盾が生じていると感じる読者もいるだろう。『教行信証』を執筆しながら、親鸞は実は密かに、この矛盾に悩み続けていたのである。この矛盾解決こそが『教行信証』という生涯を賭けた著作における格闘であったといってもいいくらいである。
◆親鸞の生涯最大の戦い
それはどういうことか。『大経』は親鸞にとっての究極の救済聖典ではあるが、しかしただ一点未解決の部分があった。のどに刺さった小骨のようなそれは、あとの九十九パーセントを木端微塵にするほどの破壊力をもつ教えである。これが『大経』(第十八願)に述べられる五逆と誹謗正法という除外規定である。
五逆とは、母殺し、父殺し、聖者(阿羅漢)殺し、仏の身体を損傷する、教団を破壊する、の五つの罪悪をいう。もう一つの誹謗正法とは、正法(仏法)を誹謗する罪である。『大経』の中心テーマとした法蔵菩薩の第十八願は、確かに万人救済の阿弥陀仏の本願である。だがその中に五逆と誹謗正法は救済から除外せねばならぬという悪人除外規定があるのだ。
おそらく親鸞は、肉食妻帯という所業が、教団(旧仏教)の破壊と正法(仏法)の誹謗にあたるのではないかと密かに考えていたのではあるまいか。まさに我は五逆と誹謗正法に該当する。これは親鸞を奈落の底に突き落とすほどの衝撃を与えていたはずである。
これが阿弥陀本願であるなら、自分のような悪人はとても往生できない。親鸞は『大経』を浄土真宗の根本経典としたが、実はこの経典において、まず自分が除外されているのだ。おそらく、これが生涯親鸞を苛んだ不安ではなかったか。このような場合、信仰によって救われるしかないのだが、『教行信証』という論書を書き始めたために、この根本的矛盾をどのように克服するかという大問題を抱えてしまうのである。
これが親鸞の生涯を賭けた内面的格闘であった。除外規定に苦悩する親鸞は、その重い問題を懐に抱えたまま、『大経』のテーマをめぐる数多くの経典、論釈群の引用に精力を傾ける。曇鸞、道綽、善導、源信の議論が次から次へと参照されつつも、思考の波は逆巻き、彼の思索的格闘が延々と続く。ここには悪人正機説の居直った親鸞の姿はない。
「大経にのたまはく・・・」、「大経にいはく・・・」と、この経典の万人救済論を盛んに紹介しながら、「ただし五逆と誹謗正法をば除く・・・」、「ただし五逆と誹謗正法をば除く・・・」と自問を繰りかえす。何故だ?どうしてだ?前に進もうにも、常に引き戻され、巨大な壁の前に佇む親鸞。親鸞は苦悶する。五逆と誹謗正法を除くをリフレーンのごとく重ねながら思索は深く沈殿していく。
しばし沈殿したかと思うと、ただちに反転して「一切衆生悉有仏性」の世界を喚起する。と思えば世界は「貪瞋、邪偽、姧詐」に満ち満ちているという現実を見よという。とにかく読む者にとって焦点の定めがたい、思考の揺れと膨大な引用文の大波である。その波頭にときどき親鸞の肉声が顔を出すが、それをあやまたず把握するのは容易なことではない。
しかし親鸞は何としても自己の信仰の正しさを論証しようともがく。その心意気こそ「われは大無量寿経を選択する」という決意であった。親鸞は諦めなかった。かくして彼は『大経』を授持したまま正面突破を試みるのだ。
そのような執念にも似た決意と模索の中で、今度は『大般涅槃経』を引用するのである『大般涅槃経』(以下『涅槃経』)には五逆と誹謗正法の罪を犯した者がゆるされる話がある。これはこの経典に語られるインドの王舎城の阿闍世(アジャセ)王が、父親の頻婆沙羅(ビンビサーラ)王を幽閉し、死に至らしめて王位を奪う話である。欲望のままに行動し、父の王を罪もないのに殺害、やがて激しく後悔し、高熱を発して全身にできものが生じた。その臭いにおいに誰も近づくことが出来ず、王は遂に地獄の報いだと観念した。アジャセ王の救済への道をめぐって、このあと曲折に富む物語がドラマティックに展開される。アジャセ王の苦悩を救うさまざまな賢者の哲学的思想が展開するが、いずれもアジャセを救済することはできない。最後に釈尊のもとで懺悔し、滅罪、求道の生き方を教えられ、やがて信を得て救済されていく場面がある。古代インドにおける親殺しの物語である。
そして親鸞がもっとも熱い視線を注いだであろうテーマである。端的にいって、父親殺しの五逆罪を犯したアジャセ王は浄土往生への道につくことができるのか、悪人、アジャセの「往相」の問題であるといっていい。かくしてここからまたこの経典の長文の引用がはじまるのだ。
ちなみに『大般涅槃経』とは文字通り涅槃について論じた経典で、具体的には釈尊の入滅 (涅槃)の場面について書かれた経典である。『法句経』の「般涅槃」(はつねはん)を発展させた大乗仏教の「般涅槃」のことである。「般」(はつ)とは「完全な」という意味である。
『涅槃経』は涅槃を「至福の世界」であると説く。そして誰でもこの世界に入れること(常楽我浄)を説く。その理由は人間すべてに仏性があるからだという。これを「悉有仏性(しつうぶっしょう)」という。いいかえると仏性を磨きだした人間は最終的に煩悩が消滅し至福の世界に至るという仏説である。そこでこの経典で語られるのが、入滅を迎えんとする釈尊が五逆罪を犯したアジャセ王を教化救済する物語である。
親鸞がなぜこれほど『涅槃経』にこだわるのか、いうまでもなく『大経』との整合性である。どちらも仏説である。「教の巻」の冒頭、それ眞實の教をあらはさば、すなわち大無量寿經これなりと大見得を切ったものの、自らが根本聖典・阿弥陀本願とした『大経』には五逆と誹謗正法は除くとある。この自己矛盾を超克するために今度は『涅槃経』を引用するのだが、この二経には矛盾がある。彼は二つの接合に悩み苦しむのである。どのように矛盾なく統一的に解釈するかという問題である。「信の巻」に至って、『大経』と『涅槃経』という二つの大きな山の谷間で、煩悶する親鸞の嘆声が溜息のように吐露される。
まことにしんぬ。かなしきかな愚禿鸞(ぐとくらん)、愛欲の廣海(くわうかい)に沈没し、名利の大山に迷惑して、定聚(ち゛やうじゅ)のかずにいることをよろこばず、眞證(しんしょう)の證(しょう)にちかづくことをたのしまず。はづべし、いたむべし。
自分は「愛欲の広海」に沈没する悲しい愚者である。名利の世界に迷い、本心では浄土への往生も、仏の悟りの境地も望んではいない愚かな人間である。ああ、恥ずべし、痛むべし・・・。自己否定を響かせる懺悔の告白である。
『歎異抄』(第九条)では、晩年親鸞はあるとき唯円の問いにこのように答えたとある。
唯円「私は念仏を称えましても、心が躍りあがるような歓喜の心が起きません。また極楽浄土へ早く往きたいという心もありません。これはどういうわけでしょうか」
親鸞「実は親鸞も同じ不審を抱いていたが、唯円房、そなたも同じことを思っていたのか」
まことに率直な弟子と師である。ここで親鸞は自分の心を正直に語るのである。「少し病気をすれば、死ぬのではないかと心配をし、また流転極まりない苦悩に満ちたこの世はなかなか捨てがたく、楽しみと美しさに満ちているはずの極楽浄土は恋しくない。いよいよもって、煩悩のいかに強く激しいかが知らされる。しかしどんなに名残惜しく思えども、この世の縁が尽き、生きる力失えば弥陀の浄土へ参るのだ。急ぎ参りたき心のない者を、(阿弥陀は)ことに憐みくださるのだ」と語る。
こういうふうに自らの心を明らさまに語った後に、親鸞独特の、というより『歎異抄』独自の逆説的な信仰思想の告白が始まるのである。それは、「自分はこの世の執着捨てがたく、恥ずかしいほど煩悩具足の凡夫である。しかしこういう私を極楽往生させようとするのが、阿弥陀仏の本願なのであるから、自分が凡夫であると思い知らされるにつけ、いよいよ阿弥陀仏の大悲は頼もしく思われる。かえって念仏するのが嬉しく、極楽へ早く往きたいというのでは、煩悩がなく、それでは本当に極楽浄土へ往生できるか危ぶまれる」というのである。つまり煩悩具足の礼賛である。
屁理屈と米粒はどこにでもくっつくと思うのは、信仰を持たない人の感性である。ここにも、『歎異抄』の煩悩の肯定、悪人往生の強靭な思想が読み取れよう。
また第七条では、唯円は親鸞の次のような言葉を聞いたという。「弥陀に救われる念仏者は、一切が障りにならぬ幸福者である。なぜならば、弥陀より信心を賜った者には、天地の神も敬って頭を下げ、悪魔や外道の輩も妨げることが出来なくなる。犯したどんな大罪も苦とはならず、いかに優れた善行の結果も及ばないから、絶対の幸福者である、と聖人は仰せになられた。」
『理趣経』(三段)でも引用したのかもしれないが、ここまで親鸞が思い込んでいたのなら大した自信家である。しかし親鸞自ら書いた『教行信証』には、こうした自信に満ちた言葉は表白されてはいない。はたして親鸞は絶対の幸福者であったか。『教行信証』を読む限り、そのような親鸞像は見えてこない。
無論この書の中で阿弥陀救済の喜びを語ってはいる。「誠なるかなや、摂取不捨の真言、超世稀有の正法」(まことだった、摂取不捨の利益、本当だった!阿弥陀の真言は嘘ではなかった)というが、今一つ実感が伴わないのだ。むしろ『涅槃経』でいう難治の機に苦悶する親鸞が見えてくる。
親鸞は『涅槃経』を手がかりにして、『大経』の除外規定を解除し、悪人往生の道筋をつけるつもりでいた。しかしここでも躓く。『涅槃経』には難治の機が語られている。難治の機とは、治し難い機根、救いに導くことの困難な人のことをいう。悪人アジャセを救った釈迦の妙薬も服用しない者まで治すことはできない。浄土往生も喜ばず、悟りの境地も楽しめない者、それがこの経典にある難治の機、すなわち愚禿親鸞、自分のことであった。
親鸞は深い悲しみの中で『涅槃経』を読んだ。何度も何度も読んだ。悪戦苦闘しながら読んだのである。唯円に語ったあの自信あふれる親鸞の姿はない。
浄土眞宗に歸(くみ)すれども
眞實の心(しん)ありがたし、
虚假(こけ)不實(ふじち)のわが身にて
清浄の心もさらになし
外儀のすがたはひとごとに
賢善精進現ぜしむ (賢く善を行いつとめているように見せかける)
貪瞋邪偽おほきゆゑ奸詐(よこしまないつわり)
もゝはし(数が多いこと)身にみてり
悪性さらにやめがたし
こゝろは蛇蝎(じゃかち=へび・さそり)のごとくなり
修善も雑毒(ざつどく)なるゆへに
虚仮(こけ)の行(ぎやう)とぞなづけたる『愚禿悲歎述懐』
このような自虐的な告白を胸におさめて、『教行信証』はもう一つのテーマである還相に向かっていくのだ。端的にいって、教から行へ、行から信へのここまでの論述は往相廻向に向かう一筋の道だった。この世からあの世へ、此岸から彼岸へ、穢土から浄土へ向かう一筋道だった。その往相のターミナルが極楽浄土である。浄土への旅が成就したことを明証するステージが「証」の段階にほかならない。
しかし『教行信証』の思想は、そこはまだ最終地点ではない。浄土から穢土への折り返し地点にすぎないなのである。再び穢土へと旅立つ新たなスタートラインなのである。往相から還相へと逆流するのである。極楽で往生したからには菩薩となって再生するのである。ここに至ってようやく「教の巻」の冒頭の宣言「浄土真宗を案ずるに、二種の廻向あり。一に往相,二には還相なり」という根本命題につながるのだ。筆者はここまで超スピードで語ったが、ここにたどりつくまで実に長きにわたる道のりで、途中で何度も投げ出したくなった。
前述したように、往還の二廻向というテーマを最初にとりあげたのは中国の曇鸞であった。したがって「還相」論の中心は曇鸞の『浄土論註』(世親の『浄土論』の注釈書)である。「証」の後半部分は曇鸞の『浄土論註』の引用、要約から成り立っている。
親鸞は主張する。曇鸞大師(宗師)は往相と還相の二廻向を明らかにされ、他利と利他の深い意義を明らかにされたのだと。要するに往還二廻向は衆生の救済、つまり菩薩行が目的であると親鸞はいいたいのである。だが「証の巻」は、この循環運動の救済論を大きく掲げたところで一気に幕を閉じる。
「宗師は大悲往還の廻向を顕示して、ねんごろに、他利利他の深義を弘宣したまへり。あふいで奉持すべし、ことに頂戴すべしと。」「証の巻」の親鸞最後の言葉はこれである。ここで曇鸞の還相論に終止符を打つのだ。教、行、信、証のうち「証の巻」の還相論に割り当てられた枚数はわずか十分の一である。いったい主題は何だったのか?
親鸞を書きながら、正直わけがわからなくなるときがある。きっと私の力では読みこなせない難物なのであろう。だが、二種回向を下地にして、悪人成仏には可能性があるか、その可能性を探りながら論証しようとする親鸞の苦闘はうかがい知れる。彼は『教行信証』を書きながらまだ何か決着がついていないようである。その何かとは何か。いうまでもなく悪人「往相」の問題である。
してみると『教行信証』を書く親鸞の真の動機は、「還相廻向」(菩薩行)にあるのではなく、やはり悪人成仏だと思わざるを得ない。「往相」に大部分の分量を費やしているのはそのためであろう。端的にいって、五逆を犯したアジャセ王は、はたして浄土往生への道にたどりつくことができるかという「往相」の問題である。つまり親鸞自身の救済問題なのだ。その難問がいぜんとして未解決のままである。「証の巻」の還相論を一気に終息させなければならなかった理由がそこにあったのではないか。
かくして悪人成仏を問い詰める親鸞が設定した新たなテーマが現れる。それが「真仏土」と「仮真土」の二巻である。いうまでもなく「証の巻」で展開された環相論を継承する気配は全くない。他利利他の「環相論」が置き去りにされたまま事態は先に進んでいく。ここにおいて往還二廻向という当初のテーマは往相にとって換わられる。
「浄土真宗を案ずるに、二種の廻向あり。一に往相,二には還相なり」をもじっていえば、今はその提言は、「浄土への道に二種の廻向あり、一には真仏土、二には化真土なり」へと変更を余儀なくされてしまっていたからである。いずれにしても、往相―還相の黄金の輪がすでに成り立たなくなっていたということだ。
◆真仏土の巻
光明無量の願
壽命無量の願
つつしんで真仏土を按ずれば、佛すなわちこれ不可思議如来なり。土はまたこれ無量光明土なり。しかればすなわち大悲の誓願に報酬す。かかるがゆへに真の報佛土といふ。すでにして願います。すなはち光明壽命の願これなり。
冒頭の書き出しである。文字通りに読むと、真仏土とは不可思議な仏の無量の土地で寿命の尽きない永遠の世界であるらしい。「真仏土の巻」は、『大経』を中心に多くの経や論書などから阿弥陀の光の世界が引用されている。親鸞の主張する極楽とはわれわれが一般にイメージする極楽とは随分違う。
往時の人々は『阿弥陀経』や『観無量寿経』などで描かれた極楽の風景を思い描いていたはずだ。一切の苦しみはなく、楽しみだけを受ける世界である。極楽国土には七重の欄干や珠飾りの網や並木があり、七宝の池があり池の底は金の砂が敷き詰められ、色とりどりの大きな蓮華が咲き、よい香りが立ち込め、天の音楽が奏でられ、美しい鳥は飛び交い、美しい声でさえずり、人々は金銀瑠璃で飾られた階段を使い、食事をし、散歩している。そういう風景である。
だから人々は極楽往生に憧れたのだ。この世の栄華を味わったであろう藤原頼道も、臨終のときは観音菩薩像と五色の紐でつながって、僧侶たちの読経に包まれて極楽国土を思い描いて死んでいった。まして、当時の貧しい民衆がこのような極楽往生に憧れないわけはない。
しかし本当の極楽とは、清浄だがやたらまぶしいばかりの、何もない世界であると知ったなら、民衆が浄土教についてきただろうか。もしかすると親鸞は『阿弥陀経』や『観経』を方便だと思っていたのかもしれぬ。もしそれで、師の法然に反してこの二経典を一段下に置いたのなら、それなりに納得がいく。
なるぼど、この二経典に描かれた極楽は人々を仏の世界に導くための方便なのかもしれない。いや、所詮経典は方便だというのなら、『大経』にもまた方便の部分がなしとはいえまい。この経典だけは純粋に釈尊の肉声であり、編者の解釈は皆無だとどうして断言できるのか。親鸞にそのような自問の形跡は全くない。
『大経』を唯一絶対とすることは親鸞の自由である。だがそれは個人的な信仰の問題であっても、他の経典を退けて唯一絶対とする普遍的な根拠にはなるまい。仏教は八万四千門もあるといわれているように、そもそも経典自体異なった方法論が説かれている。だからそれぞれの仏典の内容が相矛盾する場合がある。
そのわけは、おそらく釈尊の対機説法という方便話法からくるものだと思われる。仏説とは釈尊が時と状況と相手の能力に応じて様々に説いたもので、そこに後々の経典編者の解釈も入っている。親鸞がそういう仏典の特徴を知らぬわけはない。しかし親鸞はあくまでも経典にこだわる。矛盾する内容を何とか接合しようと、ほとんど意味のないことを試みているように見もえる。親鸞ほどの秀才が・・・。
ちなみに『観経』の場合は、誹謗正法の者は往生することはできないが、五逆の者は往生できるという。『大経』は五逆、誹謗正法、その両方を除外するという。『涅槃経』では、五逆、誹謗正法の双方ともでも救われると説いている。説いているところは三経ともみな違う。親鸞はこの三経の整合に必死で取り組むのだ。
最澄が弟子を通じて空海に『理趣釈経』の借覧を願い出たとき、密教の奥義をあくまでも文字面から学ぼうとする姿勢に対して、空海は「文はカス、ガレキだ」といったことがある。空海はその手紙の中で「理趣はあなたの中にある」といっている。つまりいつまでも書物の中に求めるな、自分の仏性(無垢なる命の声)に耳を傾けよという意味である。私はこの言葉が好きである。釈尊の自灯明の言葉に匹敵する衝撃を受けたものだ。
しかし、そのような経典好きの学長が創立した延暦寺で学んだせいか、親鸞のテクスト(経典)依拠は大変なものである。『教行信証』を読みながらしみじみそう思う。ほとんどがテクストの引用である。
「真仏土の巻」の冒頭、極楽が光明の世界だというのも、『無量清浄平等覚経』に書かれている無量光明土の紹介なのである。「真仏土の巻」は、真実の極楽が光の世界であると説く。あとは例によって『大経』や『涅槃経』や『浄土論』、『註論』、『不空羂索神変真言経』『佛説諸佛阿彌陀三那三佛薩樓佛檀過度人道経』などさまざまな経典を引用し、そこが涅槃であり、覚りであり、醍醐最上の世界であると証する。例によって諸経のオンパレードで埋め尽くさている。結局、何が言いたいのか、今一つわかりにくい。
経典は人によって書かれたものである。真如は言語を絶するものである。この理解が密教である。空海はいう。「密語は仏親(みずか)ら宣べたもう、教は人に従って伝訳す。」(『五部陀羅尼問答偈讃宗秘論』)
◆化真土の巻
つつしんで化真土をあらはさば、仏といふは無量壽仏観経の説のごとし。真身観の仏これなり。土(ど)といふは観経の浄土これなり。また菩薩處胎経等(ぼさちしょたいぎゃうとう)の説のごとし。すなわち懈慢界(げまんかい)これなり。また大無量壽経の説のごとし。すなわち疑城胎宮(ぎじゃうたいぐ)これなり。
化真土を親鸞は冒頭でこのように説明する。つまり化身土というものは、阿弥陀如来が仮に方便として現れた極楽であるというのである。そしてそれは、懈慢界、怠け者の行くところであって、疑城胎宮、つまり阿弥陀如来の救済を疑う人間の行くところであり、まだ胎宮すなわち子宮の中のような暗い極楽であるという。
こういう懈慢、疑城、胎宮、辺地という言葉を、親鸞は様々な経典から集めてきて、極楽世界には二つの世界があること、すなわち真仏土報土の極楽と、懈慢界、疑惑界、胎宮界、辺地という仮の極楽の二があることを、多くの経典の文章を引いて証明しようとするのである。そして、そのように親鸞は極楽を二つに分け、真実の他力念仏の行者は、まちがいなく真仏土報土の極楽浄土へ往生するが、自力の徒、あるいは他力でも自力を交える徒はすべて化身土浄土、懈慢界、疑惑界、胎宮、辺地浄土に往生するというのである。
つまり極楽浄土に上・下の二ランクをつけたのである。筆者などは、どうせなら、せめて上,中、下の三ランクぐらいほしいとアホなことを思わぬでもない。なにしろ自力門の信者は極楽行きの列車にはオール乗れないからだ。では行基や最澄や空海などは死後どこにいくのか。地獄しかないだろう。親鸞の思想は結局そういう結論になる。
親鸞は法然が浄土教の根本経典とした浄土三部経の一つ『観無量寿経』(観経)を一段下に見ている。そのわけは、極楽往生の方法として、定善、散善、三福、九品などの善行が説かれているからだ。親鸞はこの経典を称名念仏、すなわち他力を説いたものとしても、他力の中の自力の経典だとするのである。こういう自力交じりの他力の人は、決して真仏土に往生することはできず、辺地である化真土に往生することになるという。これを観経往生、あるいは双樹林下往生というのである。
双樹林下往生とは前にもいったように、沙羅双樹の林で往生した釈迦のような往生をいうのである。ここで親鸞は、釈迦仏教は真の他力の仏教ではなく、自力を交える仏教であり、結局、化真土にしか往生できないと考えているのである。
そもそも浄土教にいう往生、成仏とは、死後の極楽の真仏土においてさとりを開く=仏に成るという意味である。真理に目覚めた人をブッダというが、歴史的事実として、釈尊はブッダであり、この世において悟りを開いて成仏された方である。仏教とはそこから始まっており、それ以上でもそれ以下でもない。
しかるに釈尊は入滅後五百年間も押し込められる偽物の極楽で往生したというのだ。しかもこれらの教義は釈尊が生前に説いたことになっている。まさか釈尊が、「私がこの世で悟ったのは間違いで、あの世でやり直します。」そのように言ったというのだろうか。奇妙奇天烈な話である。
釈尊は信じるも信じないもない、この世の真実を語られた人である。ふつう人は、木材は燃えるという。これは事実だからだ。木材は燃えると信じるという人はいない。もしいれば、それは信仰である。水は低きから高きに流れると信じるといえば、これは信仰である。事実でなくても信じることが信仰の力である。これが事実と信仰の違いである。しかし木材は燃えるとは限らない。水に浸かっていた木材に火をつけてもすぐには燃えない。それは水という縁が木材という因を変化させたからである。釈尊のいう縁起の理法である。釈尊は信仰ではなく真理を説かれた人である。
「化真土の巻」も原文を読んで理解できる人は真宗学者以外ほとんどいないであろう。
『教行信証』の難解さはとにかく文脈のわかりにくさである。さまざまな仏典、論書を引用して、○○にのたまはく、△△にいはく、××にのたまはく、またしかじかにいはく、またいはくと、さまざまな経典が延々と紹介されるが、読む者にとってはメリハリのない散文がちりばめられたばかりの雑駁なものを感じる。私のような単純な頭では支離滅裂な感じを受けるのである。もちろんこれは私の読解力不足であるが、正直そのように感じるのだ。試に『教行信証』(親鸞著 金子大栄 校訂1991岩波書店)を読まれるといい。
空海の著書にはこのような感じは受けなかった。密教は事相(実践・修法)を伴うので、無論内容すべてが私に理解できているとは思わない。しかし文脈は通じるのである。例えば『十住心論』であれば、心の十段階だということはすぐにわかる。秘密荘厳心がどういうものか、実感としての内容は難解であるが、それは在家の自分に事相の経験がないからであり、主旨は十分理解できる。いわばそういう感じである。空海に文脈上のつながりに齟齬を感じることはなく、常に教相(教義・理論)においては論旨の一貫性を感じる。
無論空海も経典の引用する場合がある。だが自らの主張を論証するために最低限引用するだけで、独自の論述と独創性の方が主である。典籍を引用する場合は、こうしなければ、文献好きの学者は納得しないだろうなあと、ため息交じりに書いているようなものを感じる。特に顕教と密教の相違を論証する『弁顕密二教論』にはそんな気持ちが伝わって来る。
東洋では、正しい教えは昔からの教えにあるとする傾向があり、古典を引用して自説を述べる場合が多い。西洋の著書は著者の独創性というものが重視される。したがって引用文は少なく、自ら語った文章の方が多い。空海はこちらのタイプである。したがって空海には自律性を感じる。現代なら国際的な学術会議に出したいような人である。
方や『教行信証』の論述は見事に他律的である。親鸞は「証」を自分の言葉ではなく経典に語らせる。『涅槃経』のほとんど引用がそれである。別な見方をすれば経典権威主義ともいえる。というのは、親鸞が法然を信奉する理由にもそれを感じるからだ。彼は『歎異抄』(二条)で次のように語っている。
「弥陀の本願が真実だから、その本願を説かれた釈尊の教えに嘘があるはずがない。釈尊の説法がまことならば、そのまま説かれた善導の御釈も嘘ではないはずだ。善導の御釈が真ならば、法然の仰せにウソ偽りがあろうはずがない。法然の仰せが真実ならば、親鸞が申す旨もまたそらごととは言えぬのではないか。つまるところ親鸞の信心はかくのごとしである。」
このように他力思想の時間的な移譲の連鎖がとり上げられる。なぜならば、こういう媒介者の思想的な連鎖をたどるのでなければ、自分のような『愚者の信心』では弥陀の本願には到達しないからだというのが親鸞の論理である。
これは親鸞が不在となった東国の弟子たちに混乱が生じたとき、上京した彼らに対して答えた親鸞の言葉である。次のような文脈のあとに続く言葉である。
「親鸞は、ただ本願を信じて、弥陀に救われよと教える法然聖人の仰せを信じているだけである。念仏は地獄に落ちる業(行為)だと言いふらす者もあるようだが、念仏は浄土に生まれる道なのか、それとも地獄に落ちる行いなのか、まったくもって親鸞の知るところではない。たとえ法然聖人に騙されて、念仏して地獄に落ちても親鸞はなんの後悔もないのだ。なぜならば、念仏以外の修行を励んで仏になれる私ならば、念仏したから地獄に落ちたという後悔もあろう。だが、いずれの修行もできぬ親鸞は、地獄のほかには行き場がないのである(地獄は一定すみかぞかし)。」
この後に、先の他力思想の祖師たちによる浄土思想の継承の連鎖が述べられるのである。
言い換えれば「念仏」と「浄土」とをつなげる他力思想が権威ある媒介者によって保証されているということである。もしそうなら、弥陀の本願を説く経典は絶対的信仰権威である。それをリレーする浄土教の賢者も権威である。
これは不思議な信仰の論理である。権威者がみな嘘ではないというのだから私は信じる。だから信じた私のいうことにウソ偽りがあろうはずがない。だがもしかすると、念仏は浄土往きではなく地獄行きかもしれぬ。私は法然聖人に騙されるのかもしれないが、これしか方法をしらぬ自分は信じるしかないのだ。こういう論理を信仰であるというのであれば、私とは随分違う。
これは信仰という名の賭けではないだろうか。どうせ自分は地獄しか棲家がないというのだから、賭けというよりも、考えようによってはやけっぱちの信仰である。自らの思考判断を放棄したことにならないか。現代でも著名人や、その道の権威者の宣伝を信じて行動する人がいる。現代の新興宗教はそのような他律的な人々をターゲットにする。幸い浄土教は歴史に耐えぬいてきた質の良い宗教であったからよかったものの、一歩間違えば本当に地獄行きになろう。
「信心は如来の御ちかひをききて疑ふ心のなきなり」と本人がいうように、親鸞は信心とは本願を疑う心がないことであると定義している。であればあえて権威の保証など必要あるまい。『大経』第十八願に納得したら自信をもって信仰すれば済むことではないか。権威の確証のリレーを頼むということは、阿弥陀の教えを自分の頭で咀嚼していないということであり、言い換えれば自己の信仰における不確実性の告白になるのではないだろうか。
信仰心には、媒介者や権威による無謬性の保証が必要不可欠なものであろうか。少なくとも私の場合はそうではなかった。田舎育ちの私は幼少時から日常的に「自然の声」に囲まれていた。いわば密教的な如来の説法を浴びて育ったので、傲慢ないい方かもしれないが、空海の説く「密語の世界」や「法身の実相」は、ある意味自明であった。権威をたどりたどって到達したのではなく、自明だった世界を、空海という賢者によって一段と確証を得たという感じである。つまり私の中では保証人はあとから出現したのである。だから弘法大師の教えが心の底から実感として納得できたのである。つまるところ私の信心はかくのごとしである。
『教行信証』はまことに難解であるが、ただ私でも気がつくのは、親鸞は「化真土」の方に強い関心があったということである。「真仏土の巻」に対して「化真土の巻」は三倍もあり、『教行信証』全六巻のうち、四十パーセント近い分量にあたる。そこに圧倒的な論述を展開する親鸞は、やはり自己の問題、悪人成仏にこだわっていたと思えるのである。
さて「化真土の巻」であるが、さっそく「観経の願にのたまわく・・・」と、経典の引用から始まる。読者としてはもううんざりだが、そんな気持ちなどおかまいなく、経典による仏教論を延々と引用する。『阿弥陀経』『弥陀経義疏』『涅槃経』『正法念経』『月蔵経』『大集経』『賢劫経』『仁王経』『遺教経』『末法灯明記』『大悲経』『像法決疑経』『法経』『鹿子経』『般舟三昧経』『大乗大方等日蔵経』『日蔵経』『首楞嚴経』『地蔵十輪経』『集一切福徳三昧経』『本願薬師経』『菩薩戒経』『起信論』『弁正論』『仙人玉禄』などなど、それに儒教や君子や仏教先師の言葉など次々に挙げて、〇○にのたまわく、××にいわくと、言説のコピペである。こうして「のたまわく論述」が続く。「化真土の巻」だけでもざっとこれだけある。教、行、信、証、真仏土の各巻すべてがこの調子だから、よほど根気のある人でなければついていけないだろう。
このような言説の羅列を空海なら何というだろう。また空海の言葉が頭に浮かんでくる。
「なんじ来たりて道を問えども、道はもとより名なし。理の正邪を論ずれども、理は言説にあらず。」(『五部陀羅尼問答偈讃宗秘論』)
話を戻す。往還二廻向は、もはや「浄土への道に二種の廻向あり、一には真仏土、二には化真土なり」へと変更を余儀なくされてしまったが、これを真仏土への道が真の往相であり、化真土への道は仮の往相といいかえてもいいだろう。仮の往相は仮の極楽への道である。そう考えたとき、懺悔し、信を得たとしても、「化真土」こそが、悪人往生を約束する究極のターミナルといえる。それが親鸞にとってやっとの思いでつかまれた命題だった。そして、自分もまたそこにしかたどりつくことのできない人間(悪人)の一人である・・・それが親鸞の自覚であった。
悪性さらにやめがたし
こゝろは蛇蝎のごとくなり
修善も雑毒なるゆへに
虚仮の行とぞなづけたる。
私は親鸞の求道の動機を、主として個人的な煩悩に照射してきたが、むろん親鸞の意識の中では決してそればかりではなかった。上の和讃は親鸞の懺悔の告白だが、よく耳を澄ますと、それは自分のことだけでなく、時代の告発でもあるように聞こえてくる。
親鸞の生きた時代は暗黒の末法の世である。正法(釈迦の黄金時代)がすでに失われ、像法(釈迦滅後の衰亡の時代)もまた歴史のかなたに沈没し、自分たちは末法(その後の終末の時代)の荒波の中に放り出されている。
親鸞の目に当時の世相はどのように映っていたか。源平の動乱から鎌倉幕府の初めにかけては、日本歴史においても珍しいほどの動乱の世を迎えていた。源平の戦乱の中で、人間は自分の意志を超えて互いに殺し合ったのである。武士の出現と勢力争いは、親殺し、子殺し、まるで暴君アジャセ王の殺戮が横行する時代のようでもあった。加えて災害や飢饉や、はやり病にあえぐ民衆。武士ばかりか、農民も商人もまた、戦乱の中で多くの悪を犯したに違いない。悪行を犯さなかったら生きてはいけないという時代だったのだろう。親鸞はそういう戦乱の中で露わにされた人間の業の深さをつぶさに見たに違いない。彼は末法到来を如実に感じていた。現実世界を覆い尽くすのは無明の闇。しかしその暗黒の大海原に弘誓(ぎぜい)の光明ははたして見えるのか。否!
釈迦加来かくれましまして、
二千余年になりたまふ
正像の二時はおはりにき
加来の遺弟悲泣せよ。 (『正像末浄土和讃』親鸞)
血涙を流す親鸞の叫びが聞こえてくるようである。仏を失った人間どもの欲望とエゴが渦巻く終末の世界。親鸞の叫びは時代の糾弾でもあった。しかし、自分もまたそのような穢土世界に生きるまぎれもない悪人の一人である。それが親鸞の自覚であった。彼には阿弥陀仏の前での懺悔と告白と信仰しか残されていなかったのだろう。
結局親鸞にとっての救いとは、『歎異抄』(第一条)で唯円に語っているように、自分は阿弥陀によって救い摂られているという歓喜の自覚である。しかし本当にそうだったのか。私にはそのように信じるしかなかった親鸞の精神的な極限を感じる。
親鸞は法然を信じた。法然に騙されて地獄に落ちても後悔はしないといった。親鸞は実際、まさに法然聖人にだまされて地獄に落ちたのだ。法然に教えられた念仏信仰、そして自らの肉食妻帯、不殺生戒、不邪淫戒の公然たる破戒、その結果としての流罪と流浪、それは彼にとって地獄ではなかったか。それでも『歎異抄』に語るように、阿弥陀に救済されたのなら、この世における怒りの業火は消えていなければならない。
親鸞は懺悔と信による阿弥陀他力こそが安楽を招くと人々に語ってきた。そのような彼が『教行信証』を書き終わって、釈尊のように涅槃寂静の境地にいたのだろうか。私には素直にそうは思えない。
『教行信証』の「あとがき」は、次のような激しい言葉で終わっている。
ひそかにおもんみれば,聖道の諸教は行證(ぎゃうしょう)ひさしくすたれ、浄土の眞宗(しんしゅ)は證道(しょうだう)いまさかんなり。しかるに諸寺の釋門(しゃくもん)教にくらくして眞假(しんけ)の門をしらず。洛都の儒林、行(ぎゃう)にまどひて邪正の道路を辧(べん)づることなし。ここをもって興福寺の學徒、太上天皇(後鳥羽院)今上(土御門院) 聖暦承元丁の卯の歳、仲春上旬の候に奏達(そうだち)す。主上臣下(しゅじゃうしんか)、法にそむき義に違(ゑ)し、いかりをなしうらみをむすぶ。これによりて眞宗興隆の太祖、源空法師、ならびに門徒数輩(もんとすはい)罪科をかんかへず、みだりがはしく死罪につみす。あるひは僧儀改め、姓名をたまふて遠流(おんる)に處(しょ)す。豫(よ)はそのひとりなり。しかればすでに僧にあらず俗にあらず、このゆへに禿の字をもて姓とす。
<現代訳>
聖道門(浄土真宗以外の諸宗)は、すでに行(修行)も悟りへの道(証)も捨て去って久しい。ただ浄土の真宗だけが覚りへの道を示して栄えている。
しかるに坊主たちは教えについては何も知らない。真偽の別もわきまえていない。京の都の学者どもも修行の何たるかを知らず、正・邪の別あることにも無知だ。
このような危機的な時代に、興福寺の学僧たちが、何と太上天皇(後鳥羽院)のもとの駆け込み、訴状を出した。今上天皇(土御門院)の承元元年(1207) 二月の事だ。
天皇も臣下も、みな法に背き正義をふみにじり、怒りを発して怨みにからめとられている。その逆風の中で、浄土真宗の興隆を支えてくれたわが師、源空(法然)と門弟の数名が、その行為のいかんを問われることもなく、無法にも死罪にされ、また僧の身分を剥奪され、俗人の姓名与えられて遠国に流罪となった。自分もそのうちの一人だ。
こうなった以上は、自分は僧でもなければ俗人でもない。禿の字をもって姓とするほかないのである。
この「あとがき」にあるように、念仏門を弾圧する者は、たとえそれが上皇や天皇であろうと親鸞は許さなかった。「臣下」だけでなく、「主上」(後鳥羽と土御門院)までが法に背き、正義に反したことを行っていると激しく非難するのである。
浄土真宗はこのことを忘れずに原点とせよ。そのような思いであったのかもしれない。『教行信証』を書き終えたころ親鸞は七十四歳であった。妙好人といわれてもいい年齢である。まだ瞋恚(しんい)を露わにする親鸞は、本当に穏やかな阿弥陀の世界に救われていたのだろうか。
もう一度二人の肖像画を見て欲しい、肩に力の入った厳しい表情の親鸞像と、穏やかで吹っ切れた表情の空海像を。(『空海の統合性{一}』)
悪人往生というのなら、「主上」「臣下」こそまさに悪人となる。その彼らこそ真っ先に阿弥陀に救われる対象ではないのか。いや、それは違う!彼らは浄土真宗を弾圧した。浄土真宗を信じない者は異教徒である。異教徒は救われてはならないのだ。なぜなら聖道門の学者どもは修行の何たるかを知らず、正・邪の別あることにも無知だからだ。ただ浄土の真宗だけが覚りへの道を示しているからだ。
だが、阿弥陀本願とは万人救済の大慈大悲を説いたものではなかったのか。異教徒を排除する一神教的仏教に、仏道者として自家撞着を覚えないのだろうか。
◆空海と親鸞
私は親鸞を考えるとき、台密(天台宗の密教)とは何かと改めて考えてしまう。かつて梅原猛は「選別の最澄と和合の空海」といったことがある。鎌倉仏教の祖師たちはことごとく叡山出身であり、彼らの興した鎌倉仏教は現在「選別の仏教」といわれているが、そこに最澄大学の学風のようなものを感じるのである。
最澄は天台法門(法華一乗)と真言法門(密教)とは異なるところ無しという円密一致の立場をとった。にもかかわらず、天台宗にわざわざ「遮那業」(密教学科)を設置した。内容の同じものをなぜもう一つ必要としたのか。おそらく空海帰朝後、現世利益を求める貴族社会の要請に応じるため、密教の修法(儀式)を取り入れざるを得なかったのだろう。つまり密教の内実というより天台教団の経営上の問題であったと思われる。
空海が最澄に対して密教の秘典『理趣釈経』の借覧を断ったのはそれを見抜いたからだと思われる。つまり密教の内実を学ぼうとしない最澄の態度である。密教の「伝法灌頂」では何よりも受法者の機根を見る<詳しくは当サイト高橋憲吾のページ『空海と最澄』>。このことから私は最澄が天台の「遮那業」において、密教の胎蔵曼荼羅の真理を本当に叡山の学僧に教えたかという疑問を感じるときあがる。最澄の密教理解は、いわば顕教的な理解であり、その精神はあくまで法華一乗ではなかったか。そこに選別に傾いていくものを感じるのである。
真言密教では多種多様な無数の仏の存在を認める。その中で自念仏を選べばよい。曼荼羅壇上の投華得仏による仏との結縁は、そういう思想の象徴的な儀式である。親鸞が選択した阿弥陀如来は彼の念持仏(自念仏)なのである。これは真言僧ならすぐにわかることである。念持仏とは、諸仏諸尊のなかから、目隠しをした投花得仏による結縁仏のことである。親鸞が天台法門において、壮大な大悲胎蔵生曼荼羅(だいひたいぞうしょうまんだら)の真義を本当に理解していたら、阿弥陀如来が自己の念持仏にすぎないことを理解したはずである。であれば、親鸞の浄土真宗(選別の仏教)はもう少し融和的なものになっていたのではないだろうか。
そうならなかったのは、やはり時代の流れである。真言宗も浄土往生信仰を無視できなくなるほど、平安末期からの浄土信仰の爆発的な流行が背景にあったと思われる。真言密教は、来世・死後のことは第一義的に扱っていなかったために、末法の時代に入り、極楽浄土を求める人々への新たな対応を迫られることになった。平安後期に、この問題にもっとも苦慮した密教僧の覚鑁(興教大師1095~1143)が、事教二相を止揚した体系整備などをとおして、真言と浄土の融合を意図したのもそのためであった。
覚鑁(かくばん)は、浄土往生信仰の教主阿弥陀如来は、大日如来がそのまま阿弥陀如来であるから、極楽浄土の教主も大日如来であるとか、浄土についても、十方浄土はすべて大日如来一仏の教化している仏土であるから、阿弥陀如来の西方浄土はその一部であるとか(事実そのとおりなのだが)、往生の意味については、密教においては極楽浄土に往き生まれるものではなく、当処(修行しているこの場所)に得るべきものであるなど、浄土往生信仰と真言密教における即身成仏思想との整合に苦心している。
覚鑁が浄土教で盛んに使われる往生という語を、即身成仏を根本思想におく真言密教にとり入れた理由は、自力聖道は難行道であり、他力浄土門は易行道とする主張が浄土側からなされていたからである。また末法の時代にふさわしい教えとして急速に広まった浄土往生信仰が、高野山においても、浄土往生を願う念仏聖たちが現れてきたからでもある。
平安時代は、真言・天台両宗により仏教の総合化、密教化がはかられたが、鎌倉時代においては、このように総合から選択の方へと日本仏教の流れが変わった。それは仏教の単純化、易行化であり大衆化であった。そのような中で、空海以来の才と謳われた覚鑁は、真言宗中興の祖というだけではなく、平安仏教から鎌倉仏教への過渡期に登場し、古義真言宗の内実に新たな要素を加えた人物として評価されている。
しかし、覚鑁の浄土教との融合を、もしも真言宗の法灯を絶やさぬための時代を見据えた発展的教義だというのなら、本来の真言密教は、浄土教に対してどのような優位性を確保できるであろうか。これは古くて新しい真言宗全体の問題ではないかと思う。ともかく浄土信仰が日本人を圧倒的に魅了してきたのは歴史的事実であるからだ。
さて、原理主義的な宗教の多くは必ず善と悪の二分法の要素を持つ。この観点から親鸞を考えると、彼は善悪の問題を極限まで厳しく問い詰めた人であることに気がつく。人間にとって善とは何か、悪とは何かという問題を極限まで問いかけたのは、日本仏教ではおそらく親鸞が初めてであった。そういう意味で親鸞は近代的自我を掲げた哲学者的側面があるといえよう。親鸞の厳しい表情は、意外なことだが、仏者というより哲学者を思わせる。
戦後もてはやされてきた親鸞は、本当に理解されてきたか、私には疑問が残る。近代日本の知識人は親鸞の悪人正機説をその中核思想として評価してきた。それも近代的世界観のレベル、つまりヒューマニズムのレベルであったと思う。そのために、人間は善悪をはたして超えることができるのか否かという親鸞の根本的な問いかけに真正面から立ち向かおうとしなかったのではないか。私は親鸞を追いながら、信仰と哲学の狭間で、人間の魂の救済について親鸞とともに考えてきたような気もする。
こうしてみると、私には親鸞が仏者というより、善悪を超えようとした哲学者に見えてくる。その結果、『歎異抄』(後序)で語るように、親鸞は何が善で、何が悪かわからないと告白するに至った。おそらくその無力感が、阿弥陀他力の世界を信じることにしたのではないだろうか。
真実かどうかはこの際ことの本質ではない。本質は信じることで救われるということである。それが信仰である。キリスト教は「救いの宗教」である。仏教は「悟りの宗教」なのである。
さて、私はこれまで「空海の統合性」を論証するうえで、親鸞との相対化によって眺めてきた。空海も貴族社会の醜さや民衆の身勝手さや仏教界のエゴイズムをさんざん見てきたことであろう。絶望的な空海の言葉は各所に見つけることができる。空海の人間洞察による深いニヒリズムは、読む人を奈落の底に引きずり込むほどに震撼させる。だが空海は忍耐強かった。親鸞よりはるかに高い次元で絶望を希望に変えた人だと思う。空海は哲学を超越し、善も悪も超越した。生も死も、聖も俗も、清も濁も、体制派も、反体制派も併呑して、多くの矛盾を昇華統合していく、そのような人であったように思われるのだ。親鸞は自力門というだろうが、実は空海こそ真の宗教家であったと私は思う。
いま私は、空海の晩年の言葉を静かに噛みしめている。
「虚空に尽き、衆生に尽き、涅槃尽きなば、我が願いも尽きなん」
「この大空らがあるかぎり、生きとし生けるものが存在するかぎり、最後の一人が涅槃に至るまで、私の悲願が尽きることはない。」阿弥陀本願にも比する空海のこの誓願を、親鸞はどのように聞いただろうか。衆生救済を願う空海の永遠の誓願である。(完)
<引用及び参考文献>
『仏教の思想Ⅰ』梅原猛著作集51982
『仏教の思想Ⅱ』梅原猛著作集61982
『親鸞の告白』梅原猛2006
『誤解された歎異抄』梅原猛1990
『歎異抄をひらく』高森顕徹2008
『宗教の自殺』梅原猛・山折哲雄1996
『私訳歎異抄』五木寛之2007
『人生の目的』五木寛之2000
『教行信証』親鸞 著 金子大栄 校訂1991
『教行信証を読むー親鸞の世界へ』山折哲雄2010
『自在に生きる【涅槃経】』平川彰1984
『捨ててこそ得る【浄土三部経】』花山勝友1984
『親鸞とその妻の手紙』石田瑞磨1975
『最後の親鸞』吉本隆明2002
『鎌倉仏教』佐藤弘夫2014
『親鸞・いまを生きる』姜尚中・田口ランディ・本多弘之2011
★空海関係は省略