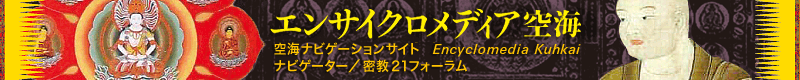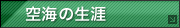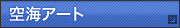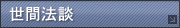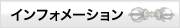第三回 釈尊と密教
◆釈尊の解脱と法身
『二教論』では空海が顕密の教判(1)を論じるに際しての基準を空海独自の言語論を中心に考察してみた。いうまでもなく、顕教は歴史上登場した釈尊の教え(仏説)に則ろうとするものである。仏説とは存在の真実(法)に教えの根拠をもつものであるが、「法」(万物存在の理法)そのものは釈尊が創造したものではなく、釈尊が人類史上初めて発見されたものである。
「法」(万物存在の理法)とは釈尊が出現されようがされまいが、変わることなく古今を貫く定則としてすでに存在するものである。顕教ではこの究極の「法」は釈尊の独覚によって明らかにされたのであって、何ものかが釈尊に啓示したものではないとするが、密教では大宇宙の開闢以来、絶対不可視なる法身大日如来によって「法」は常に説かれているとする。
そうすると仏教徒にとっては、釈尊(応化仏)の説法(顕教)と、大日如来(法身仏)の説法(密教)との関係が問題となるはずである。はたして釈尊はこの問題にどのように答えられるだろうか。
空海が下巻の冒頭に『六波羅蜜経』第一巻を引証するのはおそらくこの問題意識があったからでないだろうか。『二教論』の下巻はまさに釈尊と密教との問題から入っている。しかも『六波羅蜜経』第一巻の内容はまるで釈尊が密教を最高の教えとしていたかのごとくである。
この経典において、釈尊は仏法の宝とは何かを説くなかで、第一法宝は法身であると説くのである。(諸佛世尊如是説、(中略)第一法寶即是摩訶般若解脱法身)そして自分は救うべき方途にしたがって説法するのだと語る。
ここで注目すべきは、契経(経)や調伏(律)や、対法(論)でも、大乗の教え(顕教の般若)をもってもなお救われない者がいるとすれば、そのような人のために、まさに密教経典の教え「陀羅尼蔵」を説くと釈尊が語る件である。しかもこの五つの教えを五味に喩えて、経は「乳」、律は「酪]、論は「生蘇」、大乗経典は「熟蘇」、密教経典は「醍醐」にあたるとし、密教経典が諸経典の最高であることを認めている。また自分の入滅後は阿難陀(アーナンダ)など代表的な弟子たちに、それぞれに、経、律、論、大乗経典を守り伝えることを伝える。そして最後に金剛手菩薩に最も深遠な密教経典(総持門)を受け持たせるのである。
『六波羅蜜経』では明らかに釈尊は密教者として描かれている。無論歴史上の釈尊が後世発展し完成された密教を語るということではない。しかし、少なくとも大乗経典における釈尊像に密教的な視座が確保されているという意味において、空海が『六波羅蜜経』第一巻を『二教論』の下巻の冒頭にもってきた意図が推察できよう。なお空海の喩釈を確認しよう。
喩曰、今依斯經文佛以五味配當五藏、總持稱醍醐四味譬四藏。震旦人師等争盗醍醐各名自宗、若鑒斯經則掩耳之智不待剖割。[空海・大意]「喩していう。今この経文に依れば、仏は五味の譬えをもって五臓に配当し、総持を醍醐と称し、四味をば四蔵に譬えられている。中国の教師たちは、この醍醐を利用して自ら都合のよい解釈をしている。もしこの経典を手本にして考察するならば、他人には知られないように思っていても、必ず知られるものである。」[解釈]醍醐とは密教である。中国仏教の各宗は、自らを第五番目の最高の味といいながらも、それが密教に根ざしたものであることに耳をふさぎ、例えば法華一乗などというのである。そういう愚かな行為はいつかばれてしまうと空海はいう。つまり顕教の背景は密教であり、密教が顕教を支えているという空海の主張が込められている。空海は相手の息の根を止めるような論述はしないようだ。唯一最澄の主張(円密同一説)に対する反論を除けば、自らが気づくように道筋を示す論述が多い。私が『二教論』を顕密判釈の書というよりも「密教眼」の紹介としたのはそういう意味である。
そこで空海に促されて釈尊の解脱の体験を私なりに考えてみた。私の理解では、釈尊は覚りの瞬間、非日常的な、神秘的な体感があったのではないか、超常的な何ごとかと一体化された瞬間解脱されたのではないかと考えている。このような解釈は、釈尊の解脱に外部的な啓示を一切認めてこなかった伝統的な仏伝からすれば否定されるべき異論であろう。
釈尊は菩提樹下での瞑想中、明けの明星の出現とともに「四諦・八正道」の道理が忽然として胸裡に出現し、釈尊は大悟してブッダ(仏陀)になったというのが大方の仏伝になっているようだが、しかしそこには超日常的な体験があったと見るべきであることも指摘されている。(参考文献として、H・ベック著、渡辺宏訳『仏教』上、渡辺照宏『新釈尊伝』が挙げられる)
空海も虚空蔵求聞持の法を修するなかで、超常的と思われる体験をしていることは自ら語るところである。例えば土州室戸の崎での勤念を、虚空蔵菩薩の化身とされる明星の来影という表現(『三教指帰』)や、明星口に入り、虚空蔵光明照らし来て菩薩の威を顕す(『御遺告』)などという表現で神秘体験を語っている。
これはある種の人間に備わった高度な能力が起こす現象ではないだろうか。意識が自然界と共振する超常現象を今日ではサイ(Psi)現象(2)といわれて超心理学の分野では研究がすすんでいるが、もしかすると釈尊や空海はそれに近いような神秘的な実体験をしたのではないかと思われる。
つまり高度な覚りの瞬間には、超越的な何かと感応するのではないかということである。空海はそれを言語を超えた密教の世界で説いているように思える。であれば釈尊の覚りについても、当然空海はその秘密に関心をもったに違いない。空海は『般若心経秘鍵』の最後に次のように記している。
應化釋迦在給狐園為菩薩天人説畫像壇法眞言手印等、亦是秘密
「応化の釈迦は、給狐園に在して、菩薩・天人の為に画像・壇法・真言・手印等を説きたまふ。またこれ秘密なり」
とし、釈尊と三密行(密教)の関係を説いている。
はたして釈尊は初めから静かに瞑想されたのであろうか。これについては次のような報告もある。
「釈尊の大悟は樹下禅定の最終日の一回性の経験ではなく、七年世の長い修行経験の累積とその完成と見るべきであるというのが、最近の見解(中村元『ゴータマ・ブッダ』)である(3)」
空海もまた七年にもわたる山林修行期間があったことを思い合わせれば、両者には通じるものがあるように思われる。この仮説を裏づけためには、無師独覚とされる釈尊と「法」(ここでは法身としよう)との関係について、さらにもうひとつの問題を解決しておかなければならない。
◆釈尊の神概念と自灯明
一般に仏教は無神論といわれている。例えばイエス・キリストの背後には神が存在するが釈尊の背後には神はいないとされる。では釈尊の説いた仏教は神を否認しているのであろうか。この問題の根底にはどうも東西の神概念の違いがあるような気がする。
釈尊の生まれる以前からインドで神々とされていたのは、ヴェーダ群を起源とするバラモン教の神々である。釈尊の時代にインドで自覚されていた神は天界の住人であり、その神々を天・天人などと総称するが、天界は三界(欲界・色界・無色界)にわたって存在すると考えられていた。すなわち天も輪廻転生をまぬがれないのである。故に天が釈尊の前にひれ伏して説法を請うた(梵天勧請)と伝承されるのであろう。(ちなみに輪廻転生はあたかも仏教独自の業報思想のように思われているが、釈尊の時代すでにバラモン教の世界観として形成されていたもので、本来釈尊が説いたものではない。また釈尊が輪廻転生思想を積極的に受け入れたかどうかについては、学界では意見の分かれるところである)
つまりインドの神々とは西洋的な超越的な唯一絶対神とは異なるものである。このことは何を意味するのか。釈尊の時代、当時のインド人にとっての神とはバラモンの神々のことであった。釈尊があえて神仏を語らなかったとすれば、それはバラモンの神々すがるインド人の姿を見ていたからではないかと考えられる。
何故か、おそらくそこに人間の「苦の形成」を見たからではないだろうか。無明なる自分の心を凝視することよりも、外なる神々に供物を捧げて恩寵にすがろうとする人間の弱さ、安直さ、そして盲従性、またそこから生まれる宗教の権威主義化や固定化などに、人間の「業の形成」や「苦の原理」を洞察されたからではないだろうか。したがって釈尊の眼差しはひたすら「業熟体」としての人間に向けられることとなる。釈尊の宗教的本質は、何よりも人間の眼を自らの内面に向けさせ、自己の存在の真実に目覚めさせたことにあったといえよう。
加藤精一氏は次のようにいう。
「キリスト教やイスラム教のような天地創造神、神話の神を信ずる宗教では、互いに唯一絶対神となり、その結果神様同士の喧嘩が絶えないという矛盾をきたす。釈尊は2500年も前にこうした矛盾に気づかれて、神話の神を棄てて,この世は因縁によって成立しているのだという新しい原理を提唱された。神話の神を棄てて、かぎりなく高い人格である仏陀(ほとけ)を仰いで生活するという仏教の特色がここにある(4)」
それは神なき平等性だともいえる。釈尊はある意味では知性による実存、言い換えれば法(ダルマ=真実)に導かれつつ主体的な努力による自己救済の可能性を説かれたのである。
ここに「自らをともしびとし、自らを拠り所とせよ」という釈尊の「自灯明」の教えが生まれる。自らを灯明とせよとは、一見神の救いなき宗教のようでもある。かぎりない空漠の連打によって存在の「無」を覚るという仏教は、西洋人がいう「虚無の宗教」のようでもある。無常観というものが、あるいは無我というものが、あるいは縁起という存在の原理がはたして人生を幸せに導くのであろうか。
だが一方、釈尊は「法」をともしびとし、拠り所として生きよと「法灯明」も説かれた。これによって釈尊は拠り所すべてを無化する(空じる)虚無主義を説かれたのではないことは明らかである。釈尊がバラモン教に対峙した四姓平等観は、「神」の前ではなく「法」の前の平等である。では「法」を依り処にするとはどういうことか。むしろ問題はここである。
◆法灯明と初転法輪までの疑問
仏教が無神論だという本当の意味は、キリスト教的な人格神的かつ絶対的創造主を想定せず、あくまでも自身がダルマ(法)に目覚めることを目標とする教えであることを指す。つまりキリスト教的神学、西欧的宗教学で仏教を捉えたときに言い出されたことであって、仏教自身が無神論であるとはいっていない。
確かに仏教はバラモン教への批判という面はある。だが神話的創造神としてのバラモン教の神々を批判はするが、護法神としての神々までは否定しない。初期仏典の「スッタニパータ」にもインドラ(帝釈天)やブラフマン(梵天)や「神性を有するもの」などの護法神は登場する。それはバラモン教における崇拝対象としてではなく、仏教の護法神として再生した神々である。
特に密教ではダルマ(法)が具体的に顕現した形態の一つとして帝釈天・梵天・四天王・阿修羅・夜叉・竜王を捉える。これら守護神はダルマ(法)というファンダメンタルな世界から生まれ出されたものであるから、法灯明とは神々のもとの在所であるダルマ(法)そのものを灯明(拠り所)にせよということになろう。
密教ではそれを「法身」として明確に理論立てた。しかし同時に「法身は自らの内に有る」と空海は説く。そうすると釈尊の教えである「自灯明」と「法灯明」は結局一つのものであり、顕密も根底的には一つのもの(九顕十密)であるということにならないだろうか。
空海はおそらく『二教論』執筆当初から「九顕十密」を言いたかったのであろうが、新来の密教と旧来の顕教との基本的な相違を説くためにあえて「横の判釈」(九顕一密)を選択したとものと思われる。
それはともかく、問題は、釈尊は自らの覚りを余人においてなぜかくも理解不可能だと考えられたのか、ということである。釈尊の覚りの内容である縁起は、甚深で、難解であり、そのために人に説くことを諦められたほどである。
しかしながら縁起論自体は論理的にも経験的にも決して理解不可能というほどのものではない。故に小乗の縁覚(独覚)は縁起の理法を独りで覚りえる行者のことだといわれる。
にもかかわらず釈尊がこれほどまでに説法を拒み続けたということは、何か他の理由が考えられないだろうか。解脱は精神的に高度な覚りの世界とされるが、果たしてそれは釈尊独力による内的覚醒だけからくる体験だったのだろうか。大乗の修行者たちは、もしかするとこの点に疑問を抱いたのではないだろうか。私はそうである。
その疑問に迫れば、ひとつの推理として、前述したように釈尊は解脱されたその瞬間、言語に絶するようなある種の超常体験をされたのではないかと思われるのである。それは釈尊が「人間を超えたもの」、ある意味において「神性なるもの」を体験されたといえなくもない。そしてここでいう「神性なるもの」とは釈尊が「法」と呼んだもの、あるいは「法」自体の実在性で、のちに密教の法身仏に相当するものだったのではないだろうかと思う。
この推論を立てるについてはひとつ不思議なことがあるからだ。釈尊が最初に説かれたのは、縁起論ではなく四聖諦(5)であったということである。高野山大学大学院の谷川泰教教授はその理由を、難解な縁起を説明するために、釈尊によって考案された教育のための教えであるという。谷川教授によると、「四聖諦は、まず仏教随一の『説法』としての位置を確立する。その背後には、説けないもの、説いてはいけないとされたものの存在がある。それが『甚深』とされた縁起なのである(6)。」とされている。
しかし先述したように縁起論自体は「説けないもの」ではない。例えば十二縁起は行動心理学の参考になるほど論理的でもある。ある経典では、阿難(アーナンダ)が縁起というものはわかりやすい簡単なものだといって、仏陀にたしなめられたとあると谷川氏はいう(7)。
おそらく阿難のこの意味は、縁をまって法(事物)が生じるという(この限りにおいては正しい)解釈であろう。しかし問題は、釈尊が何故それをたしなめられたかということである。
『象跡喩経』によると「縁起を見るものは法を見る。法を見るものは縁起を見る」と釈尊は説かれたそうである。この言葉が事実であれば、釈尊のいう「法」とは、事物(モノ・コト)ではなく、この世を現象させる縁起の理法であろう。いや、縁起そのものを顕現させるもっと根源的な原理、言葉では言い表せないが、確かに実感された何かを指しているのではないかと思われる。縁起思想が弟子の誰もが容易に理解できるものでなかったのは、釈尊の覚りの実体験が、神性を有する超絶的なものの体験だったからではないだろうか。
釈尊がそれをあえて神仏と言わなかったのは、おそらくバラモンの神々しか神概念をもたぬ当時のインドにおいては伝えることができないと思われたのかもしれない。
インドでの仏教思想の変遷はそのことを追認しているように思われる。初期仏教では縁起説は「教義」として理解されたが、次第に縁起説そのものが「信仰の対象」になる。つまり仏そのものとされ、縁起=法=仏という等式が成り立つことになるのだ。
つまり私は、谷川教授氏のいう「説けないもの、説いてはいけないもの」は縁起論そのものではなく、縁起がつながるもの、(縁起すら生み出すもの)が「説けない、説いてはいけないもの(甚深)」だったのではないだろうかと推察するのである。
私見によれば、後に大乗仏教が根本命題とした「空」とは、実はこの甚深たる「法」につながるものではないかと考える。大乗仏教を真実探求の哲学体系だとするなら、その中心的概念を「空」に集約したことは、縁起→法→仏→空という発展的な等式も考えられないだろうか。逆観すれば「縁起を見るものは空を見る。空を見るものは縁起を見る」ということもできるのである。
釈尊の覚りの契機に神秘的・神性的なものの背景を考えるならば、縁起論も空観といわれるものも、単に釈尊独自の大悟というよりも、もう一つの外的世界のはたらきのようなものを考えざるを得ないのである。心身まるごと一体化されたその対象たる何かである。釈尊の宗教体験は、別言すれば「空と一体化した」、あるいは「法と一体した」ということではないだろうか。
「甚深」とは何か。谷川教授はいう。「仏教の歴史とは、この『甚深』へと迫った有名無名の仏教者達によるさまざまな試みの証であると言っても過言ではない(8)」と。
◆解脱と即身成仏
おそらく後の大乗仏教も同じ疑問を抱いたはずである。大乗仏教初期の編纂とされる『八千頌般若経』(紀元前~1世紀)には釈尊が智慧の完成(般若波羅蜜多)という「呪術」のおかげで無上にして完全な覚りを得られたことが繰り返し説かれている。智慧の完成とは偉大なる呪術であり、量り知れない呪術であり、限りない呪術であり、この上ない呪術であり、無上の呪術であり、至高の呪術であると答えられている。自分は智慧の完成という呪術によって無上の覚りを得たと明確に答えられている(9)。
羅什訳・玄奘訳の『般若心経』でも「深般若波羅蜜多」とわざわざ「深」という言葉をつけている。この「深」にあたるサンスクリット語のガンビーラは「甚だ深い」「尋常ではない」という意味であるから、「甚深」とは前述の神秘的な何かを指すのではないか。
マントラ行による神秘的体験とは真言密教でいう法身との相応渉入にあたるであろう。もしこの『八千頌般若経』が事実を伝えるものであれば、釈尊は密教的な「行」による瞑想を通して(法身)と一体化されたと考えるほかないのである。
高野山真言宗大僧正・阿字観の大先達である山崎泰廣師は次のようにいう。「釈尊はいかにして悟ったのか、それは人間の言説によって悟ったのではない。菩提樹下での深い瞑想によって、天地宇宙の真実の声を全身で聞いたのである」とし、釈尊の胸中に秘められた覚りそのものの教えを密教であると述べられている(10)。
また密教的な神秘体験によって解脱されたということは何を意味するか。釈尊の解脱は存命中のことである。釈尊が現世において仏陀になられたということは、ある意味でこれこそが完全無欠なる即身成仏を意味するのではないか。釈尊の覚りを成仏というならば、成仏とはあくまで現世での覚りの体験であり、仏教は本来「生」を中心とする密教原理に支えられた「いのちの解放・命の解脱・生命賛歌」とも考えられるのである。
<注>
(1) 教判とは教相判釈の略称。仏教経典の根本真理や仏道修行の究極目標を確立しようとする経典解釈学。教相とは教えのすがた、即ち教説・教理のことで言語の世界である。これに対して事相という考え方がある。事相とは現実的な事物の相(すがた)に目を向け、そこから言葉では表現しきれない深い真理に到達したり、あるいは真理を象徴的に表現しようとする実践的な行為を指す。たとえば曼荼羅の建立・灌頂・真言・印契・護摩などの作壇法などの密教儀礼に顕著である。密教では教相・事相を車の両輪とするが、密教の本質からすればむしろ事相こそが密教修習の中心であるといわれるほどである。密教は現実の森羅万象すべてを仏のシンボリックな説法と見るから、その説法は顕教の経典に書かれた言葉、すなわち「人語」を超えた異次元の言葉とでもいうしかない。私が『二教論』における顕密の判釈を、空海は言語論においていると考える所以である。
また密教のように実践面を重視することこそ仏道の真義である。むしろいたずらな哲学論議(学問仏教)にふけるのは、毒矢に射られながら矢を抜くことをせず、毒の種類や矢の飛んできた方向などを詮索するのにも似た愚であると釈尊はいう。(毒矢の喩え)
(2)「サイ」とはギリシャ語の「魂」の頭文字から派生し、英語でPsi(サイ)という超心理 学の用語として使用され超能力等の超常現象を意味する。サイ能力・サイ機能ともいわれるこの能力は生物の環境に対する適応行動の一つであると位置づけられている。 今日まだ未解明の多い分野でもある。
(3)『仏教文化辞典』佼成出版社p5
(4) 加藤精一『空海の風光』p.133
(5) 四聖諦とは四つの真実の意。苦諦・集諦・滅諦・道諦のことで四諦ともいわれる。
第一の「苦諦」とは迷いの生存(人生)は「苦」であるという真理。人間は自らの意思とは無関係に起きる変化(縁起)に従わざるを得ない。生・老・病・死、いずれも「苦」である。これは人生とは縁起の支配下にあり、思い通りにならないという真理でもある。
第二の「集諦」とは、この「苦」の原因を明らかにする真理。生老病死を「苦」と感じるのは老病死から逃れたいという欲望があるからである。欲望の尽きないことが「苦」を生起させるという真理。正確にいうと仏説では「苦」を生む根本原因を「無明」としている。無明とはこの世の真相が明らかでないこと。無明は欲望や煩悩など人間に貪欲・愚痴・瞋恚という三毒を生じさせる根源とされている。
第三の「滅諦」とは欲望を滅した状態が苦滅の理想的な境地であるという真理。煩悩の滅、すなわち「苦」の滅のこと。
第四の「道諦」とは、その「苦」の滅に至る道のこと。正見に立つ正しい人生の生き方のことで釈尊は八正道として説かれた。
以上は釈尊が鹿野苑で説いたとされる最初の説法(初転法輪)。仏教の根本教説。
(6) 谷川泰教『仏教要論・Ⅱ』pp.20-21
(7) 谷川前掲書p14
(8) 谷川前掲書p21
(9) 梶山雄一訳『大乗仏典②八千頌般若経Ⅰ』pp.104-105
(10) 山崎泰宏『阿字観瞑想入門』p.31