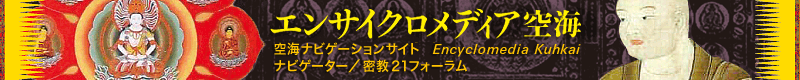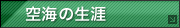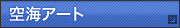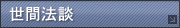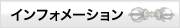◆ 剣山と空海
その②で秦氏は信仰を捨て去ったのではなく、日本に融け込んで、神道のなかに彼らの信仰を潜ませたのではないか、と愚考してみた。古代ユダヤ民族はアッシリアとも戦い、ローマ帝国に対して独立戦争も起こしている。それに対して皇帝ネロは圧倒的な軍事力をもって鎮圧し、エルサレムの第二神殿を破壊した(嘆きの壁)。つまりユダヤ人は「信仰の民」である一方「戦う民族」でもあった。
なぜ「剣山」というのだろう。「柴山古墳群」のユダヤ人埴輪の多くが「剣」を携えている。ユダヤ人は「剣の民族」でもあった。鉄剣を伝えたのはユダヤ人との説もある。ヤマトタケルが敵を討つとき、日本人とは思えない残忍な殺し方をしたのはユダヤ系の血が流れていたという学者もいる。
一方空海は「和の人」である。そう考えれば「剣神社」に空海の影が感じられなかったことも納得がいく。剣山や「剣神社」に空海の痕跡がなかったことが何となくわかるような気がするのだ。空海は「剣神社」にユダヤ的な臭いを感じ、積極的に関わる必要性を感じなかったのかもしれない。もちろん私の想像に過ぎない。
田中道秀博士によると、欽明天皇は540年に秦氏の7053戸を掌握するため「秦伴造(はたのとものみやつこ)」を用意したそうだが、ここで素朴な疑問が湧いてくる。海を越えて日本までたどり着いたユダヤ人は、おそらく体力も気力も財力も技術も知能も兼ね備えた優秀な人々であったろう考えられる。
ならばユダヤ系の秦氏はその財力や知能や組織力をもって、なぜ政権を狙う計画をもたなかったのか、という疑問である。彼らは皇室神道の中枢にも影響をおよぼすほどの実力もあった。しかも自分たちの国を再建することは悲願だったはずである。しかしそうはせず、天皇を守る方向に向かっている。
例えば奈良時代の道鏡事件、和気清麻呂が宇佐八幡のご神託を得て、道鏡が天皇の位につくことを防いだ事件もそうだ。宇佐神宮は秦氏の神社で全国の神社の総本山である。その神社が万世一系の天皇を守ってきた。
ということは、秦氏が神道に関わる天皇家の信仰形態を高く評価したためで、天皇を中心とする国家体制の平安を壊そうなどとは思わなかったからだ。
なぜ大陸系の彼らをそのように穏健にしたのかと愚問してみると、答えはすぐに返って来た。日本には荒魂を鎮める仏教があったからだ。海を渡って来た彼らは聖徳太子が仏教を国の理想とした日の昇る日本に、自分たちの理想郷を見たのだ。
宇佐八幡の主祭神がだれであれ、彼らは完全に日本と同化した渡来人だった。神道が仏教に帰依したことでもそのことがわかる(神仏習合)。空海は『十住心論』で神道については直接語っていない。「第三住心」でインドの神々のことに言及しているが、日本の神々のことは触れていない。しかし論理の流れからすると、当然日本神道の神々もこの段階に含まれることになる。天皇や貴族たち、おそらく神道関係者にとっても暗黙の裡に「了解済み」だったのではないだろうか。
その理由は神道(第三住心)がなぜ儒教(第二住心)より上で、仏教(第四住心~第九住心)の下の発達段階に位置づけられているかが、全体の論旨の中でしっかりと納得いくようになっているからである。神道を無視したのではなく、おそらく神道も「含んで超える」という総合的な空海のコスモロジーを神道関係者が納得したのだと思う。こういうことも含めて考えれば「剣神社」に空海の気配を感じなかったことに納得がいく。もちろん私見である。
◆ キリスト教と日本人
ここまで語ってきたように、古代から景教徒が日本の中枢に影響を与えていた。にもかかわらず、キリスト教禁止令が出される以前から、日本人はキリスト教的な影響をあまり受けていない。世界各地で宣教活動をしたイエズス会のフランシスコ・ザビエルが来日したとき「この国の民は賢く手強い」というような手紙を本国に送ったそうである。
それは「主の教えを信じる者は救われ、信じないものは地獄に堕ちる」と農民たちの前で語ったときのことだといわれている。日本に上陸したこの新しい神の話を聞いた時、農民たちは「じゃあ私たちのご先祖様はみんな地獄に堕ちているのか」と聞き返し、ザビエルは答えられなかったという。無学文盲の農民がそんな質問をしたのは、この国の常識として仏教の教えが浸透していたからであろう。
仏教は「因果応報」を説く(善因楽果・悪因苦果)。極楽に往生するのも地獄に堕ちるのも此の世の「行い」次第、本人次第である。キリスト教のように信、不信の問題ではない。現代流にいえば「自己責任」で、これは釈尊の、「人は生れに価値があるのではなく行為に価値がある」という教えからきている。
つまり古代から景教徒によるキリスト教的な下地はあったが、その後の日本人にその傾向が見られないのは、仏教的精神文化が浸透していたからだと考えられる。平安中期「本地垂迹説」が神と仏の整合性を理論化したのもそういう背景があったような気がする。
要するに日本人はユダヤの神を潜ませた(と思う)「神社詣」はしているが、キリスト教そのものは馴染まなかったのだと思う。現代でもキリスト教信者の数は国民の1%にも満たない。これは同じように儒教と仏教が伝来した韓国に、キリスト教系信者が30%もいるのと比較しても甚だしい違いである。
この相違をうがって考えれば、一つの仮説が考えられる。キリスト教と韓国人の共通点にその謎を解くカギがある。ニーチェが見抜いたように、キリスト教道徳の根底にはルサンチマンがある。ルサンチマンとは優れた者に対する恨み、嫉妬を含む鬱屈した反感、否定、相手を貶めることによって相対的に自己を高めようとする感情のことである。韓国も「恨」の国といわれる。韓国の反日感情は恐らくキリスト教的な屈折した感情に似たところがあって、国民の三分の一近くがキリスト教系の宗教団体に入信するのではないか。
キリスト教は弱くて貧しい者、力なき者、悩める者、病める者、乏しき者、卑しき者のみが善き者であり神にとって幸いなる者であるという道徳がある。ニーチェはこれを「奴隷の道徳」といった(『善悪の彼岸』)。
しかしそのような道徳を持つ限り幸せになれないと仏教は教えてきた。日本人は「水に流す」という言葉があるように、恨みを残さない文化である。未来永劫恨みを残す韓国人に比べれば、日本人は文化的にはるかに進化しているといわざるを得ない。
◆ 天皇と空海-仏教から読み解く日本人の倫理性-
ダグラス・マッカーサーが昭和天皇と初めて会見したとき、天皇は命乞いに来たと思ったそうだ。しかし天皇の口から語られたのは「先の戦争の全責任は私にある」ということだった。そして「私自身をあなたの代表する連合軍の採決にゆだねる」というものだった。まさに連合諸国が戦争犯罪人として天皇の断罪を主張していたときである。
マッカーサーは次のように記している。「この勇気に満ちた態度は、私の骨のズイまで揺り動かした」と。「死をともなう責任、それも私の知る限り、明らかに天皇に帰すべきでない責任を、進んで引き受けようとする態度に私は激しい感動をおぼえた。私は、すぐ前にいる天皇が一人の人間としても日本で最高の紳士であると思った」(『マッカーサー回顧録』)。
この時、同行していた通訳がまとめた天皇の発言メモを、翌日、藤田侍従長が目を通している。藤田は回想録にこう記している。「...陛下は、次の意味のことをマッカーサー元帥に伝えられている。『敗戦に至った戦争の、いろいろな責任が追求されているが、責任は全て私にある。文武百官は、私の任命する所だから、彼らには責任がない。私の一身はどうなろうと構わない。私はあなたにお委せする。この上は、どうか国民が生活に困らぬよう、連合軍の援助をお願いしたい』一身を捨てて国民に殉ずるお覚悟を披歴になると、この天真の流露は、マッカーサー元帥を強く感動させたようだ...」(藤田尚徳『侍従長の回想』)。
国民のために一命を差し出すような国王がいることにマッカーサーは感動し、その崇高さに心打たれたのだろう。天皇は国民を救うために命を懸けた。そういう天皇だからこそ、国民も天皇(国体)を守るために命懸けで連合軍と戦ってきた。マッカーサーとの会見は、天皇と国民の命がまさにひとつに燃えた瞬間だった。
さて、そのような天皇の在り方は、個人のパーソナリティ(人格)の問題に限定されるものだろうか。私はそう思わない。2600年以上続く皇室の家風と倫理観が培ってきたものだと思っている。そしてそのような家風を醸成する指導者の役を受け持ったのが仏教であったと思う。
そもそも仏教を取り入れた聖徳太子は「十七条の憲法」の「和を以て貴しとなす」に続く第二条で「篤く三寶を敬へ、三寶とは佛と法と懀となり...」と規定している。これは「仏法(仏の教え)」が「王法(世俗の法律)」の上にあるということである。もともとインド仏教では、「仏法」は「王法」の上に位置するものであった。だからインドの王様はみな仏陀(釈尊)を称えてひれ伏した。「十七条の憲法」を制定した聖徳太子は、その意味でインド仏教を正統に受け継いだ人だといえよう。
聖徳太子は仏教を中心にした理想の国の設計図を描き、天智天皇、天武天皇、持統天皇などの歴代の天皇がその方針を引き継ぎ日本の国づくりは進んだ。天武天皇の時代に「日本」という国号を内外に知らしめ日本的律令国家が確立。701年に国の基となる「大宝律令」を制定、仏の教えのもとで国家国民の繁栄と安寧を目指した。そうして聖武天皇の時代に、その象徴として「大仏殿」がつくられ、全国には国分寺・国分尼寺が建立されていった。
ところが中国仏教はそうならなかった。「仏法」は「王法」の上ではなく、皇帝の権力の下に置かれた。つまり「仏法」は国家権力の規制の中で生き延びざるを得なかったのである。この世の倫理が「仏法」ではなく、俗世の「王法」にあるということは、ときには権力の横暴を見逃すことにもなる。事実中国はそうなった。
現在でも中国は国の最高法規たる「中華人民共和国憲法」の上に共産党の独裁権力が君臨している。憲法序章において、国家は中国共産党の指導を仰ぐとしており、実質的に共産党の恣意が「王法」であり、その上はない。憲法に定められた三権分立は建前であり、共産党の方針でどうにでもなる。(チベット、ウイグル、香港問題を見よ)。アメリカの大統領は就任の時、聖書に手をおいて誓う。形だけかもしてないが、まだ「王法」の上があることを認めている。
日本を戦争に引き込んだルーズベルトは隠れ社会主義者である。スターリンとも仲が良かった。表向きはキリスト教のアメリカ人(保守)を装っているが、極左の大統領だったことは第31代大統領のフーヴァーが証明している。唯物主義の社会主義者にとって「王法」の上はない。
地上の権力は何をしでかすかわからない。「無明」の人間は暴走することがある。だから釈尊は「仏法」が「王法」の上位にあることを示したのだと思う。「仏法」に従うことによって人間の暴走をたしなめ、倫理的な存在にさせたかったのではないかと思う。
そのためにはまず国のリーダーたる王をそのように育てなければならない。古代の日本でいえば天皇である。しかし天皇といっても生身の人間で、怨恨もあり権力闘争もすることもあるだろう。誰かがそばにいて折に触れて教育をしなければならない。
空海は仏教の教えを説いて、盛んに時の天皇に「理想的なリーダー」とは如何なるものかを説いている。空海の『十住心論』では「第二住心」の叙述が半分以上も国王の忠告で費やされているのはそのためであろう。「第二住心」のテーマは倫理である。
(戦後の日本の知識人の大勢は、意味もわからずに、空海が天皇に近づいたという一事をもって空海を批判的に見てきた。空海の著作をろくすっぽ読みもしないで空海俗物説を展開するのは、先賢に対する大いなる冒涜である。)
中国史の碩学・黄文雄氏はこのようにいう。「空海の『秘密曼荼羅十住心論』は、人間の精神史の発展について、10段階に分けている。中国の主流の学である儒教は動物からやや進化した『第二住心』。反主流の思想である老荘思想は『第三住心』と分類(ランク付け)される。中国の思想文化は自画自賛するほどではなく、人類史から見れば動物に近い、文化レベルとしては『野蛮』にとどまっていると、空海は喝破していた。」と語っている。(『中国の正体』P.70~71)
しかし「第二住心」(儒教)で空海は、人間は確かに凡夫の段階からスタートするけれども、成長の可能性を持った存在であるということも語っている。まず、仏・法・僧の帰依「三帰」と世間的な道徳としての、「五常」(儒教)と仏教の「五戒」、さらに「八戒」、「十善戒」について述べていく。
「五常」とは仁・義・礼・智・信という五つの徳である。「五戒」はふつうの仏教信者が守るべき五つの戒で、盗まない、殺さない、邪な性交をしない、ウソをつかない、酒を飲まないということである。「五常」と「五戒」の二つの徳目ないし戒めは内容が完全に一致しているとはいい難いが、大事なのは精神政策として、儒教も含めあらゆる思想を全体の中に位置づけて包括するという空海の方向性である。
「八戒」は省略して、「十善戒」について、「不殺生」(殺さない)「不偸盗」(盗まない)「不邪淫」(邪なセックスをしない)「不妄語」(うそをつかない)「不両舌」(二枚舌を使わない)「不悪口」(悪口をいわない)「不綺語」(きれいごとをいわない)「不貪欲」(欲張らない)「不瞋恚」(怒らない)「不邪見」(まちがった考えをしない)である。
ここでは空海によって「神仏儒習合」という包括的なかたちで提出されていることに注目したい。おそらく神・仏・儒、共に天皇によって公認されていたために、天皇を教育する論拠としてまずもってきたのだと思われる。この手法は見事としかいえない。
日本は多元的価値を許容する文化・文明である。八百万(やおよろず)の神がいて、何でも受容していいものは残す。秦氏が受け入れられたのもこの日本人の精神性にあったからだと思われる。日本は多神教的な原始神道があるから、いかなる文化、文明、文物も排除せずに、四方八方から流入した。
空海は神道も仏教も儒教も、いいところはちゃんと押さえている。いいものはいいと考えていたようで、神・仏・儒から説き始めたのはそういう空海の包括的な思想があったからだと思う。天皇や貴族に対しては「人間は倫理的にならねばならない」といっておいて、続いてすぐに、「そして、まずは国王が倫理的にならねばならない」というふうに話が進められるのである。
「国王」という一般論で述べられてはいるのだが、時の嵯峨上皇や淳和天皇が読んだら、自分にも当てはまると感じざるを得なかっただろう。つまり、これは間接的でソフトな形でうまく上皇・天皇にお説教をしているのだ。
淳和天皇はそんなことを忠告されたくて『十住心論』を書かせたのではなかっただろうが、空海は天長の六本宗祇(=三論・法相・華厳・律・天台・真言・各宗の教義解説書)の提出のチャンスを生かして、実に巧妙に非常に多くのスペースを割いて、正しくない政治をする国王とはどういうものか、正しい政治をする国王とはどういうものかを説いている。
空海は「不正治の国王」つまり正しくない政治をする国王について相当厳しい言葉で叙述しているが、その際、自分の言葉よりも、主に権威ある皇室の経典を引用するというかたちを採っているから、天皇も内心はともかく、正面切って反発することはできなかっただろう。
すでに飛鳥から奈良時代にかけて護国の経典として公認された『金光明経』がある。その中にもしっかりしたリーダー論・国王論があるらしく、空海は一貫してこういう権威のある、いわば国王のテキストを引用するのだ。原文を簡略化すると、
これは飛鳥や奈良時代に、例えば四天王寺や東大寺が建てられた時の中心思想である。空海は淳和天皇に、「もう一度しっかり思い出してください、日本はこういう風に、仏教をベースにしてやっていく国だったはずですよね」「聖武天皇などの時代の理想はこうだったでしょう」と引用していわばクギをさしているのである。
もともと空海に人間的にも親しみ、尊敬も憶えていて、しかも嵯峨天皇の病気を治したり、雨を降らせたりする彼のものすごい呪力に対する畏れも尊敬の気持ちもある。そういう人から「国王たるものはかくあるべし」とお説教されたら、「身を慎まなければ」と天皇たちも思っただろう。嵯峨や淳和だけでなはなく、歴代の日本の天皇には、こういう厳しい仏教の忠告をする人からちゃんと学んだ天皇も少なくなかったようだ。
しかし空海は、ただただ不正な政治をする国王への否定的な言葉を採録するだけではなく、むしろ正しい政治をする理想の国王とはどういうものかを語ることに頁を費やしている。臨床心理学的な言葉を借用すれば、「肯定的アプローチ」で天皇を育てようとしているのだ。ダメな国王の話をした後、逆に正しく治める国王・「正治(しょうち)の国王」であればどうなるかについて、こう述べている。
正しく治める国王についての詩
八方四千の贍部洲(ぜんぶしゅう=我々の世界)の国王が
心をただし正しい思いを保って気ままにならず
宮殿を厳かに飾って経典の教えを講義させ
人と教えを敬って供養し
正しい理法を修行して悪行を絶つならば
上下がなごみ親しむことは乳と水のようである
慈悲と謙虚さをもって十の善行を修めれば
諸々の神々は喜んで国王を守護し
風雨は季節にしたがって、五穀は実り
災難は起こらず、国土の人々は楽しむ
うっかり読み落としそうだが、ここで注意すべきは「異生(いしょう)の正しい法で国を治める国王」といっているところである。「異生」とは「凡夫」のことである。つまり天皇陛下、あなたも本来は凡夫なのですよと、さらっと呑み込ませているのである。そういわれれば、天皇も自分は凡夫だと思ったかもしれない。
そもそも聖徳太子はそういう人だった。自ら凡夫であるという自覚があり、だからこそ「菩薩的な天子であろう」という志をもったのである。「そういう天皇の理想に沿って欲しい」というのが空海の願いであったと思う。
このあとさらに『金光明経』を引用し、
「天皇陛下、これが国の理想でしょう。あなたもそのような一国のリーダーになってください」と空海は切実に訴えているのだ。これらの教化が見事なのは、国王のあるべき姿を語るだけではなく、そういう国王になればご自分にどのような利益があるかを詳しく叙述していることだ。
例えば、姿かたちが端正で美しくなるとか、病気になることがないとか、民たちから愛されるとか、寿命が長くなるとか、真理によって統治するので国は太平であるとか、国を治めるのに武器を使う必要もなく、内外に陰謀もなく、諸々の災難や疫病や飢饉がないと教える。
おまけに種々様々な宝が集まってくるといって、国王のモチベーションを高めているのだ。つまり空海は太平の世を実現するために、様々な方便をつかって国のリーダーを教育しているのである。
さらに愉快とまでいいたくなるのは、理想的な国王になれば素晴らしい美女という宝も得られるとまでいう。実に魅力的な文章でその美女の様子を描いた箇所がある。原文は長いので一部だけ紹介する、
身体の肉はなめらかで皮膚に張りがあり
皮膚は細やかでうっすらとして、荒々しいことには耐えられない...
歯の色は玉を貫いた白瑪瑙(しろめのう)のごとく
赤い唇は頻果樹(びんかじゅ)の果実ように厚すぎず薄すぎず...
すべての美しさが完全にそなわっていて天女のようであり
天の衣と飾りと香りで身を飾り
歌や舞や、朗らかな笑い声で王を喜ばせる...
不謹慎だが現代風にいうと色白でボン・キュ・ボーンの美女が手に入るよと、密教の大先生がいうのである。最澄にも法然にも道元にも絶対書けない文章である。『三教指帰』を読んだとき、仮名乞児(修行中の空海)の描写にも抱腹絶倒したが、空海は澄まし顔で、いや真面目くさって人を笑わせるところがある。この文学性というか、ユーモア精神というか、こういうところも、私のような凡俗なものまでが空海に魅了されてしまうのである。
空海は高野山に戻ろうと天皇に帰山の許しを請う時、「人事に疎い私のような者が、華やかな宮廷の仕事は向かない」といって辞退しようとしたが、どうして、どうして、空海は実に人間味に溢れ、人間の機微にも通じた人であった。
このように空海はあらゆる方便を駆使して、天皇が「正治の王」を心がける動機づけをするのである。時代が違うとはいえ、漢文だけの空海の書物が読めた天皇や貴族たちも相当な教養人であったと思われる。ともかく以上のようなことが書かれている書物を淳和天皇が受け容れたのは、天皇が空海の言葉に納得したということである。
それがどんなに大きなことだったか。その結果、宮中の正月の最初の七日間の儀式は神道で行い、後の七日間の儀式は真言密教のかたちで儀式をする、つまり日本は皇室においても明確に神仏習合となったのである。そして平安時代は(細かいことはいろいろあろうが)ともかく江戸時代よりも長い300年以上の間続いたのである。
本稿のテーマに戻すために後は省くが、要するに天皇家、昭和天皇のお人柄はこのように身近に仏法を説く人がいて育成されたものではないかといいたいのである。
◆ 天皇陛下と日本人
神格天皇は否定され、戦後は「象徴天皇」になった。「象徴」の解釈はいろいろあろうが、本稿のテーマである人間の菩薩への進化ということならば、私たちは身近に菩薩を見ている。それは天皇陛下である。被災地では亡くなった人々のために祈りを捧げられ、避難所では膝を折り、ひとり一人の手を握って励まされる天皇陛下のお姿や、日夜国民の幸福を祈られている天皇のありようがそれである。
菩薩的な人はもちろん巷にもたくさんいる。ただ「日本国及び日本国民統合の象徴」(日本国憲法)としての菩薩は天皇陛下をおいて他にはない。菩薩の「慈悲」や「私心のなさ」や「品格」や「尊厳」や「霊的」なものまで備えた天皇こそ日本国民の象徴というに相応しいのではないだろか。
各国の元首が皇居で天皇に拝謁したときに、犯しがたい「威厳」や「品格」を感じるのは、仏教の薫陶をうけてきた歴代天皇家の伝統の重さと、背後に背負われた皇祖の御霊があるのではないかと思う。
かつて作家の三島由紀夫が日本の「文化概念としての天皇」を主張したのはこういう意味であった。言い換えると、三島由紀夫は天皇を「日本文化の象徴」だと主張したのである(『文化防衛論』1969)。まさにそのとおりだと思うが、ただ私は三島由紀夫の『文化防衛論』は天皇神道に偏重をしたものを感じた。
それに対して私は、日本文化というなら、庶民にまで広く浸透しているという意味では、神道よりも仏教の方がより相応しいのではないかとの思いを表明した。<本サイト 高橋憲吾のページ>『スカラベの愛―三島由紀夫と密教―』
その思いは今も変わらない。また世界は三島由紀夫の時代と変わった。三島のように一国の文化だけを守る「文化防衛論」の時代は終わった。神をも恐れぬ核兵器を拡散してきた世界においては、もはや人類を守る「世界文化防衛論」の時代ではないかと問うたのである。
三島の文化防衛論の思想を含んで発展させるためには、西洋の選別思想や中華思想を超えて、それぞれの文化の多様性を認め合わなければならない。そのための哲学思想は、それぞれの違いを認めつつ、なお反省と成長段階があることを教える、空海の十住心論的人間観と、すべてを包摂する密教的世界観だと思う。そこに世界が目覚めることを祈らずにはいられない。
その思いを「人間の進化と真価」という視点から本稿を書いてみた。稚拙な理想主義、いや夢想に過ぎないとの批判は甘受する。しかし実態も知らず、根拠も示さず、人さらいをしても恥じない犯罪国家北朝鮮を「地上の楽園」だと称賛してきた朝日のような理想主義ではない。私は拙い分析ではあるが、古代の日本の宗教の原点(太陽信仰)から太平洋戦争までを見直した。その上でなおいいたい。
日本は一貫して「和を尊ぶ平和国家」を目指してきた。理想を捨てた思想に何の意味があろうかと。そして国益と権謀術数が渦巻く国際社会において、自国の理想と平和は、国民自らが守り抜こうとする明確な意志と、具体的な安全保障の機能が備わってこそ維持できるものであると。