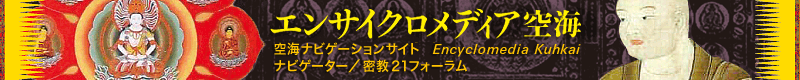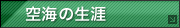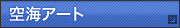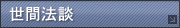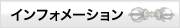自然と人間のこころの関わりについて空海は「そもそも、環境はこころにしたがって変わるものである。こころが汚れていれば環境は濁るし、その環境によってまた、こころも移り行くことになる。静かな環境に入り、そこに身を置けばこころも清らかである。そして、こころと環境が合致し、互いが無心にひびき合うことができれば、万物の根源となる"自然の道理"とそのはたらきである"知"が自ずと発揮される。そこに悟りがある」と説く。
空海に先んじて、その静かな環境、奥深い山に分け入り、そこで修行することによって悟りを得た行者が、勝道上人(しょうどうしょうにん)である。下野国芳賀(しもつけのくに、はが:今の栃木県真岡市)の人であった。
上人は少年の頃から蟻のいのちですら殺生しなかった。青年になってからも善悪の戒律を守り、こころは清らかであった。世間の生き方にこだわらず、仏教の空(くう)の教えを学び、街の喧噪を嫌い、自然の清らかさを慕って、山林での修行にひたすら励んだ。
その青年が48歳になって、日光山(男体山)登頂に成功し、開山の祖となった。
上人は、817年に83歳で亡くなられるが、その3年前に、人を介して、名勝の地、日光の記述を空海に依頼した。仲介者と空海は昔からの知り合いだったので、これを引き受けることになる。空海、41歳のときである。
以下は、その空海執筆による「沙門勝道、山水を歴(へ)て玄珠を瑩(みが)く(道を極める)の碑」からの、我が国最初の「登山記」と日光山での上人の悟りの場面を口語訳したものである。
七六七年四月上旬
(上人、)日光男体山の登頂を試みる。しかし、雪は深く、崖はけわしく、行く手を雲と霧に閉ざされ、雷にあい、断念する。中腹まで引き返し、そこに二十一日間滞在したのち、下山する。
七八一年四月上旬
再度、登頂を試みるが失敗する。
七八二年三月中旬
今回は、登頂するまでは絶対にあきらめないとの覚悟を決め、周到に準備をし、山麓に着いた。そこに一週間滞在し、日夜の登頂祈願を行なった。
「わたくしが登頂をめざすのは、すべての生き物の幸せを願うためです。その証として、わたくしが不浄のこころの持ち主でないことを示す経文と仏の絵姿図を自らしたためました。これを、山頂に辿り着くことができれば神々に捧げます。どうか、善き神々よ、そのちからを示し、災いとなる霧を巻き収めさせたまえ、山の精霊たちよ、わたくしを先導するためにその手をお貸しください。この願い、もし聞き入れなければもう二度と登頂を試みません。そして、もはや悟りを得ることはないでしょう」。
このように願いをたておわると、雪の白く続くところを越え、緑のハエマツのきらめく崖をよじ登った。崖の上から頂上までは残り半分の距離であったが、からだは疲れ果て、体力を消耗してしまったので、その場に二泊して、体力を回復し、そして、とうとう頂上に立った。
(今、この場にいることは)夢のようであり、でも現実であることを実感しながらうっとりしていると、天空を飛ぶ筏(いかだ)に乗らなくても、たちまちのうちに銀河の流れに浮かんでいるようだし、妙薬(幻覚剤)を舐めていないのに、自然の神の住むという岩屋を訪れている気がする。ただただ、喜びに涙し、こころは平静ではいられなかった。
この山のかたちは、東西は龍がうつぶせに寝た背骨のようであり、その眺望は限りなく、南北は虎がうずくまったようであり、まるで、巨大な虎が棲息しているようである。
この山は、世界を創る神の住む山、須弥山(しゅみせん)の仲間のようであり、周囲の山々も須弥山を浮かべる外海を取り巻いているという鉄囲山(てつちせん)のようである。
中国五岳に数えられる衡山(こうざん)・泰山(たいざん)もここよりも低く、諸国の伝説の山、仙人の住むという崑崙山(こんろんざん)や、よい香りのただようというインドの香酔山(こうすいざん)にも勝っていると、この山は笑っているようだ。
この頂きは、日が昇るとまっ先に明るくなり、月が昇るともっとも遅く沈む。ここからだと神通力をもつ目がなくても、万里の彼方までが目のまえにあり、一挙に千里を飛ぶという神話の鳥さえいらない。白い雲海はわたくしの足の下にあるのだ。
広がる色とりどりの景色は、機(はた)もないのに美しい錦を織りなし、いろんな高山植物は一体、誰が作ったのだろう。
北方を眺めると湖(今の川俣湖の方向にあたる)があり、その広さはざっと計算すれば一百頃(けい:中国地積の単位。一頃は百畝)。東西は狭く、南北は長い。
西方をふり返ると、やはり一つの湖(湯の湖)があり、二十余頃の広さはありそうだ。
西南方に目を向けると、さらに大きな湖(中禅寺湖)があり、広さは千余町(一町も百畝)もありそうだ。南北は広くないが、東西は長く伸びている。湖面にはまわりをとりまく山々の高い峰がその影を逆さに落とし、その山肌にはいろんな変わった草木や岩が自ら織りなす、奥深い色合いがあり、白銀の残雪のあるところからは早春の花が咲き、金色に輝いている。それらのすべての色が余すところなく鏡のような水面に映し出されている。
山と水は互いにひびき輝き、その絶景がわたしを感涙させる。四方を眺め、たたずみ、見飽きることがない。しかし、突然の雪まじりの風がそれらの景色を打ち消してしまうー
わたくし勝道は小さな庵を西南(中禅寺湖側)の隅に結び、登頂祈願の約束を神々に果たすため、そこに二十一日間滞在し、勤めを行ない、そののち、下山した。
七八四年三月下旬
改めて(今度は中禅寺湖とその周辺を探索するために)日光山に入った。五日間をかけて湖のほとりに着いたときには四月になっていた。
ほとりで一艘の小舟を造り上げた。長さは二丈(一丈は十尺)、巾は三尺(一尺は約三十センチ)。さっそく、わたくしと二、三人が乗り、湖に棹をさし、遊覧した。
湖上より周囲の絶壁を見回すと、神秘的で美しい景色が広がっている。東を眺め、西を眺め、舟の上下の揺れにあわせて気持ちもはずむー
まだまだあちらこちらを遊覧したかったが、日暮れには南の中洲に舟を着けた。その中洲は陸から三百丈足らず離れていて、広さはタテヨコ三十丈余りあり、多くの中洲のうちでも勝れて美しい景観をもっていた。
次の日からは湖の西岸に上がり、西湖(西の湖)に出かける。中禅寺湖からは十五里(平安時代、一里は約五百メートル)ばかり離れたところにある。また、北湖(湯の湖)も見に行った。そこは中禅寺湖から三十里ばかり離れたところにある。いずれも美しい湖であるが、中禅寺湖の美しさにはとうてい及ばない。
その中禅寺湖はみどり色の水が鏡のように澄みわたり、水深は測り知れない。
樹齢千年の松や柏の常緑の枝が水面に垂れ、岩の上には紺色の楼閣のような巨大な檜や杉が突っ立っている。
あじさいの五色の花は同じ幹に混じりあって咲き、朝・昼・夕・晩・深夜・明け方にそれぞれに鳴く鳥は、同じさえずりに聞こえても、それぞれに種類のちがう鳥なのだ。
白い鶴は羽をひろげてなぎさに舞い、青い水鳥は湖面に戯れている。それらの鳥の羽ばたきは風に揺れる鈴のよう。その鳴き声は磨かれた玉の響きのよう。
松風は琴となって音色を奏で、岸に寄せる波は鼓となって調べを打つ。
それらの自然の発する響きが合わさって天の調べとなり、湖水は甘く・冷たく・軟らかく・軽く・清く・臭いなく・のどごしよく・何一つ悪いものを含まず、たおやかにゆったりと貯えられている。
(湧きだす)霧や雲は、水の神があたりをおおうしわざであり、星のまたたきと稲光は、天空の神、明星がしばしばその手を虚空に入れ、それらをつかもうとするからである。
今、"湖水に映る満月を見ては、あるがままに無心に生きるということを知り、空中に輝く日輪を見ては、すべてのいのちが陽光の恵みによって共に生かされていて、その自然のもたらす英知とわたくし勝道が一体のものである"と悟る。
―そののち、この悟りの地にささやかなお堂を建て、神宮寺と名づけた。ここに住んで自然の道理とそのはたらきに身を託し、そのまま四年の歳月が過ぎた。
七八八年四月
さらに北の端に住まいを移す。この地の四方の眺望は限りなく、砂浜は好ましい。さまざまな色の花はその名も分からない不思議なものばかりであり、どこからともなく漂う、嗅いだことのない芳純な香りがわたくしの気持ちを和ましてくれる。
ここに住んでいたにちがいない仙人はどこに去ったのか分からないが、自然の神々が確かにここにはいる。
この美しい地を、中国の文人、東方朔はその著『海内十洲記』の名勝の地の一つとして、どうして記さなかったのだろう。山水を愛でる貴族たちはどうしてここに集い、舟を浮かべて遊ばないのだろう。
(ブッダは苦行の時代、飢えた虎に身を供養し、その餌食となったとの話があるが)その虎に出遭うこともなく、(不老不死の仙人)子喬もすでに立ち去ったあと。そのような聖なる地の澄みきった広い湖水からは鏡のようなこころを学び、日光山からは自然界を創りだしている無垢なる仕組みを知る。
冬は茂るツタに寒さをさえぎり
夏はおおう葉陰に暑さを避ける。
菜食をし、水を飲むだけでの生活でもこころは楽しく
あるときは出かけ、あるときは止まり
俗界を離れて、ひたすら修行しているわたくし勝道がここにいる。
八一四年八月三十日空海記す。
勝道上人が日光男体山に初登頂(782年)したとき、空海は真魚(まお)と呼ばれる、まだ8歳の少年であった。その少年が若くしてあらゆる学問に通じながらも、20歳過ぎには都の大学を去り、山のやぶを家とし、瞑想をこころとして、山林に入り修行した。
その頃のことを、空海は一編の詩に綴っている。
―前文略―
谷川の水一杯で、朝はいのちをつなぎ
山霞を吸い込み、夕には英気を養う。
(山の住まいは)たれさがったツル草と細長い草の葉で充分
イバラの葉や杉の皮が敷いた上が、わたくしの寝床。
(晴れた日は)青空が恵みの天幕となって広がり
(雨の日は)水の精が白いとばりをつらねて自然をやさしくおおう。
(わたくしの住まいには)山鳥が時おりやって来て、歌をさえずり
山猿は(目の前で)軽やかにはねて、その見事な芸を披露する。
(季節が来れば)春の花や秋の菊が微笑みかけ
明け方の月や、朝の風は、わたくしのこころを清々しくさせる。
(この山中で)自分に具わる、からだと言葉と思考のすべてのはたらきが
清らかな"自然の道理"と一体になって存在していると知る。
今、香を焚き、ひとすじのけむりを見つめ
経(真理の言葉)を一口つぶやくと
わたくしのこころは、それだけのことで充たされる。
そこに無垢なる生き方の悟りがある。
―後文略―
空海文集「山中に何の楽(たのしみ)か有る」より
そう、空海もまた、自然と人間のこころの関わりをよく理解し、そこから、悟りを得る修行をしていた。だから、日光山における勝道上人の行状をまるで見ていたかのように記述できたのだ。その記述に目を通し、上人は満足したことと思う。そこには、上人と同じ澄んだ目とこころをもつ、空海という人がいた。
<あとがき>
このエッセーは、大師が「心境冥会して道徳玄かに存す」(こころと環境が奥深く合致すれば、そこに自ずと、万象の道理にもとづく生き方が存在する)と説いておられるとの高木訷元氏からのご教示と、「日光山の開山勝道上人を讃えたわが国最初の登山記」との宮坂宥勝長老からのご教示を元として書き綴ったものである。空海の説くインド伝来の密教の教えのバックボーンが日本古来の山岳(山林)修行のなかにすでにあった。そんな確信を得ることができたのはそのご教示のおかげである。両先達に厚くお礼申し上げます。筆者