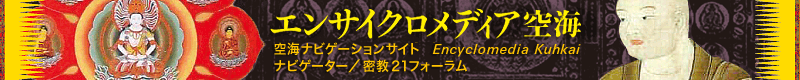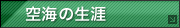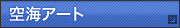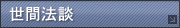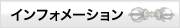「勝道上人日光開山記」と銘文-『沙門勝道歴山水瑩玄珠碑』(全訳)
<はじめに:環境と心について>
けがれのない静かな山には聖人が住み、清く澄んだ池には水神の龍が棲むという。
聖人が静かな山を居場所とし、龍が清水の中から生まれ出るにはしかるべき理由があるはずだ。
そこで、このことをまず論じておこう。
そもそも環境は心にしたがって変化する。心がけがれると環境は汚濁される。その心はまた環境によって移り変わるから、けがれなく静かな環境に身を置けば心は清らかである。
そのように心境(しんきょう)冥会(みょうえ)にして、道徳玄(はるか)に存す。(清らかな心と静かな環境とが一体であれば、万物の"道理"とそのはたらきである"いのちのもつ無垢なる知による正しい行ない、すなわち徳"とがそこに存在する)
だから、釈迦や文殊が常に静かで清らかなる山水の地を居場所として、人びとを説法・救済したこととなると、聖人たちが動かぬ山にはおおらかなる心を、湧き流れる清き水には臨機応変なる才知を託し、身心を磨き光らすことによって人びとの如何なる信仰心にも対応できるよう、日々修行を為されていたのだと思わないわけにはいかない。
<勝道上人日光開山のいきさつ>
ところで、下野芳賀(しもつけはが:現在の栃木県真岡市)に出家僧の勝道(しょうどう)という者がいた。俗姓は若田氏。
少年期から小さな蟻のいのちですら救うという心根をもち、大人になっても戒律を守り、心は清らかであった。世俗の生活に縛られることを嫌い、天台宗の説く三諦(さんたい:万物の空と有の中道を真理とする教え)を学び、悟りを求めたが飽き足らなかった。(そこで)集落の喧噪から離れ、清らかな山に籠もり、厳しい修行を行なうことによって得る(神仏習合の山岳仏教の)悟りを目指した。
この勝道のいた下野に観音の霊場と呼ばれていた山(日光山)があった。
その青い峰は夜空の銀河を挿(さ)し、昼間の白い峰は青空を衝(つ)く。とどろく雷鳴は中国の揚子江に棲むワニが山の中腹で吠えているようであり、山の周囲に広がる景色はまるで羊が角を突き合わせるように、鳳凰(ほうおう)が飛び交っているという風情であった。
また、山道は中程で途絶えていたから、奥深い山中の精霊に出会おうとしても出会いようがなく、まして、すれちがうことなどなかった。
(そういうことで)誰に聞いても未だに登頂した者はいないということであった。
勝道は(登頂を決意し、その修行に)釈尊の苦行の勇猛なる行動を思い重ね、心をふるい立たせた。
(こうして、勝道の日光山登頂計画が始まった。以下は空海執筆によるその開山記と日光の美しい自然を綴る我が国最初の登山記である)
七六七年四月上旬
(勝道、)日光山の最初の登頂を試みる。しかし、雪は深く、崖はけわしく、行く手を雲と霧に閉ざされ、雷にあい、断念する。中腹まで引き返し、そこに二十一日間滞在したのち下山する。
七八一年四月上旬
再度、登頂を試みるも失敗する。
七八二年三月中旬
今回は、引き裂いた下穿きで足をつつみ(周到な準備をしたうえで)、命をも捨てる覚悟をし、山麓に着いた。
先ずそこに野営し、経を唱え、仏を礼拝し、一日に七度ずつ七日間の毎日、登頂が成功するよう神々に祈願した。
「もし、神々に人の志しを知るちからがあるならば、どうか、わたくしの心を察してください。わたくしが登頂をめざすのは生きとし生けるものすべてが幸福になるように願うためです。その証しとして、わたくしが不浄の心の持ち主でないことを示す経文と仏の絵姿を自らしたため、背負ってまいりました。これを、山頂に辿り着くことができれば神々に捧げます。どうか、善き神々よ、その万能のちからを示し、水の神である龍は障害となる霧を巻き収めさせたまえ、山の精霊たちよ、わたくしを先導するためにその手をお貸しください。この願い、もし聞き入れなければ二度と登頂を試みません。そうなれば、もう悟りに至ることはないでしょう」と。
このように誓願し終えると、八日目の早朝に祈りの場であったベースキャンプを出発し、真白な雪のつづく樹林帯を抜け、(溶岩と火山礫の上に生える)緑のハイマツの光り輝くところをよじ登った。
よじ登ったところから頂上までは残り半分の行程であったが、からだは疲れ果て、力尽きてしまったので、その場に二晩とどまり、体力を回復させた。
そうして、(三日目に)ついに山頂に立った。
(今、この山頂にいることは)夢のようであり、でも、これは現実なのだと思いながらも茫然としていると、筏(いかだ)もないのに、たちまちのうちに横たわる銀河の流れに乗り、妙薬を舐めていないのに、神の住む岩屋に訪れている気がする。
ただただ、喜びに涙し、心は平静ではいられない。
この山のかたちは、東西は龍の背の連なりのようであり、その眺望は限りなく、南北は虎がうずくまったように盛り上がり、まるで棲息しているのではないかと想わせる。
世界の中心にあるという須弥山(しゅみせん)をも仲間とし、須弥山の浮かぶ大海を取りかこむ鉄囲山(てつちせん)のような山々を帯状に率いる。
中国五岳に数えられる衡山(こうざん)・泰山(たいざん)を低いと笑い、伝説上の山、仙人の住むという崑崙山(こんろんざん)やよい香りのただようというインドの香酔山(こうすいざん)もここよりは劣っていると笑っているようだ。
(この頂上は)日が出ると一番先に明るくなり、月が昇るともっとも遅くに沈む。
(この場に立っていると)神通力がなくても万里の先が目の前に見え、足もとには白い雲海が広がるから、その雲に乗れば一挙に千里を飛ぶという神話上の鳥、黄鵠(こうこく)に乗る必要もない。
(眼前に広がる)美しい錦のような景観は、織り機もないのに織りつづけられている布のようであり、限りなく生み出されるさまざまな神秘の図柄は一体、誰がデザインしたものなのだろうか。
(この頂上から)北方向を眺めると湖(湯ノ湖)があり、その広さは推計して一百頃(けい:中国地積の単位。一頃は百畝、百畝は一万平方メートル)。東西は狭く、南北は長い。
西方向をふり返ると、一つの小さな湖(西ノ湖)があり、広さは二十余頃ぐらいありそうだ。
南方向の眼下には、一つの大きな湖(中禅寺湖)があり、広さは全部で千余町(一町も百畝)もありそうだ。南北は広くないが東西は長く伸びている(※原文では形状が逆に記されているが現状に合わせた)。湖のまわりをとりまく山の峰々の影を逆さに水中に落とし、多くのめずらしい植物と岩とが織りなす山肌は自然の神秘そのものの彩りであり、白い残雪のあるところからはもう早春の花が枝から咲き出て金色に輝き、それらのあらゆる色合いが鏡のような水面にくまなく映し出されている。
今、山水が美しく響き合う景色の中にあって、それを見つめる自分がそこにいることがわたくしを感涙させる。
四方をただただ眺め、立ち尽くし、見飽きることがない。
しかし、突然の雪交じりの風がそれらの情景を打ち消してしまった。
わたくし勝道は小さな庵を西南(中禅寺湖を見下ろす側)の隅に結び、登頂前に誓願した成功のお礼を山の神々にするためにそこに二十一日間滞在し、勤めを行ない、そののち下山した。
七八四年三月下旬
(初登頂から二年後に)また(今回は中禅寺湖とその周辺の湖を探索するために)日光山に登り五日を経て南の湖(中禅寺湖)のほとりに着いた。
ほとりに野営し、四月上旬に一隻の簡単な舟(筏)を造り上げた。長さは二丈(一丈は十尺)、巾は三尺(一尺は約三十センチ)。さっそく、わたくしと二、三人が乗り、湖に棹をさし、遊覧した。
舟の上より周囲の絶壁を眺めると、神秘的で美しい多くの景色が展開する。東を眺め、西を眺め、舟の上下の揺れにあわせて気持ちもはずむ。
まだまだ遊覧したかったが、日が暮れてしまったので南の中洲に舟を着けた。その中洲は陸から三百丈足らず離れていて、広さは縦横三十丈余りあり、多くの中洲のうちでも勝れて美しい景観をもつ。
(翌日には中洲を発ち、湖岸に舟を着け)西方向の湖(西ノ湖)に出かけた。南の湖(中禅寺湖)からは十五里(平安時代、一里は約五百メートル)ばかり離れたところにある。また、北方向の湖(湯ノ湖)も(陸路で)見に行った。そこは南の湖から三十里ばかり離れたところにある。いずれも美しい湖であるが、南の湖の美しさにはとうてい及ばない。
その南の湖(中禅寺湖)の水は青々と鏡のように澄み、その水深は測り知れない。
常緑樹は水際に緑の天蓋を連ねて傾(かたむ)け、岩の上には紫がかった濃い青色をした巨大なヒノキやスギが楼閣のようにそびえ立つ。
アジサイの繁みには五色の花が混ざり合って咲き、同じように聞こえる野鳥のさえずりは朝・昼・夕・晩・深夜・明け方にそれぞれに鳴く違う種類の鳥なのだ。
なぎさに舞う白いツルや水にたわむれる青色の彩りもつカモの群れ、その羽ばたきは振れる鈴の音、その鳴き声はひすいの玉が触れ合うひびきのよう。
松風は竪琴を奏で、岸に寄せる波は鼓(つづみ)を打つ。
それらの自然の発する五つの音色(ド・レ・ミ・ソ・ラ)は天の奏でる妙なる調べとなり、甘く・冷たく・軟らかく・軽く・清く・臭いなく・喉ごしよく・何一つ悪いものを含まないという八つの水質はこの湖の湛える八つの徳となる。
(湧き出す)霧のとばりと雲の幕は、水の神の龍があたりをおおう仕業(しわざ)であり、星のまたたきと稲妻の閃光は、天空の神の明星(金星)がしばしばその手を虚空に入れ、それらを掴もうとして掻き回しているからである。
今、"湖水に映る満月を見ては、万物は互いを映し出すことによって存在していると知り、天空に輝く太陽を見ては、(その光のエネルギーがあるからいのちが存在し、いのちがあるからそこに無垢なる知のちからからもある)その英知のすべてがわたくし勝道の身心に宿っている"と悟る。
この悟りの地(北岸の中程)に(神仏習合の)ささやかなお堂を建て、神宮寺と名づけた。
そこに住んで"自然の道理"と"いのちのもつ無垢なる知のちからのはたらき"に身心を託して修行をし、そのまま四年の歳月が過ぎた。
七八八年四月
さらに北岸(の東の端)に住まいを移す。この地の四方の眺望は限りなく、砂浜は麗しい。
名も知らぬ花のさまざまな色を見ては驚き、どこからともなく漂う芳純な香りに気持が和む。
ここに住んでいたにちがいない仙人はどこに去ったのか分からないが、自然の神は確かにここにはいる。
この美しい地を、中国の文人、東方朔はその著『海内十洲記』の名勝の地の一つとして、どうして記さないのか。山水を愛でる貴族たちはどうしてここに集い、舟を浮かべて遊ばないのか。
釈尊は苦行の時代、飢えた虎の親子に我が身を投げ出し、その餌食となったとの話があるがその虎に出遭うこともなく、不老不死の仙人、王子喬(おうしきょう)を訪ねてみてもすでに立ち去ったあと。
万物のありのままのすがたを日光山に思う
(冬には)茂るツタで寒さをさえぎり
(夏には)おおう葉陰に暑さを避け
山菜と水を摂るだけの食事であっても日々は楽しく
気が向けば出かけ、感じるところあればそこに止まり祈りを捧げ
けがれなき自然の道場に生きる
やがて、(俗世を離れ、清らかなる自然に託して身心の修行に励んでいた勝道であったが、日光開山と生きとし生けるものへの慈悲の祈りは)沢の中の鶴の鳴き声が遠くの野に聞こえるように都にまで聞こえ、桓武天皇はただちに勝道を上野(こうずけ)の国の講師(仏典の講義をする僧官)に任命した。
勝道はそののちも(山林のなかで日々厳しい修行をつづけ、己の身心を鍛え磨き、その成果としてあらわれた徳を実践するちから「修験道」によって)他人の役に立つことであれば万物の動きに身と心をまかせ、無心となって衆生の救済にあたった。
また華厳寺院を都賀(つが)郡城山に建立するなど、ここかしこに移動し(山林を踏査し、多くの修行場を開き)現生利益のちからをもって仏教の布教を行なった。
八〇七年の旱害時には国司の命により日光山頂上で祈雨の修法を行ない、雨を降らせ、穀物を豊かに稔らせて人びとを飢饉から救ったことなどの他、その活動のすべてを一々述べるのは不可能であるぐらい多い。
ああ、月日をひき止めることは難しく、人と世はすぐに変わる。たちまちに「心の欲する所に従いて矩を踰えず」という七十歳を越え、身体の気の衰えるまえに、慈悲をもって人びとを救い導き、為すべきことを為し終えなければならない。
さて、この文章を執筆することなった事情は下野(しもつけ)に在官していた伊博士がその任期を終えて都に戻るときに、その在任中に親交のあった勝道公が日光の「山水遊記」がないのを嘆いて、それを空海に書いてもらうわけにはいかないかと依頼されたというのだ。わたくしと伊公とは古くからの知りあいだったので、断ることができなかった。そのようなことで、時間を見つけては筆を執ることになった。
(前半で勝道上人の日光開山を記録にもとづき描写し、その中で日光山の地形、気候風土、生態系のもつ厳しさと美しさが読者に伝わるようにしたが)以下は(物質と生命から成る自然の根源、人の精神と山水との関わり、日光の景勝を称賛する)銘文である。
<銘文>
(その大地に)大気が生じて空となった(だから、生物が呼吸して生きられる)
(空には)月と太陽が運行し(だから、大地に昼と夜とがあり、潮の干満が生じる)
万物は連鎖してうごめき
海と陸とはせめぎ合い
(そこに棲息するものすべてが)生まれ(交わり、子孫をつくり)そして死ぬ
(そのように)この世は生滅を繰り返して(進化して)いるから
真理のみが人の進むべき道を導いてくれる
一粒の塵(ちり)から山は構築され
一滴の水から湖は深くなる
(そのように)塵と滴(しずく)の集まりが
聖なる自然をかたち作っている
峰々への梯子はなく
鳳凰も登頂を目指さないのに
白い雪の峰に
誰が目をつけ、誰が庵(いおり)を結んだのか
勝道上人は
まっすぐで変わらぬ志しをもち
悟りを願い
仏法を唱え
観音の慈悲に身を任せ
釈迦を礼拝し
欲望を捨て、殉教の覚悟をもって
直ちに険しい山に入り
龍のように跳び上がり
舞い上がる鳳凰のように峰を飛び越え
自然の神々に助け守られて
山河を巡った
山は高く険しくそびえ
水は何処までも澄みわたる
花は美しく輝き
見知らぬ野鳥は四六時中さえずり
天と地をそれぞれに吹き抜ける風の調べは
弦楽器の筑(ちく:五弦の楽器)や筝(そう:十三弦の楽器)の音色のよう
感性のすぐれた人がここにいると
それらが妙なる音楽となって聴こえるだろう
(日光の自然を)一巡りすれば憂いは消え
さまざまな煩悩は自ずと休まる
(この景勝のちからに)人間は敵わないし
天上世界ですら敵うものはない
東晋の文人、孫興(そんこう)も(その万物の深い道理を説く)筆を投げ出すだろうし
(遊仙詩を綴る)郭璞(かほく)の文才も遠く及ばない
ああ、同志よ
(この地を訪れて)のんびりと心のままに遊ばないか
弘仁年間の敦牂(とんしょう)の年、(黄道を十二年で一巡する木星が十二支の星座の午にある年。<敦(とん)>はずっしりと安定していること、<牂(しょう)>は牝の羊を表わし、美、善行、吉祥の象徴。弘仁五年)、月次は壮朔(そうさく:八月の暦)、その三十日の癸酉(みずのととり:山に適度にうるおいを与える恵みの雨がもたらされるとき)。(八一四年八月三十日)
(筆を置くにあたって思うことは)人がお互いを理解し合うのに、必ずしも対面して長く語りあわなくてもよい。心が通えば、親しく交わったことと同じである。わたくし空海は勝道公と直接お会いしたことはなかったのだが、幸いに彼と親しかった伊博士から「公は清廉で奥深い心情の持ち主である」と聞いたうえ、本人のたっての願いとのことでこの「洛山(日光山)の記」の執筆を頼まれた。
わたくしにどれほどの文才があるか分からないが、『論語』に「仁に当たりては師にも譲らず」とあるから引き受けることにした。
努力をして書き綴ったが、(自然を描写することは、万物の道理とそれらを映す人の精神・運命をも論じることになるから、中国前漢の思想家揚雄が著述した『太玄経』<易経>が)玄(黒いという意味をもつ)と言いながら白いなどと揶揄されたことを踏まえると、物質と精神の幽玄さをどこまで表現することができたのかと心配になる。
拙い言葉の寄せ集めの文章となったが、わたくしとしては一生懸命に著述したのでご容赦願いたい。
(この執筆の機会を得たことにより)わたくし空海は勝道上人(が山岳修行とその実体験がもたらすイマジネーションによって悟りに到達し、慈悲の行力をもって人びとの救済に当たられた聖人であること)を一生忘れることなく思いつづけるであろう。西岳(高雄山)の沙門遍照金剛(空海)記す。
あとがき
七八二年、勝道上人が四十八歳の春に日光男体山に初登頂し、悟りを得たとき、空海は真魚(まお)と呼ばれる、まだ九歳前後の少年であった。
その少年が若くしてあらゆる学問に通じながらも二十歳前後には都の大学を去り、山のやぶを家とし、瞑想を心として、山林に入り修行し、悟りを得、そののちに唐に留学して密教第八祖となるのだが、若き日の空海もまた、自然と人間の心の関わりをよく理解していたのだ。
だから、山岳仏教の師である勝道上人の日光山における行状とその心境をまるで見ていたかのように記すことができた。
その文章に目を通し、上人は大いに喜んだことと思う。そこには上人と同じ澄んだ目と心をもつ空海がいた。