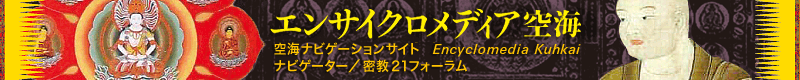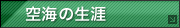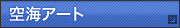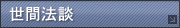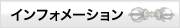司馬遼太郎が『空海の風景』上・下(中央公論社)を書いたのは昭和50年である。
初出は「中央公論」誌の昭和48年1月号から始まった連載であるから、今から30年以上も前のことになる。
空海関連の書物の中でも本書の文庫本(中公文庫)は今でも群を抜いた売れ行きをみせている。これに続くのが、陳舜臣の『曼荼羅の人―空海求法伝』上・下(集英社文庫)である。
司馬遼太郎の代表作といわれる『坂の上の雲』や『龍馬が行く』に比べると、『空海の風景』は分量的には劣るものの、上下二巻の大作である。初版本の帯には「構想十余年、司馬文学の頂点を示す画期作」とある。
著者の「あとがき」によると、『坂の上の雲』の下調べをしていた頃、空海全集を読んでいたらしい。司馬はこの本で芸術院恩賜賞を受賞している。自他共に「司馬文学の頂点を示す画期作」と認める作品が、『空海の風景』なのである。
司馬は平成8年に没した。国民作家と呼ばれる小説家の手により空海を広く世に知らしめてくれたということに、空海を宗祖と仰ぐ宗派からも高い評価が下されてきた。
中公文庫の解説で大岡信は、「いったい司馬遼太郎以外のどんな作家が、空海を主人公とした『小説』を書くことを夢想し、かつ実現し得ただろうか」と述べ、その上で、この本は、「まさしく小説にちがいなかったが、伝記とも評伝ともよばれうる要素を根底に置いているがゆえに、空海を中心とする平安初期時代史でもあれば、密教とは何かに関する異色の入門書でもあり、最澄と空海の交渉を通じて語られた顕密二教の論でもあり、またインド思想・中国思想・日本思想の、空海という鏡に映ったパノラマでもあり、中国文明と日本との交渉史の活写でもあるという性格のものになった」と評している。
そして最後に、「このようなタイプの主人公がこの国の小説でかつて扱われたことがなかったという事実に、あらためて注目せざるを得ない。司馬氏が空海を主人公に選んだという事実は、そのこと自体において、文学史的にもひとつの事件だったということができるのである」と結んでいる。批判的言辞は皆無で、手放しの絶賛である。
この本が、空海を単に「素材」として選んで書いた純然たるフィクションとしての小説だったならば、そこにどれほど荒唐無稽なことが書かれていようと、問題にするつもりはない。むしろ胸のすくような無比の超人ぶりを講談風に描き出してくれていたら、拍手喝采を送るだけのことだった。
しかし、大岡信が指摘しているように、この本は「伝記とも評伝ともよばれうる要素を根底に置いている」ことは確かであり、学術的成果もしっかり踏まえている。
この本で空海を知り、学んだひとは大勢いることだろう。小説なのだからフィクションと割り切ってしまえばよいのだが、ほとんどの読者は、これをフィクションとしてではなく、むしろノンフィクションとして、しかも現代の最も良質な作家の手による空海の伝記として読むだろう。
そのように読まれることを司馬が期待していたかどうかは分からない。司馬が本書をあくまでも小説として書いたということは事実であり、これを「風景」という曖昧な表題にしたのは、あまりにも偉大な空海そのものを捉えきれないという謙虚な姿勢の表明と受け止められなくもない。
そうしたことを勘案しても、私は司馬が描き出した空海像をどうしても好きになれないのである。いったいどうしてこの本が、大岡信の言うように、「密教とは何かに関する異色の入門書でもある」のか甚だ疑問に思っている。
私がこういう話をすると、同宗の僧侶の方々も怪訝な顔をする。「この本によって空海が嫌いになった人がいるだろうか。たぶんいないのではないか。いかに空海が偉大な天才であったかということをこの本によって知ったという人が大勢いる。それはまことに結構なことではないか。何が不満なのだ。」ざっとそんな感じの反論がかえってくる。
だが、そういう方々はまずまちがいなく『空海の風景』を読んでいない。読んでなおかつ、この本は素晴らしいと評する僧侶がいたとすれば、私はその方の見識を疑う。
司馬は、知る人ぞ知る無神論者であった。このことをご存知だろうか。もっとも、司馬がどんな思想の持ち主であったとしても、それを問題にするつもりはない。司馬が空海にいかなる神秘性を認めなくてもかまわない。しかし、いわゆる無神論の人が空海の生涯をあくまでも唯物論的に解釈しようとすれば、どのようなものになるか。
それは本書のほんの最初の部分を読むだけで判然とする。やはりこういうことになるのかという、ひどいものなのである。この本の第1章で司馬は次のように書いている。(括弧内の頁数は中公文庫本)
「筆者は、空海において、ごくばく然と天才の成立ということを考えている」(上巻、10頁)
司馬は空海を「天才」だと思っていた。大岡信も認めているように、これが『空海の風景』という大作のモチーフであった。
そう述べる分には何も問題はない。書・詩文・語学においてしかり、宗教家・思想家としてのみならず、教育者としても、あらゆる面で、空海はまさに万能の天才であったということに異を唱える人はいないだろう。司馬ならずとも、空海は凡人だったが偉い人だったなどという人はいない。空海はたしかに凡常を超えた天才だった。実際、日本仏教史上、誰もが天才と認める宗教家はそんなにいない。諸宗の開祖を含めて、すぐれた宗教家は大勢いたが、天才と称される人物は空海だけであろう。
だから、司馬はそうした万人の常識を追認したにすぎない。いかにも司馬だけが初めて空海を天才と認めたかのような書きぶりは胡散臭い。「筆者は、空海において、ごくばく然と天才の成立ということを考えている」などと、もってまわった言い方をせずに、「万人が認める空海の天才とはいかなるものであったか」と素直に書くべきだった。
ためにするような難癖を付けているように思われるかもしれないが、司馬の考えた空海の天才とはいかなるものであったか。それは実に愕然とするほど意外なものだった。
『空海の風景』は、司馬が空海の生地である四国の讃岐を訪れるところから始まる。
空海は讃岐の満濃池を修築した。
満濃池の決壊は永年の課題だった。その解決策を地元民は空海に請うた。その要請に空海はこたえた。国司が京に書き送ったとされる書状にあるように、人々が空海に対して「百姓恋ヒ慕フコト父母ノ如シ」と思っていたというのは事実であろう。だが、そのすべては空海の自作自演であったかのように、司馬は書くのだ。
「空海のずるいところであり、もし空海が大山師とすれば、日本史上類のない大山師にちがいないという側面が、このあたりにも仄見えるようでもある」(上巻、17頁)
空海に関して、このような評価を下した人がかつていただろうか。空海はずるくて「日本史上類のない大山師にちがいない」と。
満濃池修築が空海の自作自演であったという証拠はない。だが、百歩譲って仮に司馬の夢想する通りのことだったとしよう。つまり満濃池の修築を願う地元民の声を代弁して、空海自身が誰かの名前で朝廷に嘆願し、結局は空海が出向くことになった。そうだとしても、一番喜んだのは讃岐の地元民たちであった。それは空海にとっては当然の衆生済度の実践であった。
満濃池の修築に関して、空海はその天才をいかんなく発揮した。現代の土木工学の観点からしても驚嘆すべき技法を駆使して満濃池を修築した。しかし、その大事業の達成をもって、空海は偉大な天才だったと、司馬は認めているのではない。自作自演をした「日本史上類のない大山師」であったというところに、空海の天才を認めているのである。古今まれにみる信じがたい評価(?)である。そうまでいわれても、弘法大師空海を祖と仰ぐわれわれ真言末徒は、この小説家に賛辞を送るのだろうか。
次。若き日の空海が出家するに到るまでのことについて司馬は次のように書く。
「性欲は普遍的に存在している。空海にもある。というよりは、若者のころのこの人物は人一倍それが強かったにちがいなく、その衝動に堪えかねて喘ぐような日もあったと考えてやらねばならない」(上巻、71頁)
「考えてやらねばならない」というのである。
「空海のような地方豪族の子弟の場合は、色をひさぐ家の軒をくぐらざるをえないが、宇宙の神秘や人間の生理と精神と生命を不可知なものについてずばぬけて好奇心の旺盛な空海が、そういう家に行って性の神秘を知ろうとする自分の衝動にどのようにして堪えたであろう。あるいは堪えなかったかもしれない」(上巻、72頁)
小説家はそのような想像をするのか、そういう見方もあるのか、と笑って見過ごす手もある。しかし、彼の『空海の風景』の全編がこの調子なのだ。大岡信が評したように、この著が「伝記とも評伝ともよばれうる要素を根底に置いている」とすれば、由々しきことではあるまいか。
初版の単純なミスも、文庫本で修正されていない。たとえば、
「空海がその最初の著作として十八歳のとき『三教指帰』を書いたということはすでに触れたが、そのなかに色情にちなむ叙述が多い」(上巻、73頁)とある。
『三教指帰』の執筆は、空海24歳のときである。これを18歳としたのは司馬の単なる思い違いであるが、この程度の初歩的なミスを、編集者が見過ごして厖大な版を重ねている出版社の見識が疑われる。
それにもまして聞き捨てならないのは、「色情にちなむ叙述が多い」である。
司馬は色情にこだわりすぎている。『三教指帰』のモチーフを、司馬は色情に歪曲している。前代未聞の解釈である。
「筆者は空海がなぜ大学をとびだしたかについてなにごとかを知ろうとつとめている」(上巻、77頁)
「さて十八歳のころの空海である。空海は自分が生物であることに、後世のわれわれが信じがたいほどの大きさで衝撃を受けたであろう。たとえば海潮のように自分の肉体に満ちてくる性欲に驚き、それを認めざるをえなかったであろう」(上巻、80頁)
司馬独特の文体といってしまえばそれまでであるが、「空海がなぜ大学を中退したか」ということは、空海研究者の誰もが抱く疑問である。司馬だけが「なにごとかを知ろうとつとめている」わけではない。
なぜ空海は大学を中退したのか。その理由を、司馬は現代的な観点、というより、司馬個人の独断で「性欲」のせいにしている。真言教学上の立場から、これに反論する人は今までいなかったのか。
「つまりは作業用の仮設として、かれにおける性の課題を考えようとしている。ひるがえって考えれば、人間における性の課題をかれほどに壮麗雄大な形而上的世界として構成し、かつそれだけでなくそれを思想の体系から造形美術としてふたたび地上におろし、しかもこんにちなおひとびとに戦慄的陶酔をあたえつづけている人物が他にいたであろうか」(上巻、77頁)
意味不明の文章である。
こう述べた直後に、「理趣経というのはのちの空海の体系における根本経典ともいうべきものであった」と、唐突に『理趣経』を持ち出して論理を飛躍させている。どうも司馬は『理趣経』を単純に性欲肯定の経典と考え、それを若き日の空海に重ね合わせている。前代未聞の珍解釈である。
『理趣経』が伝統的に真言宗の主要な読誦経典であることはたしかであるが、この経典が空海の思想体系の根本にあったとは言えない。
いったい空海の全著作の中で、「人間における性の課題をかれほどに壮麗雄大な形而上的世界として構成」したようなものがどこにあるというのか。
司馬はここで要するに、空海は性欲の悩みで大学を出奔し出家した、と言いたいがために無理な連想の飛躍を犯している。
次。入唐直前の空海。
「かれが正規に得度をして官僧になるのは、遣唐使船に乗る前年である。このころになってようやく僧になる自信を得たかとおもわれる。禁欲についての自信を得たということではなく、禁欲という次元からはるかに飛翔し、欲望を絶対肯定する思想体系を、雑密を純化することによってかれながらに打ち樹たてることができたときに、僧になってもいいと思ったに違いない」(上巻、207頁)
結局、性欲の悩みで出家した空海は、30歳頃それを克服して、僧になってもいいと思った? まさか、である!
私の考えを端的に言うと、空海は北伝仏教の「釈迦十九歳出家、三十歳成道説」を信じていた。みずから仏陀になろうと決意し、釈迦のように19歳で出奔し、30歳までは世に出まいと修学に励んだのだ。この12年間があればこそ、成道を遂げた空海を一目見た恵果阿闍梨はただちに伝法を決意したのである。
それが司馬によって、性欲の悩みを克服する期間に矮小化されてしまった。
伝記が書かれるほどの人物にとって、その人が世に出たときが最も重要である。いかに偉大な人物でも無名の時期がある。伝記作家はその無名の時期をも埋めなければならないわけだが、史料が限られているか、ほとんどない場合、どうするか。
何を想像して書いてもよいというものではなく、その人物の偉大な功績の準備期間とみるのが最も妥当ではないだろうか。性欲を克服したとおぼしき外国の青年に、大唐帝国の国師が数千人の弟子をさしおいて両部の大法を授けるということがありえようか。
空海の歴史舞台への登場はいつか。『続日本後記』によると、承和2年3月、31歳で空海は得度している。空海の得度年については多くの異説があるが、この日本の正史の記録を疑う理由はない。空海は釈迦にならって三十歳まで世に出るつもりはなかったと考えるなら、なんら遅すぎる歳ではない。
ただし、その時点で空海の令名は旧都奈良の諸大寺に知れ渡っていたと私はみている。
当時、正式に得度するということは官僧になるということであり、今ならさしずめ国家公務員上級職の試験より何百倍もの難関であった。すでに都は平安京に遷っていたとはいえ、奈良の諸大寺の許可なくして正式な得度はできなかった。
空海が入唐のため、あわただしく国家に登録された僧になったのは「いかにも異常である」と司馬は書いているが、当時と今とは全然違う。思い立って簡単に正規の僧になれるというものではないのだ。奈良仏教が総力を挙げて空海の入唐を支援した、というのが私の持論であるが、ここはさて置く。
空海の得度年がいつであろうと、その時点で、空海はまだ歴史舞台に登場していない。
四艘の遣唐使船のうち二艘がはぐれ、最澄の乗る第一船だけが予定地に到着、空海の乗る第二船は福州の赤岸鎮に漂着した。日本の国使の来るべき場所ではないところに流れ着いてしまい、密輸業者か海賊扱いされ、海岸にとどめおかれた。遣唐大使の藤原葛野麻呂が地方長官宛にいくら嘆願書を出しても、相手にされない。そこで空海が筆をとった。
大使の代筆という体裁であったが、そこは文と書の国。中国本土にもこれだけの文章を書ける人はいないと長官をうならせた。一行はただちに上陸を許され、最高の待遇を受けることになった。この時、空海は歴史舞台に華々しく登場したのである。
たぐいまれな文才、中国人を驚かす書の腕前、古典に精通している知識。ただし、それはまだ空海の全貌ではない。天分の一端にすぎない。それでも唐の国のインテリ長官を驚かすには十分だった。この消息を司馬はどう書いているか。
「空海という、ほんの一年か二年前までは山野を放浪する私度僧にすぎなかった者が、幕を跳ね上げるようにして歴史的空間という舞台に出てくるのは、この瞬間からである」(上巻、265頁)
事実はまったくその通りである。ただ、行間ににじみ出る空海蔑視の態度はぬぐいがたい。問題は次の文である。
「空海が、唐の大官をおどろかすほどの文章力をもっていながら、ひそかに蔵して、大使の葛野麻呂のうろたえる姿を見つつ、手をさしのべなかったについて、かれの奥床しさと見るのは、空海の性格からやや遠い。空海の生涯の行蔵からみて謙虚という、都会の美学はもっていなかったとおもわれる。かれがのちに謙虚さをみせる言動が多少あるにせよ、それは駈引きからくる演出にすぎなかったであろう」(上巻、273頁)
これが空海の歴史舞台への登場に対する司馬の評である。謙虚さがなかった? 駈引きからくる演出にすぎなかった?
「空海は、のちのかれの行蔵からもうかがえることながら、自分の行動についてはすぐれた構成力をもっていた。かれの才能の中でいくつか挙げられる天才や異能のうち、この点がもっともすぐれたものの一つといっていい。かれが『三教指帰』という戯曲を書いた男だということを、ここで思い出すべきであろう」(上巻、273頁)
司馬には空海に対する尊崇の念は微塵もない。貶めるのみである。
自分をいかに売り出すか、そのことにおいて空海は天才であったと全巻を通じて言い立てているのである。それが『空海の風景』のまぎれもないモチーフであった。
大使をさしおいて、一介の留学僧に何をせよというのであろうか。空海の出番はいつだってある。このときでなくてもよかった。空海は別に奥床しかったわけでもなく、謙虚であるもないも関係なかった。何の駈け引きも演出もする必要はなかった。空海は出番に応じて、なすべきことをしただけである。なしたことが天才的であった(天才的な文と書を示した)ということであって、何一つ駈け引きをしたわけでもない。したこともない駈け引きを「天才」という司馬の空海評は、歪みきっている。
きわめつけは、長安の都で空海が恵果阿闍梨に遭遇することになる場面である。これについては空海自身が『御請来目録』の中で、自分は恵果に偶然遭ったのだと書いている。ここを司馬は次のように言う。
「そう書けば文章としては眉目は美しくなるが、しかし『密一乗』を求めて入唐した者が、密一乗の最高権威である恵果にたまたま遇ったということは、あまり正直であるとはいえない。この文章の不正確さのなかに、むしろ逆に、右のような、空海のけれんじみた操作が匂い立っているといえる」(上巻、368頁)
空海自身の言葉に対して「正直であるとはいえない」「不正確」「けれんじみた操作」と酷評している。空海の真意、意図はどこにあったのかということについて、あたかも詐欺師まがいの操作をしたという想像しかできなかったのだろうか。
結論として言えば、『空海の風景』はよく文献を調べて書いているものの、司馬の本にしては駄作と断ぜざるをえない。この駄作に与えられた芸術院恩賜賞とは何だろう。
最後にもう一点、同工異曲が、陳舜臣の『曼荼羅の人―空海求法伝』である。
この本は空海の入唐期間のみに焦点をあてた小説である。
次の一文を御覧あれ。
「留学期間をできるだけ短縮するために、密教に有効に接近しなければならない。その戦術として、空海は自分を目立たさせ、便宜を得る手がかりをつかもうとした」(TBSブリタニカ発行初版本、上巻、205頁)
司馬の視点と同じである。そんな小手先(自分を目立たせるための工夫)にのせられて恵果は(つまりは空海に騙されて)空海にすべてを伝授したのだろうか。陳舜臣はそう考えているらしいが、ありうべからざることである。わが祖師、弘法大師空海に対する冒涜この上ない暴言である。なにが「戦術」だ。正覚者にどのような戦術が必要だったというのか。
作家の想像というのは、さすがにいかにも奔放である。歪曲・矮小化も自由だ。だが、正直言って、この作家らに共通している空海「山師」説は、明治以来の日本のインテリに共通するいわれのない俗説である。