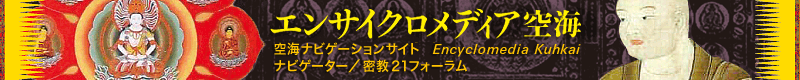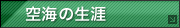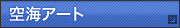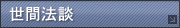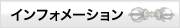朝、高知新聞に小渕政権を嫌って円は147円まで下落、株も下落のトリプル安とあった。浮世のマネーゲームは相変わらず忙しい。朝のコーヒーを飲みなが ら、新聞から目を離して外を見ると快晴である。第三十六番霊場・独鈷山青龍寺近くにとった宿舎は、土佐湾を見下ろす半島の景勝地にある。私はすでに浮世離 れした遍路である。一昨年の続きは、ここから始まる。
●第三十六番札所・青龍寺
 横波半島の東部、宇津賀山麓は深い密林に囲まれていた。長い石段を登って山門をくぐると、すぐ脇に水子地蔵がある。妻は地蔵菩に祈りを捧げると千羽鶴を
飾った。彼女は昨年中ずっと鶴を折っていた。これからは各霊場に捧げるのだといって箱一杯折り、今回訪れる札所分だけ糸を通してきていた。私の病気回復の
お礼だという。
地蔵堂の裏山の岩壁からは小さな滝が流れ落ちている。脇には赤い炎を背負って宝剣を手にした「波切り不動明王像」が安置してある。霊場の空気はやはり清浄
である。老杉の繁る森に吹き込む風がかすかに潮の香りを運んでくるようだ。波切り不動を眺めながら、私はまた海の空海を連想する。さらに長い階段を登りき
ると本堂、大師堂、薬師堂などが横一列に並んでいる。大師堂に灯明を捧げて合掌する。
横波半島の東部、宇津賀山麓は深い密林に囲まれていた。長い石段を登って山門をくぐると、すぐ脇に水子地蔵がある。妻は地蔵菩に祈りを捧げると千羽鶴を
飾った。彼女は昨年中ずっと鶴を折っていた。これからは各霊場に捧げるのだといって箱一杯折り、今回訪れる札所分だけ糸を通してきていた。私の病気回復の
お礼だという。
地蔵堂の裏山の岩壁からは小さな滝が流れ落ちている。脇には赤い炎を背負って宝剣を手にした「波切り不動明王像」が安置してある。霊場の空気はやはり清浄
である。老杉の繁る森に吹き込む風がかすかに潮の香りを運んでくるようだ。波切り不動を眺めながら、私はまた海の空海を連想する。さらに長い階段を登りき
ると本堂、大師堂、薬師堂などが横一列に並んでいる。大師堂に灯明を捧げて合掌する。
さて、その後の空海のことである。
18歳で都の大学を飛び出して乞食僧となった空海の足取りは不明である。ただ、24歳のときに著した『
空海の年譜上この期間は空白期間とされてはいるが、のちの空海の爆発的な宗教活動を考えると、決して空白の時代ではなく、全く充実した日々であったと考
えねばならぬ。おそらく、多数の仏典や密教経典を読みあさっていたのではないだろうか。同時に、求聞持法をはじめとする奈良朝以来断片的にこの国に入って
いた古密教(雑密)や、古神道の修法も実践していたであろうと推察される。見方によれば、入唐を決意するに至る充電期間と見ることができるのである。
空海が再び歴史の表舞台に現われるのは七年後のことである。空海は、故郷の屏風ヶ浦で見たあの遣唐使船に乗っていた。空海31歳。時に延暦23年
(804)の7月6日。九州田浦を出港した四隻の遣唐使船は、唐国を目指して南方洋上に帆を張っていた。季節風を利用する繰船術や天文航法すらろくに知ら
れていない当時のことであれば、捨て身の渡海である。天子の勅命による栄えある遣唐使節とはいえ、選ばれた官吏の中には狂乱状態に陥る者や、命に背いて脱
走する者のいた頃のことである。片道燃料で出撃命令を下された特攻機乗りのようなものである。
だが、真理を求めて命を賭ける日本人はいた。第一船には密教をわがものにせんとする空海がいた。第二船には中国天台宗発祥の地を目指す最澄が乗船していた。だが、四隻は途中で暴風雨に遭い、たちまち四散してしまう。空海を乗せた第一船はどうか。
ここから、空海は伝説の人となる。吹きすさぶ嵐の中で唱える空海の真言は天に通じ、空に現れた不動明王が宝剣で荒れ狂う波を切り開いて難を救ったとい
う。まるでモーゼである。しかしこの伝説は、私の海洋修験者空海の面目躍如たるところである。このときに空海が見た不動明王を、帰国後彼自ら刻んで奉納し
たものが、ここ青龍寺の本尊「波切り不動明王」であるといわれている。
さて、空海たち23名を乗せた第一船は約一ヶ月間漂流した後、はるか南の福州に漂着する。最澄ら一行27名を乗せた第二船は二ヶ月もの間海上をさまよった
末に明州に流れ着く。第三船は南シナ海の孤島で難破し、第四船は行方不明。唐土の浜に辿り着くことができたのは二隻のみであった。天の配剤か歴史の意志
か、のちに日本仏教の二大巨星となるこの二人を、運命は見捨てることはしなかった。この二人の高僧が平安仏教を花開かせ、日本仏教を発展させる原動力と
なったことは周知の通りである。
九死に一生を得た空海一行は、さまざまな障害を乗り越えて中国大陸を横断する。実に7520里(中国里程)を踏破する辛苦の道程であったという。唐は徳宗の代。貞元20年(804)12月23日。空海はついに長安の都に入った。
長安で半年間、あらゆる情報収集と最後の準備を整えた空海は、いよいよおのが入唐の目的、密経一条の伝法を受けるべく、青龍寺の高僧恵果和尚のもとを訪
れる。恵果は唐王朝歴代の信望を一身に集めた不空三蔵の愛弟子であり、彼自身も三代の王朝に仕え三朝の国師と仰がれていた名僧である。しかも、不空の正嫡
として法を継いだ正統密教の継承者第七祖でもあった(第一祖は宇宙の大日如来)。恵果の名声は国の内外に知れ渡り、中国はもちろん、インドや朝鮮、南海あ
たりからもその教えを求めて門下生が集まっていた。その数2、3000人ともいわれている。
空海は恵果和尚の門を叩いた。一方、老いたる恵果はいまだ密経の正嫡を決めかねていた。そこへすでに密経の奥義を高度に自得していた(と私は考えるが)
空海が現れた。ここに空海と恵果和尚との劇的で宿命的な出会いが実現する。空海を一目見た恵果は「われ先より、汝の来れるのを知り、相待つこと久し。今
日、相まみゆるは、大いに好し大いに好し。報命尽きなんとするに、付法する人なし。必ずすべからく速やかに香花を弁じ、灌頂壇に入るべし」と言って喜ん
だ。
密教の師資相承は霊感のようなものが働くのかもしれない。一瞬で空海の資質を見抜いた恵果は、空海に教法の全てを受け継がせることに余命を注ぎ込んだ。
空海もよくそれに応えて、師の教えをことごとく吸収した。それは、師をして「唐梵差ふこと無くして悉心に受く、猶、瓶を写すが如し」と言わしめたほど見事
に受け継いだ。
空海は驚くべきことにわずか三ヶ月という異例のスピードで、密教の師、阿闍梨の法灯を授けられた。十年以上も恵果の直弟子として修行して、なお伝法受法できない並み居る弟子たちの中から、異国から突然にやってきた空海が選ばれたのである。
18歳、都を捨てて以来、大自然の中で孤独な修行を続けていた空海には、密教の基礎は十分できていたのだ。恵果は空海に最後の点睛を与えたようである。
わずか二年前まで無名の一修行僧が、大唐帝国随一の名匠から密教の全てを譲り受け、2000人の仏弟子の代表となったのである。ここに、大日如来から数え
て密教伝灯第八祖としての空海が誕生する。32歳。
人の一生は不思議である。人生を左右するような貴重な出会いというものは、一瞬早からず、一瞬遅からず訪れるものらしい。「待つこと久し」、そう言っ
て、空海の入唐を心待ちにしていたかのような恵果は、空海に最期の教戒を授けると、翌年大日如来の印を結んで静かに息を引き取った。
師が空海に授けた最期の教えは「速やかに密教を母国に持ち帰り、その真義を伝えよ」というものであった。インドで興った密教は中国に伝わり、そして空海
によって最終的に日本にもたらされた。今日かの国々では時代とともに衰亡していった密教は、空海によってわが国にもたらされ、最終的に日本真言密教として
根を下ろすことになったのである。
ここ青龍寺の仁王門の左手前には「恵果堂」がある。
「寺伝によれば、このお寺は弘法大師が師である恵果和尚の報恩のために建立したんだってさ」
「それで恵果堂があるのね」
「帰国したら恵果和尚のために一寺を立てようと発心して、唐から日本に向かって独鈷杵(密教の法具)を投げたんだってさ。帰国して大師が四国巡りをしていたら、独鈷杵がその辺の松の枝に引っかかっていたのを見つけて、この地を聖域として感得したんだよ」
「まあ、空海って怪力なのねえ。そんな由来があるから山号が独鈷山なのね」
「なにしろ嵐だって鎮めてしまうんだから、独鈷杵の一つや二つ日本まで放り投げるくらいわけないさ。それでさっそく嵯峨天皇に奏上して勅許を得ると、不動
明王を刻んでこの堂宇を建立したと伝えられる。空海は師の徳を慕って恵果和尚の住んでいた長安の青龍寺を倣ってこの寺も青龍寺としたそうだ。怪力空海はと
もかく、嵯峨天皇の勅許を得て建立したというのは史実だろう」
「だって、嵯峨天皇は空海の大ファンだったんだもの。空海の頼みなら何でも聞いたでしょう」
「これまで見てきたように、寺伝には確かに荒唐無稽なものが多いけど、人間の想像力って実に豊かだし、人間臭いっていうか温かいなあ」
「想像力の問題を抜きにして人間は語れないわね。実際にはありえないような寺伝をインテリってすぐに非科学的だ、やれ政治的だといって片づけようとするけど、そういう合理主義って、私好きじゃないわ」
「神話や伝説それ自体は確かに荒唐無稽だが、神話や伝説が象徴している意味を見落としたら、結局歴史の中の人間は見えてこないと思うよ」
「だって、そこに人間の願いや理想が込められているんですもの。文化とはそういうものでしょう」
「それに、第一、人間そのものがいわば非合理的な存在じゃないか。人間が合理で説明がつくのなら、この世から宗教などとっくに消えていなければならないさ」
漁師たちが船出の前には必ずお参りをしたという本堂は、軒先から内陣まで奉納された絵馬が並んでいる。海の男の厚い信仰心が伝わってくる。
青龍寺をあとにすると、「横波黒潮スカイライン」をぶっ飛ばす。しばらく半島の背骨を縦断するドライブである。左眼下には白波寄せる絶壁が次々と展開
し、紺碧の太平洋を見下ろす壮大なスカイラインを愛車は快調に走って行く。カーステレオはベンチャーズのパイプラインの軽快なリズムを奏でている。
武市瑞山(半平太)の像が太平洋に向かって立っているところで途中下車。土佐勤王党の全員の名前がずらりと並んだ碑石がある。
「ざっと見たけど、岡田以蔵の名前はなかったみたい。かわいそうね」
妻はそんなことをポツリと言った。私は(男はやはり海に向かって立つものである)などと全く関係のないことを考えている。
スカイラインはまもなく国道56号線に合流し、須崎市郊外で給油。車はさらに四国の南の縁をなぞるように続く海岸の道を西へと走る。途中で妻が見つけて
おいた国道沿いの物産店にある「日本一のトイレ」で用を足したあと、なお56号を西へ走る(何が日本一なのか物産店の従業員に聞いてみたがわからない。で
も、大きな看板は出ていた。変なトイレ?)。
中土佐町を過ぎると、国道は四万十川の流れる内陸部へと入って行く。予定より一時間遅れの午後一時、窪川町に到着。第三十七番札所・岩本寺は、JR土讃線窪川駅の近くの街中にあった。
●第三十七番札所・岩本寺
 仁王門には目をクリクリさせた四頭身の可愛らしい仁王さん。さほど広くない境内には大きな銀杏があり、その大木の先に本堂、大師堂、庫裏などが並んで
建っている。本堂は戦後再建されたもので、欄干の丹塗りもまだ鮮やかである。中もきれいで「貼紙厳禁」の立札まである。この寺の住職は古惚けた雑駁なお堂
は好みではないのかもしれない。
仁王門には目をクリクリさせた四頭身の可愛らしい仁王さん。さほど広くない境内には大きな銀杏があり、その大木の先に本堂、大師堂、庫裏などが並んで
建っている。本堂は戦後再建されたもので、欄干の丹塗りもまだ鮮やかである。中もきれいで「貼紙厳禁」の立札まである。この寺の住職は古惚けた雑駁なお堂
は好みではないのかもしれない。だが、本陣内の天井絵を見て驚いた。格子にはめこまれた現代絵がビッシリ並んでいる。仏画あり、花あり、動物あり、マリリン・モンローの肖像画ありで、 その数575点。昭和53年に堂が新築されたときに全国から公募されたものだそうで、住職の遊びごころに感心して眺める。JR土讃線が本堂の真横を音を立 てて走って行った。
歩き遍路は、この岩本寺を立つと足摺岬の先端にある第三十八番札所・金剛福寺までの約120キロを歩かなくてはならない。遍路道全行程1450キロメー トルのうち、札所間としては最長の距離である。四国の海沿いの辺地を「いつしか衣は潮垂れて」歩く土佐の修行の道場最後の山場である。
私たちはといえば、まっすぐに三十八番に向かわずに、窪川町から川伝いに内陸部へと方角を切り替える。日本最後の清流といわれる「四万十川」を見るためである。なにしろ、四国はくまなく探訪するのが「夫婦で愉しむ道草遍路」のモットーなのだ。
窪川町から四万十川に沿って国道381号を上流へと上り、愛媛県との境の十和村まで行く。今度は西の中村市へと流れるもう一本の四万十川に沿って、441号線を河口まで下りてくるおよそ90キロのコースを選択した。
窪川町から西に伸びる国道381号は、大正町、十和村、西土佐村を経て愛媛県へ抜ける道である。大正町までは片側一車線の道路で快適走行。助手席側には 緩やかな蛇行を示しながら、四万十川の深い緑の流れが展開してくる。妻はお気に入りのPPM(ピーター・ポール・アンド・マリー)のCDをかけてすこぶる ご機嫌である。川幅が広いために山間の道とはいえ視界は広々としている。青空を背に緑濃い山の風を延々と列ねて、その裾野に蕩々と水をたたえる四万十川の 姿は、日本の自然美をあますところなく伝えている。
「轟公園」は幡多郡大正町の(といっても、川沿いののどかな田舎街だが)四万十川を見下ろす高台にあった。また寄り道をして、この町のシンボル「石の風 車」を見に行く。公園には高さ5メートル、重さ18トンの石作りの名物オブジェがあった。石の風車の一番大きい羽は2トンもある。この話をどこかで仕入れ ていた妻と、実際に回るのか確かめに寄ってみたのだ。
そよ風が吹くと静かに回り始めた! 二人は度肝を抜かれる。
「すごいなあ」と感嘆する私に、
「風は石をも動かす」と妻が意味深長なことを言う。
少し風が強い日には怖いぐらいのスピードで回るそうである。ちなみに、岡山県の吉備高原にある「うかん常山公園」にもくるくる回る石の風車が7基あるそ うだ。これは、「有漢町村おこし委員会」が町の活性化のために頭をひねっていたときに、ここの石の風車の話を聞いて、製作者の門脇さんに依頼して製作して もらったもの。どういう仕掛けになっているのかは部外者にはよくわからないらしい。だが、石の風車のお陰で有漢町は年間30万人の観光客が訪れるように なった。(風は人をも動かす)
話がそれた。先を急ごう。
大正町を過ぎると道はしだいに狭くなり、四万十川の緑色も深まってくる。
「いよいよ憧れの四万十川上流だぞ」
「日本最後の清流だもの、なんだか胸がドキドキするわ」
車窓からは、しかし単調に日本の自然美が繰り広げられるだけだ。美しいことは美しい。だが、どういうわけか期待していたほど感動しない。しばらく二人は沈黙している。そのうち同時に大笑いした。
「どこかで見たことがある風景じゃないか」
「そうよ、私たち毎日見ている景色だわ。広島の太田川と同じね」
広島は川の街である。一級河川の太田川も全国的に清流といわれている。私の自宅は太田川の中流で、夏は子どもたちが水遊びやキャンプをするほどの自然環 境が残る山紫水明の地にある。塾舎は車でひと山下りた街中にあるので、毎日このような川沿いの道を走って出勤しているのだ。ときには川原に下りて妻と弁当 を開げてから出勤することもある。これは、私たちが選んだ生活空間と生活スタイルであった。
「四万十川を一回り小さくすればウチの近所と全く同じだ」
「四万十の自然の美しさに憧れて全国から人が来るでしょう。あまり感動しない私たちって、きっとずいぶん贅沢なところに暮らしているのね」
私は忘れていたが、二十年以上も前に東京から今住んでいる場所に初めて来たときは、その自然の豊かさが実に懐かしく、また新鮮に思えたものだった。こちらに住んでしまえば当たり前の自然環境であるが、それほど東京は過密な人工的都市だったのだろう。
結婚当初は、練馬区の桜台から日本橋まで、毎朝ラッシュアワーに揉まれて会社に通っていた。退隊前の配属先は都内にほど近い陸上部隊であり、大学も民間のサラリーマン時代も東京だったので、東京生活はけっこう長かった。
東京は広いというが、私にとっては檻の中に封じ込められたような息苦しい空間であった。行けども行けどもコンクリートの街の中である。山も草原も青い海 もない。風も吹かない。あの大海原を吹き抜けるような風が。東京の風はビルの谷間をすり抜ける乾いた冷たい風だった。 しかし大都市の生活が長くなるにしたがって、閉鎖的な都会の生活環境にもしだいに慣れてきた。いや、麻痺してきた。私はそれが健康的な適応ではなく、栄 養ドリンク剤で無理に活力を得ているような、あるいは薬物患者がクスリによって意識の表層部だけを異常に覚醒させているような、そういう一種の躁状態であ ることを自覚していた。決して眠ることのない不夜城の東京で。
私の日常はめまぐるしい流行を追うファッション業界にあり、東京の街の最も華やかな空間を仕事場としていた。海軍の伝統を受け継ぐ海上自衛隊という男性 社会の中で育った私にとって、この業種の変化は天地がひっくり返ったかと思ったが、役員をしている大学の先輩が引いてくれた会社だったので是非もなかっ た。
ファッション業界は、芸能界のような一種のケバケバしさがあった。そして、一瞬も気の抜けない弱肉強食のすさまじい販売競争、きらびやかな売場の裏で繰 り広げられる打算とかけ引き。虚飾の厚化粧に酔う夜の接待。けたたましい笑い声と阿諛追従、空疎なおしゃべり......。そのような世界で、私は酔えない不夜城 に醒めていた。
私は華やかな照明の中で、彼、彼女らの横顔にふとよぎる孤独と疲労の影を見落とせなかった。しのぎを削るファッション戦争の夜会が終われば、彼らはみな 都会の片隅のコンクリートの部屋に帰って、そして仮面を取る。実はそこにこそ素顔の自分が待っているのだが、そういう自分と向き合うことを避けて彼らは今 日も仕事に狂奔する。
一シーズン何千万、何億円もの仕入れをする大店舗のバイヤーに自社商品を売り込むメーカー同士の戦争。ブティックの女主人は洗練された応対と笑顔で、量産品を一品物のオートクチュールと偽って客に高額で売る。
それはある意味で、都会の虚飾の典型であった。市場原理とは、人の感覚を麻痺させ、また麻痺することによってしか生き残れない自由競争のことなのだ。仕事の価値や、人間の生き方に疑問をもつ者は脱落するしかなかった。
広告業界(これも派手な世界であったが)で、あるコピー・ライターが自殺した話を聞いた。彼はこう書き遺していた。「夢がないのに夢は売れず、ハッピーでないのにハッピーは売れない」と。
ある日、私の直属の上司が西新井の踏み切りで飛び込み自殺をした。詳しい理由はわからないが、支店長から命じられた売上げノルマ(それは見計らい販売を 含む本社向けの売上げ操作でもあったが)に悩み疲労していたようであった。あとで社の命令でその月の給料を自宅に届けに行ったとき、奥さんがまだ幼い子ど もを抱えてぽつねんと遺されている姿を見てしまった。このことがあってから、私はサラリーマンというものの、ある決定的な何かを見た気がした。
当時は高度成長期にあり、会社第一主義とするサラリーマンの生き方に疑いをもつエコノミストはいなかったが、私はすでに企業組織に人生を委ねる生き方そのものに疑いの目を向けていた。
バブル崩壊後、無謀な過剰融資をしてきた銀行経営の実態が明るみになることにより、日本の企業倫理が問われてきた。そして結局、リストラと自己責任と能 力主義という、より露骨な資本主義の論理に落ち着いた。先の二つの死の意味を問うことを、今も日本は先送りしているのではないか。
二十五年前、私は自分自身の将来の生き方にからめてこの問題を考えていた。私には資本主義が何か虚飾に感じられてならなかった。札束の飛び交う欲望渦巻 く大都会の光と影が、何か幻影のように思われた。高度経済成長のさなか私は東京を捨てたが、その後日本は土地バブルが起こり、急速に実態経済から遠のき、 マネーゲームと粉飾決済に突入していった。
そして、予感していた通り"宴の時代"は終焉した。兜町の紳士たちが一夜で何十万も飲み明かし、銭湯代わりに吉原のソープへ通った舞踏会は終わったので ある。日本経済全体がその厚化粧を落としたとき、そこに残されていたのは観衆の去ったあとの劇場のような空洞ではなかったろうか。
エコノミストの誰もが信じていた4万円台の日経平均株価も幻想であった。土地神話も銀行神話も崩壊し、終身雇用も年功序列賃金体系も幻想であったことが わかった。先送りされた問題は、実はここにきて表面化しているのである。自殺、失業、自己破産、離婚、犯罪。リストラされた中高年の自殺者は増えるばかり である。欲望資本主義が「消費者」に売る夢を食えば、消費者とは裏を返せば「消費される者」ではないか。
幻想に踊らされて自らの人生を消費するよりも、企業とともにバブル劇場に踊らされるよりも、自分ひとりの劇場で自ら脚本を書き、確かな舞台で主役を演じ よう。二十数年前に地方都市に移ったのは、つまるところ身の丈に合った生き方をしたかったからである。妻と二人で演じてきた小舞台は、休む間もない地方公 演ではあったが、しかし二十数年のロングランとなり今なおヒットしている。
三島のキャンプ場(四万十川本流域で最大の中洲)を下見したり、佐田の沈下橋を渡ってみたりする。沈下橋とは、川の水量が増したときには文字通り水没し てしまう橋のことで、四万十川を対岸まで繋ぐ欄干のない幅3メートルほどの長い橋のことである。大水のときには15メートルも水没するという名物橋であ り、それは川のところどころにあった。今は水面から数メートルの高さにあり、キャンプを楽しむ人たちが橋の上から川に飛び込んでいる。私は急に嬉しくなっ て、車を止めて自分も飛び込もうと思った。だが、海水パンツがない。
「下着で泳ごうか」
「よしなさいよ。子どもならともかく、年を考えなさいよ」
「ヤッパリ駄目か」
「あなたを見ていると、時々子どもじゃないかと思うときがあるわよ。ケンちゃん、駄目です」
飛び込みは大好きである。中学生の頃はトロール船のマストの上から海に飛び込んで、そのまま百トンの船底を潜っては船の反対側に浮き上がる競争をしたも のだ。昔はよかった。大人も子どもの遊びには干渉しなかった。ガキ大将は網元の息子であったから、親父は船底で息が切れるような男は海の男にはなれないと でも思っていたのだろう。「甲板に落ちんようにやれ」としか言わなかった。
4時30分、佐田の沈下橋の近くの神川で観光遊覧船に乗った。エンジン付きの屋形船である。こうして実際に川面に浮かぶと、さすがに四万十川の清らかさ と水量の豊富さに感激する。船頭さんの説明によると、四万十川は愛媛や高知などの十本の川が合流して一日に四万トンの水量が流れ込むゆえ、四万十川と呼ば れてきたそうである。
喫水の低い屋形船は乗客を乗せて川面を走る。妻の伸ばした手が水面を切って気持ちよさそうに走る。他の客がみんな屋形船から腕を伸ばして水の感触を楽しんでいた。
この日はそのほか「四万十ふれあいの家・カヌー館」などを見て、仕事を引退したらカヌーを覚えるのだという妻の夢をたっぷりと聞かされた。子どもがいな いせいで妻は私を子ども扱いするが、私から見れば彼女も夢の尽きない少女である。明日を夢見て、二人は中村市のホテルで熟睡した。