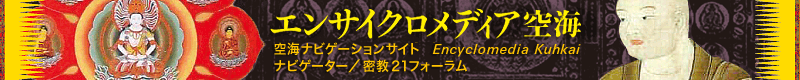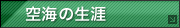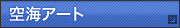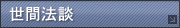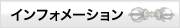翌日、牛野川に行ってみた。
昨日描いた絵とほとんど変わらぬ風景が広がっていた。日差しに乾いた坂道を妻と歩きながら、私は四十年以上も前にも、こうして額に汗をにじませて母と歩いたことを思い出していた。
「無縁坂」という歌がある。
母がまだ若いころ僕の手をひいて、この坂を登るたび、いつもため息をついた......。
運がいいとか悪いとか、人は時々口にするけど、
そういうことって、確かにあると、
あなたを見ててそう思う。
忍ぶ、忍ばず、無縁坂、
かみしめるような、ささやかな僕の母の人生。
あの歌を耳にするたびに、私はいつもこの坂を登る母の姿がまぶたに浮かんでくる。母の人生は苦労の連続であった。とりわけ当時は最もつらい頃であった。
私の父親は、家族思いで働き者の芝家の叔父とは正反対だった。あの星空の夜、母はもしかしたら一瞬にしろ自らの人生を終わらせようと思ったのかもしれな
い。
住む人の絶えたその家は、夏草の生い茂る荒れ果てた庭に埋もれていた。雨戸が締め切られた家屋の中には、かつて囲炉裏を囲んだ明るい親戚一家がいて......そして、母と私がいた。
妻は思いに耽る私を少し離れたところから黙って見ている。近所の家から虫採り網を持った5、6歳の男の子が出てきて向こうの坂道を駈けて行く。その後ろ姿に私は幼い自分の姿を見ていた。その距離わずか4、50メートル、しかし、四十数年の歳月が横たわっていた。
男の子はまるで何かを振り切るように元気よく坂道を駈け下りて行く......私は妻のいるところに戻ろうと思った。
牛野川のことも死んだ母のことも、私は妻に話したことはない。
昼過ぎに宇和島市内に戻った。汗をかきながら、宇和島城の石段を登った。成川渓谷といい、お城といい、何も知らない妻は二つながら不思議な選択をする。
私は昔何度か登った城山である。その頃は城内には入れなかったが、今は内部が見学できるようになっていた。天守閣から宇和島市街が一望できた。予讃線の終
着駅でもある港町宇和島は、同時に文化の香り高い城下町でもある。そして、母の生まれた町でもある。
母の生家はかつて薬研堀にあって、当時手広く養蚕業を営んでおり、社名を「太陽館」といったそうである。その名が示すように、家庭は明るく円満であった
という。兄弟四人は全員旧制中学に進学し、姉妹五人も高等女学校卒であるから、家庭の教育レベルは高かった。生前の母の話によると、兄弟たちの学校の友達
が家に遊びにくるたびに、姉妹たちが連れてきた女学校の娘たちとも交歓し、いつも屋敷内は若い華やいだ雰囲気で満ちていたそうである。それを歓迎する父親
は、明治の人にしてはかなり進歩的だったと思われる。ともかく、リベラルな家庭で育った母の娘時代は幸せだった。家庭的には申し分のない父親だったが、事
業家としての才覚や野心はなく、子どもたちを学校へ上げ娘たちを嫁がせ始めた頃、家業はしだいに傾いていったようである。次男、三男は将校として出征し、
戦死した。
城の入場券を売っている老人に、戦前、薬研堀に太陽館という事業所があったのを憶えていないか聞いてみたが、老人に記憶はなかった。薬研堀という地名
も、今ではなくなっているという。この世の存在の証は人の記憶の中にしかなく、やがてそれも時の流れとともに消えていく。私は父母の人生を心に捺そうとし
ていた。
父の家庭は複雑である。宇和島市から予讃線で一時間あまり上れば、佐田岬の付け根に八幡浜という遠洋漁業で栄えた港町がある。私の祖父は、浅野という生
家から八幡浜の高橋という家に養子に来て、「兼屋」という海産物問屋の跡継ぎとなった。明治から大正にかけて、八幡浜は伊予の大阪といわれるほど海産物の
集散地として賑わっていた。
多くの使用人を使っていた祖父は長浜町の元士族の娘を嫁に迎えるが、三人の子どもをもうけたあとで伴侶に先立たれた。私の父が学生時代のことだったらし
い。祖父はまもなく後妻を迎えるが、後妻と長男である父との反りが合わず、そのことがもとで祖父とも不仲になった。結局、父は母と結婚後まもなく郷里を捨
てて満州へ渡った。
大連で父は領事館警察の剣道の師範をしていた。母は満州で二人の息子と娘一人をもうけしばし幸せな日々を送るが、末の三男が生まれた時はすでに敗戦の混
乱期にあり、食料も乏しく三男は栄養失調で死んだ。残った三人の幼児を連れてシラミだらけの引揚げ船に乗ったとき、母は私の命を体に宿していた。昭和21
年の冬、ようやく本土に辿り着き、翌年私が生まれ、そして妹はこの世に縁がなかったのである。
戦前宇和島の「太陽館」に八幡浜の「兼屋」の評判は届いており、家の釣り合いに問題はないが、姑が後妻であることに母の実家はかすかな危惧を抱いてい
た。父と母が満州から裸一貫で引き揚げたときから、この不安は的中した。郷里を捨てた長男を不快に思う祖父と継子を快く思っていなかった継母は、この子沢
山の食い詰め夫婦に冷たく、何かと母につらくあたった。私は母の膝に抱かれたまま、祖父母の前で母が泣いて詫びていたのを今でも憶えている。
後妻は祖父を丸め込み、嫁いだばかりの自分の娘(後妻には娘がいた!)を無理に別れさせて父の弟といっしょにさせるという異常な行動に出る。自分の意の
ままになる病弱で気弱な次男と娘を夫婦にして、「兼屋」の実権を握ったのである。「兼屋」の後継ぎは次男に決まった。後妻が入ってからの高橋の本家は、財
はあれども因業の家になり果てていた。
父は当座のわずかな生活費をもらい、満州に持って行った実母の位牌だけを唯一の財産にして本家を追われる。育ちざかりの四人の子どもと母を抱えて、八幡
浜から少し離れた漁村に住家を見つけて移り住んだ。あの「鯉のぼりの村」である。田畑も漁をする船も持たない引揚げ者一家がどうやって生計を立てていたか
は、幼い私に知る由もなかった。もともと無口な父は、こうしてますますもの言わぬ人間になっていった。
死期が近づいた頃、父は理由も言わず周囲の止めるのも聞かず、独断で宇和島市の病院に移った。そして、一人で勝手に息を引き取った。父が何故自分の育っ
た八幡浜ではなく、宇和島を死に場所に選んだのか。今この町を見ていると、私にはその理由がわかるような気がしてきた。母を亡くした父は、最期を宇和島で
迎えたかったのだろう。宇和島は父が母と出会った町である。
父はいつの頃からか、自分の死ぬ日は8月15日だと言っていたが(父の易はよく的中した)、予言通りその日に息を引き取った。なぜ8月15日なのか。今
日までその意味を遺族は誰も考えようともしない。ただ、私はこのごろになって、父は人生の何かにケリをつけたかったのではないかと思うようになってきた。
8月15日は日本の敗戦の日である。
かつて日本中が満州国の建設に沸き上がっていた頃、若い夫婦は満州に新天地を求め、束の間の幸福と第二次大戦による挫折という時代の大転換期に遭遇す
る。父は自分の人生を日本の敗戦とともにどこかで終わらせていたような気がする。母との幸福な日々は満州にあり、しかし、それが日本の植民地政策による現
地住民の犠牲の上に成り立っていた矛盾を、父はどこかで気がついたのではないだろうか。そう思われるフシがあるのだ。
敗戦直後の満州はソ連軍と八路軍(共産軍)、それに国府軍が怒濤のようになだれ込み、日本人街は混乱のるつぼと化した。特に軍人、軍属、元警官、新聞記
者、教師、満鉄職員などは日帝の奸賊とされ、次々と戦犯拘置所に送られた。裁判とは名ばかりの現地復讐裁判によって多くの日本人が処刑されていった。元領
事館警察の父は何度も連行され、そのたびに母は「今度こそ最期だ」と思ったという。最後に中国共産軍に連行された父は「新生中国のために働け」と言われ
た。さもなくば銃殺刑に処すという二者択一を迫られ、自ら銃殺刑を選んだのである。「俺は共産主義は嫌いだ」と言って協力を断ってしまった。
父は転向することを拒絶したのだろうか。死の選択は思想上の問題だったのだろうか。それとも節義の問題だったのだろか。いや、私は父は何か責任を取ろうとしたのではないかと思われる。
父が銃殺されていれば、私はこの世に存在しなかった。銃殺前日、父は戦地でそれだけは肌身離さず持っていた実母の位牌を取調べの士官に渡して、私は高橋
家の総領である故この位牌を守ってきた。もはや自分はこの地の骨となる身であるから、どうかこの位牌を本国の実家に送り届けてほしいと願い出た。そのと
き、担当の士官は「シン、テンホー」(清々しいとか潔いとかいう意味)と言って、その夜こっそり父を収容所から逃がしてくれたのである。幸い、中国は長男
を何より大切にする儒教の国であった。いや、もともと現地裁判などというものは勝者の復讐劇であり、処刑の罪名などどうにでもなったのである。
だが、赤紙一枚で徴兵されたとはいえ、満州を植民地化しようとした日本人の一人であったことは確かなのである。父は戦後、自分は国家の犠牲者であったと
か、あの戦争は間違っていたなどという反省めいたことや弁解がましいことは一言も口にしなかった。中国人の悪口も言わなかった。
九死に一生を得た父が、昼間はコウリャン畑に身を潜め、夜陰に紛れて這うようにして家族のいる大連に着いたとき、各地で暴徒化した満人や、日ソ不可侵条
約を破ってなだれ込んだソ連軍で街は混乱の極に達していた。ソ連兵は領事館警察の官舎にもなだれ込み、強奪、強姦、狼藉は頻繁に起こっていた。母は黒髪を
切り、子どもたちの口を押さえて屋根裏に身を潜めるという日々を送っていた。
あまりの狼藉に腹に据えかねた一人の日本の元警官がソ連兵をサーベルで斬り倒し、それが発端となりまた局地戦になる。敗戦で武装解除はされていたのだが、どこからか小銃などの武器を集めてきて、官舎地区にバリケートを築いたときには野砲まで出てきたという。
戦後育ちの平和ボケした日本人が唱えるヒューマニズムなど、戦場では何の役にも立たない。あるのは狂気のような非情な現実だけである。先の戦争と父親の世代を批判する団塊の世代が、そのような現実の渦中にいたとして、はたして今と同じことが言えるだろうか。
昭和20年8月15日を境にして、日本人は180度生き方を変えた。天皇は人間宣言をし、日本は国際的犯罪国家であるという罪悪史観を受け入れたのであ
る。皇国史観を捨てた日本人は、今度はアメリカ民主主義を受け入れ、神州日本の勝利を信じて散っていった特攻隊を馬鹿げた犬死だと笑い、敗戦を終戦と言
い、占領軍を進駐軍と言い換え、昨日まで戦ってきた自分を国家の犠牲者だと言い、敵将マッカーサーを新たな救国の神として崇め、そして民主主義と家族主義
を最上の価値観として新たな世に適応していった。
私の父にはそれができなかった。8月15日で父の人生は終わっていたのかもしれない。 戦後の復興の中で家族が温め合いながら立ち直ろうとしていたと
き、父はその努力をしなかった。滝に打たれたり易に凝る。子どもたちはオカシクなった偏屈者の父親に反発してみんな離れて行った。私たちは日教組の民主教
育で育った「戦争を知らない子どもたち」である。
だが、ひたすら自国を卑下し、歴史を否定し、欧米の表層的な物質文化ばかりを追い求めてきた戦後の日本を見ていると、うわべのヒューマニズムや個人主義といった戦後の生き方を受入れようとしなかった父の気持ちが、今少しわかるような気がする。
宇和島は、私にそんな父と母を考えさせていた。
●第四十一番札所・龍光寺
 城山を下りて「和霊神社」を見学したあと、正午に宇和島を出発。ここから第四十一番札所・龍光寺は三間町に向かって7キロほどである。四十番の観自在寺
から行脚すると約50キロの南伊予路を辿ることになるが、道中には大小の島が織りなす宇和海が広がり、そののどかな景観は遍路の心を癒してくれる。「菩提
の道場」第二番寺は三間平野の見渡せる静かな山裾にあった。
城山を下りて「和霊神社」を見学したあと、正午に宇和島を出発。ここから第四十一番札所・龍光寺は三間町に向かって7キロほどである。四十番の観自在寺
から行脚すると約50キロの南伊予路を辿ることになるが、道中には大小の島が織りなす宇和海が広がり、そののどかな景観は遍路の心を癒してくれる。「菩提
の道場」第二番寺は三間平野の見渡せる静かな山裾にあった。
山門はなく、その代わりに正面の石段を登りきって見上げれば、注連縄を飾った赤い鳥居が見下ろしている。祀ってあるのは稲荷神。一瞬場所を間違えたかと思ったが、ここは地元では「三間のお稲荷さん」で通っている神仏習合の霊場である。
縁起によると、大同2年(807)、この地を巡錫していた弘法大師の前に稲を担いだ白髪の老人が姿を現し、「我はこの地に住み、仏法を守護し庶民に利益
せん」と大師に告げて姿を消したという。それで、大師は本尊の十一面観音菩薩をはじめ、脇侍の不動明王、毘沙門天などを刻んで堂宇を建立して安置されたと
いう。稲を担いだその老人がここの稲荷神である。大師はその老翁が五穀大明神の化身であると悟られたのである。
この縁起に、私は次の二点のような感想をもった。第一は、この地で大師が稲荷神に会った時期がやはり大同2年であること(稲荷神はおそらく空海がこの地
に感得した祖霊神だったのではないかと思うが)。やはりと言ったのはこの一つ前の第四十番・観自在寺の縁起と同じ時期だからである。つまり、空海帰朝後の
空白期間(自由に行動できた時期)に当たっているから、開基の時期の信憑性が高いという点である。
穿って考えれば縁起の方を空海の履歴に合わせて創作したとも考えられる。だが日本人の性格からして、庶民信仰がある意図をもって真っ赤な嘘を作るとは考
えにくい。原理を考えるのではなく、原理をもとにして話に尾鰭をつけることをむしろ得意とするのが一般的な日本人ではないだろうか。すなわち大同2年に空
海は「ここに立ち寄った!」という「原理」だけは残る。そういう感想が一つ。
二つ目は縁起の意味である。稲荷神をお大師さんが諸仏と共に祀ったという話は一見何でもないようだが、この話こそ空海の「存在」を語っている。稲荷神を
荼枳尼天という仏と習合させたのは真言密教なのである。荼枳尼天の神体を白狐としたので、稲荷=白狐信仰が広がった。だから、稲を荷う老人の神姿は稲荷神
として祀られることになったのである。ここで重要なことは、日本古来の稲作の神(神道)を空海が仏教と習合させたという思想にある。
「ということは、蘇我氏と物部氏の宗教戦争はいわば空海によって和平がもたらされたことになるわね」
「うん。そういう大仕事ができるのは空海しかいないんだ。だから、この寺の縁起に僕は空海の足跡を感じるんだよ」
「6世紀の初め仏教伝来時に、日本古来の神を崇拝する物部氏と、新しい仏教を崇拝した蘇我氏との宗教戦争は古代史の夜明けでしょう。つまり、日本文化の夜明けでもあった......」
「そこさ。この古い神と新しい仏との天下分け目の戦いは結局崇仏派の勝利に帰した。それによって日本は仏教が主流になるが、空海のすごいところは深層部に
残る文化の亀裂をアウフヘーベンしたところだよ。新来の仏教を崇拝しながらも、古代の日本の心を吸収しているところだよ」
「さすが空海ね。でも、空海にしかできなかったのはどうして?」
「それが密教なんだ。少し勉強したんだが、空海密教の教義は仏教も神道も見事に包括し整合しているんだ」
「なるほど。兄ちゃんも少しはお勉強するんだ」
「当たり前だ。ボケてばかりはいないぞ」
●第四十二番札所・仏木寺
 稲を荷った神と仏が出会う霊場をお参りすると、次は牛を引いた老人と大師が出会ったといわれる霊場である。霊場巡りは伝説だけでも実に面白い。龍光寺から田園地帯の県道を約4キロほど行くと「お大日さん」と親しまれている仏木寺に着いた。
稲を荷った神と仏が出会う霊場をお参りすると、次は牛を引いた老人と大師が出会ったといわれる霊場である。霊場巡りは伝説だけでも実に面白い。龍光寺から田園地帯の県道を約4キロほど行くと「お大日さん」と親しまれている仏木寺に着いた。
県道沿いには夏空を突き上げるようにして、はや重厚な山門が迎え立っている。中を覗けば真っ赤な仁王が目を剥いてボティビルのようなポーズをとって怒っ
ている。だが、すっかり馴染みになってしまった仁王さんは入り口でニラミをきかせているというより、「四国巡りもついに半分来たぞ。頑張れ!」と遍路を激
励してくれているようだ。
山門をくぐると、すぐ脇にはお大師さんのお出迎え。雲水姿のお大師さんに挨拶をして石段を上ると、右手に茅葺き屋根の珍しい鐘楼がある。妻が景気よくひ
と打ちした鐘の音は、暑さを忘れさせるように青空に吸い込まれていった。この寺の開基も大同2年。私は南伊予を歩きながら、密教布法の根回しをする空海を
思い描く。空海は人々に仏の心を残して行った。
その昔、この地を巡錫中のお大師さんが牛を引いてきた老人に出会ったそうじゃ。お大師さんは勧められるままに牛の背に乗んさってのう。ほいで老人が夜な
夜な光るという不思議な樟の木に近づいてみたら、まあその枝に宝珠が輝いちょっての。アンタそれがナシ。なんとお大師さんが唐から三鈷とともに投げられた
宝珠であったそうな。それを見たお大師さんはここを霊地であると感得されてナシ。その大樹で大日如来を刻まれてこの寺をお開きになったがよ。お大師さんは
やっぱりガイヤナ。ガイナことするぜよ。
「お大師さんたら何でもかんでも放り投げるのネ」
「きっと、唐から持ち帰った密教宝具の荷が船に積み切れなかったんだろう」
アホな話をしながら清々しい境内を散策する私たちの目には、明るい三間平野が南に広がっていた。
門前でアイスクリームを売っているおっちゃんと世間話をしながら、クリームを舐めて汗を引かせたあと出発。宇和町へ向かう。目指すは第四十三番札所・明石寺である。
●第四十三番札所・明石寺
 田舎の県道は信号もほとんどなく車は快走する。妻が車窓ののどかな風景を楽しみながら何か喋っているが、私は寺が近づくにしたがって無口になってく
る。あの寺に行くとまた遠い記憶が蘇える。過去を遡れば父母の影と向き合うことになる。それは否応なく逢着せざるを得ない原点に還ることでもある。
田舎の県道は信号もほとんどなく車は快走する。妻が車窓ののどかな風景を楽しみながら何か喋っているが、私は寺が近づくにしたがって無口になってく
る。あの寺に行くとまた遠い記憶が蘇える。過去を遡れば父母の影と向き合うことになる。それは否応なく逢着せざるを得ない原点に還ることでもある。私は少年時代のある冬、明石寺で修行したことがある。あのときは里のたんぼ道を辿って、村はずれの寂しい山に入ると、雪の積もった杉木立の山道があっ た。明石寺のその参道を息を荒くして登った。確か父の使いでこの寺に来たのだが、なぜかそのまま二日ほど滞在してしまった。一人過ごした離れの宿坊には、 真冬だというのに小さな火鉢しかなかった。
早朝、顔を洗いに井戸に行くと、白衣の行者たちが雪の積もった井戸端で気合もろとも井戸水をかぶっていた。私はここで、目も鼻も口も穴という穴はすべて 一つひとつ冷水で洗う洗面行を行者たちに教わった。凍てつくような朝の勤めは広い境内から御堂の掃除。やっとありつけた朝食は一杯の芋粥とタクワンだけ だった。寒さとひもじさと、何か苛烈な印象が残っている寺である。
少年時代の明石寺の面影を抱いて来てみると、山門下まで一気に車で上がれるようになっており、広い駐車場や食堂や土産物店まである。昼なお暗かった杉木 立の参道はすっかり開発されていた。あまりの変わりように驚きながら石段を登ると、しかし、四十年振りに見る山門は、私を一気に少年時代に引き戻した。か つて息を切らせながら見上げたあの威風堂々たる山門が変わらぬ姿で立っている。古刹の七堂伽藍の境内もあのときに感じた霜烈な空気を残している。ここは四 国霊場唯一の通夜道場、修行の場であった。
聖武天皇の天平6年間、役小角に縁をもつ修験道の中心道場として興隆したこの霊場は、今では少なくなった仏教真理霊道にもとづく禅宗修行を、戦後まだ遍 路に対してまで続けていた。その内容は、朝の勤行をはじめ堂宇の掃除、境内の草むしり、食事の作法、霊道行、洗面行など、現代人にとっては厳しい内容を課 していたという。
私の家は禅宗である。父がここの住職と親しかったのは、おそらくその関係だろう。父は住職に用事があって私を使いに寄こしたのだが、いま思えば、そのついでに私は修行させられたのだ。
もう代替わりした住職に、昔の宿坊と井戸の場所を尋ねると、はたして境内の片隅にひっそりと残っていた。あの厳冬の朝、寒気を引き裂いて水をかぶってい た遍路たちの凛烈な井戸は、今は苔むした古板で蓋がされており、中を覗くと病葉が浮かんでいた。井戸の前の宿坊も残っていたが、これも用済みの破屋になっ ていた。
私の脳裏にボロボロになって死んでいった母がよみがえる。この部屋は中学一年のときに私が泊まった部屋である。それから一年後、再び あげいしさん(地元では明石寺をそう呼ぶ)のお参りに来たとき、両親と私と姉の四人で休んだ所でもあった。六畳一間に流しがあるだけの遍路用の質素な二軒 長屋の宿坊だが、母は部屋に上がると、
「いいところね。耀子ちゃん」と嬉しそうに姉に言った。
それは、まるで温泉旅館の上等な部屋に案内された客のような華やいだ声だった。たかが宿坊である。でも、母は家族旅行(といっても日帰りだが)ができたこ とがよほど嬉しかったのだろう。母のあの声だけが、今も私の胸を締めつける。私の一家が家族旅行をした思い出はこれくらいである。
家庭円満が母の生涯の夢だった。しかし、唯一の「あげいしさん参り」も家族は全員そろってはいなかった。修験者の真似事をする父親を嫌っていた兄たち は、すでに家を飛び出していた。家族の確執など語る気もないが、四国の寺ならどこにでも売っている遍路の金剛杖が、そんな我が家にはいつも二、三本床の間 に転がっていた。
妻が言い出さなければ、私は生涯遍路なんかしなかっただろう。うまく言えない滓のように沈む澱みが四国にはあり、遍路の心象風景はそれに重なっていた。 郷里に近づくほどに、埋めたはずの過去が顔を出し、それは父母の面影が揺れるつらい道である。そんな故郷の「へんろ道」が、亡き両親を弔う「菩提の道」で あることに、このとき私はまだ気づいていなかった。