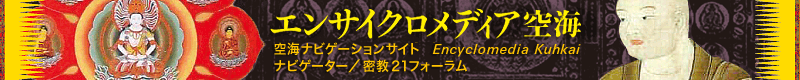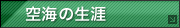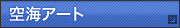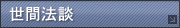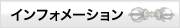●第七十六番札所・金倉寺
 9時30分、最終日坂出市のホテルを出発。
9時30分、最終日坂出市のホテルを出発。
坂出市から再び善通寺市の方へ戻ればやがて金倉町の古い家並みに入った。商店や家々が軒をつらねる街中のほぼ中心部、背後には田園の広がる一角に樹木に
囲まれた金倉寺があった。眼光炯々たる豪快な金剛力士像の守る仁王門の入り口では、近所のお婆さんが三人仲よく並んで座っておしゃべりをしている。この寺
は空海の甥である智証大師が誕生された寺として有名である。
境内の片隅に「一太郎松」と言う松があった。
「何かしら?」
「おそらく一太郎の母のことだろう。戦前の人はみんな知っている話だが、輸送船で出征する息子一太郎に向かって、岸壁で母親が叫んだというあの一太郎のことだろう」
「何て叫んだの」
「一太郎やーい、天子様に御奉公するんだぞー。わかったかー。聞こえたら鉄砲を挙げろ。この一言で一太郎の母は全国的に有名になったんだよ。軍国主義華やかなりしころさ」
一太郎松」の向いに「乃木将軍妻返しの松」があった。これが金倉寺を有名にしたもう一つのエピソードである。
明治三十一年10月3日から同34年5月まで、当時陸軍中将乃木希典が善通寺第11師団長に就任し、この寺に寓居していた。赴任した年の大晦日に静子夫人
が東京から面会に来たが、将軍は会わなかった。静子夫人は将軍の意をくんで会わずに帰って行ったという。しばらく夫を偲んで佇んでいた松が「妻返しの松」
となって今日に伝わっている。(現在の松は二代目)
将軍夫妻の心は現代人には不可解かもしれないが、別に乃木さんが冷たい夫であったわけではない。肉親や妻子と分かれて兵役についている部下を思えば、自
分だけ妻に会うということを控えただけであろう。そして静子夫人もまた軍人の妻である自分を思い直して帰っていったのである。公私の区別に厳格な乃木らし
いエピソードである。だがどこか切ない話である。この切なさは夫人に対してだけではなく、乃木に対してでもある。
乃木将軍は日露戦争で二人の息子を戦死させたが涙ひとつ見せずに指揮をとった悲劇の将軍である。さらには明治天皇の死に伴って殉死し、静子夫人もまた夫
のあとを追って自害をしたことでも広く世に知られている。多大な死傷者を出した旅順攻略の責を、最後にこういう形でとったのかもしれない。いずれにせよ死
をもって自らの宿命を受入れたのである。
乃木夫妻のこの事件は日本中に衝撃を与え、新聞各紙は乃木大将夫妻の死を悼み、また賛美し、世間も大いに感動した。一太郎の母は軍国日本の母たる鏡、静
子夫人は辛抱と従順に生きた妻たる鏡である。明治以来、近代化を急ぐ日本は国家秩序の形成の強化に努めた。良妻賢母は、そうした中でつくられた日本女性の
あるべき姿であった。
さて、現代のフェミニストからすれば、静子夫人の生き方は男性中心社会の典型的な犠牲者だと言うだろう。同時に男尊女卑という家族制度意識の昂揚に協力
した女(少なくとも女性を良妻賢母へと誘導する役目を果たした)ということになる。批判こそされ、決して賛美されてはならないだろう。
だが、このような類別的な見方には、人の「死」に対する思いの深さや敬虔さが感じられない。あるのはイデオロギーである。彼女たちのいうフェミニズムと
は「女性の自由、平等、人権を求める思想」であり、それと逆行する生き方は前近代的なものとして克服されなければならないのである。フェミニズムは近代自
由主義思想の華である。日本は思想的後進国なのである。この図式もまたエリート好みの舶来思想である。
確かにフランスは文化の香り高い国ではあるが、文化とは一人の人間の死に深く思いを留める心なくしては育つまい。戦後左派が主張してきたように、列強と
戦った日本人はみな反戦論者であったろうか。戦争責任はひたすら天皇制と軍部に押しつけ、国民は全てその犠牲者であったという単純な図式を与えたのはアメ
リカの占領政策ではなかったか。
乃木は戦ったのである。日本人は戦ったのである。戦わずして植民地の奴隷となることを拒否したのである。この思いを、戦後は敵国の歴史認識によって否定
する。手法は間違ったかもしれない。しかし、自国民の「思い」まで否定する資格が一体何人にあるというのだろうか。文化とは「思い」の累積ではないのか。
「思い」を断ち切れば、「祖先の思い」の累積の上にある自分とは何者であろう?
大師堂に貼られたお札の中に、擦り切れた名刺大の写真が目にとまった。写真は古い軍艦であった。その下に細かい文字が書かれていた。
《南太平洋の海に残る我が艦最上と我が友よ。吾命ある限り鎮魂の祈りを捧げん。 |
年老いた遍路の、一人歩き続ける後ろ姿が目に浮かんだ。
 第五回遍路の最後の札所である。いつの間にか七十七番まで来てしまった。万葉の昔から瀬戸内海の要所として栄えてきたという港町多度津にほど近い田園地
帯に道隆寺はあった。時折思い出したように降っていた小雨もやみ、午後からは陽の光が差して寺に着いたときには少し暑くなっていた。
第五回遍路の最後の札所である。いつの間にか七十七番まで来てしまった。万葉の昔から瀬戸内海の要所として栄えてきたという港町多度津にほど近い田園地
帯に道隆寺はあった。時折思い出したように降っていた小雨もやみ、午後からは陽の光が差して寺に着いたときには少し暑くなっていた。仁王門をくぐると、ずらりと並ぶ観音像が目に飛び込んできた。その数何と二百七十体。その林立する観音像の列をたどって進むと正面に本堂、その右手に鐘 楼、大師堂、多宝塔などの伽藍が立ち並んでいる。本尊は「目なおし薬師」の別名をもつ薬師如来。盲目の人がここにお参りして視力が回復した例は枚挙にいと まがないという。そのせいか老人の参詣者が目立つ。境内の掃除をしている老人もいる。父が生きていたら、ちょうどあの年齢か......。
さて、「歴史を知る」ということは、過去に生きた人々の思いに触れることであろう。太平洋戦争を日本の国際的犯罪と決めつけた東京裁判の軍事判決は、先 勝国アメリカの事後立法によるものである。むろん、歴史は「物語」である。だが、「物語」は他から押しつけられるものではなく、自ら創るものでなくてはな らない。ヒストリーを「彼の物語」というのなら、東京裁判史観は「彼=アメリカ」の書いた「物語」である。
歴史観は時の支配者が作るというのは誰でも知っている。権力が民衆を囲い込み、あたかも「そうであったかのごとく」押しつけるのは支配者の政治的常套手 段であろう。そのような権力のフィクションにからめ取られたとき、人は歴史の真実を見失う。それは、歴史から、文化から、民族から人間の温もりを失うこと であり、結局今日ある自分を見失うことにもなる。
Aの両親から生まれた子どもをBの両親から生まれたと言いくるめられた子どもには、自分の本当の「物語」をもつことができない。自らの「物語」をもたぬ国民もまた民族のアイデンティティーをもつことはできないだろう。自己確認ができない民族は根無し草である。
日本人は「マイ・ストーリー」に生きなければ自己を回復することはできまい。その作業は過去の光と陰を見据えることであり、その上でなお自己を捨て切ら ないことである。占領国やそれに迎合してきた進歩的文化人たちの民族否定の歴史観を鵜呑みにせず、自分自身の目を信じるべきだろう。"自らを灯とし法とす べし"と釈尊が説いた通りである。
私たちは、今、歴史に生きた空海を訪ねている。司馬遼太郎も空海を「肉眼で見たい」という思いから『空海の風景』を書いた。彼もまた空海を書くことで本来の日本人を探し求めた。
空海に会いたい気持ちは私も同じである。だが、手法は司馬と異なる。私は四国遍路を通してかつて空海の生きた空間を共有する。そこにかすかに遺された空 海の足跡や息吹に触れることによって、あるいは伝説の背後の意味を考えることから空海のメッセージを聴こうとする。文献はむしろそれらを裏づける手段であ る。
つまり、客観的事実と主観的真実の違いである。司馬は主知主義で空海に会おうとしたようであるが、私は感性で会おうとしている。私は千二百年前のいにしえに生きた人間に知識で会うには限界があるし、主知主義はむしろ迂遠であるとすら考える人間である。
瀬戸内海の海岸沿いに多度津町がある。町の西に弘田川があり、その河口付近の西白方というところに「仏母院」という質素な寺がある。八十八ヶ所の札所で はないのでいわゆる順拝コースではないが、例によって道草遍路が信条の私たちは、最後は先に進まずにまた遍路コースをはずれてこの寺に来た。ここは、妻が 旅行雑誌の隅っこでたまたま見つけており、何かピンときたという場所である。妻は物事の核心部分で霊的と思えるような勘が働く女性である。
ここへ来て驚いた。この寺は空海の母、玉依御前の実家跡に建てられたものであった。往古は大善坊と称し、寛永十五年(1683)、嵯峨御所より改めて 「仏母院」の院号を下賜されたとある。院号の由来は弘法大師の母、玉依御前がこの地の産土神に祈願をしてお大師さまを身籠られたことによると伝えられてい る。
屋敷跡には玉依御前を祀る「御住屋敷」と呼ばれるお堂があった。そのすぐ横の竹群には空海のヘソの緒を納めた「胞衣塚」もある。空海が産湯を使ったと伝えられる古井戸もある。妻と私はごく素直な気持ちでそれら空海の形見に一つひとつ合掌した。
また、空海は幼いときから仏を思慕し、一心に
辺りは静かな農村である。海から吹いてくる風が青々とした稲田をそよがせてやさしく私たちを包み込む。
「どうだろう。空海は善通寺で生まれたのだろうか。僕はどうもこの辺りのような気がするんだが」
「私もさっきからそんな感じがしてたのよ。四国にはどこにでも空海の足跡はあるけど、それにしても奥さんが実家でお産をすることはよくあることじゃない。空海が偉くなったので、父方が善通寺で生まれたことにしたんじゃないのかしら」
空海の父方は
だが、異説もある。実はここ多度津町の海辺にある海岸寺ではないかともいわれているのだ。私は今回の最終日にそれを確かめるべく海岸寺に行ってみようと 思っていたのだが、妻に促されて仏母院へ先に来てしまったのだ。仏母院から海岸寺までは徒歩の至近距離であるため、もし実家で空海を出産したとすれば、海 岸寺はもとは実家の産屋跡だという可能性が考えられる。
仏母院のあとで海岸寺の奥の院まで行って確かめてみると、そこにも産湯の井戸や大師産湯の手拭を掛けた老松の残骸などが祀られてあった。いずれにしても生誕の地を私に感じさせたのは、地理的に父方の実家よりも母方の実家である。
御住屋敷のある仏母院の門をくぐると、庫裡の隣は保育園なのか可愛いらしい滑り台が見えた。境内は狭く参詣者は私たちの他に誰もいない。棟つづきの本堂に外から参拝しようとしたら、中から若いご住職が出てきて私たちを本堂へ上げて下さった。
私たちが今しがた境内のそこここで感じた空海の誕生地について率直な感想を述べると、ご住職は自分もこの寺が本当の生誕地だと思うと語られた。そして、 本堂に祀られてある一つの証拠を見せて下さった。それは、何と幼い真魚が作ったあの伝説の泥仏であった。10センチほどの黒ずんだ小さな泥人形は、確かに 正座して合掌する仏の姿である。私たちは目を皿のようにして見入った。
「もっと目近でご覧下さい。下の立派なの台座は後世作られたものですが、上の仏様の部分がお大師さまが作られたものです」
注意深く泥仏を観察すると、抑えの指型といい、その出来具合の拙さといい、ちょうど幼児の手の大きさで握ったことがわかる。私はいいようのない感動を覚 えた。作品というものは作者の心性が直に表れるものだ。私は空海の作品だと思った。造作は拙いが、その中に凡人には決して表現できない気品のようなものが 漂っている。私も幼いときに泥人形ぐらい造った覚えがあるので、どの程度のものが仕上がるかはわかる。決して技巧的に優れているわけではないが、何という か、作りが温かくて丁寧なのである。子どもの真心が表れていて、鑑賞する者の心に何か誠実さを呼び起こすようなところがある。
「ご住職、これはお大師さんの作られたものにちがいありませんね。私にはそう伝わってきます。ちなみに、いつごろからこちらに」
「しかとわかりませんが、代々当寺に伝えられているものです。お大師さんの時代のものであることだけは科学的な分析でも確認されています」
ご住職はまた胎蔵界、金剛界両部曼荼羅の描かれた二幅の大きな軸も見せて下さった。胎蔵曼荼羅は紅の八葉華の中央に大日如来が坐り、五色の光線が四方に 放射していて、光明の世界の中に諸仏が生み出されている。本堂には金剛界大日如来(鎌倉時代の作)が本尊として祀られてあった。これも目近で見せて下さっ た。これまで回ってきた寺の本尊は秘仏が多く、厨子の中に納められて容易に拝観できなかっただけに、私はご住職のご好意に心から感謝した。
両部曼荼羅があるということは、もしかして胎蔵界大日如来像もあるのではないかと思って尋ねてみると、 「ええ、ございます。お見せしたいのですが今子どもたちが来ていまして。ウチは保育所をやっていてそちらに置いてあるのです」とさらりと言われる。
「まあ、こんな貴重な仏像を保育園に? それは子どもたちが触れられる場所に置いてあるのですか」
「ええ、いつでも触れられます」
「素晴らしいですね!」、妻は絶句する。
私たちも教育の末端にたずさわっている者である。この保育所の教育方針がどれほど素晴らしいものか、ご住職の一言ですべてを了解した。胎蔵とは胎児が偉 大な生命力をもって発育伸長するように、菩堤心の徳が成長発展していく様を示した語である。くだいていえば母性そのものを象徴しており、しかも、その仏さ まが子どもたちがいつでも触れることのできる身近にあるのだ。母性こそフェミニズムが否定してきた中心思想である。彼女ら進歩的知識人が現代の若い母親の 意識をどれほどミスリードしてきたことか。
「何か仏教を通して教えられるようなことはなさるのでしょうか」
「話を聴かせたりはしますが、特に宗派的なことはいたしません。礼儀作法のようなものです。仏さまの前で合掌させたり、食べ物に感謝の気持ちを捧げたりとか......」
そう言いながら、住職はこのような躾が今の若い母親たちにとってはあまり評価されないとポツリと漏らした。しかし、母親たちはお寺さんの話をあまり真剣 に聴くことはないが、子どもは素直なので聴いてくれるという。その子どもが食事の前に合掌するのを見て、母親のほうがいつしか真似をするようになるという ことだった。
日本はいつからこんな情けない国になったのか。親子が逆である。だが、私には実によくわかる話である。私も学習塾で似たような経験はずっとしてきた。人 格形成などよりも、ただ人より勉強のできることが母親の望みなのかと思うときがしばしばある。厳密にいえば、それは学力というよりも他人との比較の中で位 置づけられる優越感にすぎない。その子が将来生きる力をどのように身につけるかではなく、どのランクの学校に入ったかという単一の価値を競い合う。日本の 子どもの危機は、まさに母性の危機にあるのだ。
私は空海を通して母性を考える。
「ご住職、私は空海は母親の血を濃く受け継いでいる気がしてならないのですが」
「私も同感です。阿刀大足はお大師さんの母方の叔父ですから、たぶん学者肌の家系であったと思われます」
空海の母方は阿刀氏だといわれている。
ただ、私は空海を別な視点から考えていた。すなわち、空海の真言密教の核心をなす宇宙的生命観は母性の多大な影響なくしては生まれるはずがないというものである。
司馬もそうであるが、多くの専門家の語る空海論は男性的かつ父性的な空海像である。その理由はおそらく荒々しい山林修行を積んだ空海と、その後の彼の多岐にわたる社会的業績や天皇との親交、国家鎮護などの政治性を帯びた宗教活動などに目を奪われるためであろう。
だが、それらは空海の外面だと思う。私は、空海の本質はむしろ母性原理にもとづく宗教性にあると思われてならない。この感覚は遍路旅を続けていくうちに 確信に近づくのだが、このときは私は母性につなげて、空海の生誕地の方にこだわっていた。すなわち、善通寺ではなくもっと海辺のどこかである。
海岸寺は文字通り屏風ヶ浦の海岸にあった。海岸の松林沿いに県道が走っているが、砂浜はまだわずかに残っている。砂浜を見下ろす小高い丘が「屏風ヶ浦公 園」となっており、そこから瀬戸内海が一望できる。かつて遣唐使船が西に向かって帆送した海である。宝亀八年(777)、空海が4歳のときにも船団を組ん で航行した内海である。私は4歳の真魚の気持ちになって沖行く遣唐使船を想像していた。
「空海の生誕の地は、いまの善通寺の境内である。善通寺には五岳山という山号がある。そのまわりに五つの山が茸のようにそれぞれ峰をつき立ててちょうど風 をたてめぐらしたような景状をなしているためにその名がある。いまの地理的風景ではうそのようだが、空海のころは海がいまの善通寺のあたりまできており、 その五つの山はじかに入り江にのぞんでいた。そのかたちをとって、このあたりは屏風ヶ浦とよばれたらしい。空海はその屏風ヶ浦でうまれた。瀬戸内海をゆく 白帆も、館の前の砂浜から見た」
これは、地勢的に全くでたらめである。私はこの文章を読んだとき、現在はもう屏風ヶ浦は面影すらないものと思った。だが私は今、屏風ヶ浦に立っている。しばらく、司馬の歴史講義の間違いを論証しよう。
まず多度津から5キロほど内陸にある善通寺まで海がきておれば、多度津までの広大な平野は全て埋め立て地ということになる。これは、四国の海岸線の形が 変わるほどの大工事である。逆に善通寺から多度津の海に向かって北上すれば、途中の第七十四番札所・甲山寺はかつて海上にあったことになるし、そのまた先 の天霧城跡のある天霧山(360メートル)も、その先の第七十六番・金倉寺も海上に位置することになる。さらに、平地を海に向かって進めば、仏母院や海岸 寺や、第七十七番・道隆寺に至るが、むろん、これらもすべて海中に没する。そうすると、多度津は万葉の時代から瀬戸内海を航行する船の要所であったという 話も嘘だということになる。
仮に途中の山々はもとは島だったとして、馬鹿ばかしいことだが何かのはずみで潮が引いて平野になったのか。平野部については、念のために多度津の教育委 員会に問い合わせてみた。すると、多度津の周辺からは弥生時代の遺物が出土するし、古墳まであるので昔からの四国でしょうとの回答であった。当たり前であ る。例えば、天霧山の東方約1,5キロには盛土古墳(5世紀末)や三井古墳などがある。善通寺まで海がきていたらこのような遺跡はありえない。
司馬が言うように、瀬戸内海をゆく白帆は善通寺の館の砂浜(はないのだが)からはとても見ることはできない。空海が遣唐使船を見たのは、この浜辺であ る。10トンそこそこの遣唐使船であっても、帆を張り沿岸航法で走航しておれば、ここ屏風ヶ浦の砂浜からなら小さく見ることができる。佐伯一族は里人とと もに使節団長・
さて、司馬遼太郎ともあろう作家がなぜこのようなミスを犯したのだろうか。想像するに、彼は人間空海を書くつもりが、教団側の弘法大師伝記を踏襲したか らであろう。お大師さまが善通寺境内で誕生したというのは、真言宗善通寺派の総本山(善通寺)の言い分であり、それは信仰上の理由である。海岸寺のほうは 同じ信仰上の論理からお大師さまは海岸寺でお生まれになったと主張してきた。この誕生地をめぐる本家争いは昔からあって、遂に訴訟にまで発展し、結局善通 寺の勝ちとなった。以来、空海は善通寺の境内で生まれたことになっている。
つまり、司馬はここで持ち前の実証主義を発揮しなかったのである。故に屏風ヶ浦は善通寺であったと、「そうであったかのごとく」歴史話を進める。司馬は 地形的な無理を検証もせずに受け入れ、善通寺の付近にある五岳山がじかに入り江にのぞんでいたとか、それが屏風に見えたなどと言うのである。
ちなみに、この山も間違いである。五岳山とは我拝師山、火上山、香色山、中山、筆ノ山のことであり、これらは海岸線よりもかなり内陸の山々である。沖か ら風のように連なって見える山は、天霧山、弥谷山、黒戸山、黒藤山、海岸寺山などもっと海辺寄りの五山である。海岸寺のある海辺の県道から振り返れば今で も屏風のように見えるが、まして沖から見れば、海岸にじかに接しているように見え、まさに屏風ヶ浦と呼ぶにふさわしい地形となる。
司馬は『空海の風景』で次のように語っている。
「ところで、こうも想像を抑制していては小説というものは成立しがたいが、しかし、空海は実在した人物であり、かれの時代のどの人物よりも著作物が多く、 さらには同時代と後世にあたえた影響の大きさということでいえば、かれほどの人物は絶無であるかもしれない。このため、かれのような歴史的実在に対しては 想像を抑制するほうが後世の節度であるようにおもわれ、むしろそのほうが早ばやと空海のそばに到達できるということもまれにありうる」
このように、司馬は実証主義的歴史観で空海に会おうとしている。このあと続けて、
「しかしながら抑制のみしていては空海を肉眼でみたいという筆者の願望は遂げられないかもしれず、このためわずかながらも抑制をゆるめてゆきたい」と語 り、ゆるめた結果、次に「空海の生誕の地は、いまの善通寺の境内である。空海のころは海がいまの善通寺あたりまできており、五岳山はじかに入江にのぞんで いた」という荒唐無稽な想像に発展する。
つまり、想像すべきところは安易に寺伝に従い、肉眼で見るべきところで実証主義を発揮していないのである。
空海の生誕地をめぐる紛争は結局善通寺が生誕地を勝ち取り、海岸寺は善通寺の奥の院とすることで落着した。地元で有名なこの話は、善通寺市に取材に来た 司馬の耳にもむろん入っていた。もしかすると、司馬は善通寺に配慮したのかもしれない。だが、作家は独立不羈でなければなるまい。たとえどれほど大師信仰 や宗教権威が強大であろうとも、自己の感性を信じなければ作家の敗北である。司馬は、彼がつちかってきた新聞記者魂と実証主義に賭けても自己の目を信じる べきであった。
私は帰国後の空海の行動が知りたくて、空海に詳しい善通寺のお坊さんに司馬遼太郎の空海史について質問した。そのとき「ああ、あれは小説ですから」の一言で軽くあしらわれたのは意外だった。
もう一つは、司馬にとって空海の出生地はあまり重要ではなかったのであろう。私は重要だと思っている。個人史にしろ民族史にしろ、「自分がどこから来たか」ということは単に地理的な問題にとどまらず、文化の問題がからんでくるからだ。
司馬遼太郎はただ面白い小説家だと思っていた私は、こんなことをあげつらうつもりはないのだが、知識人が彼の歴史観や思想をこうまで高く評価すると、それほどのものかと言ってみたくもなるのである。司馬文学にそれほど深い歴史観があるとは私にはどうにも思えない。
例えば、天皇の問題を避ければ日本史は骨抜きになると思うが、司馬の歴史観からは日本史における天皇の存在理由は見えてこない。彼の人物主義歴史観の背 景には、民族の精神史を掘り下げた様子が感じられないのである。左派的イデオロオギーで天皇を見れば支配権力となるが、日本人の深層意識からすれば、天皇 は祀り事(古神道)と繋がってくるだろう。つまり、日本人の信仰心、例えば自然崇拝などの民族的無意識の問題がからんでくるだろう。三島由紀夫の言うよう に、日本文化の基層もそこに横たわっているのかもしれない。まして空海ほど天皇と密接な関係をもった高僧はいなかったはずである。
天皇から庶民に至るまで日本人に多大な精神的影響を与えた空海とは、一体どういう人物だったのか。日本人の精神史に生きてきた大師像を避け、知識をより どころに空海を見ようとした司馬は、その手法が皮肉にも肝心な生誕地において虚像の空海を描くところからスタートしてしまった。なぜなら、主知主義では空 海に逢うことはかなわないからだ。真実に出会うためには、知に頼らずわが心に拠れ、そう教えたのは他でもない空海自身である。
「理知、他にあらず、すなわちこれわが身心なり」
「一鳥声あり、人心あり、声心雲水倶に了了」(空海)
雲光のもれ射す風ヶ浦の風の中に、私は空海のつぶやきを聴こうとしていた。