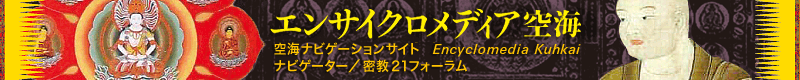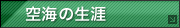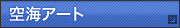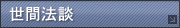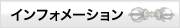◆中道とは何か
「中道」とは何か。一般向けの解説書を読むたび、筆者はいつも隔靴掻痒の感を受ける。釈尊の「悟り」の真髄とされる「中道」とは「両極端を離れた」という意味だとされる。無論そうには違いないが、この程度の説明を仏陀の「悟り」の内容とすることに、おそらく一般読者は得心がいかないはずである。専門家にとっては自明の理について、あえて一般人の目線で疑問を呈してみる。
ちなみに『岩波仏教辞典』には次のようにある。
「相互に矛盾対立する二つの極端な立場(二辺)のどれからも離れた自由な立場(中)の実践のこと、(中)は二つのものの中間ではなく、二つのものから離れ、矛盾対立を超えることを意味し、(道)は実践・方法を指す」
二つのものから離れ、矛盾対立を超えるとはどういうことか。アウフヘーベン(止揚)のことか。門外漢には結構難問であろう。
続けてこのように解説されている。
「釈尊は苦行主義と快楽主義のいずれにも片寄らない(不苦不楽の中道)、精神集中を内容とする八正道によって悟りに到達したとされる。初期仏教ではこの(不苦不楽の中道)が主であるが、(不断不常の中道)(非有非無の中道)も説かれている」
とあり、龍樹の中道、すなわち『中論』へと進む。
「竜樹の『中論』では、縁起・空性・仮・中道を同列に置いているが、これは、すべてのものは縁起し『空』であると見る点に中道を見、空性の解明によって中道を理論づけるものである」
とあり、続けて瑜伽行派の「唯識中道」や三論宗の「八不中道」、天台宗の空・仮・中の三観による「中道」が説かれているが、専門性が高くて、一般の人にはほとんど理解できないだろう。
そのせいか、一般向けの説明はごく平易に説かれている。しかし今度はアバウトすぎて「中道」の本質を突いているとは思われない。よく目にするのが、「中道」を「いい加減」と説明する論述である。例えば、ひろさちや氏の『中道を歩む』(1998鈴木出版株式会社)の中にはこう述べられている。
「私は、仏教が教えている―中道―が、この『いい加減』にあたるのではないかと思います。(中略)中道とは、ゆったりと努力することです。血眼の努力をするのではなく、ゆったりと努力を続けることです。努力すること、そのことが楽しいような努力をするのが中道です」。(pp.18~19)
氏のいう「いい加減」とは投げやりやおざなりのことではなく、「好い加減」のことを指すのはいうまでもない。このような説明は結構多いようである。大下大圓師(真言宗飛騨千光寺中興第24代住職)の『いい加減に生きる』(2004講談社)もそうである。
「中道というのは足して二で割るということではなく、右にも、左にも偏らないということを大事にする知恵です。『評価』したり、AとBとで『比較』をしてしまうと、必ず偏りが生まれてしまいます。そうではなく、あらゆるものをあるがままに、ほどよく、つまり、『いい加減』にしてバランスをとるのが仏教の、そして生きる極意だとわたしは考えています」(p.126)
念のため中村元博士の『ブッダ入門』(2012春秋社)も見てみよう。四諦の教えのあとに続けてこのように述べられている。
「中道の教え これは、(四諦の教えを指す:筆者注)別の言葉では『中道』の教えであるともいわれます。最近では政治の世界でも、『中道』ということがよくいわれます。誤解を受けやすい言葉ですが、『中道』は、どっちつかずという意味ではありません。漢訳仏典では、『至要之道』という訳語もあります。これはいい訳だと思います。肝心かなめの道だというのです。具体的には『不苦不楽の中道』です。わが身を苦しめるのでもないし、快楽にふけるのでもない。どちらでもないから中道というのです。」(pp.158~159)
このように概ね初期仏教の「不苦不楽」を中心に説く。現代風にいえば自分を極端なストイシズムに追い込まないで、しかし欲望に耽らずこつこつと精進する生き方、あるいはほどよい精神的ゆとりを保つということであろう。頑張りすぎるある種の人たちに対する"癒しの書"として一読の価値はあるが、そこに「中道」の内容を求めると、「中道」とは物事のほどよい加減やバランス感覚のことかと思ってしまう。だとすると論語の「中庸」と同じだと理解する人もいるだろう。現に大下大圓師はそのような表現で説いている。
「中道とは『偏らないこころ』です。仏教の真髄はなにかと問われたら、わたしは迷わずこの『中道のこころ』と答えます。東洋的には『中庸』と表現します」。(『いい加減に生きる』p.124)
こういわれれば読者はやはり二つの立場の中間の道を思い浮かべるのではないか。だが『岩波仏教辞典』では(中)は二つのものの中間ではないとある。では二辺のどれからも離れた自由な立場の実践とはどういうことか、矛盾対立を超えるとは?(中)の実践方法である(道)とは何か?いよいよわからなくなるのではないだろうか。
「偏らないこころ」が生きる極意だとしても、これで本当に仏教の真髄が伝わるのだろうか。「中道のこころ」は確かに仏教の真髄ではあるが、真髄はあくまで悟りを開いた「仏陀のこころ」のことである。仏陀は「無明」(注1)を滅せられた方である。対して未だ「無明」の眠りの中にいるのが凡夫であるから、凡夫の「いい加減(好い加減)」なバランス感覚が仏教の真髄だといわれて、一般の人が仏教の深さに触れることができるだろうか。
だからこそわかりやすく「中庸」の精神で言い換えるのだと思うが、しかし「中庸」とは孔子の教えである。「中道」は釈尊の教えである。であれば「儒教(中庸)」を説いて「仏教(中道)」を説いたことにはなるまい。釈尊は何事も一方に極端に偏らず、「ほどほどに」「好い加減に」「いい塩梅に」という、誰でも考えつくような平凡な経験知を「悟り」の真髄とされたのだろうか。「過ぎたるはなお及ばざるが如し」、長屋のご隠居さんでも諭しそうな人生知である。それを仏教の真髄だと説く専門家の解説にはどうしても疑問が残る。
また一方では「中道政治」などという政治用語?まで流布している現代において、一般人はますます混乱するのではないか。専門家は平易であっても正確に解説してほしいと思わずにはいられない。
ちなみに空海は『三教指帰』において儒教・道教・仏教を載然と分けて論じているし、晩年の『十住心論』においても、儒教を第二住心とし、第四住心からの仏教(顕教)はそれと一線を画している。それは儒教と仏教とは根本的に異なるからで、この点を解説とともにきちんと押さえている。
◆「中道」の内実
以下は私見である。必ずしもオーソドックスな学説に沿うとは限らないが、筆者自身が考える「中道」を試論してみたい。
「十二支縁起」(注2)に支配された無明の私たちは、常に自我に囚われた縁起の世界から脱することはできない。縁起の世界とは相対の世界でもある。相対的世界にいるかぎり、評価や比較や偏りはつきものである。そのために無意識に自己を基準とするのが人間である。自分に理解できるものだけが正しく、理解できないものは間違っていると考えがちだ。このような状態にある人間に"偏りのない中道"の生き方を説いても、せいぜい「心構え」で終わるのではないだろうか。
私たちが日常、常識的に身につけている意識は、自己と他者を分け隔てている感覚である。互いが切り離された孤立的な存在であるかのように思っている。その結果として、固定的、実体的な自分に過剰に執着せざるを得ないのだ。
釈尊はあらゆる「苦」の状況がその執着から生じていることを悟られた。釈尊が「苦」を解消されたのは、「苦」を生じさせる執着の正体を自覚したからである。さらに「苦」とは「無明」に縁(よ)ってそこからか因縁生起していることを悟られたからである。解脱とは「無明」が「明智」に転換されたときだといわれるが、おそらくそのとき釈尊は、日常的な感覚や思考を離れた高次元の世界を実感されたと思われる。それが「仏の世界」であろうと思う。
考えるに、一般的な解説による「中道」がわかりにくい理由は、直接その内容が説かれていないからではないかと思われる。「不苦不楽の中道」というが、これは極端な修行を戒める心構えのことではないか。「両極端から離れる」とか「いい加減」とかというのも、それは「中道」そのものを説明しているのではなく、「中」を悟るための意識の持ち方を説いているように思われる。苦行林における過酷な修行をやめたシッタールタの物語はそのように伝えている。
いや、「中道」とは「四諦」「八正道」(四つの真理と八支による聖なる道)であるというだろう。確かに仏伝ではそのように定説化されている。苦悩を生み出す原因は無明から生じる執着にあり、執着心がある限り人は輪廻界のとりこであり、次々に生死転生を続けながら永久に「苦」を味わい続けるとある。この「苦」の連鎖から脱却する道は「八正道」を守った正しい生活を行うことだとされる。仏教学者や僧侶はそのように説く。そこに「中道」の内容は示されているではないかと。
「正しい見解(正見)」を持ち、「正しい思惟(正思)」をし、「正しい言葉(正語)」を使い、「正しい行い(正業)」をし、「正しい生活(正命)」を送り、「正しい努力(正精進)」をし、「正しい意識(正念)」を整え、「正しい精神統一(正定)」を行うことが、苦滅に導く八つの正しい実践道であり、これが「中道」の内容だとされる。だから「八正道」を実践しましょうと仏教書にはよく書かれている。
◆「八正道」の正しさとは
だが、「正しい」「正しい」というが、そもそも何をもって「正しい」とするのか、少し考える人であれば必ず迷うだろう。正邪善悪の考え方は人によって、民族によって、文化によって、時代によって、立場によって、国家によって千差万別である。キリスト教の正義、イスラム教の正義、中華思想の正義、みな違う。
個人の衝突においても、国家の衝突においても、生育によって、環境によって、教育によって、国家の成り立ちによって、信奉する宗教によって、双方が自分の方が正しいと主張して一歩も引かず、アラブとイスラエルの長い戦いは解決の目途さえ立たない。つまり、「正しさ」とは人の数ほどあるのだ。
要するに「八正道」を実践しようにも、「正しさ」のスケール(物差し)が異なれば、相対的な人間社会において混乱をきたすばかりである。真剣に仏法を考えようとする人なら必ずそのような疑問を持つだろう。
仏教専門家はこの疑問に対してどのように答えるのだろうか。前掲『岩波仏教辞典』の編者の一人である中村元博士は「正しさの基準」を次のように説く。
「この中道の立場の本質は、時代によって事情によって違いますので、一概にはいえません。(中略) 結局のところ、具体的な基準というのはしょっちゅう変わるのです。要はその時々の社会通念の範囲内で、もっとも適切な道を実践するということに、尽きるのではないでしょうか。」(『ブッダ入門』春秋社2012・pp158~160)
一瞬唖然とした。筆者の誤読かと思った。さて読者は、博士がここで「中道」ではなく「中庸」を語っていることにお気づきだろう。「中庸」とはまさにその時々の事情によって物事を判断する上で、一方に偏ってはならないとする儒教の教えである。これは俗世(人間社会)における倫理的な概念である。世俗の倫理は時代や事情によって異なる。時には互いの正義が紛争の種になる場合もある。
もしかすると中村博士はこのように言いたかったのかもしれない。例えばプロのアスリートとアマチュアとでは、トレーニングの質も量も異なるように、肉体にかける負荷の基準は人それぞれだと。だから事情によって具体的な基準というものはしょっちゅう変わるものだと。
しかし明らかに「中道」を時代論や社会通念の文脈で語っている。そのなかで「中道の立場の本質」とは臨機応変することだといわれれば、それは自己否定である。これでは一般の人は、仏教とは事情や状況に適応する処世道徳に過ぎないのだと思うかもしれない。つまり仏教の普遍性に疑問を抱くことになる。仏教とは世俗を超えた普遍的な真理であり倫理思想である。時々の社会通念で変わるものではないと専門家は明確に説くべきではないだろうか。
仏教はバラモン教的な伝統社会の通念に対して、人間は出自ではなく行い(身・口・意)の三業によって判断されなければならないとして、カーストによる区別や差別を否定し、徹底して命の平等主義を説き実践した。この高度な普遍性が仏教の根本にある。
人の世の価値観が時代や事情によって転変極まりないのは「諸行無常」というものであって、釈尊はそれを超えた揺るがぬ真実の世界を悟られたはずである。仏教を諸行無常の社会通念の範囲内に収めることは仏教とはいえない。
このことからもわかる通り、例えば「八正道」を実践しなさいという仏教指導者も極めて常識的な判断で「八正道」を説いているように思われる。ために内容が社会通念や道徳論になっているように思えてならない。本来ステージの異なる釈尊の悟りの世界を、迷いの世界(娑婆世の社会通念)に引きずり下ろすことは、仏教の自己否定になるのではないだろうか。
したがって一般人が「八正道」実行しようとすれば自己満足にすぎなくなる。何故なら正しい道を歩もうにも「正しさ」の基準が曖昧で内実が不明だからだ。結局「その時々の社会通念の範囲内で、もっとも適切な道を実践するということに、尽きるのではないでしょうか。」という、曖昧模糊とした答えになる。
◆「八正道」の基準
釈尊は「四諦」の自覚を促すために弟子たちに「八正道」を示されたという。釈尊に帰依する修行者たちは、しかしさすがに「八正道」の意味を理解していた。それは道徳論ではなく真実を見る仏の智慧を得ることである。
そのためにはまず自分の生活を見直し整える必要があると考えた。かくして弟子たちに戒律が生まれた。「戒学」・「定学」・「慧学」(三学)のうちの「戒」である。「三学」の「学」とは、この場合、「学ぶ」という意味ではなく実践を意味する。実践戒律の初めは、基本的な「五戒」、すなわち「不殺生」「不偸盗」「不淫」「不妄語」「不飲酒」の五つぐらいだったが、「十善戒」など次第に増えていき、宗派によっては何百にものぼるのようになった。
さて、問題はここからである。「八正道」の具体的な実践規範でもある戒律を、弟子たちは本当の意味で実践することができただろうか。筆者はあえて否といいたい。例えば「不殺生戒」であるが、私たち人間は他の命を殺して食べていかざるを得ない存在である。生きる営みとは多くの命を「奪い」「殺す」営みでもある。この時点ですでに「不殺生」「不偸盗」は破戒されている。
水と空気だけ吸って生きている仙人のような人がいたとしても、その水も空気も外界から摂取しているかぎり「偸盗」である。出家者は一切の性行為をしないといっても、自分はもともと両親の性の営みの結果であり、自分がこの世に生まれ出る以前から、性は因縁としてわが身に内在している。
「不妄語」にしろ、嘘をつかない人間はいない。人間は無意識に嘘をつくものである。第一、神ならぬ人間が常に真実を語ることなどできない。正直のつもりでも結果的に虚偽であったことはいくらでもある。これは認識の問題でもある。中世キリスト教会の地動説の例を引くまでもなく科学の世界でも間違いは多い。政治や歴史認識においても、マスコミ報道においても、私たちの日常はほとんど妄語・綺語・両舌の世界で暮らしているといっても過言ではない。ことほど左様に戒律のひとつ一つは実行不可能なものである。
そこで仏弟子たちはなぜ実行できないのかと考えたであろう。あるいは体力の限りを尽くして荒行に打ち込んだ修行者もいたであろう。しばらくは煩悩を断ち切ったような状態も、時間がたてば元の木阿弥である。そのあがきの中から、自分は煩悩の塊であることを嘆いたかもしれぬ。厳しく自己を凝視する人間は必ずそういう思いに陥る。これは修行者も一般人も同じである。
最澄も法然も親鸞もみなそうであった。そこに彼らの純粋性があった。しかし思いのままに実践できないその苦悩の中から、「自力とは何か」「自分とは何か」「人間とは何か」「生きるとは何か」という人間実存の根本問題を考え始める。自己探求の始まりである。正に煩悩が菩提への第一歩である。釈尊の出家は、現代風にいえば人間探求の旅立でもあった。生老病死に収斂される人間の「苦」の正体を究明する旅であった。
戒律を守ることが、どうしてこうまで「ままならない」のか。それは人間というものが元々そのようにつくられているからである。それが釈尊のいう「苦」の意味である。かくして弟子たちは「十二支縁起」を理解する。人間として存在する自分は、本来意志とは関係なく「因」と「縁」の和合によって現象していることを知る。ここにおいて「苦」の実相が「縁起の支配下にある」ことを認識する。
筆者には、「八正道」とは弟子を自己探求(悟り・菩提)に導くために、釈尊が与えられたメソッドではないかと思うときがある。私たちが縁起の支配下にあるかぎり戒律を守ることは本来不可能なことなのである。そのことに気づかせる意味もあったように思う。
逆に言えば解脱された釈尊には可能であった。何となれば解脱とは「縁起の世界」からの離脱を意味するからだ。むろん釈尊が生老病死を克服したわけではない。しかし精神的には縁起の支配から自らを解放したからだ。(これを心解脱という)
ということは、俗世(縁起の世界)における正邪善悪を超えた世界の「正しさ」、つまり「仏の世界の真理」を知っているということだ。それが仏の智慧による「道諦」である。
凡夫の筆者が想像するに、適切な例ではないかもしれないが、釈尊の悟りとは地球人が宇宙に飛び出したようなものではなかろうかと思う。宇宙時代の現代人には理解できるが、もし地上しか知らぬ古代人が宇宙遊泳を体験したらどうなるか。物は落下しない。天地も東西南北もない。昼夜の区別もない。地上のあらゆる常識は覆されるのである。(注3)
したがって、宇宙(仏の世界の例)を体験した釈尊が、再び引力の支配する地上(縁起の世界の例)で宇宙の真実(仏の正しさの例)を説くにも説きようがない。ブッダが初転法輪までは沈黙された所以である。
では釈尊は凡夫が「真の正しさ」を理解できないと諦められたのか。否、釈尊は明確に説かれている。筆者はそれが「法灯明」(法帰依)の教えだと思う。「法に依れ」とは、「仏の真実」を拠り所にせよという意味である。すなわち人間社会の通念など「俗世の正しさ」に依るのではなく「法=仏の正しさ」に依れと教えられる。
では依るべき「法の世界=仏の世界」はどこにあるのか。それが「自灯明」(自帰依)の教えである。自分を「灯」としたとき必ず感得できると釈尊は遺言された。何故なら釈尊は、自分が外なる権威や倫理を頼まず、自己を「灯」としてひたすら深い瞑想に依ったからである。その結果の「悟り」の体験が、確信をもって「自灯明」と言わしめたのである。同様のことを空海も繰り返し何度も何度も説いている。
釈尊の「悟り」とは、宇宙の一部である自己(人間)の存在の真実の姿であった。「法の世界の真実」とは存在の究極の姿である。万物は孤立しているものではなく関係そのものである。わが身もまた宇宙の大生命・大日如来の脈々と流れる血脈にあり、無限に広がる自他非分離のいのちを生きている。したがって所得も無所得もなく、個我の欲望も執着もない。故に生老病死もなく「苦」もなく、「私は全てであり、全ては私である」という時空を超えた永遠の「生」を実感されたものと思われる。つまり「法」と一体化されたのである。
この悟りへの修行が深般若波羅密多といわれる行の実践である。そのとき因縁和合にしか過ぎない自分の命が新たな地平で輝き始めるのだ。すなわち八正道の「正しさ」とは「如来の正しさ」のことに他ならないのだ。「俗世の正しさ」は仮の正しさである。
そこから初めて真の「八正道」が見えてくる。正見、正思、正語、正業という一連の正しさの基準は、実は「仏の目から見た正しさ」であり、無知な人間の思いはからいによる正邪ではない。
最古の詩集の一つ『法句経』には釈尊の教えが遺されている。
「善し悪しのはからいを超え、目覚めたる人は、怖れあるなし」(第39詩)
だから「八正道」を示されたのであろう。その座標軸が「正見」である。「四聖諦」(苦諦・集諦・滅諦・道諦)の一つ一つを正しく照見し、智慧として収めることである。この第一の「正見」を起点にすることによって、あとに続く「正思」「正語」「正業」など七つの正道は、一見世間的な道徳論に似ていても内実は仏教倫理となる。これが真の「八正道」の実践徳目であり、時代や事情によって変わることのない真髄であり、仏教の不動の根拠である。
ここから世俗の道徳的な善悪は、本来「仏の正しさ」つまり「仏法」を基盤として考えなければならないこともわかってくる。仏法が王法の上にあるという意味もこのことを指す。仏法を国家の基本においた聖徳太子はさすがである。だが庶民にとって、欲望を捨てて直接仏道に沿って正しく生きることはなお苦難の道である。王法(為政者による世俗のルール)に従って生きる方が遥かに楽である。だからこそ、より純粋に「仏に近い生き方」を求めた人々がいた。それが出家修行者である。いわずもがな若き空海もその一人であった。
だが私たち在家は生産活動をしなければ生存できない。現実において人間がみんな出家したのでは人間社会は成り立たない。人類の歴史はそこから労働が始まり、富の蓄積が始まり、あるいは言語や集団が形成され、役割が形成され、ルールを取り決め、文明がそれぞれの地域の風土や歴史に合わせて発達した。しかしそれらは、あくまで人間が生きる(食う)ための「仕組み」である。
様々な仕組みや枠組みの中で生産生活をしている私たちは、皆が皆出家することはできないしまたその必要もない。では在家者は仏道を歩む必要はないのだろうか。
否である。釈尊はそれこそを「中道」と言われたのではないだろうか。釈尊は、世界は「諸行無常の人間世界」と、「諸法無我たる仏の世界」との二重構造であることを教えられたのではなか。
所詮、諸行無常の縁起の次元を超えることができない人間は、日常生活においては自己の命を最優先に生きている。加えて地球は人類が支配できるという人間中心の神さえ出現させた。ゴッドの許しを得れば正義の名のもとにエゴの残虐性が発揮されることは歴史の語るところでもある。しかし仏教はそれを戒める。それが「八正道」の正しさの基準である。
◆龍樹の「中道」について
ナーガルジュナ(龍樹)以降の「中道」を仏教学的にいえば、諸存在は縁起の故に空であり、しかも「仮」として表明されるものであるから、有でもなく無でもなく「中道」とする。龍樹は究極的・絶対的真理(勝義諦)と、世間的・相対的真理(世俗諦)という二つの真理(二諦)を説いた。彼の『中論』ではこの「二諦」の立場が「中道」とされている。仏教学的にはまあこのような説明になる。しかしこれでも一般の人には何のことかわからないだろう。
そこで筆者は、究極的・絶対的真理(勝義諦)を「仏の世界の真理」、世間的・相対的真理(世俗諦)を「人間界の真理」と言い換えている。「人間界の真理」とは我々が日常認識している現実である。言葉によって表現される世界のことでもある。言葉による思考とは理性と分別であり、整合性と実証性を証明する論理学や科学の世界でもある。縁起に依存した世界といってもいい。
対して悟りによる「仏の世界の真理」とは、人間の思考とは次元を異にした、言語では説明不可能な絶対の世界(真如)である。そこに相対性はなく自他の分別や区別はない。つまり「中道」とはこの二つの真理を、二つながらわきまえて生きよという教えではないかと解釈しなおすことにしている。
もしそうであれば、「中道」とは「仏の世界の真理」が前提にあり、龍樹の言葉を借りれば、究極的・絶対的真理である「勝義諦」が前提となる。ではあるが「勝義諦」を基盤として「世俗諦」がある。言い換えると「世俗諦」は「勝義諦」に包摂されているという意味では本来繋がっているものである。
人間界の真理(世俗諦)を超えた仏の心は、この世の諸々の存在が縁起上の現象であることを悟るが故に「空」を照見している。「空」なる世界においては「色」なる自己は存在しない(色即是空)。自己が存在しなければ無明も我執もそこから生じる煩悩もない。つまり「苦」から解放された状態である。これが解脱(仏の心)である。だから物事が偏りなく見えるのではないか。「中道」の真髄はこういう世界を踏まえた上での説法ではなかろうか。
例えば、反原発派を蒙昧といい切り、生涯原子力推進を主張し続けた吉本隆明氏は、時の世俗社会においては一つの見解で必ずしも間違いとはいえない。氏は科学技術と原子力に固執し、それ以外の思索を一顧だにしなかった信念の人である。彼がいうところの「元個人」とは、時流によって思想や主義を変えない志操堅固な知識人という意味で肯定的に使っている。
だが仏の心で眺めれば、自らの思想に囚われた我執の人となる。仏教では執着が煩悩を生じると説く。その根源を無明と呼ぶ。無明とは人間の根源的な無知のことである。科学技術などの「知」は外に向かって拡大するものだが、その「知」の内に関しては全く無知である。これが本来的な「無知」である。智慧はそのことに気づかせる。であれば仏教の造詣が深いと高評される「知の巨人」は、「"知識"の巨人」であっても「"智慧"の巨人」とはいえない。筆者が仏教徒の立場から氏の科学至上主義を批判したのはこの理由からである。
◆「中道」を生きる
不殺生戒は仏の心から見た戒めである。仏道に依って正見、正思、正業しようと努めれば、人間は行き過ぎた文明の行為を自制するしかない。外なる文明の進歩は重要だが、内なる智慧の完成はさらに大切ではなかろうか。極端な効率主義や欲望主義に偏らず、真の「正しさ」は"仏の基準"にあるという自戒の意識を含むことこそが「中道」であろう。筆者はそのように理解した。
「中道」とは、人間の営みの中で、「本当は何が正しいことか」と常に仏に問いかけることである。在家は修行僧のような清貧でストイックな生き方をする必要はないが、かといって移ろいやすい俗世の価値観だけを行動の原理にすることでもない。仏の世界と人間の世界の双方が同時に視野に収まった、いわば中間の道を生きることが肝要なのではないか。これが『至要之道』(肝心かなめの道)なのではないだろうか。仏の声を聞きながら娑婆を生きる。こういう生き方を説いたのが「中道」であろうと思われる。
要するに「中道」を生きるとは、「仏の心を持って俗世を生きること」である。できるだけ「仏の心・仏の智慧に近づいて生きようとすること」である。そうすれば自らの心が安定し、行き過ぎた方向を修正しようと思うだろう。そして文明の発展や世界の進歩発展とはどういうものか、人類の本当の進歩向上とはどういうものかということを考え始めるだろう。人類が最高に進化した姿、大乗仏教ではそれを「菩薩」と呼び、人類の理想像としたのである。
菩薩とは聖と俗の中間にありながら、ただの中間ではなく、それを超えられた方である。衆生に寄り添いながら、慈悲の心をもって、如来と衆生をつなぐ正に偉大なる「中」を顕現した存在といえよう。
◆あとがき
筆者の「中道」における試論は、学問的追求というよりも、一般の人が生きる手がかりを仏教に求めたとき、わけても「中道とは何か」という問題にどういう説き方があるかと考えた私論に過ぎない。「中道」があまりにも軽く説明され、とりわけ政治の世界においても使われている昨今、それらの違和感を述べてみたくなったものだ。
・無明
・十二支縁起無明とは苦に直結する人間の根源的無知。煩悩を生む三毒といわれる貧、瞋、癡のうちの癡はこの無知に収まる。貧と瞋は欲望に収まる。仏陀とは無明の眠りから目覚めた人のことである。逆に凡夫とは無明の眠りの中にあり、実体のない夢を現実だと思っているような状態をいう。「縁起に依存し」、「縁起の支配下にある」ということを例えれば、眠っている限り夢の中の(現実)は夢に依存し、夢の支配下にあるのに似ている。夢を見ている人は夢を見ていることを自覚できないように、無明の凡夫は無明の中にいる自分を自覚できない。これが無明の特徴である。目覚めた仏陀から見れば、夢を人見ているが、夢の中でどんなに執着しても、それは幻をつかもうとしていることだとわかる。だから『般若心経』では私たちが執着する現実を「顛倒夢想」という。
私たちはいつから無明の眠りが始まったのだろうか。仏教では自分が生れるはるか前から始まっているという。生まれること自体自分の思いどおりにならないのは、命の連鎖がすでに縁起の支配下にあるからだ。遡れば、無数の祖先から無限の因縁和合を繰り返し連綿と受け継がれてきた命の先端に自分がいる。自分の命は直接的には両親という因と縁が和合した縁起上の果報(現象)であるが、自分を産んでくれた両親もまた因縁和合の現象であるように、誰一人として縁起に依らないものはない。そして生老病死の縁起に依存せざるを得ない苦の一生を送る。生老病死という苦は直接的には無明から始まるのではなく、生に執着するところから始まる。正しくいえば無明の種を持ってこの世に芽を出すところから生の執着にまでつながっていくのである。そして死苦に至るまでの人間の因縁生起の発生順序を「十二因縁」、または「十二支縁起」という。(苦集聖諦のこと、逆観が苦滅聖諦)順序は以下の通り。
無明→行→識→名色→六入→触→受→愛→取→有→生→生老病死・憂悲苦悩
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫
無明の縁により行あり、行の縁により識あり、識の縁により名色あり(以下同じ)有の縁ありて生あり、生の縁により生老病死・憂悲苦悩を生ず。これがこの世に人間として煩悩が形成される十二の縁の連鎖である。
(注3)菅で編んだ丸い形の遍路傘は、宇宙を象徴する大日如来を表しているが、そこには「迷故三界城(迷うが故に三界に城して)」・「悟故十方空(悟るが故に十方は空なり)」・「本来無東西(本来東西なし)」「何処有南北(いずこに南北あらん)」と書いてある。