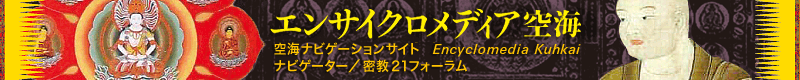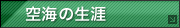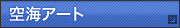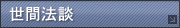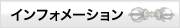◆「葬式は誰のもの?」の愚
親鸞は「自分が死んだら賀茂川に入れて魚に与えるべし」と遺言したが、実際はそうならなかった。荼毘に付されて東山大谷の地に葬られた。遺族門徒は親鸞の墓を作っているではないか。
親鸞上人を慕い訪れる人は後を絶たず、この廟所(墓)を浄土真宗の本山(本願寺)としたことは氏も知っているはずだ。しかるにアメリカ生まれの詩「千の風になって」までもち出して、墓はモヌケの空だというのなら、「そんな場所に親鸞上人はいませんよ」と信者仲間を教育すればどうだ?
第一どうして教祖様の遺言を守って魚のエサにしなかったのだ。不心得な門徒たちだ、というよりも、遺族門徒の感情として墓なしでは忍びなかったからではないのか。それが日本人の心情というものであろう。浄土真宗もやっぱり墓から始まっているのだ。
氏は「オレの葬式はオレが決める」の大間違い(p.36)でこのようにいう。
しかし、葬式とは何かということを、根本から考えてみてください。自分の葬式を執りおこなうのは誰ですか?自分で自分の葬式ができますか?(略)自分の葬式は自分でできない。つまり、自分の死後におこなわれる儀式は、「オレの葬式」ではない、というのが葬式の根本。(略)その認識がなく、オレの葬式だと思い込んでいるから、形式はどうだ、費用はこうだ、規模はああだ・・・・とつべこべと希望を述べ立てることになる。そんなに葬式を取り仕切りたかったら、自分が棺桶を担げといいたいですね。(略)自分の葬式は妻や子どもたちの葬式ということになるのです。だったら、妻や子どもたちにまかせておけばいいということになりませんか。その領分にあれこれ口出しするのは、それこそ余計なお世話以外のなにものでもありません」(p.36-37)
なら、親鸞上人が真っ先に大間違いを犯しているではないか。「死後に行われる葬儀はアンタのもではない。オレの葬式だと思い込んでいるから、死後は賀茂川に入れろとか口出しをする。それこそ余計なお世話だ。そんなに葬式を取り仕切りたかったら、自分が死体を賀茂川に放り込め」と教祖親鸞にいってあげなさい。
このような自己撞着に陥るのは、「自分の葬式」だの、「遺族の葬式」だのと分けて考えるからである。葬式は当然亡くなった当人のためであり、同時に遺族のための儀式でもある。この当たり前のことに屁理屈をつけるのは、何としても葬式や法要を止めさせたいと思うからだろう。それでは氏はどうしようというのか。
仮に妻から、「あなたのお葬式はどうしたらいいですか?」と聞かれたら、「知らん」のひとことで片づけるのが、道理がわかった人間のふるまいです。(p.37)だそうである。
つまり遺族の好きにやれ、ということだ。だったら氏の遺族が世間体を考えて、著名な氏の為に多くの会葬者に告知して氏のお嫌いな盛大な葬儀を行うかもしれないではないか。氏がどうしても直送や散骨を希望するのなら、自分の死体を直接窯(カマ)に入れて、自分で散骨するしかないだろう。自分がいっていることの矛盾にすら気がついていない。
◆法事文化は必要である
オウム真理教でも高学歴の若者が次々と密教まがいのカルト教団に入信した。今でも大人が新興宗教にハマったり、霊感商法に騙されて高額な金を巻き上げられたりしているが、そういう人たちは基本的に邪宗に対する免疫力が不足しているのではないかと思う。
芸術作品でも、格調高い本物を身の回りに見て育った者は、贋作を本物だといわれてもどこかおかしいと感じるだろう。仏教は2500年以上の風雪に耐え抜いた本物の宗教である。寺の賽銭は小銭である。キリスト教の献金もわずかなもの。伝統宗教に触れているだけでも、大金を要求してくる宗教はおかしいと気がつくものである。
江戸時代までは庶民は主に檀家寺によって伝統仏教に触れてきた。戦後は信教の自由の名の下に、公教育の場で宗教教育は禁止された。海外では学校教育の基本に宗教がある。だから無宗教は最も信用できない人種とみられるが、日本では無宗教であることに知的自尊心を持つ。特に高学歴者はそれが知的態度であるかのように信じている。
だが、宗教に過剰な警戒心をもつよりも、子どものころから寺や仏壇に親しみ、盆の行事や彼岸の墓参りなどの仏事に触れて育てば、怪しげな新興宗教に騙されることは少ないと思う。ところが、東大出身の有名な宗教学者は、『葬式は、要らない』というハイカラ学者であった。そして見事にカルト集団オウムに騙された。実に象徴的である。
ひろさちや氏も「墓参りを年中行事にする愚」において似たようなこという。墓参りは「ふだんからご先祖様を偲んでいる、というそのことの延長上の行動にあるべきだ」という。
折に触れてご先祖様を偲ぶ、心の中にいるご先祖様に語りかける。そんな日々を送っていたら、何も彼岸という特別な日の墓参りを年中行事化することもありません。墓はあってもなくてもいい、ということになりませんか。ふだんは祖先のことなどすっかり忘れていて、彼岸になったら形式的に墓に足を運び、かたちだけ拝むよりはるかに意味があることだと思うのですが、どうでしょうか。(略)『彼岸に墓参りさえすりゃいい』というのは自己欺瞞というしかありませんね。(強調文字ママp.69)
普段ご先祖様のことなど考えていない子どもたちも、盆や彼岸で両親とともにお花をもってお墓参りをすることにより、大人たちからご先祖様の話を聞くこともあろう。年忌供養ならお坊さんに触れることもあろう。親が檀家寺に行けば説法も聞きご本尊を拝む所作も身につけよう。法事文化に触れて育つだけでも、伝統からくる本物の直感が育つ可能性がある。私はそうやって育つ子どもの方がカルト宗教に騙されにくいだろうと思う。忙しい現代人は、特別な日の墓参りを年中行事化してでも機会を設けた方がいい。
第一世の中は、節目、節目で、たいていそういう年中行事によって大切なものを保存しているのではないか。各地の祭りもそうやって地域文化を継承しているのだ。宗教的感覚の土台がないままに、いきなり仏教は「心の問題」だ、心さえあればOKでは、基礎力のないところにいきなり高等数学を解かせるようなものである。
実はこの方が危険である。最近若者の間で増えてきた「新型うつ」といわれる新しいタイプのうつ病は未熟性、自己中心性、他罰的、攻撃性などの特徴が挙げられる。そして彼らが宗教に走ると一気に神秘主義や超常現象などに関心が飛び、超世などのカルトに走るケースが報告されている。
ご先祖様はどこにいる?氏は「私たちの心の中にいる」という、さらにいえば「お浄土に行っておられる」、だから墓参りは自己欺瞞であるといい、形ある葬式も墓も祖先供養も、オールナッシングにして、子どもたちの学習機会(免疫力)を奪おうというのである。
賽銭を盗んだり、神社仏閣に落書きしたりして聖域を汚す事件は後を絶たない。それも重文や国宝級の世界遺産を含む貴重な寺社である。信仰の対象を汚す許せない行為だと大人たちは憤慨するが、それ以前に学校や家庭で宗教に対する基本教育をやってきたか、神仏に対する尊崇の念を育ててきたかと問いたい。
法事ですら価値を認めようとしない氏のような仏教学者が流行るご時世だ。聖域に対するも恐れも礼儀も育つわけがなかろう。だから海外に行っても、普通の若者がノリノリの観光気分でその国の聖域に土足で入ったり、落書きしたりして現地の人々の怒りを買う。戦後70年、国内での宗教教育の排除が海外でこのような振る舞いに出てしまうのだ。
沖縄ではこれを「やーなれーぬふかなれー」という。「やー」とは家のこと、「なれー」とは躾のことである。「の」は「ぬ」と発音し、「ふか」とは外という意味である。つまり家庭での行いや躾は外に出た時に表れるという意味である。家できちんと躾けられた人は外に出ても礼儀正しく振る舞うが、家でだらしない人は外でもだらしなく振る舞って恥をかくという家庭の訓育である。氏は沖縄の人にでも教わるがいい。
◆遺骨はモノではない―弘法大師の教え―
山口県の長門先崎漁港は古くは捕鯨で栄えた港町。当地には今も「鯨墓」(くじらばか)が残されており、鯨寺には「鯨過去帳」まである。捕獲した鯨に戒名をつけ位牌や卒塔婆を作りずっと鯨の供養をしてきた。現在も年1回の「鯨法会」を盛大に行っている。これは江戸幕府の命令でもなんでもない。「キリシタン鯨?」を摘発するために、寺で鯨の葬式をしろとはいっていない。寺が鯨を檀家にしたわけでもない。誰も強制せぬが、鯨の命を憐れむ当地の漁民の心から生まれた行為である。
大分県臼杵市にも鯨墓があり、京都府の伊根町の蛭子神社には三つの鯨墓がある。これらは、鯨を捕獲し、その食料や資源で自分たちが救われているという日本人の自覚があるからだ。「命をいただく」感謝から、生き物を供養する行事は全国津々浦々にある。私は四国の漁港で育ったが、岬の先端には魚供養の魚霊塔(墓)がある。
たこ漁が盛んな広島県三原市は毎年8月8日を「タコの日」と定めている。8本足のタコの八ちゃんの恵みに感謝する「タコ供養」が毎年執り行われている。みんな感謝の気持ちがそうさせてきたのである。高野山にはシロアリの供養塔まである。生をこの世に受けながら、人間の生活と相入れないために失われていく生命の憐憫を見つめた日本人の眼差しがそうさせるのだ。
それどころか日本人は有情・非情、分け隔てなく拝む。「山川草木悉皆成仏」である。これは果たして前近代思想であろうか。念仏他力の「浄土門」にとって、これは自力本願たる「聖道門」旧仏教の伝統思想(天台本覚思想)だと一蹴するするかもしれない。しかしここには万類共存の先駆的な思想さえみられる。
イギリスの科学者J・Eラヴロックは地球全体を一個の巨大な有機体(生命体)と見なすことを1960年代に提唱した。近年のエコロジー運動にも影響を与えた「ガイア仮説」(地球生命圏)である。「山川草木悉有仏性」の日本仏教では大昔にわかっていたことである。
「お浄土」を強調しすぎると、天国思想(キリスト教)と同じ人間中心主義になる。地球の環境破壊が人間中心主義から起こったことはいうまでもないことだ。
遺骨でさえ供養するに値しないただの物質であれば、まして大木や巨石に注連縄をはって祀り、あるいは鉱物までも供養する日本人は何者か?氏の論理ではほとんど未開人ということになろう。
だが日本人は命なき鉱物まで供養する。針供養、包丁供養などがそれである。広島県の熊野町は「熊野筆」で有名な筆の産地である。当地には「筆塚」が建てられている。いつだったか写真家たちが、使用済みの古いカメラを廃棄するために持ち寄って山積みにし、僧侶を呼んで盛大に供養している様子をテレビで見たことがある。愛用したモノや道具には魂が宿ると思うのが日本人の感性である。故に剣は武士の魂なのである。
この感性がいま欧米でブームになっているのを知っている人も多かろう。今年「世界で最も影響力のある百人」に選ばれた近藤痲理恵さん(片づけコンサルタント)である。2010年末に出版した『人生がときめく片づけの魔法』(サッマーク出版)はミリオンセラーである。世界最大の物質文明のアメリカも、「捨てる=悪」のイギリスも、やっと断捨離の意味に気がついたのだ。彼らはいかに無駄なモノを溜め込んでいたかを、この若い日本の女性に教えられただけでなく、モノにも自分のスピリットが宿ることを理解し始めたのだ。
いま欧米人は不要になったモノを捨てるとき、一つ一つに「サンキュウ」といいはじめた。イタリアではモノに感謝し、人生を変える革命との評が出ており、このブームは第二の産業革命とまでいわれている。これはある意味日本のモノ供養の萌芽でもある。
高野山大学大学院(通信制)の卒業生で、川田研究所の川田薫氏がいる。氏は物理工学が専門の工学博士であるが、高野山の大学院では「密教学」を学んだ。氏がいうには、ミクロ(ナノ)の世界では、岩石にもダイヤモンドにも「空間」がたくさんあるそうだ。その空間に人間の思いが入るのだそうである。氏は空海の「六大」説にヒントを得て、現在は常温での超伝導の研究に取り組まれている。
カメラマンが使用済みのカメラの供養をするのも、針供養、包丁供養、筆供養、人形供養などをするのは迷信からではない。物理学的にも不合理ではないのだ。長く愛用した道具はただの物質ではなくなっている。まして肉親の遺骨はどうか。それをただの物質・ゴミ扱いにするひろさちや氏とは一体どういう仏教を学んできたのだろう。
弘法大師空海は、インド哲学の「五大」説(または「四大」説)に対して「六大」説を唱える。「六大」とは。世界を構成する地・水・火・風・空の物質的な五大原理に、精神的原理である「識大」を加えたものである。空海は顕教(仏教)では「五大」を生命現象のない存在(非情)と見るが、密教では「六大」すべてを宇宙的な生命(法界体性)と見做すと説いている。
『即身成仏義』偈頌の冒頭「六大、無礙にして、常に瑜伽なり」というのは、「六大」は矛盾なく融け合い、常に結合し相応しているという意味である。
「仏六大を説いて法界体性となしたまう。諸々の顕教の中には、四等大をもって非情となす。密教は即ちこれを説いて如来の三摩耶身となす」「いわく、六大とは五大と識大なり」(『即身成仏義』)
今日の量子力学の重要なテーマは、ミクロの世界から発見された自然の「相互依存性」である。釈尊がすでに紀元前に把握していた「相依性」(縁起・縁滅の理法)がミクロの世界の現象で現われたのである。
例えば、電子の状態を観測するため、電子に電磁波を当てようとすると、被観測物である電子が乱されてしまう。これを物理学では「ゆらぎ」というが、観測が状態に影響を及ぼしてしまうため、結局のところ、観測目的である電子の状態は永遠に突き止められないという。これが因(電子)を変化させる縁(観測)による因縁生起である。
自然現象は観測者の有無に係わらず、常に同じように起こるというこれまでの科学の前提(西洋の因果論)が成り立たなくなってしまったのだ。観測される自然(客体)と観測者(主体)を完全に還元できると考えた近代科学の前提は、ミクロの世界ではもはや成り立たなくなったのである。これは観測者と自然との相依性を示している証左で、空海は1200年も前にそのことを繰り返し述べている。
西洋の二元論は、世界や事物の根源的な原理を、相反するそれぞれ独立した二つの基本的要素から構成されるというものである。代表的な二元論として17世紀ルネ・デカルトの唱えた実体二元論がある。例えば肉体・物質といった身的実体とは別に、自我や精神、魂・霊魂と呼ばれる心的実体を明確に区分する考えである。その西洋の二元論の概念はサイエンスの世界ではもはや成り立たなくなっているのだ。
要するに人間が死ねばその瞬間、霊魂は「お浄土」にテレポートして切り離されているというのは西洋的二元論である。遺骨はただの物質で供養の価値はないという氏の考えは日本人本来の感性にはない。量子物理力学も驚くような感性を日本人は古代からもっていたのであって、決して未開人ではない。
◆「終活」も他国礼賛・自国批判
さて、いよいよ氏の考える真の終活とはどんなものか。少しは期待して読んでみたが、見事に裏切られた。6章 真の終活とは何かではさっそく他国の例に見習えとくる。インド人の生き方で作家五木寛之が好んで使う「四住期」のことである。人生を「学生期」「家住期」「林住期」「遊行期」という四つに分ける。
ひろさちや氏は、学生期(がくしょうき)を文字通り学びの期間、家住期(かじゅうき)は結婚して家族を養う働き盛り、林住期(りんじゅうき)は、一線からリタイアし、自然の中で悠々自適の隠居生活暮しであるという。遊行期(ゆぎょうき)はこれも文字から各地を気ままに旅する悠々自適の暮らしであるという。ところが本人は「林住期」と「遊行期」の区別がよくわからなかったらしい。最近、やっと林住期の意味を悟ったそうだ。それが何と「孫の教育」だというのだ。
林住期は仕事の第一線から退いても、孫教育に関しては現役でいなければいけないのです。(「真の終活とは何か」(p.157)
これから発展して、人生経験を豊富に積み、酸いも甘いも噛み分けてきたおじいちゃんおばあちゃんは、孫の嫁選びなどの相談相手になれという。結婚相手を見抜く眼力が確かだからだ。現代の年寄はそういう「役割」を放棄していると非難する。その役割を担うことが真の終活だという。「自分の人生経験のありったけを譲り渡す。これこそが相続です。」という。その意味では間違っていない。
しかし終活を「相続」だけに見るように、相続する子どものない年寄は「終活」の視野に入れていない。高齢者全般の社会的な「役割分担」という高い視座に立つのかと思えばそれもない。だから家族がいれば終活なんていらないと続けるのである。
そこでまた他国の例を挙げる。氏の知り合いのパキスタン人の家族は、一族郎党をあわせ277人もいるという。そこでは一族の誰かが歳をとって病気になり、看護や介護が必要になっても、誰かが面倒をみているというのである。そこで「つまり何の憂いもなく老人生活を送れるのですから、終活なんていうものはまったくする必要がないのです。」といい出すのである。(「家族がいれば終活はいらない」(p.163)
アホか?ここは日本である。しかも核家族化が進み、少子高齢化が世界一加速し、独居老人や孤立老人も増加し続けているわが国の問題なのだ。そこには目をつぶって、パキスタンの例からこうノタマウ。
大家族であったかっての日本もそうだったのです。それを、近代化だか、個人尊重だか、知りませんが,訳のわからない理由を掲げて、すっかり壊してしまった。(p.163)
あなたに言われたくない。そんな日本にしてきたのは、人間関係の面倒くさい農村社会を嫌い、近代化と個人主義を礼賛してきた進歩的知識人だろう。かつての日本の農村は村の全体が大家族であった。誰かが死ねば村中で葬儀をしたものだ。それは檀家寺を中心としたコミュニティーがあったからである。その檀家寺をさんざんこき下ろしておきながら、ここでは近代化と個人主義を槍玉に挙げて「いいとこ取り」をする。いいかげんにせいといいたい。
◆支離滅裂な啓発精神
最終章は最期を明らめてこそ生が輝くである。ここでいよいよ浄土教の考え方が展開される。その最初が「自分のなかにお浄土を」(p.174-180)である。
70代半ばの氏は、「心はきわめて穏やかで、日々、清々しく過ごしている」そうである。それは日々心の中に「お浄土」をつくっているからだという。まことに結構なことである。しかしそれは、個人の信仰として、自己満足として仕舞っておけばいいことではないか。
しかしながら知識人の思い上がりだろうか、やはりこういう。
「なんとか相続税を節税する方法はないだろうか」「生前贈与した方が得かな?」等 と金銭勘定に躍起になっている終活と、自分のなかにお浄土をつくることに幸せを感じる終活、私は後者がはるかに素晴らしい、前者は老いの生き方として恥ずかしい、と考えるのですが、みなさんはどうでしょうか。(強調文字ママp.175)
と迫ってくる。私も先の◆余計なお世話はやめなさいにおいて、「終活」は最後に精神の問題、死を迎える心構え(さとり)だと述べた。だがその前に、避けては通れない具体的な諸問題の処理こそが「終活」であるとも述べた。だが氏は一気呵成にお浄土という「心構え」に入っていくのだ。
そうはいいつつ氏にとって実際的な「終活」問題は、ただ金銭にまつわることしか思いつかないようだ。だからお浄土論は早速相続税対策なんていらないで始まる。はやはり金銭勘定の話になる。ここでは相続税の節税対策が実際はさほど得にはならないことを、エコノミストよろしく各種数字を挙げて証明している。そして結論はこうである。
「みんなのために使われる税金なのだから、少々でも支払えたらうれしいな」というぐらいの余裕があってこそ、立派な年寄りというものだ、と思ってほしいですね。本来、日本人はそんなに「みみっちく」はないはずなのです。(p.179)
氏の本はよく売れるらしくて大学の給料の三倍くらいになったこともあるという。何しろ600冊も出版する売れっ子作家である。だから余裕をもって、わずかな金をケチるような相続税対策なんていらないといえるのだろう。
したがって相続の心配をする「終活」を「我欲」だの「執着」だのといいだすのだ。そこから遺言書も、葬式の思案も、戒名も、位牌も、お墓も、すべては現世に対する「執着」と見て、いい歳をして「まだいい思いをしたいのか」となるのである。返す刀で「自分の中にお浄土を作ること」こそが素晴らしい仏教的な生き方だと教えを垂れる。
で、次の項、「金離れのいい人、悪い人」では、自分がいかに金銭に恬淡(てんたん)としているかをご披露する。ここでの啓発は、人生の晩年は金に執着するな、ということである。だから「金離れ」を実践する自分のような老人を「かっこいいいじいさん」(p.180)だというのだ。
その論拠に道元の『正法眼蔵』まで引き合いに出してくる。「生をあきらめ、死をあきらむるは、仏家一大事の因縁なり」という道元の言葉にもじって「最期を明らめてこそ生が輝く」という最終章のタイトルを掲げるのである。
氏の言葉で言うと、「人は何も持たないで裸で生まれてきて、何ものも持たないで還っていく。その道理に気づくことが、生死をあきらめることです」となる。「すべてを投げ捨てていくのが死ということなら、終活などアホらしいかぎりであることはいうまでもないことでしょう」(p.167)というのである。
つまり、あの世に金は一銭ももっていかれないのだから、金はこの世で使い切りましょうといっているのだ。その通りである。大いに賛同する。「金は天下の回りもの」、散在してこそ世のためになる。特に多額の箪笥貯金をしている老人は金を社会に還流させるべきである。
であるのなら、葬儀など無用だという前に、葬儀に金をかければ葬儀屋が儲かるとは思えないのか。葬儀会社が儲かれば従業員の懐が潤う。斎場を飾りたてる花屋も提灯屋も関連業者が儲かる。料理も無意味だというが、料理を出せは料理屋も儲かる。墓など無用だというが、墓を作れば墓石屋が儲かる。70万円の戒名料を高すぎるというが、支払う人の勝手だろう?そんなものはただの見栄だとお叱りだが、見栄っ張りの金持ちもそれによって自己満足し、景気よく散在していることになる。
お寺はペテンのぼったくりだというが、余裕がなければ寺は荒れ放題。お寺が儲かれば寺院の修復もできる。それで宮大工の仕事が増える。大工の父ちゃんが儲かれば母ちゃんも子どもも喜ぶ。中には高級車を乗り回してゴルフに行く俗物坊主もいるが、それだって自動車産業に寄与しており、ゴルフ場の客が増えれば売り上げが伸びる。それで職員が儲かる。金はどんどん末端に流通していく。それが資本の再分配だろう。
「直送」で火葬場のカマの温度をもっと上げて、死体が跡形も残らないようにすれば、火葬場の人も手がかからないというが、その結果リストラされたらどうする?葬儀屋が潰れたらどうする?石材屋が潰れたらどうする?散骨のお蔭でみんな職を失ったらどうするというのだ?やっぱり「後は野となれ山となれ」か?
こういうことは、「ひろさちや散骨株式会社」でも設立してから言いなさい。あなたのオールナッシングで失業した人たちを全員雇用できるようにしてから言いなさい。
氏は直前の金離れのいい人、悪い人で、税金をきちんと納めて「みんなのために使われる税金なのだから、少々でも支払えたらうれしいな、というくらいの余裕があってこそ、立派な年寄りというものです」と説教を垂れながら、葬式仏教に関しては一切の金離れを認めないのである。途端に「余裕のない年寄り」に変身するのである。これこそ「かっこ悪いじいさん」ではないか。支離滅裂な妄言は無責任な売文学者の思いつきである。
◆悪魔のささやき
中でも一番人々を惑わすものが、氏の説く「お浄土」論である。本人は素晴らしい浄土真宗の教えを説いているつもりだが、その素晴らしさは自分個人の胸の内に止めてもらいたい。何故なら、場合によってはそれが他人を死に導く可能性があるからだ。
こういうと、おそらく本人も氏の愛読者も目をパチクリであろうから、まず氏の説く「お浄土」なるものを本人の言葉から拝聴しよう。
「お浄土とはこういうところ」(p.181-192)
ここでお浄土について少し詳しくお話ししましょう。お浄土がどんなところなのかが描かれているのが、『阿弥陀経』という経典です。(略)お浄土では阿弥陀仏が説法しますが、そこにいるあらゆるものはいっさいの苦しみから解放されて、まさしく極楽の日々を送っているのです。
その世界は、『阿弥陀経』が書かれた当時の人びとが、あらんかぎりの想像力を駆使して、つくりあげたパラダイスだといってもいいでしょう。
ただし、実際にそんな世界が存在するかどうかは、仏教では問題ではないのです。重要なのは、死んだ人は必ず、そこに行けると信じることです。揺るぐことなく信じきることで、「死後の世界はどうなっているんだ?」「死んだらどうなるんだ?」などと余計なことを考えなくてすむからです。
江戸幕府を開いた徳川家康は旗印に「厭離穢土 欣求浄土」と染め抜いていたことを知っていますか。この二つの文言はお浄土ときわめて密接につながっています。
厭離穢土は穢れた場所を厭い、離れること、欣求浄土は浄らかな場所を欣び求めること、です。
穢土は私たちが生きている現世、この世のことですから、そこを離れてお浄土を求めなさい、と文言は教えています。これが浄土思想の根本です。
仏教ではこの世を苦の世界としていますから、生きている間は思うにまかせないことがしばしばあります。他人のために何かしたいと思っても、自分にそれだけの甲斐性がないということもあるでしょうし、自分の成功のために心ならずも、他人を蹴落としてしまうこともあるかもしれない。(略)しかし、それでよかったのだろうか、もっと人としてよりよく生きられなかったのだろうか、そういう思いは残ります。できるものなら生き直したい、そういう気持ちが衝き上げてくるかもしれません。
そこで、お浄土が大切になってくる。
「自分は必ずやお浄土にいって、もう一回、やり直すのだ」と信じる。それが欣求浄土です。お浄土はこの世でままならなかったことを、実現する、実践する場でもある、といってもいいでしょう。(強調文字原文ママ)
このような言葉は終末期の患者や死刑囚に向けた教誨師の言葉としては一定の意味はあるだろう。しかしこの本は間違いなく一般読者向けの「生き方」を説いた本である。氏は現代人の悩みや苦しみを知った上でこのような楽天的なことをいうのか。メンタル・ケアに携わっている私はそう思わざるを得ない。私は「産業カウンセラー」と「キャリア・コンサルタント」の資格があり、日頃、職場や家庭などで悩める人の相談にのっている。
現在の日本は、かつての高度経済成長時代とは違い、経済市場のグローバル化や、少子高齢化、若年労働市場の減少、高齢労働者人口、外国人労働者の増加などが、労働市場の構造変化をもたらし、さまざまな雇用問題が発生している。一方、非正規社員の増加、賃金格差の拡大が社会問題として注目されている。また成果主義の導入、技術革新、処遇制度の変化などは、能力、業績を厳しく問われ、配転や、早期退職などを迫られている。
これも本来日本人には馴染まないアングロサクソンの欲望資本主義からくる新自由主義(市場原理主義)や効率主義を取り入れた必然ではあるが・・・。その結果、心労、不安、過重労働などの複合的ストレスに起因する職場不適応やメンタル不調は増加の一途をたどり、うつ病などの精神疾患が多発し、労働者の自殺率は世界一となっている。現代は一億総うつ時代とさえいわれる始末である。
うつ病は特殊なものではない。「心の風邪」といわれるように、だれもがかかり得る可能性のある国民病である。5年前に厚労省は、がん、脳卒中、心筋梗塞、糖尿病の四大疾病に精神疾患(うつ病など)を加えて五大疾病としている。日本がうつ病大国といわれる所以だ。
初期の抑うつ状態は治りやすいが、重いうつ病になった人たちは、心療内科でも、薬でも、心理療法でも治りにくく、ついに統合失調症になる人もいる。私はそのような人たちの心の支援などもやっている。
うつ病になると、睡眠障害や食欲不振が続き、頭痛や全身のひどいだるさを感じる。何をするのも面倒で、好きだった趣味も楽しめず、仕事に身が入らず、頻脈、吐き気、過呼吸などの身体的症状をきたすこともある。ひどい場合は寝たきりになってしまう。身体障害と異なり、精神障害は外からは見えにくいので、患者は周囲の理解と支援が思うように得られず、孤立無援のうつ病地獄を長期間にわたって味わうことになる。精神的苦痛に疲れ果て、最悪の場合は自殺してしまうこともある。
自殺念慮者は「死にたい」「楽になりたい」「この世から消えてしまいたい」「もとの自分に戻りたい」「もう、おしまいです」など、絶望的な言葉を絞り出す。そういう極限状態にある人たちは、カウンセラーとかすかな糸で日々の命がつながっている状態だといってもいい。もちろん死にたいと思う人間はいない。人間は生きたいと思うようにプログラミングされている。死にたいと思って死ぬのではなく、絶望と孤独が死を選択させるのである。崖っ淵にいるこの人たちは、誰かが背中をあと一押しすればすっと実行するだろう。
「お浄土では、そこにいるあらゆるものはいっさいの苦しみから解放されて、まさしく極楽の日々を送っているのです。」
もし、彼や彼女たちがこのような言葉を信じたら即自殺を決行するだろう。多くの女性はうつ病地獄から解放されて「もう一度やり直したい」「人生を取り戻したい」と泣きながら訴える。
「自分は必ずやお浄土にいって、もう一回、やり直すのだ」と信じる。それが欣求浄土です。お浄土はこの世でままならなかったことを、実現する、実践する場でもある、といってもいいでしょう。
このような言葉を聴けば、それが自殺に至る一瞬のトリガーになるかもしれないのだ。死にたいというのはもう一度生き直したいという切なる叫びなのである。
うつ病は、生きるエネルギーの低下状態であるから、生きようとして何かにすがろうとする。時には依存症に陥ることもある。買い物依存、アルコール依存、ギャンブル依存、薬物依存、恋愛依存・・・。何かにすがろうとする意味では、まさに他力浄土を求める精神状態である。
「阿弥陀仏のお浄土では、あらゆるものはいっさいの苦しみから解放されて、まさしく極楽の日々を送っているのです。」「阿弥陀様は苦しむ人こそ温かくお迎えくださる」「厭離離穢土は穢れた場所を厭い、離れること、欣求浄土は浄らかな場所を欣(よろこ)び求めることです」
人間はもともと「絶望の真実」より「希望の嘘」を好むところがある。ましてこの世を苦しみの世界、穢土としか思えない人たちにとって、氏の語る甘美な「お浄土」の世界は「救いの地・希望の地」と映るのではないか。
彼、彼女らは日々死の誘惑と懸命に戦っているのだ。遮断機の下りる踏切の中に飛び込みそうになったり、電車の入ってくるホームで必死になってベンチにしがみついて投身をやり過ごす人たち、リストカットを繰り返す少女たち・・・そういう人たちにとって氏の語る言葉は、死へと誘う「悪魔のささやき」となろう。
彼や彼女らは高学歴者も多く、メンタルに関する本や、人生論、宗教関係の本などを読むこともある。しかしうつ病のために正常な思考状態では読めない。読むとしても思考がまとまらない状態で読んでいるのだ。ここが問題である。というのは、言葉がストレートに入ってくるからだ。ひろさちや氏の好んで使う洒落や冗談、逆説や機知、頓智は通用しないと思った方がいい。
統合失調症の障害の中の特徴的なものは「統合能力の障害」である。ものや行動を一つにまとめ上げることができない、融通が利かないために、読書でいえば著者の主訴を正確に読み取れない。諧謔やユーモアやギャクなどの「あそび」がない。思考過程において外部からの刺激にフィルターをかけて調整する機能が損傷しているからだ。
図書館の司書をしているカウンセラーの知人は、うつ病を病んでいる人が救いを求めてこの手の本を求めてきた場合は詩集を勧めるという。詩集は受け止め方に幅があるので、散文の語るストレートさが緩和されるからだという。
確かにうつ状態は読書量が減るが読まないわけではない。うつ病になる以前に読んでいる可能性はある。もしかすると、ひろさちや氏の仏教をベースに説く「人生論」も読まれているかもしれない。なにしろ600冊も刊行するほどの売れっ子作家である。「お浄土」の話も心に残っているかもしれない。
自殺の危険性が非常に高まっている人は衝動的に自殺することがある。また自暴自棄にもなっているので、いっそ「お浄土」に行こうと決心しないともかぎらない。そこが気になるのだ。『世逃げのすすめ』『「狂い」のすすめ』『無責任のすすめ』など、奇をてらった氏の著書の表題だけを眺めた自殺念慮者もいるかもしれないのだ。
以前に触れて感銘を受けたり、死をテーマにした小説や本、死にざまなどが「死ぬことは正しい」という思考を進めてしまうこともある。例えば多重債務に苦しむ自殺念慮者が、自分が自殺すれば保険金で家族が救われると思うように死に理由づけをする心理である。
殉教のヒロイズムも死ぬことが正しいという思い込みである。
またうつ病の人は自分を責め,ダメな自分ばかりを意識し、自信がなく、よけい将来に不安を抱く。何をやってもうまくいかない未来像しか見えてこない。悪いのは自分である。この思考が死を惹きつけるのだ。キリスト教の原罪意識や親鸞の「業」の思想はこの精神構造から生まれる。(この問題は◆カウンセリングから見た他力と自力において後述する)
このように氏の納得しやすい平易な「生き方論」や、情緒に訴えるその文章によって、もしかすると「お浄土」に救いを求めて、東尋坊から投身した若者もいたかもしれないのだ。
私はハイド・パイパーを思い出してしまう。ハーメルンの笛吹男は、笛を吹きならして、町から子どもたちを連れ去って破滅の洞窟に閉じ込めた。子どもは昔からチンドン屋について行く。愉しいリズムに乗せられて・・・氏は、自分は「お浄土」にいけると思うとワクワクするというが、行った経験もないそのような信仰の言葉に釣られてついて行っても、ハーメルンの笛吹男は日本のチンドン屋のおじさんではない。その正体は異国のマグス(魔法使い)なのである。
◆老人ハイド・パイパー
もちろん作品というものの受け止め方は読者の自由であり、作者がその結果にいちいち責任を負うものではない。文学作品は特にそうである。一流の文学作品は人間の深淵を覗かせ、読者を崖っ淵まで連れて行ってそこで放り出すところがある。その先には多分宗教があるのだろうが、その場に置き去りにする。それが文学の魅力であり毒であり価値である。文学に限らず芸術作品に責任を問うならば名作は生まれない。
だが氏のこの本は創作作品でも芸術でもない。年配の学識経験が直接実人生の指針を説く「人生論」である。であれば影響を受けた読者に対して一切の責任がないと言い切れるだろうか。
上記の意味から、「お浄土」を勝手に空想する氏の個人的な思いから「終活」をやめよというのは言語道断である。老後を迎えんとする人たちの人生設計を狂わせる恐れがあるからだ。
もともと「終活」という言葉は、平成21年に『週刊朝日』が言い出したもので、当初は文字通り「人生の終わりに向けての事前準備」を意味していたが現在は違う。「人生の終わりに向けての事前準備をしつつ、残りの人生を自分らしく生き、自分らしくエンディングを迎えるための活動」を意味するようになっている。要するに残りの人生を悔いのないように生きるための活動のことである。
私は生老病死のうち、「老」「病」「死」は人生の危機管理(リスク・マネジメント)であると述べた。老化は思っているより早く進行する。筋肉は減少し、足腰は弱り、四肢の身体機能は衰え、気力、暗記力など、脳機能も衰える。目も耳も悪くなる。呑気にしていると老後の人生設計全てが手遅れになるのだ。
例えば、一軒家に住む高齢者が雪下ろしで落下したり、溝に落ちて死んだりする。元気なころは町まで車でひとっ走りの地域でも、いずれそれもできなくなる。買い物、病院は遠くなる一方だ。かといって今更家の中の物を整理して町のアパートやマンションに引っ越す体力も気力もない。何とか移っても、環境が急変すると、それを切っ掛けに認知症になるケースも多く報告されている。不便でも長くその土地に住むほどにその環境に馴染んでしまって、新たな環境に適応できなくなる。
気力・体力のあるうちなら便利な町に転居もできよう。古い家なら価値ある家具や置物などもたくさんあるだろう。欲しがる人がいれば譲ってあげて物を活かせばいい。ガレージセールで売ることもできる。これらも早めの断捨離だ。放っておけば最後はただのガラクタになるしかない。「終活セミナー」の事前準備ではそういう具体的なノウハウも教えるはずだ。
ちょっと私的なことをさしはさむと、私は60歳過ぎてから事情があって沖縄に移転したが、これを「終活」の第1回目の節目にして、家具その他は4分の1に断捨離した。狭いマンションには収容もできず、暮らしにも必要がない。幸い自宅を買ってくれる人が家具調度品全て気に入ってくれたので、そのまま譲ってあげた。お蔭で廃棄処分する手間も省け、物も活かせたし気分もすっきりした。
元の自宅は団地の戸建で芝生の庭園を広くとっていた。周囲には貝塚伊吹や百日紅、木蓮、椿、むくげ、桜、ヤマモモなどの背の伸びるものから、花壇の周りにはミヤマキリシマ、芙蓉に牡丹など花木など植えて楽しんだ。そのために庭の手入れには休日一日かかった。芝刈りも、脚立に上って剪定バサミを使うのも、パーゴラの藤蔓を屋根に上って切るのも、体力の衰えから二日、三日と延びてきたので無理をすることはやめた。高齢になって自宅を管理する大変さは予想できたのでそんな暮らしはやめた。あのまま住んでいればいずれ庭は荒れ放題になってしまうだろう。
また郊外の団地は自然が多く若い頃は快適だったが、大雪の日には車で30分の大型スーパーまでの買い出しも億劫になってきた。私が去る頃、団地は高齢化が進んでおり、いずれ過疎化と限界集落化は目に見えた。移転後の今は、スーパーまで徒歩で5~6分である。この範囲にデパートもスーパーも総合病院もコンビニも銀行も郵便局もシネマもカラオケもレストランも何でもある。現在のマンション暮らしは自宅の管理も管理会社が全部やってくれるので実に楽である。
もう使わない子供部屋のモノ、家の中の山のようなモノたち、仕事や人間関係、すべてにおいて膨れ上がった現役生活は、夫婦二人になれは少しずつ整理しなければならない。老人ホームに入るころはさらに断捨離を余儀なくされるし、最期は棺のスペースだけである。だから愛着のあるモノとの愛別離苦に慣れるためにも老後の生活は節目、節目でコンパクトにしたほうがいい。そして住居環境も年寄にはコンパクト・シティが便利なのである。
以前は自然豊かな雪深い郊外に住む田舎者だったが、今はシティボーイ、いやシティジジイである。車の運転ができない妻が一人になっても暮らしていける町で安心である。また高齢者が過疎地に分散しているよりも、都市部に集中している方がいい。在宅介護ヘルパーの移動の軽減など効率性からしても、介護労力にも寄与できるのではないかという問題意識もあった。
団塊世代がどっと退職を迎えたころ、都会を離れて緑豊かな自然の中での「田舎暮らし」が流行った。老後は家庭菜園でもやりながらの悠々自適の生活を勧める不動産業者も続出した。ほとんどの場合、日常生活の目線で考える奥さんは移住に反対する。それでも夫の夢に我慢をしてついて行ってもたいてい3年と続かない。買い物や病院など、生活が不便だからである。それで結局、元の自宅の売却費や退職金をはたいて新築した家や、改築して買った古い農家を棄ててまた町に戻る。「田舎暮らし」はいいことばかりとはかぎらない。
青い海を眺めて暮らす沖縄の「離島暮らし」も流行した。これもほとんどが続かない。沖縄県庁の職員が話してくれたが、パンフレットの甘い言葉に誘われて退職後の高齢者が離島に居を構えても、数年で本島に引っ越してくるという。離島には大きな病院がないし買い物にも不便なのだ。長年都会で頑張ってきた企業戦士が田舎暮らしに憧れる気持ちはわかるが、自分が老いてくるということを計算に入れないで、おそらくバカンス気分でシニアライフを考えていたのではないだろうか。老いは確実に忍び寄ってくる。
また都会人は島民とトラブルを起こすことが多いそうだ。文化も風習も違うところで自分たちの生活習慣(価値観)を通そうとするからだ。都会人の移住は離島では無条件に歓迎されているとはいえない。朝日新聞が北朝鮮を地上の楽園だといえばそれを信じ、毛沢東語録を称賛すればそうかと心酔したような幻想世代は、現地調査もせずに勝手に彼の地に憧れていただけである。それと同じく宣伝に踊らされて勝手に夢を描いて田舎に移住し、虎の子の老後の資金を失ったシルバー世代は少なくない。そのような世代に向けて、氏は巷の「終活セミナー」を無駄であるというが、この考えは再び幻想世代を失敗に導くことになるだろう。
私は氏の本を読むまで、実は巷に「終活セミナー」があることも知らなかったし出席したこともないが、おそらく有効なセミナーもあるだろうと思う。そこでは法律家や福祉・医療関係者や、ファイナンシャルプランナーなどの専門家が講義するだろう。もしかすると警察関係者などの講義もあるかもしれない。
成年後見人制度のしくみや利用方法を学んだり、福祉や医療の情報を入れたりとセミナーの中には役に立つものもあると思う。財産管理のノウハウも学ぶだろう。振り込め詐欺の手口は年々巧妙化し、いくら用心していても多くの高齢者が被害に遭う事件は後を絶たない。
また独居老人を狙って若いセールスウーマンも近づいてくるだろう。油断するとわずかな年金さえ吸い上げられる。独り身の寂しさから結婚詐欺に引っかかる場合がないともいえない。最近も財産目的で60代から70代の独身男性を次々に騙して殺害する事件があった。高齢者の孤独からくる心の隙への対策も必要である。セミナーではそういう情報も入るだろう。
財テク目的の投資など、ウマイ儲け話にのせられて、コツコツ蓄えた貯蓄を一瞬にして喪失する事件も少なくない。みんな自分だけは大丈夫と思っているにもかかわらず騙されるのだ。老境に入れば思考力が衰えていることを自覚しておかなければならない。また健康管理についての具体的な話もあるだろう。いずれにせよセミナーは「老後の現実」にもとづいた話であろうから、「老後の幻想」を避ける役には立つだろう。これらの準備を含めて「終活」というのである。だから私は氏のように一概にセミナーを無駄だという気はない。
別段「終活セミナー」に出かけなくても、ふだんから世間の様子や自分の老後を考えておけば、大部分は自分で解決できることである。しかし日頃から問題意識をもって手がけなければできないことである。知力・体力が衰えてから急に始めても手遅れになるのだ。
それに対して氏は老後の問題は人生を「明らめる」ことだという。この意味はギブアップではなく、仏教でいう「真理を明らかにする」という意味だ。氏は「終活」問題を明らかにした結果、このようにいう。
自分のなかで明らかになれば、何をしようが、うまくいくときはいくし、うまくいかないときはいっかない、ということがわかるはずです。どれほど綿密かつ入念に終活をしようが、思惑が外れて、とんでもない事態になることもあれば、終活なんてことには無頓着なまま逝った後、家族はすこぶるうまくやっていることもあるのです。もちろん、その逆もあるわけですが、もたらされる結果は終活をするかしないか、ということには何らかかわりがありません。
つまり、老後の生活設計は「なるようになる」から放っておきなさいといっているのである。
とすれば、労力や時間を使って終活に取り組むのは、ただただ、無駄骨を折っているだけということになりませんか?振ってみなければわからないサイコロの目について、「どうやったら"一"の目が出るのか?う~ん、これはよくよく考えなければいかんぞ」とやっているのと少しも変わりません。アホらしい労力と時間の浪費です。みなさんが、真っ先に「明らめる」べきはそのことでしょう。「気まぐれな理想主義程の迷惑なし」(p.33-34)
私のやっていることはアホらしい労力と時間の浪費らしい。確かに人生は想定外の事態が起り得る。だからといって「なるようになる」というのは人に勧める話ではない。それを仏教の教えだといえば、著名な大先生のいうことだからと真に受ける人もいるだろう。
人生を成り行き任せにしようが計画性をもたせようが、すべて「なるようになる」つまり諸行無常という真理だけで終わるならば、仏教は単なる虚無主義にしかならない。釈尊はそのような意味のない教えを説いてはいない。諸行無常のあとには諸法無我・一切皆空・涅槃寂静と続くように、真に仏法を「明らめた」生き方を説かれている。この仏の智慧を人生に当てはめれば、同じ現実も見方や生き方が変わってくる。
だから私は田舎暮らしに憧れる都会の団塊の逆をやった。ここは人口30万人の那覇市内、日常生活はすこぶる便利で住みやすい。無論先のことはわからない。しかし自分らしく生きるためには人は人事を尽くせ、「備えあれば憂いなし」という。悔いなく努力して、そして天命を待て、最期は仏の御手に委ねればいいことだ。それまでは自己の責任において命を正しく生かす。それが釈尊の自力本願の教えであると私は思っている。
この「仏の御手に委ねる」という大安心(あんじん)を、氏は阿弥陀仏の懐に飛び込んでいくという浄土宗の表現をする。そしてほかの宗派でも、宗教でもそれは変わらないとして、密教系なら大日如来の胸だというが(p.139)、これも基本的に間違っている。
密教が仏の御手にゆだねるという場合、委ねるのは法身という万物を生み出し、生かし、包み込む宇宙他力(大日如来)を意味する。宇宙の「他力」によって生み出された万物の命は、個を活かすための「生」の欲求が肯定される。人間においては、その欲求を高めて他者との関係性において互いに生かし合える「大いなる欲望」に昇華せよという教えである。そこに自力がある。
一方欲望を「肉の欲望=業」だと、自力ではどうにもならぬと否定して、はなから自力を放棄した念仏他力とは「他力」の次元と意味が異なる。つまり飛び込んでいく先が違うのである。密教は基本的に人間(仏性)を信じる。浄土真宗は人間よりも阿弥陀仏を信じる。だから自力否定であるが、密教はあくまでも自力肯定である。密教における阿弥陀如来は絶対唯一ではない。大日如来(宇宙の真理)の徳の一つ(妙観察智)を司る如来の中の一仏なのである。宇宙他力を背景に持つ密教の阿弥陀如来は他力といえども個人の自力を否定するものではない。
氏のいう他力論は浄土教も密教もごっちゃ混ぜにしているように、他力というもについて極めて大雑把である。だから氏の勧めるお浄土任せが「後は野となれ山となれ」とも受け取られるのである。
死者はみんなお浄土に行っている。阿弥陀仏のもとにいるのだから、いつまでも霊魂の問題にかかずらって煩わしいことをする必要はないという。氏は、「終活」を死後の一点に絞ってこのようにいう。
せめて、この本を読んでいるみなさんは、正しい知識を持ち、正しく行動してください。世間でいわれている終活にそっぽを向き、笑い飛ばして、余計なことは「考えず」「せず」に、おおらかにお浄土に行きましょうよ。(p.152)
氏の『終活なんておやめなさい』を読んで、ある読者が言った。「老後の準備は何もしなくていいのだ、すっかり気が楽になった。もう終活なんてやめた」と喜んでいた。こうやって、高齢者をなんら保障のない幻想の老後に導いていくのなら、氏は「老人ハイド・パイパー」といわれてもしかたないだろう。
◆カウンセリングから見た他力と自力
ひろさちや氏の主張の一つは、世間体に縛られないで「ありのままの素直な自分を出しなさい」ということであろう。カウンセリングも、クライアント(不安を抱える人・悩める人)の「ありのままに」の思いを受け入れるところから開始される。
一般にうつ病になりやすい人は真面目で責任感が強く仕事においても頑張り屋が多い。なんとか自力で達成「しなければならぬ」と考えがちである。そのために困った時「たすけて」といえない人が多い。能力主義や自己責任が問われる現代は特にそうである。それで何かの要因で落ち込んだとき孤立無援となり、うつ病という精神疾患になることがある。
だが失敗や挫折は誰にもあることで、それが即ち落伍者や弱者というわけではない。だから辛い時は泣きわめいてもいいのだ。助けを借りて立ち直ればいいのだ。人間を大切にするなら行政も企業もそう考えるべきである。人は支え合っているから「人間」なのである。人間は一人で生きることはできないように、多くの人のお蔭で生きていることに思い至れば、助けること、助けてもらうこと(他力)は当たり前なのである。
しかし実生活において全てを他力にすがるならうつ病は治らない。自分で出来ることは自分でやろうとする健全な自力が回復したときに治るのだ。ところが自信を失っているクライアントは自分をダメ人間だと責める。多く見られる特徴にこの無力感と自責の念がある。キリスト教の原罪意識や親鸞の「業」の精神構造にも見られる自己否定である。これが精神の縛りになる。
念仏他力は自力を否定して阿弥陀仏を信じ、阿弥陀にすがってお任せする。これは自力を疑って精神の自由を放棄しようという意味では、中世のキリスト教がそうだったように、神への隷属である。だからニーチェは神を殺し、神のくびき(不自由)から人間を解放しようとした。
仏教は自力による精神の自由を説くものだが、氏の説く浄土他力にはその部分が見えてこないのである。ただ早々と阿弥陀様に一任すれば人生何とかなるというのは、一見解放的で弱者の側に立っているようにも聞こえるが、人間の放埓と無責任な他力に思えてならない。氏の言葉のニュアンスには親鸞のような苛烈な自己凝視の跡さえ伺われないのだ。
カウンセラーの仕事とは、いわば溺れかかっている人に救いの手を差し伸べるのに似ている。浮いたり沈んだりアップアップしながら、放置しておけば最終的に海の底に沈んでしまう人を、取りあえず息のできる海面にまで引き上げるような仕事である。
ただ溺者救助とカウンセリングには本質的な違いがある。それがまさに「他力と自力」なのである。溺者救助は安全エリアまで救助者が運ぶ。つまり溺者は救助者にオールおまかせである。いや力を抜いてまかせてくれた方がむしろ救助は楽である。つまり溺者にとって「絶対他力」こがそが究極の救助なのである。
死の恐怖に直面している溺者は必至で何かにすがろうとする。経験のある人は実感したことであろうが、一度しがみつかれたら救助者もろとも海の底に引きずり込むぐらいの凄まじい力である。いわゆる火事場の馬鹿力だ。だから溺者救助には技術が必要である。それに似てカウンセリングにも技術が必要である。例えば救助者は不用意に溺者に近づいてはならないように、カウンセリングにはクライアントを受容しつつも一定の距離が必要である。
しかし技術が未熟だと、クライアントを過剰に依存させてしまう場合がある。そしてカウンセラーへの依存心からくる、ある種の支配と服従関係が生まれることがある。カルトの宗教の信者と教祖の関係を考えればわかりやすいだろう。これはカウンセリングとしては完全に失敗である。仏教的にいえばカウンセリングという「他力」によってクライアントの「自力」(自立と自由)を奪ったことになる。
現在日本で主流になっているロジャーズのクライアント中心のカウンセリングは、クライアントの内にある自己実現傾向(生きる力)をクライアント自身が発揮できるように援助することである。クライアントに生きるエネルギーの回復支援をするのがカウンセラーである。
溺者救助に例えれば、カウンセラーは溺者を最後まで救助はしない。安全エリアに辿り着くのはあくまでもクライアント自身の力でなければならないからだ。人間はもともと浮くようにできているように、本来人間に備わっている「生きる力」を引き出すサポートをするだけである。浮身のコツを思い出させて、溺者自身の力で岸に辿り着かせるといえばわかりやすいかもしれない。これがクライアント中心のカウンセリングで、カール・ロジャーズの唱える「来談者中心療法(Client-Centered Therapy)」である。
いずれにせよ問題を解決するのはクライアント自身であって、カウンセラーが問題を解決するわけではない。自分の脚で歩けるようになればうつ病は治っている。カウンセリングも仏教的にいえば「自力本願」に近い考え方なのである。
密教には「業」や原罪意識はない。密教は人間だけでなくすべての存在を肯定する。犬はワンと吠えることによって、猫はニャーと鳴かせることによって「ありのまま」の存在を認めてその命を賛美する。猫はワンと吠えることができない自分を責めるとも悲しむこともなく、犬はありのままにワンと吠えてノイローゼにもならずに自力で生きているのだ。本来人間も同じように、ありのままで宇宙他力(大日如来)によって「生きる力」を与えられている。この「存在の秘密」を法身(大日如来)が常に説法していることを悟るのが密教である。
大日如来の説法とは、万物は如来の大いなる「他力」によってもともと「救われている」という慈悲のことに他ならない。密教の「他力」は大日如来の懐に抱かれた命をそのまま肯定されているという安心の中で、ときに様々な助けを受けつつも、自力で問題を解決しつつ「生」を全うし、そして再び大日如来の元に還る。日本真言密教の租空海はこのことを次のように読んだこともある。
阿字の子が、阿字のふる里たち出でて、また立ち還る阿字のふる里
(阿字とは宇宙そのもの。万有の根源)
つまり我々人間には阿字のふる里という「ホームグランド」あり、そこから現世に躍り出て、力いっぱい生き抜いてまた母なる大日如来の待つふる里に還るのである。言い換えると、自己の出自がしっかりしているという感覚である。これが密教の「他力」で、仏の他力に保証されているのだから、思う存分自力を発揮せよという世界である。
浄土他力は根本的に人間(自力)を無力とし否定する。故に親鸞は自らを悪人とした。自己の出生にホームグランドを感じることができないいわば家なき子である。だから自己確認を求めてひたすら阿弥陀の胸、極楽浄土を求める。
カウンセリングにおいて仏教の他力と自力を重ねるなら、「来談者中心療法(Client-Centered Therapy)」は、浄土他力よりも、自力本願の真言密教に近いといえるだろう。
◆私たちの「終活」
ちなみに私の考える「真の終活」を少し理屈っぽくいえば「発達による行動変化」という概念である。心理学では、受精に始まり死に終わる一連の人間の行動変化のプロセスを発達という。発達心理学では、乳幼児心理学、児童心理学、青年心理学,成人心理学、老年心理学のように、ライフ・ステージに分けて取り扱う(発達段階)。
現在の「キャリア形成」の概念は、職業のスキル・アップ(職業的自己実現)だけではなく、人生をトータルで考える。つまり人生活動すべての場において、その人らしく生きる幸福実現のことなのである。キャリア・コンサルティング的にいえば、「終活」は老年期における「キャリア形成」という能動的な意味になる。
氏の6章 真の終活とは何か(p.153-160)には、「現役時代にはできないことがある」といいながら具体的な内容は全く書かれていない。「役割分担」とか、「自分の生き方を見直す」などという抽象論だけがあって、中身のない虚仮威しであった。「真の終活とは何か」と大そうな看板を掲げて人目を惹きつけただけである。それもそのはず、氏は「終活なんておやめなさい」の人、中身があるわけがない。
人は晩年、ピンピンコロリで死ねなければ、大多数の高齢者は最終的に若い世代の厄介にならざるを得ない。リハビリ、通院の付き添い、掃除、洗濯、食事、入浴、用便の介助、おむつの交換などなど・・・。申し訳ないことを頼まなければならないのだ。ホームに入っても介護料金の支払いだけで済む話ではない。
私は氏のように、金を支払ったのだからちゃんとやれよ、というには忸怩たる思いに駆られる。世話になりっぱなしで終わっても、食い逃げでも、あの世にまで悪口は聞こえないとタカをくくれないのである。だから生きているうちに「お世話になるお礼の先払い」をしておきたい。そこから「現役時代にはできないことがある」という本気の思考が始まるのである。
私は「終活」を「老年キャリア形成」だと考え、生きているうちに「お世話のお礼の先払い」をすることにした。別に老人になったからといって、社会から加齢請求書がくるわけではないが、私の老年キャリア活動は「社会への先払い」である。
それでいろいろ考えた結果、次世代の人たちの「心の相談」を担当することにして「産業カウンセラー」と「キャリア・コンサルタント」の資格を取得した。これは単なる年寄りの人生相談ではない。専門的な知識や技術を習得したのは60代半ばである。
うちのばあさん(妻)も「老年キャリア形成」に参加して、心理学やカウンセリング理論を学んだ。古典的なフロイトやクレッチマーから現代のロジャーズに至る日米欧の70人余りの心理学者の学説や手法など、まだまだ未熟だが実技やスキルも身につけた。また、産業・組織の心理学、労働経済や労働関係法規などを勉強してキャリア・コンサルタントの資格まで取得した。物覚えが悪くなった身に専門知識の資格受験はこたえたし、いい歳をして今更こんな認定資格を取ってと周囲からは不思議がられたが・・・。
悩みのごとの解決なら、ひろさちや氏も仏教的視点から執筆や講演活動でやっているのかもしれない。問題にしたこの著書も、高齢者の心の不安を軽くしようと思っていることは理解できる。しかし本は売れなければ出版社は儲からない。そのせいか氏も妙に読者受けを狙っているきらいがある。だから「終活」ブームに湧くご時世に、タイムリーに「終活なんておやめなさい」と意表を突くのであろう。印税や講演料が入る営利活動であればそうせざるを得ないとすれば、仏の尺度を語っているようでも、結局世間の尺度(売上)からものをいっているのである。仏教を売り物にしているとまではいわないが、何か偽善的なスッキリしないものを感じる。
私たちは基本的にカウンセリング料やコンサルティング料はとらない。それは私たちが料金を支払う余裕のない人を対象とすることが多いからだ。無料奉仕がいいのである。営利活動を離れた年金暮らしだからこそできることである。
それで2人は現役世代の「悩みの相談・心のお世話」をやっている。それが自分にとって、せめてもの「仏道」だとばあさんは信じている。心を病んでしまった人は、キサゴータミーの「枯れかかった苗木」に似て、誰かのサポートを必要としているのだ。少しでもお役に立てれば望外の幸せである。
これが私たちの「老年キャリア活動」であり「終活」なのである。共に暮らして共に老い、晴れて人生を卒業するために、釈尊によって気づかされた自己完結だと思っている。
◆葬式仏教と寺院と僧侶
『終活なんておやめなさい』の反論には、「終活問題」と「葬式仏教」という二つのテーマを引き受けて論じねばならず、心ならずも長文になってしまった。
最後に「葬式仏教」であるが、私は、「葬式仏教」は今や日本仏教の核心といってもよいと思う。寺院は社会的財産であり資源である。寺が変われば社会が変わるとまでいい切る人もいる。この意味するものは何か、僧侶は今一度自己を検証して、確信をもって取り組んでもらいたい。現代、確かに一般の人にとってお寺は気軽に出入りできる雰囲気にはなく、僧侶は人々の日常生活に溶け込んだ身近なものとはいいきれないだろう。また葬儀一つとっても、一流の葬儀社は電話を受けた瞬間から遺族の心のケアが始まるという。体調を崩す遺族のために病院との連携までしているという。僧侶はどうか。
80年代、アメリカでは宗教離れがおこった。教会に人が来なくなったのだ。神父や牧師はどうしたか、大学院に行って心理学を学んで教会から社会に飛び出していった。そして親を亡くした子どもたちや夫を亡くした女性たちのケアなどに乗り出したそうである。
日本人には日本人に合うやり方があるはずだ。仏教はすでに「唯識学」という優れた心理学がある。私はある意味では欧米の心理学を凌駕する部分があるとさえ思っている。例えば心理療法のうち、論理療法(Rational Emotive Behavior Therapy・REBT)や認知行動療法(Cognitive Behavioral Therapy・CBT)などには大いに応用できるのである。メンタル・ケア一つとってもそうであるように、仏教は他にも限りない可能を秘めたものがあると私は思っている。コミュニティーの中心として檀家寺を考えれば、僧侶は各方面で日本を元気にできるはずである。
戦後は個人主義と経済至上主義の風潮から、物的欲望と個人的利便性を追及するあまりに社会の人間関係が希薄になった。それに伴い、人々の心が孤立し疎外分断されていくなかで、もうひとつ孤立化してきたのが「生老病死」ではないかと思う。言い換えれば、生、老、病、死が個別バラバラになってしまったのだ。
私の目に映る現代人は「老につながらない生、病を忘れた老、死を含まない生」即ち、老、病、死を忘れた浮薄な「いのち」を生きようとしているように映る。もてはやされるアンチエイジングや生涯現役などもそうだ。現代の都市化と消費社会は「生」ばかりを謳歌する明るく楽しい世を現じたが、享楽的で刹那的であり、実は心の深いところでは不安を抱える孤独な群集社会に映る。勝ち組だの負け組だのといい、一歩レールを踏み外せば脆くも心が壊れ、だれもがうつ病と隣り合わせである。
このような現代社会において、日本の伝統仏教はどうあるべきか。寺はどうあるべきか。「葬式仏教」は将来どのように展開すべきか、ひろさちや氏に投げられたボールを打ち返すのは、やはりこちら側の責任ではなかろうか。