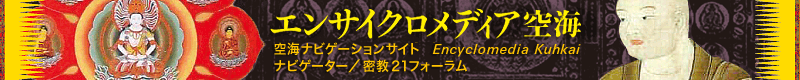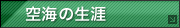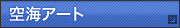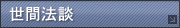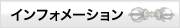井筒俊彦(いづつ としひこ、1914-1993)は、文学博士、言語学者、イスラーム学者、東洋思想研究者。慶應義塾大学名誉教授。エラノス会議メンバー。アラビア語を通じてイスラーム思想に接し、1958年に日本で最初の『コーラン』の原典訳を完成させた。
その他にも、ギリシャ思想、ギリシャ神秘主義と言語学の研究の取り組み、ギリシャ、アラビア、ヘブライ、ロシアなどの多くの言語を習得・研究し、晩年には仏教哲学、老荘思想、朱子学などの分野にまで研究を広め、独自の東洋哲学の構築を試みた。
上記経歴の内、井筒がメンバーとなっていたエラノス(注1)会議とは、宗教学、神話学、深層心理学、神秘主義などをめぐり、東西の研究者が参集して開いた学際的会議の名称である。
1933年にオランダ系イギリス人女性、オルガ・フレーべ・カプタインによって設立され、それ以来、スイスのアスコナ近くのマッジョーレ湖岸にある彼女の屋敷で毎年会議が開かれた。60年以上にわたって、このイベントはつづけられ、世界各国の思想家たちが集い、人間の精神に関するさまざまな事柄を学習・討議する場として貢献した。
エラノスでは、"精神の起源"の問題に関心があったため、会議の初回テーマは『東と西のヨガと瞑想』であったという。
井筒は1967年以来、12回の講義をエラノス会議で行ない、15年間にわたって主体的に参加し、後半は中心的存在としての役わりを果たした。
(注1)「エノラス」という呼称は古典ギリシャ語の「晩餐会」に由来し、幾人かの客たちが自前で食べ物を持ってきて、互いにわかち合い、食卓を囲んで談笑しあう会食を意味する。
そのエラノス会議に寄稿された論文は会報として世界各国に情報発信され、日本では『エラノス叢書』として1990年から平凡社によって順次刊行された。その発刊に際して、井筒は次のようなことばを叢書に寄せているー
「真昼時、地上の万物がそれぞれの輪郭線を露出しつつキラビヤカに浮かびあがる光りの世界に、どこからともなく夕闇に翳りがしのび寄ってくる。事物は相互の明確な差別を失い、浮動的・流動的となって、各自本来の固定性を喪失し、互いに滲透し合い混淆し合って次第に原初の渾沌(コントン)に戻ろうとする」と。
つまり、エラノス会議の重要なる関心事であった"精神の起源"というテーマに対して、その起源となる精神的存在が、暗黒の手前の仄暗い"コントン"の中にあるのではないかという彼なりの見解を提言した。
では、原初の"コントン"とは何か、その理念を寓話にして説いたのが古代中国の思想家、荘子(そうし、紀元前3,4世紀)である。
『荘子(そうじ)』33篇の第7「応帝王(おうていおう)」篇に"コントン"のことが、以下のように記されているー
「南海の(とある地方に、万象のイメージを分別してコトバ《声・文字》にし、そのコトバによってお互いの意思を伝達しあって、つかの間の人生を生きる民がいた。この民は、絶えず目新しいコトバの組み合わせを考え出しては、コトバによる世界を更新しつづけなければならなかった。この民の)王の名をシュク(儵)という。
北海の(とある地方に、世界を感情によってとらえ、その瞬間の喜怒哀楽にしたがってつかの間の人生を生きる民がいた。この民は、感情の発露となるもの《音楽・踊り・悲喜劇など》を絶えず創作して、その中に浸りつづけなければならなかった。この民の)王の名をコツ(忽)という。
(その南と北の地方の)中央の(位置に、コトバにも感情にもとらわれずに自然のあるがままに生きる民がいた。この民は、南海や北海の民のように余計なものを作り出すことがなかったから、余計なことに悩まされることもなかった。この民の)王の名をコントン(渾沌)という。
(南海の王の)シュクと(北海の王の)コツとは、ときどき(中央の王の)コントンの土地で出あったが、(目も口もなく、もやもやしていてすべてが分別されることもなく、全体が一つにまとまり、まるく溶け合っているような存在であった)コントンはとても手厚く彼らをもてなした。
シュクとコツとはそのコントンの恩に報いようと相談し、人間には誰にも(目の穴が二つ、耳の穴が二つ、鼻の穴が二つ、口の穴が一つの)七つの穴があって、その穴で、見たり、聞いたり、食べたり、息をしたりして(人生を楽しんで)いるが、コントンにはそれらがないから、その穴を試しにあけてあげようということになった。
そこで一日に一つずつ穴をあけていった(一日目には片目の穴を、二日目にはもう片方の目の穴をあけた。こうして、コントンは世界中の色・かたち・うごきを目で見なければならなくなった。三日目には片耳の穴を、四日目にはもう片方の耳の穴をあけた。こうして、コントンは世界中の音を耳で聞かなければならなくなった。五日目には片方の鼻の穴を、六日目にはもう片方の鼻の穴をあけた。こうして、コントンは息をして、世界中の臭いを鼻で嗅がなければならなくなった。そうして、とうとう七日目には口の穴があけられた。こうして、コントンは世界中の食べ物を味わうだけならまだいいが、コトバを話さなければならなくなった)。
ところが、七日目に七つの穴がそろったところで、コントンは死んでしまった。(そうさ、余計な知覚によって、脳裏には絶えずイメージが浮かび、そのイメージを分別してコトバにし、そのコトバによってコミュニケーションしたり、そのイメージのもたらす喜怒哀楽によって絶えず感情に左右されながら生きて行くなんて、コントンには耐えられないことであったのだ)」
というような寓話である。
当然ながら井筒はこの寓話の主題である"コントン"を知っていた。そうして、エラノス会議のテーマ"精神の起源"を、そこに見つけた。
その上で、井筒の提言は次のようにつづけられているー
「存在は根源的に現象的なものだ。根源的現象性の見地から見るとき、われわれは普通、何の疑念もなしに"現実"のすべてだと信じこんでいるものが、実はリアリティのすべてではなく、それのほんの表層にすぎないことをさとる。存在の表層は深層の可視的形姿にすぎない。すべての現象は"現象以前"から現象して来る。人は自らその"現象以前"に参入して、一切そこからとらえなおさなければならない」と。
人は自らその"現象以前"に参入して、つまり"コントン"に参入して、一切そこからとらえなおさなければならないとしたのだ。
井筒にとってのエラノス会議とはその"コントン"の理念を模索するための場であった。だから、主体的に会議をリードし、日本においては『エラノス叢書』の刊行に尽力し、その発刊に際し、井筒なりの"精神の起源"への見解を示すことになった。
さて、その"精神の起源"、つまり"現象以前"の"存在の本質"である"コントン"を余計な知覚によってではなく、瞑想と洞察によってとらえた人物がいる。
空海(774-835)である。
空海はその著『即身成仏義』の中で"存在の本質"、つまり"コントン"を、次のような構造をもつ世界として明解に定義しているー
(一)「六大(ろくだい)無碍(むげ)にして常に瑜伽(ゆが)なり」
万物(生命をふくむ)をかたち作っている六つの質料<地(固体)・水(液体)・火(エネルギー)・風(気体)・空(空間)・識(生命のもつ意識)>は、さえぎるものがなく、つねに相応し、とけ合っている。《万物の本体》
(二)「四種(ししゅ)曼荼(まんだ)各(おのおの)離れず」
万物の様相はイメージ・シンボル・声と文字・作用の四種によってとらえることができるが、それらによってとらえられた様相と万物とは結びついていて離れることがない。《万物の様相》
(三)「三密(さんみつ)加持(かじ)すれば速疾(そくしつ)に顕われる」
いのちのもつ無垢なる知のちからが為す三つの活動性、動作性・コミュニケーション性・精神性と、個体が日々為している活動性とが応じ合うとき、たちまちにして、そこに真実の世界が開示する。《個体の活動性》
(四)「重々(じゅうじゅう)帝網(たいもう)なるを即身と名づく」
万物の六つの質料と万物の四種の様相と個体の三つの活動性とによって、すべての生きとし生けるものが、お互いを照らしあい、共に生きていることを、この身このままの存在という。《即身》
(五)「法然(ほうねん)に薩般若(さはんにゃ)を具足して」
生きとし生けるものは、ありのままに量りしれないほどの多くのすがたを成していて、それらのすべてが万物の六つの質料と万物の四種の様相と個体の三つの活動性を具えている。《ありのままのすがた》
(六)「心数(しんじゅ)心王(しんのう)刹塵(せつじん)に過ぎたり」
いのちをもつものすべてには、対象に反応する心の作用が具わっていて、その心の作用と心の主体(いのちをもつもの)は数限りない。《心の作用と心の主体》
(七)「各(おのおの)五智(ごち)無際智に具す」
その心の作用と心の主体のそれぞれに、いのちのもつ無垢なる五つの知による根本的なちから<生命知(日の光と水と大気によって存在するちから)・生活知(呼吸と睡眠によって生存するちから)・創造知(衣食住を生産し、それらを相互扶助するちから)・学習知(世界を観察し、記憶・編集するちから)・身体知(からだをうごかすちから)>とその限りないはたらきが具わっていて、欠けることがない。《知のちからとはたらき》
(八)「円鏡力(えんきょうりき)の故に実覚智(じっかくち)なり」
それらのいのちのもつ無垢なる知のちからとはたらきによって、存在するものすべてがお互いを鏡のように明らかに照らし合って生きていると感得するとき、そこにあるがままのさとりがある。《成仏》
以上のように空海は、"コントン"をもやもやしていてすべてが分別されることのない神秘としてではなく、秩序をもった"存在の本質"として明解に定義した。そうして、それらの本質を感得することを《即身成仏(この身このままのあるがままのさとり)》と名づけた。
この空海の定義、古代の賢人たちが思索し、それぞれが提唱した世界の"本質体系"に並ぶものである。
「古代ギリシャには古代ギリシャ特有の本質体系があったし、古代中国には古代中国独特の本質体系があった。事物の永遠不易な本質"イデア"を探求することで新しい哲学運動を興したソクラテスも、同じく事物の本質"実"を求めてその上に、正名論(注2)を建てた孔子も、それぞれの文化の規定する本質体系の制約を脱することはできなかった。"本質"は彼らによって創造されるものでなく、ただ発見され、正しくとらえられるべきものであった」
と井筒はその著『意識と本質』(1982年刊)の中で論じているが、空海の定義した"存在の本質"も仏教文化一千年の変遷の中で発見されたものにちがいない。
しかし、そこにとらえられた存在は井筒のいう「それぞれの文化の規定する本質体系の制約」を遥かに超越したものであった。
(注2)名称と実質との一致を志向する思想。「名」正からざれば「言」したがわず、「言」したがわざれば「事」成らず云々。
さて、空海によって定義されたこの"存在の本質"、つまり"コントン"的存在は、コトバ以前の根源世界をとらえたものである。
その根源世界に生きる人間が、風土・歴史による地域固有の生活を育みながら、そのライフスタイルによって物事のイメージをとらえ、そこに文化の元となるさまざまな"意味"を発見した。
井筒の言語哲学によれば、その"意味"がコトバの母胎であり、コトバが意味を分節するという。
分節とは、フランスの言語学者アンドレ・マルティネ(1908-1999)によれば、「言語活動を分析してゆくと、第一段階で意味をもつ最小単位としての<形態素>が見出される。最小とは、それ以上分解すると意味をもたなくなるという段階。これを第一次分節と呼ぶ。さらに形態素を分解してゆくと、意味をもたない音(オン)が抽出される。これを第二分節と呼ぶ。この有限少数の音の単位<音素>が組み合わされて、数限りない形態素が作り出される」と定義される。
この定義に対して、井筒は仏教の唯識哲学によるとして、第二分節の音素を次のように解説している。
「言語種子(音素そのものがもともとの象徴的な意味をもつとし、その組み合わせによって、合理的に形態素が作り出されるとするもの。注3)、コトバの、コトバへの、可能体とし、言語種子はコトバとしての名を求め、名を志向し、名を得れば意味として発芽する」と。
そうして、コトバが万物の基底となり、コトバが万物を生み、コトバによって"存在の本質"が実在的に呼び出されるという。
(注3)近代言語学の父と呼ばれるソシュール(1857-1913)は、言語を形成する音声(シニフィアン)と意味(シニフィエ)の恣意性(世界にさまざまな言語があることから分かるように、音素にもともとの意味はないとする考え)を説いた。これとはほぼ反対の立場として「音象徴」という見解がある。これは、「音素そのものが、何らかの意味や感覚、印象をあらかじめもっている」というものである。この見解に近いのが言語種子である。
その言語種子によるコトバのパワーを認め、コトバを唱えることによって、あらゆる存在はコントロールできるとするのが空海の「真言」の教えである。
その「真言」を含めた言語一般を学問的に解説したのが、『声字実相義』になる。
空海による日本初の言語学書である。
その書に「言語の定義」として、以下のような詩が記されているー
(一)「五大(ごだい)にみな響(ひびき)あり」
物質<固体・液体・エネルギー・気体・空間>によって音が生じる。《物質のひびき》
(二)「十界(じっかい)に言語を具す」
音があるから、その音が言語(声)となって、さまざまに分別されている社会の中で生きとし生けるものがさまざまな声をもってコミュニケーションし合っている。(しかし、その声によって多くの嘘が社会に蔓延っている)《社会と言語》
(三)「六塵(ろくじん)ことごとく文字なり」
知覚<目・耳・鼻・口・身・意識>によってとらえたことが、ことごとく文字(声を字にし、字によって書き留めることによって、後世にすべてを伝えることができる)となっている。(その文字によって世界のもつ意味がさまざまに分節され、さまざまな社会が形成されている)《言語の意味》
(四)「法身(ほっしん)これ実相なり」
(しかし、文字によって作られた世界よりも)いのちのありのままのすがたが成す世界の中にこそ、"存在の本質"がある。(その本質の中に真のコトバがある)《言語の本質》
その"存在の本質"をもつ世界とは『即身成仏義』の説く世界であり、そこにはじめから存在しているのが真のコトバであると空海はいう。
では、その真のコトバ「真言」とは具体的にどのようなものなのか、空海は『即身成仏義』の中に、次のように記しているー
(《万物の本体》の言語種子について)
万物は、固体・液体・エネルギー・気体という物質の状態と、その物質の容器となる空間と、それらの物質と空間との存在によって誕生した生命のもつ意識の、六つの質料によってかたち作られている。
(その万物をかたち作っている六つの質料、すなわち万物の本体の意味が分節されて、以下の六つの言語種子になった)
「わたくしは万物の本体(質料)が
存在のおおもとであるから、生滅を超越した絶対なものであること<ア>、
言語表現を超越していること<バ>、
妄想分別を超越した、けがれのない本体であること<ラ>、
原因と条件とに束縛されない存在であること<カ>、
虚空のようにさまたげなく自由な存在であること<キャ>、
をさとった<ウン>」と。
また、「これらの六つの言語種子、ア・バ・ラ・カ・キャ・ウンの梵字(サンスクリット)がもつ意味の展開として、
とも記している。<ア>字は、万物の本体がもともと存在していて新たに生じたものでないことを象徴し、そのゆるぎないことが、大地の堅固さに比べられるので<固体(地)>を示す。<バ>字は、万物の本体が言語の元であることを象徴し、言語によって生じるすべての分別を洗い清めることが、水のちからに比べられるので<液体(水)>を示す。<ラ>字は、万物の本体がけがれのないことを象徴し、すべてのけがれを焼き尽くす火のちからに比べられるので<エネルギー(火)>を示す。<カ>字は、万物の本体は原因と条件を超越した存在であることを象徴し、すべてを吹き払う風のちからに比べられるので<気体(風)>を示す。<キャ>字は、万物の本体がさまたげなく自由に偏在していることを象徴し、その様が虚空のようであるので<空間(空)>を示す。<ウン>字は、わたくしはさとったという精神のはたらきであるから<意識(識)>を示す。」
このように、万物の本体の意味を分節したところに、言語種子があり、その組み合わせによって名(コトバ)が生まれ、その真のコトバ、すなわち「真言」によって世界が存在しているとするのが空海の教えである。
このことについて、井筒も高野山での特別講演「言語哲学としての真言」の中で、次のように語っているー
「人がアと発声する、まだ特定の意味は全然考えていない。しかし、自分の口から出たこのア音を聞くと同時に、そこに意識が起こり、それとともに存在性の広大無辺な可能的地平が拓けていくのであります。ア音の発声を機として、自己分節もはたらきを起こした大日如来のコトバは、アからハに至る梵語アルファベットの発散するエクリチュール(書き言葉)的なエネルギーの波に乗って、次第に自己分節を重ねていきます。そして、それとともに、シニフィエ(音声の意味、すなわち概念)に伴われたシニフィアン(音声)が数限りなく出現し、それらがあらゆる方向に拡散しつつ、至るところにひびきを呼び、名を呼び、物を生み、天地万物を生み出していきます。"五大にひびきあり"といわれるように、それは地水火風空の五大ことごとくをあげての全宇宙的言語活動であり、"六塵ことごとく文字なり"というように、いわゆる外的世界、内的世界にわれわれが認識する一切の認識対象のことごとくが、文字なのであります」と。
そうして、以下のような要旨で結んでいるー
「全存在世界をコトバの世界とし、文字と声とひびきによって世界の本質が開示し、存在するという教え、すなわち神のみが真実のコトバを発し、そのコトバによって世界が創造され、その世界の住人となった人間にもともとの神のコトバが流布していったという教えは、イスラームの文字神秘主義や、ユダヤ教のカッパーラー(6世紀の神秘思想のこと)でも説かれている。(空海も『声字実相義』の「言語論の典拠」の章で、「インドの最高神、梵天自らがコトバを創造し、一つの語の中に多くの意味を含ませた」と説いている)
このように"存在は言葉である"という命題の絶対性において、真言密教の教え、すなわち空海の言語哲学の教えは東洋思想の歴史的展開の中で、決して孤立無援の思想ではなかったのであります」と。
井筒は自らの言語哲学を通じて、国際の場に空海を連れ出した。そうして、一千年前の空海の言語哲学が、世界の思想史の中に位置づけられるものであることを、高野山の僧侶たちを前に語った。
ではもう一度、空海の言語学書である『声字実相義』を開いてみよう。
以下は書の序となる「大意」の章の現代語訳であるー
「はじめに、(当、言語学の)大意を論じる。
いのちのもつ無垢なる知のちからによって真理を説くのは、必ず文字による。
文字は、見る・聞く・嗅ぐ・味わう・触れる・考えることによって、対象をとらえたものである。
対象をとらえる行為の本質とは、いのちのもつ無垢なる知のちからによって生きる個体の三つの活動性、動作性・コミュニケーション性・精神性である。
それらの三つの活動性は絶えず平等であり、全世界に満ちていて、永遠である。
また、いのちのもつ無垢なる五つの知のちから、生命知・生活知・創造知・学習知・身体知と、それらより成る、いのちの四つのありのままのすがた、生命の存在そのものと、多様な種のすがたと、生殖による遺伝のすがたと、個々の個体のすがたは、あらゆる世界を住み場としていて、欠けることがない。
以上のような真理を感得できる者がブッダ(目覚めた人)となり、感得できずに迷う者が衆生である。衆生はおろかだから、真理を理解する方法すら分からないが、それでも、いのちのもつ無垢なる知のちからが自ら発揮されて、その帰るべき真実のところに目覚める機会は誰もがもっている。
帰るべき真実のところの根本は、すぐれた教えによる。そのすぐれた教えを興すのは、声と字による。
その声と字による真実のすぐれた教えは、いのちのもつ無垢なる知のちからによる三つの活動性によってもたらされ、そこに生きとし生けるものの存在の本質がある。
それゆえに、大日如来(いのちのもつ無垢なる知のちからの象徴)は、真実の言語を用いて存在の本質の意義を教え聞かせ、生きとし生けるものを長き眠りから目覚めさすことができるのである。
だから、仏教のさまざまな教え、あるいは仏教以外のさまざまな宗教や思想であっても、どんな教えであれ、言語によらぬものがあるだろうか、いま、わたくし空海もわたくしの師の言葉と多くの経典のみちびきよって、すぐれた教えを得ることができた。後学の者たちも声と字(言語)のことを大いに研究し、その言語によって多くを学ぶべきである。
以上で大意を終わる」
この「大意(Ⅰ言語の理念)」の次には、以下のような内容がつづいているー
Ⅱ言語の構造
(2-1)声と字と実相との関係性
(2-2)上記の梵語「複合語解釈法」による論証
(2-3)言語論の典拠
Ⅲ本論
(3-1)言語の定義
(3-2)定義の展開
第一定義「物質のひびき」
第二定義「社会と言語」
第三定義「言語の意味」
a形象の定義
b定義の展開
(b-1)物質と現象
(b-2)生命と環境
(b-3)共生の事象
(b-4)心象の本質-イメージと概念-
(第四定義「言語の本質」)
これらの全章は、「言語の意味」<心象の本質-イメージと概念->の項の次のような問答をもって結ばれている。
「問い。あるがままのものと、条件にしたがってあらわれているものは、何が生み出すものであり、何が生み出されるものなのか。
答え。万物を生み出している本体は、固体・液体・エネルギー・気体・空間の五つの質料であり、それらは黄色・白色・赤色・黒色・青色の五つの色彩をもつ。
(五つの質料と五つの色彩によって)生み出されるものは、いのちのもつ無垢なる"知のちから"と、その知のちからによって"生きるもの"と、(それらの生きものの住み場所となる)"環境"との三種である。
この三種に、限りなき形相がある。
これらの形相を文字によって表現するにあたっては、(イメージによって)あるがままにあらわれているととらえるか、(概念によって)条件にしたがってあらわれているととらえるかによって、文章が異なってくる。(その文章の異なりによって、形相は同じであっても、その存在の"意味"に違いが生じることになる)
以上、すでに、視覚による形象についての言語の意味を論じ終えた。(その他の知覚、聴覚・嗅覚・味覚・触覚によって生じる言語も、同様によく考察・研究せよ)」と。
こうしてみると、平安初期の日本には仏教思想の中においてではあるが、すでにすぐれた言語学が存在していたことになる。
その教えが真言宗によって今日に伝えられていた。
そこにイスラーム教の『コーラン』によって言語のもつ神秘性に学問的興味をもっていた井筒がアプローチし、彼の言語学の中に「真言」を取り込んだ。
イスラーム哲学によると、事物の"本質"には二種類ある。「フウィーヤ」と「マーヒーヤ」である。「フウィーヤ」は"実在"しているそのものを指し、「マーヒーヤ」はそのものが何であるかという"概念"を指す。
"実在"しているのは個体そのものであり、その多様な個体を分別し、コトバにしたものがそのものの"概念"である。
実在する個体そのもののもつ本質と、概念(コトバ)によってそのものの普遍的な存在性を示す本質とは、本質の有している二面性であると、井筒は主著となる『意識と本質』の中に記している。
空海の密教哲学においても、『即身』は「フウィーヤ」を指し、『声字』は「マーヒーヤ」を指す。
つまり、実在するありのままの身体(即身)とコトバの真実(声字)との二面性によって、空海も"存在の本質"を説いていることになる。
空海はイスラームと同じ哲学的土俵(井筒のいう「共時的構造化」)の上に立って思考していたのだ。
このように、言語学者の井筒は、空海の思想をイスラームから、ギリシャ・中国・インドの国際的な哲学の場に持ち出した。
その国際の場で説かれる空海の「真言」の思想は、人類共通の哲学的命題である「世界の本質」や「実在と概念(コトバ)」への充分なる回答を与えるものであった。
井筒俊彦のしつらえた言語哲学の国際の場に、空海がしっかりと立っていたのだ。
そこに、両者の確かな接点がある。
あとがき
今回、井筒俊彦の言語哲学を通じて、空海の『即身成仏義』を改めて読むと、そこに説かれている「この身このままのさとりの道理」が、「真言」という言語哲学の確固たる基底となるものであることに気がついた。
その言語哲学の基底となる内容とは、
「万物の本体となる構成要素(質料)の中には、あらかじめ言語種子が存在している。その言語種子が組み合わされることによって、世界の意味が開花する。その万物の本体となる構成要素(質料)によって、いのちも誕生した。
だから、万物の本体が発する言語種子と、身体(いのち)の発する言語は初めから同じものである。
そこに言語の根本がある」というような事柄である。
だが、世間には余計な言語(物の見かけから生じる語・夢想から生じる語・妄想から生じる語・空想から生じる語)が溢れている。それらの虚妄の言語と真実の言語との違いを総合的に論じたのが『声字実相義』となる。
その日本初の言語学書には、
「万物の本体となる質料<固体・液体・エネルギー・気体・空間>の奏でる音と、いのちのもつ無垢なる知<生命知・生活知・創造知・学習知・身体知>のちからと、その知のちからから成るありのままのいのちのすがたと、そのありのままのいのちのすがた、すなわち個体が発揮する活動性<動作性・コミュニケーション性・精神性>とによって発せられるのが真実の言語である」と記されている。
そのように、"この身このまま"が発する"声と字"、それが真実の言語である。
そうであるならば、そのことを説いた「密教」が成立したのは彼のインドである。つまり、梵字(サンスクリット)の中に真実の言語があることになる。
そのサンスクリットによる「真言」を唱えると、それが"この身このまま"のあるがままのさとりとなるのだ。
そこに「真言」の実践がある。