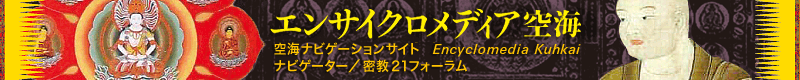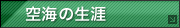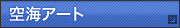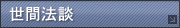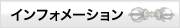第八章 「一乗」主義を問う
一、一道無為住心
大乗のレベルの三番目、「出世間心」の第五段階で、法華「一乗」の立場、すなわち天台宗の教説である。
空海は、この住心で、最澄ではなく天台智者大師智顗(ちぎ)の『摩訶止観(まかしかん)』などの教説によっている。
天台宗の起りは、中国南北朝時代、北斉出身の慧文が出て『中論』の「空・仮・中」をもとにした「一心三観」の禅定によって、大乗の「空」の実相を中国流に説いたことにはじまる。つまり天台の初源は、中観思想を教義としそれを観得する禅定を修行とした。
慧文に次いで弟子の慧思(えし、よく南岳慧思と言われる)が出て、思想的には『般若経』の「空」から『法華経』の「諸法実相」(「空」である「諸法」はそのまま真理の顕れであるとする考え方)に重点を移し、大乗の菩薩はすべからく持戒・忍辱・精進を実践し、勤めて禅定を修習して、「法華三昧」を専心勤学せよと言った。
また、『法華経』方便品の、
餘乘ノ若シクハ二若シクハ三有ルコト無シ。
をもとに、菩薩の大慈悲は「一乗」の行を具足していると言い法華「一乗」を主張した。声聞・縁覚の「二乗」や、声聞・縁覚・菩薩の「三乗」は、釈尊の説法の「方便」であり、それらは菩薩のレベルの『法華経』の「一乗」に収まるというのである。
然らば、中国の天台宗はこの慧思の弟子智顗によって大成された。
智顗は、三論宗の教理を大成した吉蔵とも親交をもっていたせいか、中観の「空・仮・中」にはことのほか思い入れがあったようで、天台の観法をまとめた『摩訶止観』は慧文の「一心三観」を踏襲した中観の「三諦」思想で裏づけられている。
一方また、慧思の法統に従って『法華経』を第一の所依とし、注釈書『法華玄義』・『法華文句』を著し、『摩訶止観』と合せて「天台三大部」とした。比叡山の最澄は、延暦二十三年(八〇四)夏、空海と同じ第十六次遣唐使船で入唐し智顗のいた天台山に上るが、智顗が没して二百年後のことだった。
「一道無為住心(いちどうむいじゅうしん)」とは、空海はこの住心の名称に付して「如実知自心」・「空性無境(くうしょうむきょう)心」と同じだとわざわざ言っている。
「一道」とは、「相対性を超えた立場」とか、「主体も客体もなくなった一つの境地」とか、「汚れに染まっていない自分の本性を観想し、人はみな清浄だと知ること」とか、いろいろな言い方があるが、これはまさしく法華「一乗」の意味であり、すなわち『法華経』の教えと、『法華経』によって瞑想修行する「法華三昧」だと見るべきであろう。
「無為」とは、アビダルマや唯識が説いた「七十五法」・「百法」のうちの「無為法」と同じく、因縁によって有為転変しない絶対の世界を言う。
二、法華「一乗」の根拠
天台宗の法華「一乗」は『法華経』至上主義による。この主張は、今もふれたように、『法華経』の教えそのものであり、それは中国天台宗の当初からあった。最澄が比叡山に建てた寺を最初「一乗止観院」と言ったのも、この法華「一乗」を観得する道場という意味である。
インドでは『般若経』系と同じ初期大乗経典に属する『法華経』だが、思想的にはただ「空」を説く『般若経』とちがい、具体的に「空」の実践、衆生済度を説きながら、「一乗」の絶対や、久遠実成の仏身としての釈迦牟尼や、末世の衆生を救う唯一絶対の経証などを説く。
『法華経』の日本伝来は早く、聖徳太子は推古十四年(六〇六)に『法華経』を講じ、推古二十三年(六一五)には「三経義疏(さんぎょうぎしょ)」の一つとして『法華経義疏』を著している。
大乗の立場から衆生済度を説き末世救済の唯一の経典だとされる『法華経』を、国家指導者たる天子あるいは摂政が民衆を救い国を守る護国の教えと受けとめたのか、『法華経』はその後空海の時代に至っても国家鎮護の経典として扱われた。
一方、『法華経』は山岳信仰の行者の間にも広がった。若き日の空海が渉猟した和泉・大和・紀伊の山や海辺には『法華経』の経巻を笈のなかに持ち、行者道や海辺の行場を往来する持経行者がいた。行場には、『法華経』の二十八品を一巻ずつ納めていく塚や宿があり、そこを巡錫してそれぞれの品を読誦するのである。金剛山系にも大峯山系にも古くはあったという。
ちなみに空海は、『法華経開題』を書き、亡くなる前年の承和元年(八三四)二月、東大寺の真言院において『法華経』と『般若心経秘鍵』を講じた。『法華経』の講釈は生涯最後の講釈にもかかわらず詳細な講釈書をつくったという。最澄が『法華経』を諸経の第一とし「法華円教」を言うのを尻目に、空海は聖徳太子以来の護国経典の伝統に従い、鎮護国家の本拠地東大寺で密教的な解釈による『法華経』を講じたのである。
『法華経』には漢訳が三種あるが、そのうち『妙法蓮華経』(鳩摩羅什訳)が日本では重用された。天台が依用したのも、それを踏襲して日蓮が依用したのも、この『妙法蓮華経』だった。
余談ながら、お題目の「南無妙法蓮華経」とは、この羅什訳の『妙法蓮華経』に帰依するという意味になる。天台や日蓮にとって『法華経』に三種類の漢訳があることは問題ではなく、この『妙法蓮華経』がすなわち唯一無二の『法華経』であった。
『妙法蓮華経』には二十八品ある。智顗は、このうち前半の十四品を「迹門(じゃくもん)」とし、後半の十四品を「本門(ほんもん)」とした。
「迹門」とは、これもいろいろな言い換えがあるが、菩提樹下でサトリを開き、そのサトリの内容を説いた歴史上の釈尊を、衆生済度のためにこの世に垂迹した(仮の姿で現れた)仏であるとし、その釈尊が衆生を「一乗」すなわち『法華経』に導く法門、と言えばいいだろうか。この釈尊を、のちの仏身説では「報身」という。
「本門」とは、その釈尊の本性は、五百億塵点劫(じんてんこう)も大昔の過去世においてすでに成仏をした「久遠実成(くおんじつじょう)」の仏(本仏)であり、その本仏が説く法門。この釈尊を、のちの仏身説では「法身」という。
『法華経』を奉ずる宗門には、この「迹門」と「本門」に優劣を見る向きもあるが、天台はそうしない。
以下、『妙法蓮華経』二十八品の概要である。
霊鷲山(りょうじゅせん、インドビハール州の中央にある山、『法華経』の説法処)の説法処に雲集した聴衆(釈尊の弟子、諸菩薩、ヒンドゥーの神々、鬼神、動物など)に『無量義経(むりょうぎきょう)」を説き終って、釈尊がしばらく三昧に入ると、天から花が降り落ち、釈尊の眉の間からまばゆい光が放射され、過去世まで照らし出される。
この光景のわけを弥勒菩薩に問われた文殊菩薩が答えて言うに、遠い昔にこれと同じ光景に遭遇し、その時日月灯明菩薩(にちがつとうみょうぼさつ)が現れて、声聞に「四諦」を、縁覚に「十二因縁」を、菩薩に「六波羅蜜」を説き、次の時代にもやはり日月灯明菩薩が現れて『無量義経』を説き、続いて『法華経』を説くのを見た、と。
三昧に入っていた釈尊が出定し(三昧から覚め)、仏のサトリの教えはとても難しく理解ができないので、ここでこれ以上話すのは止めることにすると舎利弗に言うと、舎利弗は何度か説法を願い出たが聞き入れられず、三度目でやっと聞き入れられた(「三止三請」)。
釈尊の説法をこれ以上聴いても意味がないとばかり、すでにサトリを得た弟子たち五千人が席を立ったが、釈尊は舎利弗ほか残った者に「十如是」を説き「諸法実相」を諭した。
また声聞・縁覚の「二乗」も、菩薩を加えた「三乗」も、聞き手の根機によって法を説く方便であって、仏のすべての教えはこの「一乗」すなわち『法華経』に収まることを説く。
「方便品」で『法華経』こそが尊い「一乗」の教えのあることを聞いた舎利弗が、釈尊に「一乗」とはどんなものかと聞くと、釈尊が答えて、「三車火宅(さんしゃかたく)の喩え」で「三乗」は「一乗」に収まることを説く。
釈尊の弟子大迦葉(だいかしょう)らが、「譬諭品」の理解として「長者窮子(ちょうじゃぐうじ)の喩え」を釈尊に告げると、釈尊が一切の衆生に仏性があることを説く。
大迦葉たちから「長者窮子の喩え」を聞いた釈尊は満足し、さらに「三草二木の喩え」で仏の大慈悲と「一乗」による衆生への平等利益を説く。
「三草二木の喩え」を聞いて、弟子たちの理解が深まったことを認めた釈尊が、弟子たちも仏になれることを保証(「授記」)する。
大昔、大通智勝如来(だいつうちしょうにょらい)という仏がいて、十六人の子がいたが、その十六番目の子が釈尊で、その釈尊が過去世で『法華経』を説いて教化したのが弟子たちであり未来の信者である、と。そして「化城宝処の喩え」で、宝(「一乗」)を求めて修行してもなかなか宝が見つからないので、仮の教え(化城、「二乗」)で衆生に安らぎをまず与え、その仮の教えも「幻」のように消えてしまうから、また宝を求めて努力し得ることを説く。
釈尊が、富楼那(ふるな)などの五百人の弟子に成仏の保証(「授記」)をする。「衣裏繋珠(えりけいじゅ)の喩え」で、「二乗」の段階で満足し眠りこけていた声聞が、仏の教えで「一乗」を知るに至ることを説く。
釈尊が、従兄弟の阿難(あなん)や実子の羅睺羅(らごら)をはじめ、学修中と学修済みの弟子二千人に成仏の保証(「授記」)をする。
釈尊が薬王菩薩など八万の菩薩に言う。『法華経』の教えを聞き一瞬でも有難いと思う人がいたらサトリを得ることを保証すること、『法華経』を受持し、読み、誦し、説き、書写する人(五種法師)、感謝をする人は、仏になれること、さらに『法華経』こそがすべての教えのなかで最もすぐれていると説く。
霊鷲山の上空に「宝塔」が涌き出て、そのなかにいた多宝如来が釈尊をなかに招き入れ、二人して同じ座に坐り、多宝如来が『法華経』の正しさを説く。弟子たちも釈尊の神通力で上空に引き上げられる。
大地は衆生界、「宝塔」は「仏性」、多宝如来は真理の比喩。「衆生」誰にでも本来「仏性」が具わっていて、「仏性」のなかに「諸法実相」の真理が宿っているという。
提婆達多は、釈尊の従兄弟で阿難の兄といわれる立場ながら、一度釈尊の弟子になったものの、「五事の戒律」の提案を釈尊に申し出たところそれを拒まれたため釈尊を殺そうとまで憎んだ悪人。
その提婆達多にも、未来無量劫ののちに「天王如来」という未来仏になる保証が与えられる。この悪人成仏説は、鎌倉仏教の親鸞や日蓮に少なからず影響を与えたという。
さらに、文殊菩薩に導かれた龍女がサトリを得たのを舎利弗が疑うと、龍女は男性に変身して成仏する。衆生の平等利益を説く『法華経』の女人成仏説である。
龍女も成仏可能なのを知り、薬王菩薩や大楽説(だいぎょうせつ)菩薩など、先に授記された八千人の弟子たちが、釈尊入滅後も『法華経』を護持し、衆生救済のために「不惜身命(ふしゃくしんみょう)」を心がけて広めることを説く。
次いで釈尊は、叔母と妻に成仏の保証を与え、『法華経』は正しいがために誹謗中傷に遭うが、その困難に耐えることを説く。
文殊菩薩が、末世にどうやって『法華経』を護持し、広めたらいいかを釈尊にたずねると、身の処し方(「身安楽行」)と、コトバの使い方(「口安楽行」)と、心の調え方(「意安楽行」)と、『法華経』で人々を安楽にする誓い(「誓願安楽行」)の四つを説く。
また「髻中明珠(けいちゅうみょうしゅ)の喩え」で、『法華経』が他の経典よりもすぐれていることを説く。
他の国土から釈尊のもとに来ていた菩薩たちが、釈尊が入滅したあと、娑婆世間にとどまって『法華経』の教えを広めたいと申し出ると、釈尊はそれを断って、すでにこの娑婆世間には無数の菩薩たちがいて、『法華経』を護持し広める覚悟でいると言う。
その話が終るや否や、大地が振動し地割れを起し、そこから無数の菩薩たちが涌いて出た。その姿は三十二相などみな釈尊と同じで、釈尊が今言った無数の菩薩たちだった。そのなかの代表が、「四弘誓願(しぐぜいがん)」に相当する上行・無辺行・浄行・安立行の四菩薩。
この光景を目の当たりにした弥勒菩薩が、どうやってこの無数の菩薩たちを教化したのか、そのわけを釈尊に問う。
それに答えて釈尊は、「良医病子の喩え」で、釈尊の本性は、五百億塵点劫(じんてんこう)も昔の過去世においてすでに成仏をした「久遠実成(くおんじつじょう)」の仏であり、釈尊が入滅したこともそれは衆生教化の「方便」であり、「法身」の釈迦としていつどこでも衆生のために『法華経』を説いていて、仏の命は永遠(「仏寿無量」)であると説く。
「如来寿量品」の「仏寿無量」を信じることの功徳を述べる。「四信」と「五品(ごほん)」である。
「四信」は、釈尊在世中の功徳で、『法華経』の信仰のレベルを言う。具には、「一念信解」(一念に『法華経』を信解する)・「略解言趣」(『法華経』の言葉の趣旨を略解する)・「広為他説」(広く他のために『法華経』を説く)・「深信観成」(深く『法華経』の観の成就を信じる)。
「五品」は、釈尊が入滅したあとの功徳で、「四信」に同じく『法華経』の信仰のレベル。
具には、「随喜」(『法華経』の教えを聞いて喜ぶ)・「読誦」(『法華経』を読誦する)・「説法」(『法華経』を説く)・「兼行六度」(「六波羅蜜」を兼ねて行う)・「正行六度」(「六波羅蜜」を正しく行う)。
「五品」のうちの「随喜」の功徳を説く。「如来寿量品」の深い教えを聞いた者が、随喜してほかの人に話し、その人がまた随喜して別な人に話す、というようにして伝言し、五十番目の人が随喜を起したその功徳は、四百万億阿僧祇の世界の地獄から天上界までのすべての凡夫に欲しいものを施し、阿羅漢果を得させる功徳にも勝ると言う。
さらに、「五品」の功徳が続く。もし、『法華経』を受持し、読み、誦し、説き、書写するなら、八百の眼の功徳・千二百の耳の功徳・八百の鼻の功徳・千二百の舌の功徳・八百の身の功徳・千二百の意の功徳を受け、六根はみな清浄となる。
さらに、眼・耳・鼻・舌・身・意が、天眼・天耳などを持たなくとも壊れないことを説く。
仏が言う。仏法が衰えようとした時に、常不軽という菩薩が現れ、比丘・比丘尼・優婆塞・優婆夷など、誰にでも礼拝し、ほめたたえ、「私は深くあなた方を敬います。決して軽んじることはありません。菩薩の修行に励めば必ず仏になれる方だからです」と言い続けた。迫害を受けてもくじけず、生れ変るたびに『法華経』を広める努力したのである、と。そこまで言って釈尊は、自分がその常不軽菩薩だと明かす。
『法華経』を説くことで迫害を受けても、自分の過去の罪業をこれで消していると受けとめ嘆かないことを説く。宮沢賢治はこの常不軽菩薩を自分にダブらせていたという。
仏が十種の「神力」を現し、上行ほか地涌の菩薩たちに『法華経』を付嘱する。「神力」とは「出広長舌」・「毛孔放光」・「一時謦咳(いちじきょうがい)」・「倶共弾指(くぐたんじ)」・「六種地動」・「普見大会(ふげんだいえ)」・「空中唱声(くうちゅうしょうしょう)」・「咸皆帰命(げんかいきみょう)」・「遥散諸物(ようさんしょもつ)」・「通一仏土(つういちぶつど)」である。
「出広長舌」は、舌を出すこと。コトバがウソでないこと。
「毛孔放光」は、毛孔から光を放つこと。世間の闇を照らすこと。
「一時謦咳」は、声を出して説法すること。
「倶共弾指」は、指をはじいて鳴らすこと。了解すること。
「六種地動」は、天地のすべてのものが感動したこと。
「普見大会」は、釈尊が『法華経』を説いている法座を誰でも見ることができたこと。
「空中唱声」は、空中から諸天善神が『法華経』を説いた釈尊を供養せんと呼びかけた。
「咸皆帰命」は、その呼びかけに応じてみな釈尊に帰依した。
「遥散諸物」は、華・香・瓔珞などが美しい帳(とばり)に変化して如来の上を覆った。
「通一仏土」は、十方世界が一つの仏国土となった。
そして「如来の一切の所有の法・如来の一切の自在の神力・如来の一切の秘蔵の蔵・如来の一切の甚深の事・皆此の経に於て宣示顕説す」、すなわち、すべての仏の教法が『法華経』には含まれていると説く。
如来の神力を説き終えた仏が立ち上り、右手で菩薩たちの頭をなで、無量百千万億阿僧祇劫という長い問かかって得た得難き法を、これからはお前たちに託すと言う。
宿王華菩薩が、釈尊に薬王菩薩がどんな修行をしたかたずねると、それに答えて、遠い昔に、一切衆生憙見(いっさいしゅじょうきけん)という菩薩として『法華経』を一万二千年もの間修行し、一切の衆生を救おうと思い、教えを受けている日月浄明徳如来(にちがつじょうみょうとくにょらい)と『法華経』を供養するために自分の身体に火をつけ、自身を灯明として八十億恒河沙の広大な世界の闇を照らし、燃え尽きて一度は死んだのだがまた生れ変り、今度は両腕を燃やして供養した、と。
そして、「十二論の利益の喩え」を言い、『法華経』の実践の功徳を説く。「十二論の利益の喩え」とは、池のきれいな水を飲んで喉の渇きを潤すように、病人が医者を求めるように、河を渡るのに船が必要なように、などである。
浄光荘厳という世界にいた妙音菩薩が、釈尊が放った眉間からの光に感応し、娑婆世界にきて釈尊と『法華経』と菩薩たちを供養する。
妙音菩薩は、過去世で一万二千年もの間、妙なる音楽を奏して仏を称え、八万四千もの数の七宝の鉢をささげ仏を供養したという。その功徳により、三昧神通力と三十四身を得たと言い、その三十四身の姿になって妙音菩薩は説法教化したことを説く。
いわゆる『観音経』である。観世音菩薩が三十三身の姿になって娑婆世間に現れ、一心に観世音菩薩の名を称え、その救済力を念ずる人を救うことを説く。
薬王菩薩、勇施菩薩、毘沙門天、持国天、十羅刹女及び鬼子母神とその一族が次々と現れ、釈尊に対してそれぞれの陀羅尼(「五番神呪」)を説き、それによって『法華経』の護持者たちを妨害や迫害から守ることを誓う。
釈尊の脇侍をつとめる薬王菩薩と薬上菩薩の前生譚。遠い昔、雲雷音宿王華智仏(うんらいおんしゅくおうげちぶつ)の時代、妙荘厳という王がいて、バラモン教を信仰していたが、その王子の浄蔵と浄眼の二人は仏に帰依し「六波羅蜜」を実践していた。
ある時、雲雷音宿王華智仏が妙荘厳王のために『法華経』を説くことになり、この二人の王子は母の浄徳と相談して異教徒の父の前で奇跡を起し、『法華経』が説かれる所に誘ったところ、父は奇跡に驚き二人に従って大勢の家臣を引き連れ、母は女官らを伴って雲雷音宿王華智仏の話を聞き、大変喜んで改宗したという。
この話は、異教徒を『法華経』の信者に改宗させる話。浄蔵と浄眼は薬王菩薩と薬上菩薩であり、浄徳は光照荘厳相菩薩(こうしょうそうごんそうぼさつ)であり、妙荘厳王は華徳菩薩である。
普賢菩薩が大勢の菩薩たちを連れて東方の世界からやってきて、釈尊の入滅後、どうすれば『法華経』の功徳を得ることができるかについてたずねると、釈尊が答えて言うに、仏に守られているという確固たる信念・徳のもととなる善行・正しい教えを信ずる仲間・ひとに尽くす利他の四つである、と。
普賢は感激して、いつでも六牙(「六波羅蜜」)の白象王(清らかな実践)に乗って『法華経』の護持者を守ると応じ、そこで陀羅尼を唱える。
釈尊は満足して、普賢菩薩のように『法華経』の教えを実践することができるなど、『法華経』の護持者を守る功徳を明らかにする。
以上、『法華経』二十八品の概要である。『法華経』の絶対性・優位性、法難の予言、改宗の勧め、そこに『法華経』至上主義の根拠を見た。
三、諸法実相
今見てきた『法華経』の「方便品」第二に、「ただ仏と仏とのみ乃ちよく諸法実相を究尽せり。いわゆる諸法の如是相、如是性、如是体、如是力、如是作、如是因、如是縁、如是果、如是報、如是本末究竟等なり」とあるのが、天台宗が重視し、道元などが論じた「諸法実相(しょほうじっそう)」の典拠である。
すなわち、「諸法」の「実相」とはただ仏にしかわからない、その「実相」とは「如是相」などの「十如是」である、という。
智顗は、『法華玄義』や『摩訶止観』でこれを取り上げ、
「是の相も如なり、乃至、是の報も如なり」、
「是の如きの相、乃至、是の如きの報」、
「相も是の如し、乃至、報も是の如きなり」、
と、「十如是」を三様に読み取り、これを「空」・「仮」・「中」の「三諦」に配した(「三転読文(さんてんどくもん)」)。
余談ながら、「諸法実相」の典拠とされる羅什訳『妙法蓮華経』「方便品」第二の「ただ仏と仏とのみ乃ちよく諸法実相を究尽せり」だが、サンスクリットの原典では「諸法実相」に対応する原語がない。漢訳の際に羅什が補った可能性を指摘する説があるが、中国天台の祖師たちは羅什の訳をそのまま訳語の通り受け取っただけであろう。
「諸法」は「実相」である。
「実相」とは「真理の相」。すなわち「空」の姿である、という意味。「諸法」とは、モノと私たち「凡夫」が一瞬一瞬に感受する物理的・感情的・知的・心理的な情報のすべてである。つまり、その「諸法」にいちいち反応し執著し左右され、我執・我欲に染まっている私たちの現実が「実相」である、よく見れば「空」の真実と違わないという考え方である。
この「諸法実相」は大乗にとっては非常に重要なキーワードである。「法性」・「真如」、「生仏一如」・「煩悩即菩提」など、「無執著」・「無我」・「無自性」など否定形だった「空」が肯定形に転じるポイントの概念だからである。
『理趣経』は、愛欲は縁起生の故に「無自性」「空」であり、その故に「清浄」であり「世間」とサトリの世界の橋渡しである菩薩にとって無垢なる「大欲」だと言った。
空海は、私たちの現実が真実である「即事而真」の裏づけとして本有の「菩提心」=「仏性」を見た。「菩提心」とは「空」の真実(「実相」)が覚れる仏種のことである。「菩提心」を生れながらに持っている私たち「衆生」は、本来「実相」なのである。
四、「空・仮・中」を観想する「止観」
ときに、天台の慧文は「空」・「仮」・「中」を「三諦」とし、それを中国禅の方法で「一心」に「三観」を観想した。智顗(ちぎ)は、これを『摩訶止観』で「円頓(えんどん)止観」に発展させた。
『摩訶止観』は、「空」・「仮」・「中」を観想のテーマに依用しながらも、龍樹の中観とは似て非なる中観になっている。これは、中国仏教の解釈法のクセで、華厳の法蔵や澄観(ちょうがん)、法相の窺基、三論の吉蔵もそうである。
以下『摩訶止観』の通覧である。
最初に「大意」として「六即(ろくそく)」と「四種三昧(ししゅざんまい)」等が述べられる。「六即」とは、天台で言う「円教(えんぎょう)」(『法華経』)の修行をする者の修行の段階六つを言う。
具には、
「四種三昧」は、「法華一乗」の実践である「止観」による瞑想法。
具には、
次に、「釈名」として、「止観」についての意味説明がある。
まず「止」の説明で、具には、「止息」・「停止」・「不止に対する止」が説かれる。
「観」は、「貫穿(かんせん)」・「観達(かんだつ)」・「不観に対する観」。
この「止観」は、二項対立の「相依相待」関係を観想するもので「相待止観」と言い、二項対立を超え、コトバを超えた「止観」を「絶待止観」と言う。
次に、「体相」として、「三止」と「三観」が説かれる。
まず、「三止」で、具には、「体真止」・「方便随縁止」・「息二辺分別止」。
「三観」は、「従仮入空観」・「従空入仮観」・「中道第一義観」。
次に修行の前の準備としての「方便」。「二十五方便」を説く。
具には、まず環境を調える「具縁」の五。
次いで、「五欲」を抑える「呵(か)欲」の五。
次いで、「五蓋(ごがい)」を抑える「棄蓋(きがい)」の五。
次いで、身心を調える「調和」の五。
次いで、「菩提心」を堅固にする「方便行」の五。
次に、「止観」の「正修(しょうしゅう)行」の際、執著の対象(障礙)となる「十境」。
具には、「陰入界(おんにゅうかい)境」・「煩悩境」・「疾患境」・「業相境」・「魔事境」・「禅定境」・諸見境」・「増上慢(ぞうじょうまん)境」・「二乗境」・「菩提境」。
次に、「十境」の一つ一つを観想する「十乗観法」。具には、
次に、「一念三千」が説かれる。私たちの一瞬一瞬の「一念」に一切諸法が収まっているという意味。
「三千」とは、具には、「六道」+「四聖(ししょう、声聞・縁覚・菩薩・仏」=「十界」。この「十界」は「界」ごとに他の「九界」を具するので「百界」(「十界互具」)。
その「百界」はおのおの「十如是(にょぜ)」(相・性・体・力・作・因・縁・果・報・本末究竟)を具するので「千如是」。そして、「千如是」は「三種世間」(衆生世間・国土世間・五蘊世間)にまたがるので「三千世間」。すなわち、合計で三千の一切諸法の意味である。
五、最澄の天台宗と空海の真言宗
平安仏教の両雄、最澄と空海は、「南都六宗」の学解的仏教の環境で仏道をスタートさせた。偶然に、同じ第十六次遣唐使船の第一船・第二船に乗り東シナ海を渡った。最澄は短期留学の還学生(げんがくしょう)で教えを乞いに行く請益僧(しょうやくそう)、空海は二十年留学の留学生(るがくしょう)で中国の仏教を本格的に学ぶ学問僧だった。
最澄は、天台山で道邃(どうずい)と行満(ぎょうまん)について天台の修行・教学を学び、一年を経ずして先に帰国した。帰国してまもなくは、天台山からの帰途、紹興(しょうこう)の峰山道場(ほうざんどうじょう)で順暁(じゅんぎょう)から授かった不備な密教が宮中の耳目を集め、桓武天皇の病気平癒や高雄山寺での日本初の「潅頂」をさせられた。最澄が本意とする法華「一乗」の天台宗が「年分度者(ねんぶんどしゃ)」(=官僧の定員)を認められて立教開宗となったのはそのあとだった。
その最澄が亡くなるまでこだわっていたのは大乗の「菩薩戒」の戒壇を比叡山に設けることであった。奈良時代、官僧の第一歩となる「具足戒」受戒の戒壇院を擁し国家仏教の中核として君臨する東大寺に対抗し、「菩薩戒」の大乗戒壇を擁し大乗を旗印に平安京の新しい国家仏教の中核ならんとする意欲は満々だった。その背景には、失脚していた和気清麻呂が桓武による平安遷都のブレーンとして復活し、最澄に自らの氏寺である高雄山寺を任せるなど大きな外護者になっていたこともあるだろう。最澄は弟子の光定(こうじょう)を使者とし朝廷との交渉に当らせた。
この最澄の動きに対し、小乗戒を守る旧都奈良の仏教勢力は当然面白くなかった。都を遷されて権勢にほころびが生じた上、比叡山で「菩薩戒」を受けた者は天台宗の僧となり、比叡山で十二年籠山修学するなどということには当然反対だった。
当時、国家仏教の機関で官僧の位階などを管理する「僧網所」の上首だった元興寺の護命は、国家仏教の立場から反対した。この護命はたまたま空海とは友好関係にあり、空海には吉野の「自然智宗」や法相学などのことで何かと指南をしていたことが推定される。空海はこの護命から最澄の大乗戒壇の話を聞き、最澄の構想に首をかしげたかもしれない。
東大寺にしてみれば、東大寺で受戒し南都で学んだ最澄に伝統と実績のある小乗「具足戒」を真っ向から否定され、中央の戒壇院をもつ国家仏教中核としての面目をおびやかされた上、東大寺をはじめ諸国の国分寺では『仁王経』・『金光明経』とともに護国経典の一つに過ぎなかった『法華経』が法華「一乗」といって立宗の表看板に掲げられ、しかも『法華経』は『華厳経』にくらべ大乗思想のスケールの点で及ばないものであったし、念仏行で念ずる阿弥陀仏は華厳の慮舎那仏の一部であり、めざす西方浄土は慮舎那仏の蓮華蔵世界の一部に過ぎず、最澄の傍系の密教は東大寺別当になった空海の正統の密教に及ばず、さほどに新しいとは思えない「円(『法華経』)」・「禅(「止観」)」・「戒(「菩薩戒)」・「密(傍系密教)」の「四宗兼学」を言って大乗の立場を主張してくる最澄をいぶかったにちがいない。
空海は、奈良の国家仏教勢力とは事を構えずむしろ友好的だった。おそらく朝廷の雄藤原氏や渡来系氏族ながら藤原氏と婚姻関係をもって中央政権にも根を張っていた秦氏と親しい関係にあったり、大安寺の勤操や元興寺の護命など南都には若い日に世話になり指南を受けた大徳が多くいたからであろう。そうした関係で、国家仏教の中枢だった東大寺の別当に迎えられたのでもあろう。入京後の空海は、多忙だったせいか最澄のように一宗をかまえる気配もなく、一宗の開創より国家の鎮護の方が優先していた。
真言宗の場合は、空海がかかわった寺ごとに「年分度者」が認められた。高雄山寺がそうであり、東寺がそうであり、高野山もそうだった。「年分度者」三名が認められ、金剛峯寺が官寺に準ずる定額寺(じょうがくじ)となったのは承和二年(八三五)の初め、空海入滅の直前である。いわば、空海の真言宗は、空海の帰国後約三十年かかっての立宗だった。
最澄以後、天台宗は、最澄に付いて天台山に学んだ義真(ぎしん)が初代座主となり、その法統が二代座主の円澄、三代座主の慈覚大師円仁へと引き継がれた。
円澄は、武蔵で最澄の支持グループを率いていた道忠のもとから比叡山に上って最澄に師事し、円仁は、下野大慈寺の広智の室から比叡山に上って最澄に師事し、苦難の入唐留学を経験して再度比叡山に密教をもたらし「台密(たいみつ、天台宗の密法)」を集大成した。広智は、比叡山に在山しなかったが、下野大慈寺を拠点に最澄の東北進出をサポートしたことで知られている。
最澄は、人柄のせいか、「四宗兼学」の総合学習に魅力があったのか、すぐれた弟子に恵まれた。その弟子のうち、後継者と目されていた泰範(たいはん)、そして円澄・光定、また円仁の同輩でのちに義真と後継争いをして敗れ天台山に上った円修(えんしゅう)や、円澄の門下の徳円(とくえん)など、愛弟子たちを惜しげもなく空海のもとに派遣し正統密教を学ばせた。空海もこれに快く応えた。
とくに円澄は終生空海と親交を続けた。天長八年(八三一)には、円澄を上首とする最澄の弟子十数名に空海は病身をおして密法を付法(ふほう)し、円澄は円澄で、第二代天台座主になった翌年の承和元年(八三五)、自ら発願建立した西塔院(さいとういん)の落慶法要に空海を招き、空海は實恵ら六人の弟子とともに比叡山に上り、「咒願師(じゅがんし=施主・願主に代り法要で祈願文を読む役)」をつとめた。空海がその生涯を了えるちょうど一年前の三月だった。高野山から比叡山へ、大変な道のりだったであろう。
この円澄と空海の親交は、最澄と空海の『理趣釈』をめぐっての決別、そして泰範が最澄を捨て空海に走った事件にも左右されなかった。空海はすでに自分の死期をさとり約二年前から五穀を断っていた。さまざまに良きライバル最澄への思いが募ったのであろう、弱りつつある法体におそらくムチ打っての命がけの比叡山登嶺だったと思われる。円澄は、空海が長安から帰国してまっ先に手紙を書いた人であった。
円仁は、下野都賀郡(今の栃木市岩舟町下津原の盥窪(たらいくぼ))で生れ(※)、近くの大慈寺の広智の室に入り、やがて広智に連れられて比叡山に上り最澄に師事した。その比叡山で「四宗兼学」したのち、請益僧として最後の遣唐使船で入唐し、「会昌の廃仏」で揺れる長安で、大興善寺(だいこうぜんじ)の元政(げんせい)から「金剛界」の潅頂と「金剛界法(こんごうかいほう)」を、空海が学んだ青龍寺では、空海とともに恵果和尚の正嫡だった義操(ぎそう)の直弟子・法全(はっせん)から「胎蔵界」の潅頂と「胎蔵界法」を、さらに「蘇悉地法(そしっぢほう)」を受法した。
しかし、帰国するにも滞在期間をとうに過ぎた不法滞在者で、官憲の目を避けながら逃亡者の仕儀となった。途中捕縛され還俗する憂き目にも遭った。帰国した円仁は、比叡山の密教の整備に着手し、「金剛界法」・「胎蔵界法」と「蘇悉地法」の「三部秘経」法をもって最澄の傍系密教の欠陥を補充した。留学中の日記『入唐求法巡礼行記』を残している。
円仁と同時期、比叡山はまたすぐれた学僧を輩出した。
下野大慈寺の広智の弟子で第四代座主の安慧(あんね)。
若くして比叡山の学頭となり、入唐して天台山から長安に入り、青龍寺の法全から「金剛界」・「胎蔵界」の「潅頂」と「蘇悉地法」を受法し、帰国後「円(『法華経』)」と「密(『大日経』)」の同意義を説いた第五代座主の円珍(えんちん、空海の姪の子、「寺門派」(三井寺系)の宗祖)。
その円珍とともに青龍寺の法全から受法し、唐に残って十九代皇帝宣宗(せんそう)の帰依を受けた円載(えんさい)。みな最澄の弟子である。
一方、空海以後の真言宗は、十大弟子ほかに受け継がれた。
高雄山寺を守り『性霊集(しょうりょうしゅう)』を編んだ真済(しんぜい)。
空海の実弟で、清和天皇の護持僧となった真雅(しんが)。
空海の一族の出自で、高野山開創の折泰範とともに骨を折り、東寺の初代長者となった實恵(じちえ)。
實恵と同じく空海の同族で、第五代天台座主円珍の伯父ともいわれ、東大寺の華厳宗に長けた道雄(どうゆう)。
東大寺で三論を学び、實恵とともに東大寺真言院の管理と定額僧(じょうがくそう)二十一人を指導し、東大寺別当にもなった円明(えんみょう)。
平城(へいぜい)天皇の第三皇子で、一度退位して弟の嵯峨天皇に譲位した平城が愛妾藤原薬子と計り皇位に復活して嵯峨を悩ませた「薬子(くすこ)の乱」が鎮圧され、平城とともに出家して空海に預けられ、東大寺の真言院で潅頂を受け名を真如(しんにょ)と改めた高岳(たかおか)親王。
真如はのちに入唐し、長安に残っていた比叡山の円載の好意で空海の止宿先だった西明寺に迎えられた。しかし、折からの「会昌の廃仏」がいよいよ激しく長安での密法受法は叶わなかった。然らばインドに行くことを決意し渡海を試みたがそのまま行方不明になった。
さらに、實恵・智泉(ちせん)とともに高雄山寺の「三綱(さんごう、上座・寺主・維那)」となり、伊豆の修禅寺を創始したといわれる杲隣(ごうりん)。
空海の姉の子で、ずっと空海のそばで仕え、師にも親にも孝順の誉れ高い、早逝の智泉。
真済が入唐した際、高雄山寺を預かって守った忠延(ちゅうえん)。
そして泰範である。
泰範は、はじめ奈良の元興寺で学び、そののち最澄に師事した。最澄にすこぶる信頼され、後継者とも目され、最澄が愛弟子たちを空海のもとに送り正統の密教を学ばせたなかに泰範もいた。しかし、空海の近くで空海とその密教にふれていくなかで空海を師とする気持ちが募り、最澄からの再三にわたる帰山要請にもかかわらずついに最澄のもとには帰らず、空海の高野山開創では大きな役割を担った。
以上の十大弟子のほか、
空海亡きあと高野山を預かり衰微の傾向にあった高野山を復興した、空海の甥の真然(しんぜん)。
その弟子で、高野山初代座主の寿長(じゅちょう)。
『三十帖冊子』の返還問題で苦渋した第二代座主の無空(むくう)。
第六代天台座主の惟首(ゆいしゅ=真然から密法を受ける)。
真言系修験(当山派)の祖で、醍醐寺(だいごじ=小野流)の開祖の聖宝(しょうぼう)らがいる。
さらに、空海の使者として下野大慈寺の広智や会津慧日寺の徳一(とくいち)に密教経典の書写を依頼にいった康守や、空海付法の弟子にはまだ入唐経験者の常暁(じょうぎょう)・円行(えんぎょう)がいる。
天台は、最澄以後もすぐれた後継者たちが輩出し、「四宗兼学」や「山王神道(さんのうしんとう)」の法灯を絶やさず、途中山内に山門(円仁派)と寺門(円珍派)の対立分派が生じたり、源平の争いにかかわったり、後白河法皇とも確執があったが、織田信長の全山焼打ちを越えて、江戸期には「東照大権現(とうしょうだいごんげん)」となった徳川家康を日光山にいただき、以後将軍家の帰依を受けた。全国の日枝(ひえ)神社は、大津市の日枝大社を中心とする天台宗の山王神道(さんのうしんとう)の神社である。
ちなみに、江戸時代天台宗に帰依した大名に十九家が挙げられ、紀州徳川家をはじめ上野の松平家・小田原の大久保家・弘前の津軽家、津の藤堂家、佐倉の堀田家、丸岡の有馬家などが見える。
天台宗系には、天台宗(比叡山延暦寺)・天台寺門宗(大津市圓城寺(三井寺))・天台真盛宗(大津市西教寺)がある。
空海の真言宗は、こちらもすぐれた後継者が輩出し、高野山・東寺・高雄山寺あるいは安祥寺(あんしょうじ)・円成寺(えんじょうじ)・仁和寺・醍醐寺・大覚寺などを拠点に真言密教の宣布につとめた。
途中高野山と東寺の間で本寺末寺争いがあったり、高野山の無人化があったり、覚鑁(かくばん、興教大師)とその支持者(新義派、根来寺)の離山があったり、寺領の紛争などがあったが、藤原摂関家や武家政権の信助を受け、法灯を維持した。
江戸時代は、「高野山法度」・「高野山衆徒法度」・「東寺法度」・「真言宗法度」などで縛られ、空白の二〇〇年と言われ、真言宗に帰依した大名も米沢の上杉家くらいであった。
しかし、徳川将軍家の浄土宗と天台宗に何歩も譲った状況のなかで、浄厳(じょうごん)や慈雲(じうん)らが戒律の復興につとめたり、『大日経』や『大日経疏(だいにちきょうしょ)』や『金剛頂経』や『菩提心論』や『釈摩訶衍論』などの宗乗(しゅうじょう)典籍や「念誦法(ねんじゅほう)」などの事相(じそう)を研究する学匠が輩出した。しかし、明治政府が断行した廃仏毀釈は、神宮寺などを通じて神仏習合を長く保持してきた真言宗には大きな痛手となった。
真言宗系には、主なもので、
高野山真言宗(和歌山県高野町金剛峯寺)
東寺真言宗(京都市教王護国寺)
真言宗醍醐派(京都市醍醐寺)
真言宗御室(おむろ)派(京都市仁和寺)
真言宗大覚寺派(京都市大覚寺)
真言宗泉涌寺(せんにゅうじ)派(京都市泉涌寺)
真言宗山階(やましな)派(京都市勧修寺(かじゅじ))
真言宗善通寺派(善通寺市善通寺、京都市随心院)
真言宗須磨寺派(神戸市須磨寺)
真言宗中山寺派(宝塚市中山寺)
真言三宝宗(宝塚市清澄寺)
信貴山(しぎさん)真言宗(奈良県平群町朝護孫子寺(ちょうごそんしじ))
新義真言宗(岩出市根来寺)
真言宗智山派(京都市智積院(ちしゃくいん))
真言宗豊山派(桜井市長谷寺)
真言律宗(生駒市宝山寺、奈良市西大寺)
などがある。
六、天台宗から出た念仏・唱題・坐禅
法然は、浄土思想と禅とが一体になった「観想念仏(かんそうねんぶつ)」、すなわち五台山の音曲的な「念仏三昧」を学んだ円仁が帰国後比叡山に広めた「常行三昧(じょうぎょうざんまい=阿弥陀仏のまわりを行道しながら南無阿弥陀仏を称える立ったままの行)」をきらったのか、結局善導(ぜんどう)の『観無量寿経疏(かんむりょうじゅきょうしょ)』により、中国の浄土教では主流ではなかった「称名念仏(しょうみょうねんぶつ=専修念仏)」を選択したという。「観想念仏」はとても民衆に難しく、「称名念仏」なら受け容れられるということだったのか。
親鸞は、比叡山で修学しながらよほど戒・定・慧の「自力」の行が性に合わなかったのか、法然の「称名念仏」に弥陀の救いすなわち「絶対他力」を加えた。「絶対他力」とは煩悩具足のまま、この「私」を無条件で弥陀にゆだねることである。
然るに、この「私」を弥陀にゆだねても、「私」と弥陀は二律であって「一如」ではない。「私」を「否定」して「絶対他力」にすがっても、「私」は否定されたままの「私」で「肯定」されたわけではない。「私」と弥陀はずっと二律のままである。だからこそ、この「私」は「往生」によって「絶対他力」のなかに摂せられ救われなければならない。
だが、「往生」は「私」と弥陀との相互相入ではない。「絶対他力」によって「私」が摂受されるだけである。「称名念仏」とは、そのためにひたすら「絶対他力」にすがる「自力」放棄のコトバであり、真言のような「生仏一如(しょうぶついちにょ)」のコトバではない。「自力」を捨てた自棄のコトバに自己肯定の力などありえないのである。
だから親鸞は、「仏性」も「菩提心」も「自力」のすべてを捨てた虚無の果てで、煩悩の闇の底に沈む「悪人」に往生権を与えた。その「悪人」を、「本覚」の故に、真実の「私」であると「逆対応」させたとしても、それは畢竟あなたまかせや現実逃避の正当化に過ぎない。
日蓮は、過激なまでに『法華経』至上主義に徹し、それをもとにして国家の安泰を主張した(「立正安国(りっしょうあんこく)」)。同時期の他宗に厳しく、「真言亡国(しんごんぼうこく)」・「禅天魔(ぜんてんま)」・「念仏無間(ねんぶつむげん)」・「律国賊(りつこくぞく)」の「四箇格言(しかかくげん)」を言って批判し、自説の正当性を強調した。
高野山や東寺にも遊学し、真言宗の教義には相当の理解をもっていたはずの日蓮であるが、「久遠実成」の釈迦への信に偏したのか、「法身」大日如来を立て釈迦を「報身」とする密教を受け容れず、釈尊や『法華経』を軽んじ架空の「法身」を説く真言は亡国・亡家の教えだとし、真言宗の家では長男が成長できないとまで言った。
空海は『法華経』を重んじた。『法華経開題』を著し、死を目前にして東大寺で『法華経』を講じ、「諸法実相」の「実相」という概念を多用した。真言宗には「如来寿量品」第十六を読誦する法会もある。
栄西は、れっきとした台密の学僧だった。数々の密教研究書を著し、空海と同じ「遍照金剛(へんじょうこんごう)」を自ら名のった。然るに、比叡山の「常坐三昧」に嫌気がさしたのか、日本を出て中国に道を求めた。二度目の入宋の際にはインドに向おうとしたがはたせず、帰国する途中船が逆風に遭って再上陸し、その機会に登った天台山で万年寺の虚庵懐敞(きあんえじょう)に出会い、禅が密教に通じることを諭され、虚庵懐敞と天童山で黄龍派の臨済(りんざい)禅を得て帰国した。禅が他宗を排除するものではないと言って禅の布教を試みたが受け容れられず、鎌倉に出て幕府の力を借りた。鎌倉寿福寺の住職就任や京都建仁寺の創建がそれである。建仁寺では、台密と臨済禅の両方を兼ねて修する「密禅兼修(みつぜんけんしゅう)」を行ったが、やがて「公案(こうあん)」中心の臨済禅専修になった。
道元は、十三歳で比叡山の首楞厳院(しゅりょうごんいん)に入室。翌年「菩薩戒」を受けたが、早々に比叡山を離れ建仁寺の栄西を頼った。しかし、栄西は翌年没してしまい、高弟の明全(みょうぜん)に師事した。六年後、明全とともに宋に渡り、天童山の如浄(にょじょう)から曹洞(そうとう)禅を学び、「只管打坐(しかんだざ)」・「身心脱落(しんじんだつらく)」を日本に伝えた。最初、京都深草の興聖寺に入り弟子を養成するかたわら『正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)』を書き続け、のち福井の大仏寺(今の永平寺)に移った。鎌倉にも招かれたが容れられなかった。
道元は自分の禅は末法思想とは関係がないと言ったそうであるが、武家の政権は「諸行無常(しょぎょうむじょう)」「もののあはれ」の真っただ中だった。禅は、明日をも知れぬ武家のはかない命と不安に応えなければならなかった。
しかし、これら鎌倉仏教を空海から見れば、念仏も阿弥陀信仰も西方極楽浄土も、『法華経』の「諸法実相」も題目も、臨済の「直指人心(じきしにんしん)」・「見性成仏(けんしょうじょうぶつ)」・「教外別伝(きょうげべつでん)」・「不立文字(ふりゅうもんじ)」の「観」も、曹洞の「只管打坐」・「身心脱落」も、それぞれ密教の前の段階の「大乗」であり「顕教(けんぎょう)」であったし、みな「十住心」に織り込み済みなのだった。
然るに、法然の浄土宗は、江戸時代、三河の大樹寺を通じて徳川将軍家の帰依を受け、江戸三百年を優位に過した。宗家・尾張・水戸の徳川御三家をはじめ、丹波の京極家・岡崎の本多家、松山の松平家、長岡の牧野家、古河の土井家、郡上の青山家、三河の大岡家、多くの所領を治めた水野家など、帰依した大名は六十八家を数えた。芝増上寺・京都知恩院・鎌倉光明寺はそのシンボルである。
浄土宗系には、浄土宗(京都市知恩院、鎮西(ちんぜい)派)・西山浄土宗(長岡京市光明寺)・浄土宗西山深草派(京都市誓願寺)・浄土宗西山禅林派(京都市永観堂)がある。
親鸞の浄土真宗は、室町時代、門徒を組織化して講にした蓮如(れんにょ)とその講による「一向一揆(いっこういっき)」で知られる。加賀にはじまった「一向一揆」は北陸一帯に及んだ。また京都では「天文法華の乱」で「法華衆」とも対立した。そのため、多くの戦国大名がその禁止令を出した。戦国時代、石山本願寺の顕如(けんにょ)は織田信長の宿敵だった。
以後は京都の西と東の本願寺を得て、門主大谷家は皇室とも結ばれるようになった。門徒の民衆が一揆をもって権力者に反抗した信仰の宗門が、時を経て日本の最高権威側に立ったのである。民衆の信仰を武力化し、一揆をもってたびたび戦国大名の手足となって功を挙げたものの、江戸時代に浄土真宗を宗旨とした大名は藤枝の本多家、近江の加藤家など四家だった。
浄土真宗系には、
浄土真宗本願寺派(京都市西本願寺)
真宗大谷派(京都市東本願寺)
真宗高田派(津市専修寺)
真宗仏光寺派(京都市仏光寺)
真宗興正寺派(京都市興正寺)
真宗木辺派(野洲市錦織寺)
真宗出雲路派(越前市毫摂寺)
真宗誠照寺派(鯖江市誠照寺)
真宗三門徒派(福井市専照寺)
真宗山元派(鯖江市證誠寺)
などがある。
日蓮宗は、『法華経』の「本迹(ほんじゃく)」論で、『法華経』二十八品に本迹・勝劣はないとする「一致派」と、前半の十四品を「迹門」とし、後半の十四品を「本門」として、「本門」が「迹門」よりも勝れているとする「勝劣派」の二派に、また「本仏論」で、釈尊(「久遠実成」の釈迦牟尼仏)を本仏とするグループと日蓮を本仏とするグループに大きく分かれた。
具には、
日蓮を本仏とする勝劣派に、日興の法流(富士門流、富士宮市大石寺)。
釈尊を本仏とする勝劣派に、日什・日隆・日真・日陣の法流と、日興の法流の一部。
釈尊を本仏とする一致派に、日昭・日朗・日向・日常の法流。
という。
戦国時代の天文(てんぶん)年間、日蓮宗を信仰する町衆が京都の大半を占め、いわば自治権まで握るような勢いの時期があった。これに対抗するように、一向宗門徒が京都に集結するうわさが流れると、町衆(「法華衆」)は市内の一向宗寺院や山科本願寺を焼打ちした。しかし、やがてこの争乱に比叡山の延暦寺が介入し、洛中洛外の日蓮宗本山はすべて焼かれ、「法華衆」の多く(三千人~一万人)が殺害された(「天文法華の乱」)。
その後、京都の「法華衆」から、本阿弥光悦や俵屋宗達や尾形光琳や長谷川等伯が、さらに武家出身の正信・元信・永徳の狩野派がアートの世界で一時代を築き、禅林文化から法華文化と言われるようになった。織田信長も親法華だったという。
江戸時代は、久遠寺などが徳川将軍家や諸大名の帰依を受けたりしたが、むしろ備前法華と言われるような法華衆徒の教化や宗論の研鑚の時代になった。
日蓮宗を宗旨とした大名に、厚木の大久保家、浜松の井上家、亀山の石川家、浜田の松平家など十三家が見える。
日蓮宗系には、
日蓮宗(山梨県身延町久遠寺)
日蓮正宗(富士宮市大石寺)
顕本法華宗(京都妙満寺)
日蓮本宗(京都要法寺)
本門法華宗(京都妙蓮寺)
法華宗陣門流(三条市本成寺)
法華宗真門流(京都本隆寺)
法華宗本門流(京都本能寺など四大本山)
日蓮宗不受不施派(岡山市妙覚寺)
日蓮宗不受不施講門派(岡山市本覚寺)
などがある。
栄西の臨済宗は、鎌倉末期から室町時代にかけ、北条氏から鎌倉五山、足利将軍家から京都五山の名誉を授かった。建長寺・円覚寺・寿福寺・浄智寺・浄妙寺(鎌倉五山)と、天龍寺・相国寺・建仁寺・東福寺・万寿寺(京都五山)に、別格として南禅寺(京都)である。大徳寺と妙心寺はそれぞれの理由ではずされている。
また、足利三代将軍義満の別荘金閣寺(北山文化)、八代将軍義政の別荘銀閣寺(東山文化)にも寄与し、堂宇の建築意匠や庭園の設計などを通じ枯淡・幽玄・侘びの引き算の文化を具象化した。
栄西が宋から持ち帰ったというお茶がやがて「茶道」となり、室町時代から安土桃山時代にめざましく発展し、大名は茶の宗匠(「茶頭」)をかかえるようになった。
千利休(せんのりきゅう)を頂点にして「利休七哲」といわれる蒲生氏郷(うじさと)・細川三斎(さんさい)・牧村兵部(ひょうぶ)・瀬田掃部(かもん)・古田織部(おりべ)・芝山監物(けんもつ)・高山右近(うこん)が出たり、小堀遠州(えんしゅう)・片桐石州(せきしゅう)・織田有楽(うらく)などは一つの流派をなした。茶道の精神的な部分は主に大徳寺系の臨済寺院が担った。今も三千家の家元になる宗匠は、必ず一度大徳寺の門をくぐり修行をする。
江戸期には白隠(はくいん)が出て衰微しかけていた禅画や墨蹟を多く書いて臨済禅の復興に努力した。
臨済宗に帰依した大名は、妙心寺派五十二家、大徳寺派三十四家、円覚寺派四家などで、浄土宗をはるかにしのいでいる。目立つところでは、彦根の井伊家、岡山の池田家、小倉の小笠原家、丸亀の京極家、仙台の伊達家、宇都宮の戸田家、盛岡の南部家、福岡の黒田家、会津の保科家、熊本の細川家、加賀の前田家、郡山の柳沢家など錚々たる顔ぶれである。
臨済宗系には、
建仁寺派(京都建仁寺)
東福寺派(京都東福寺)
建長寺派(鎌倉建長寺)
円覚寺派(鎌倉円覚寺)
南禅寺派(京都南禅寺)
国泰寺派(高岡市国泰寺、東京上野全生庵)
大徳寺派(京都大徳寺)
向嶽寺派(甲州市向嶽寺)
妙心寺派(京都妙心寺)
天龍寺派(京都天龍寺)
永源寺派(近江市永源寺)
方広寺派(浜松市方広寺)
相国寺派(京都相国寺)
仏通寺派(三原市仏通寺)
興聖寺派(京都興聖寺)
がある。
道元の曹洞宗は、臨済宗が永く武家政権に接近し精神文化などの面で重んじられたのに対し、地方の大名や土豪や下級の武士や一般民衆の間に浸透した(「臨済将軍、曹洞士民」)。今、全国に一万五千ヵ寺の末寺を擁するのは、その成果ではないか。
しかし、一宗には確執や抗争がつきもので、道元の滅後、道元の直弟子で師の「只管打坐」の禅道を忠実に守る人たちと、民衆教化に目を向け法儀も可とする人たちに分れた(「三代相論」)。加えて、永平寺の直弟子と深草興聖寺から出た旧達磨宗の人たちとの間にも確執があり、矢面に立って事態の収拾を図ろうとした第三世の徹通義介(てっつうぎかい、旧達磨宗系)は、結局永平寺を出て加賀大乗寺(現、金沢市)に支持者とともに移った。
義介の弟子の瑩山紹瑾(けいざんじょうきん)は能登の諸岳寺(もろおかじ、真言宗?)を譲られ、それを総持寺として開山した。今の総持寺祖院、鶴見総持寺の前身である。紹瑾は、民衆教化のために密教的な儀法も採り入れたという。
永平寺はその後、外護者の地頭波多野家による支援も思うようにいかなくなり、一時は無住状態にまで衰微したが、越前大野の宝慶寺から永平寺第五世になった義雲が、再び波多野家の援助を受け、堂塔伽藍の整備や山内の綱紀に着手し復興に導いた。
江戸時代には、宗学研究の学僧が出て、道元の『正法眼蔵』の研究や「面授嗣法(めんじゅしほう)」に帰るべきとの主張に見るべき学績を残し、曹洞宗を宗旨とする大名も六十四家を数えた。広島の浅野家、薩摩の島津家、佐賀の鍋島家、姫路の酒井家、萩の毛利家、高知の山内家など有力大名が帰依した。
江戸時代、各宗とも徳川幕府の諸「法度」の統制を受け、宗義を宣揚して他宗とのちがいを強調するよりも、それぞれの宗門の持ち味や仏教寺院の機能を活かし、民衆教化や社会的役割の活動に意をそそぐようになった。
そうしたなか、幕府はキリシタン対策の一環として民衆に「寺請(てらうけ)」を義務づけ、誰もみないずれかのお寺を菩提寺とし、檀家であってキリシタンではないことを証明する証文(「寺請証文」)を寺から交付してもらうことになった。檀家制度のはじまりである。
毎年一回、調査や申告が行われ「宗門人別帳(しゅうもんにんべつちょう)」が改められた。今の住民登録と同じで、結婚や奉公先の移動などでほかの土地に移住する時、宗旨をふくめた個人情報が移住先の菩提寺に送付された。
幕府は、檀家となった人々に菩提寺護持の義務を法によって明示し、檀家は菩提寺への参詣をはじめ、葬儀・年忌法事・付届けを義務づけられた。この檀家制度によって、宗派を問わず仏教寺院の過半は寺院の維持活動の基盤が安定した。
この檀家制度を葬式仏教の根拠にして日本仏教が変節したとか僧侶が堕落したとか言う人がいるが、木を見て森を見ざる意見である。檀家になった人々は、士・農・工・商の身分制度が厳しかった社会で唯一、自分の身元や身分の証明をしてくれる場所がお寺であり、檀家として菩提寺護持のために義務を課せられたが、死者が出た時の遺体処理から悪霊退散から悲しみの治癒まで、一括して寺という宗教専門家に頼めるようになった。死者の霊は単なる死霊から、成仏して戒名をもらえるようになり、死者への畏敬の念を一段増したのである。この檀家制度に基づき、寺では死者の名簿すなわち過去帳をつけることになった。
もしこの檀家制度がなかったら、日本の仏教寺院の過半は明治の廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)や敗戦後の農地解放・信仰の自由といった法難に耐えらず、無住・廃寺になったであろう。兜率天の空海が見れば、日本仏教の荒廃ここに極まれりだったに相違ない。
七、空海と良きライバル最澄のこと
伝教大師最澄は、神護景雲元年(七六七)近江国滋賀郡古市郷(現在の大津市)で生れた。渡来系の三津首の家系を出自とする。十二才の時近江国分寺の行表の室に入り、十四才で得度し最澄と名のった。
延暦四年(七八五)、十九才の時に東大寺戒壇院で「具足戒」を受け、ほどなくして比叡山に上り草庵を結んで山林修行と仏典読破に専念する。延暦七年(七八八)に今の「根本中堂」に当る「一乗止観院」を創建し、自ら刻んだ薬師如来を本尊として祀る。
桓武天皇が平安京に遷都をしてまもない延暦十六年(七九七)、内供奉十禅師(ないくぶじゅうぜんじ)の一人に任ぜられた。
延暦二十一年(八〇二)、高雄山寺において法華会を行い『法華経』を講義する。この年、第十六次遣唐使に同行する還学生の許可を上奏して認められた。
延暦二十二年(八〇三)、通訳に弟子の義真(のちの天台宗第一世座主)を連れ、第十六次遣唐使船で難波ノ津(なにわのつ)を出発するも一週間の内に悪天候のため船が損傷し、船の修理のため翌年の六月まで大宰府で待機を余儀なくされた。
延暦二十三年(八〇四)七月、遣唐大使藤原葛野麻呂ほか空海たちを乗せた再出発の第十六次遣唐使船団の第二船に那ノ津(なのつ、博多)で乗船、明州をめざしたが東シナ海で暴風雨に遭い再び船が損傷。九月に辛くも明州に上陸しただちに天台山に向った。
翌延暦二十四年(八〇五)夏に帰国するまでの九~十ヵ月の間、天台教学の始祖天台智顗の孫弟子になる道邃(どうずい)と行満(ぎょうまん)に天台教学を、また道邃からは『梵網経』の「十重四十八軽戒」を、翛然(しゅくねん)からは禅を、明州に向う帰途紹興の峰山道場で龍興寺の順暁から密教を、それぞれ受学した。
同年七月に帰京し、唐から持ち帰った仏典類の二百三十部四百六十巻を「将来目録」として上奏するとともに、病床にあった桓武天皇の病気平癒を宮中において祈願した。桓武は最澄の「将来目録」から日本に密教がもたらされたことを知って大いに喜び、九月には早速高雄山寺において潅頂を行わせ、南都仏教の長老たちを呼びつけて受法させたほか、自らも受法した。
しかしその後最澄を重用していた桓武天皇が崩御し、最澄の運気にもかげりが見えはじめる。この年の秋十月、在唐二十年を義務とする留学生として長安にいたはずの空海が、正統密教の伝法八祖となって帰国し、短期ながら長安留学の一大成果を「請来目録」として朝廷に提出し、その内容を知った最澄は自らの密教の不備を察知した。
大同四年(八〇九)七月、空海は最澄が住持をしていた和気氏の私寺高雄山寺に迎えられるが、この時最澄はこころよく住持の立場を譲った。また、空海が高雄山寺に落ち着いたばかりの八月下旬、最澄は弟子経珍を空海のもとにやり、十二部五十五巻からの密教経軌や悉曇関連典籍の借覧を申し出た。経珍にもたせた手紙の末尾では「下僧最澄」とまでへりくだっている。
しかし、空海はこれを一度断る。密教の受法は師から根機の弟子に口授をする「師資相承(ししそうじょう)」が習いで、まして密教の儀軌(ぎき)や梵字悉曇の経軌を書写しそれを読んだところでわかるわけがなく、それを心得ないためか、いきなり密教典籍の借覧を申し出てきた最澄のマナーや真意にいぶかしさをおぼえたであろう。
それでも最澄は空海のもとに使いをやり借経をつづけた。空海もそれに応じた。さらに最澄は自分の代りに勝れた弟子を空海のもとに置き密教を学ばせることを申し出たが、空海はこれも了承した。
空海のもとに派遣されたのは最澄の最も信頼厚い円澄・泰範らであった。最澄は、比叡山の「遮那業(しゃなごう)」(密教)の指導者または試験官を養成する目的だっただろう。しかし、好事魔多しで、やがて愛弟子泰範があろうことか比叡山と最澄を捨て空海に走るという、最澄にとっての痛恨事に発展した。
その原因はおそらく、最澄がずっととりつづけた密典の借覧・書写・読解といった独学自習がいかに密教の「師資口授(ししこうじゅ)」の鉄則に違背しているか、それを我慢して貸しつづける空海の神経をどれだけ逆なでしているか、空海のもとで密教をじかに修めていた泰範には師の無神経な誤ちがたまらなくなったのであろう。泰範はもと南都の元興寺にいた。若き日に大安寺や元興寺や興福寺ほかの官大寺に出入りしていた頃の空海と、その頃から気脈を通じていたのではあるまいか。
弘仁三年(八一二)十一月、高雄山寺で空海から金胎両部の「潅頂」(「受明潅頂」)を受けるが心中に期待をしていた正式な「潅頂」(「伝法潅頂」)でなく、大いに落胆する。
弘仁四年(八一三)になると、最澄は再度空海に正式な「潅頂」の要請をする一方、空海のもとから帰る気配のなくなった泰範にたびたび手紙を送り、預けたままの『止観弘決(しかんぐけつ)』を返してほしいと厭味も添えるようになる。そしてこの年の十一月になって、最澄は『理趣釈』(『大楽金剛不空真実三摩耶経般若波羅蜜多理趣釈』不空訳、『理趣釈経』ともいう)の借覧を申し出る。
『理趣釈』とは、『金剛頂経』系密教の奥義を説いた『般若理趣経(はんにゃりしゅきょう)』(『大楽金剛不空真実三摩耶経般若波羅蜜多理趣品』不空訳)の注釈である。
『般若理趣経』では大毘盧遮那が「他化自在天(たげじざいてん)」(「欲界」の最高天)において、人間の性欲さえも「菩薩」の清浄な心位に価値転換できる「生仏一如」・「煩悩即菩提」の境地を男女交合の悦楽をメタファーに説くためやたら密教未修学の者には与えない。与える場合は、師が弟子の機根をよく見極め、講伝という厳粛なかたちをとる。師と離れたところで独学自習することなどもってのほかである。最澄はそれを心得なかったのであろうか。『理趣釈』を空海から借りて一人読解しようとした。空海がこれに応ずるはずがなかった。
空海は最澄の願い出に、返事して言う。
然リト雖モ疑フラクハ理趣端多シ。求ムル所ノ理趣ハ何レノ名相ヲ指スヤ。
夫レ理趣ノ道、釈経ノ文、天ノ覆フコト能ハザルトコロ、
地モ載スルコト能ハザルトコロナリ。
冀クハ子、汝ガ智心ヲ正シクシ、汝ガ戯論ヲ浄メ、理趣ノ句義、密教ノ逗留ヲ聴ケ。
夫レ秘蔵ノ興廃ハ唯汝ト我ナリ。汝若シ非法ニシテ受ケ、我若シ非法ニシテ伝ヘバ、
則チ将来求法ノ人、何ニ由テカ求道ノ意ヲ知ルコトヲ得ン。
非法ノ伝受、是レヲ盗法ト名ヅク。即チ是レ仏ヲ誑ス。
又秘蔵ノ奥旨ハ文ヲ得ルコトヲ貴シトセズ、唯心ヲ以テ心ニ伝フルニ在リ。
文ハ是レ糟粕、文ハ是レ瓦礫ナリ。
子若シ三昧耶ヲ越セズシテ、護ルコト身命ノ如クシ、
堅ク四禁ヲ持テ愛スルコト眼目ニ均シクシ、教ノ如ク修観シ、
坎ニ臨ンデ績アラバ、則チ五智ノ秘璽、踵ヲ旋ラスニ期シツベシ。
況ンヤ乃チ髻中ノ明珠、誰カ亦秘シ惜シマン。
文の途中で最澄を「汝」「子」と見下しながら、くどいほどに暗喩を借り、最澄の密典読解の態度や『理趣経』に対する無知を暗に批判し、無神経な借経の申し出に応じない。
時に、最澄は空海との間で密教に苦悶したが、会津磐梯山にいた法相の学僧徳一にも悩んだ。晩年に五年つづいた「三一権実諍論(さんいちごんじつそうろん)」である。そのため、会津から常陸にかけて徳一の教団勢力に阻まれ、念願の東北地方への教線拡張をはたすことができなかった。
正直な性格により真摯かつ厳格な修学僧として比叡山を舞台に天台の教義と密教・禅・戒律・念仏などを組織化し、平安時代の国家仏教の担い手たるべく奮闘をした最澄であったが、生涯の後半は多事多忙となり自らの天台の教義を体系化するに至らないまま、弘仁十三年(八二二)六月四日、五十六才で示寂した。
この十二年後の承和元年(八三四)三月、宣旨によってこの山に上った空海は六人の高弟とともに西塔院の落慶供養法会に参じ、咒願師の役をつとめて座主円澄の温故に答えた。空海は生涯を了えるちょうど一年前、よきライバルであった最澄の比叡山に詣でたのである。感慨は無量だったであろう。
八、日本人の付和雷同性とマインドコントロール
『法華経』の教説に基づく法華「一乗」、すなわち「一乗」主義は、天台宗においては「三乗一乗」であったり「一念三千」であったり、すなわち「すべてが一つに収まる」という意味で「包摂的な一乗」であったが、比叡山を下りた鎌倉仏教の祖師たちはこの「包摂的な一乗」を「択一的・画一的な一乗」にした。弥陀の「一仏」信仰も、『妙法蓮華経』の「一経」絶対も、禅の端坐「一行」も、「一」を最上とし、他を容れない「一乗」主義であった。
これは、末世・末法、諸行無常・もののあわれ・濁世(現世)からの逃避といった厭世的な時代の風潮に付和雷同し、比叡山の厳格な修行と総合学習を捨てて世俗の武家や民衆に迎合し易行の「択一的・画一的な一乗」を案出したにほかならず、武家や民衆もまたその「択一的・画一的な一乗」に新しい流行の仏教パラダイムとして付和雷同した。
このような、時代の風潮とか新しい流行への迎合や付和雷同、この日本人の特性とも言える付和雷同性は、その後の日本、あるいは現在の日本にたびたび暗い影を落としている。
明治政府は、天皇中心の近代的な中央集権国家建設のために天皇を絶対化して神道を唯一の国教とした。ここから神国ニッポン・皇国思想・軍国教育がはじまり、「天皇陛下万歳」・「天皇のために死ぬことが日本人の誉れ」が当然のこととなった。そして、日本はその精神の高揚によって日清・日露の戦争に勝った。
およそ一神教の絶対は盲信・狂気になって顕れる。ましてや、戦争に勝とうものならそれが正当化される。誰も逆らうことはできない。それが太平洋戦争に日本を導いた。日米開戦時、日本駐在のアメリカ大使だったジョゼフ・グルーは、日本が太平洋戦争に突入していった真の原因は軍人の心を支配していた「国家神道による狂信的な皇国思想」だったと述懐している。日本人はこぞって、神国ニッポン・天皇絶対・国家神道・軍国教育・大東亜共栄圏に付和雷同したのである。
時にまた、日本人は付和雷同が昂じて宗教的なマインドコントロールにかかりやすく、よくカルトにはまる。
高度経済成長期、創価学会による『法華経』絶対の猛烈な折伏運動が全国的に展開された。入会勧誘に押しかけてくる信者は、今までの人柄がウソだったかのように変身し、法座などでたたき込まれたそのままに、口々に『法華経』を信じなければ起るであろう不幸について病気や災いや不幸や悪運を例に挙げ、気が進まない人や戸惑う人に入会を迫った。顔は引きつり、目は血走り、ハイテンションで尋常な形相ではなかった。それに圧倒され半信半疑で入会した人も、一年も経てば立派な信者になっていた。
折伏の嵐が収まったあとも、教祖・教団への帰依というマインドコントロールにより凶悪な反社会的事件をひき起したり、サギ商法に手を染めたりするカルト教団があとを絶たない。
寺の住職をしていると、檀信徒からさまざまな相談を受けるのであるが、一番深刻で答えがすぐ出ないのが若い息子・娘をカルトにとられて親や親族が困っているという事例である。
親が苦労して学資を工面し、そのおかげで大学に入れた息子がカルト教団に入信し、偏狭な一方づいた考え方で家族や親族や友達に迫り、反論や意に沿わない応答をすれば「地獄に堕ちる」などと言って怒り出す。話が始まればなかなか終らない。親は工面した学資もムダになり落胆の極み。親子の情などまったく通じない、といった事例。
大学を出て会社に勤めていた都会で独り暮らしの娘がカルトに染まり、目はつり上がり言葉激しく教義を口にし、知り合いのところに行ってはカルトの宣伝誌を無理強いし、毎日一日中宣伝誌を配って歩き、世の中すべてわかったようなことを言っている。親の言うことなどバカにして聞き容れない。知り合いからは苦情が絶えない、といった事例。
「子供の育て方がまちがっていたのでしょうか」、「先祖の供養が足りなかったのでしょうか」、「水子の供養でも足りないのでしょうか」、「何かがタタっているのでしょうか」。困り果てた末こんなことを気に病んで相談者がお寺に見えるが、先祖や水子のタタリの問題でもなくお経を唱えて解決することでもない。マインドコントロールされてかたくなになっている息子・娘をこの手に取り戻す有効な知恵や方法などすぐには浮ばない。
空海が今生きていたら、宗教は普遍的な哲学や倫理や世界観や生き方を教え、かたよらず、かたくなにならず、人の心を豊かにし、落ち着かせ、幸せにするものであり、ひとと敵対し、周囲に迷惑をかけ、自己だけがいいためにあるのではない。信仰は心静かにじっくりゆっくり自分の心に育てるものであって、やたら周囲に押しつけひとを巻き込むものではないと言うだろう。
選挙のたびに、日本人の付和雷同性を「民意」だとか「世論」だとか「支持」だと勘ちがいする政治家やメディアがいる。小泉人気は「民意」だったか。民主党の勝利と敗北は「民意」だったか。自民党の政権復帰は「民意」だったか。みな、無党派層といわれる「強い者に従う」・「勝ち馬に乗る」・「新しい流行にとびつく」・「長いものに巻かれる」・「みんながそうするからオレもする」国民大衆の付和雷同ではないか。
宗教団体や労働組合や業界・推薦団体の組織票。あれも「民意」か。人物も政策もよくわからない候補者に上からの指令や業界・団体の利益誘導を目的に「清き」一票を投ずるのは付和雷同以外の何ものでもない。これが戦後民主主義の根幹である選挙の実態である。
戦後日本は西欧型自由主義・民主主義に付和雷同し、戦前の日本を否定し日本の歴史や伝統を忘れてきた。日本人の付和雷同性のマインドコントロールは、時にこの国を危うくする。