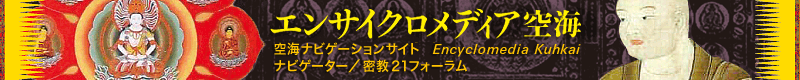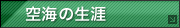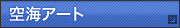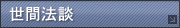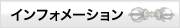空海密教と編集思想
【1】
 世紀末である。すでに二十一世紀へのカウントダウンは始まり、一〇〇〇年単位のミレニアムに大きなピリオドが打たれる日が近づいている。
世紀末である。すでに二十一世紀へのカウントダウンは始まり、一〇〇〇年単位のミレニアムに大きなピリオドが打たれる日が近づいている。 そうであるにもかかわらず、次世紀のニューパラダイムを予告できるプログラムは極めて乏しく、新たな牽引者による鮮烈なメッセージもまったく聞こえてこない。いや、牽引者が誰であるかさえ、ほとんど見当がつかないままにある。
とりわけ日本では、日本という国そのものの意識が混濁し、日本人の視線も宙をさまよっているか、ほんの一メートル先ばかりを見ているような状況が続いている。こういう打つ手のない体たらくの過渡期にこそ、空海の存在や思想が大胆に語られていいように思うのだが、巷間ではほとんどそんな議論も湧き上がってはいない。西暦でいうのなら、空海もまた八世紀の世紀末に渦巻いた末曾有の混乱を眼の当たりにして立ち上がった青年だったのである。桓武天皇が何度も遷都に迷い、自分を支えるリーダーすら見つからなかったとき、空海こそはひとり「この国」のことを構想しはじめたのだった。
しかし、空海は急ぎはしたが、焦っていなかった。時代は暗く淀み、南都は荒み、新たなパラダイムはまったく出現していなかったにもかかわらず、空海は独自の準備を重ねて、落ち着き払っていた。王法がさまよい、仏法が低迷していたにもかかわらず、空海は深く時代を読んでいた。
そんな空海の自信を、私は、最近になってしばしば『秘蔵宝鑰』の中の憂国公子と玄関法師の十四問答として思い出す。僧尼たちは頭を剃っても欲を剃らず、衣を染めても心を染めていないとしかおもわれない当時の状況に業を煮やした憂国公子に対して、空海とおぼしい玄関法師が淡々と諌める有名な問答である。玄関法師は焦りまくる公子に「麒麟や鳳凰が見えなくなったからといって、すぐ動物を絶滅してはならないし、如意宝珠が得られないようになったからといって鉱物を唾棄すべきではない。いまの世に聖者が見つからないといって、すぐに仏法を捨てるべきではない」と諭す。まるで今日の世紀末の苛立ちに対する説法のようではないか。
だが、憂国公子もなかなか譲らない。「たとえ聖者が見えなくとも、多少の大悟と智慧をもつ者くらいはいてもよさそうではないか」と反論をする。法師はそこで、現代はあきらかに末法であり、またその様相も随所に出ているが、そのことを認めたうえで、断固として仏法の機能を確信するべきだと言う。また、このような時代の人々には誰が賢者で誰が愚者であるかは見きわめられないのであって、優れた逸材がいても気がつかれにくいものなのだから、そんなことで落胆せずに、王たる者は王法を確信し、仏教者はしっかり仏法を見つめていればそれでいい、そう説くのである。
私はこの問答を思い出すと、少し心が鎮まってくる。自分の中に住む憂国公子の苛立ちも、多少はおさまってくる。そして、あらためて空海の偉大を味わうことになる。
さすがに空海はこの国に密教を適用するにあたって、透徹した見方をもっていた。すでに中国の歴史は、不空「密教ナショナリズム」と一行の「密教タオイズム」と恵果の「密教インターナショナリズム」ともいうべきを生んでいたが、空海はそのいずれでもあって、そのいずれでもない独自の密教を、日本という国に定着させるための構想をもっていたのだったろう。それぞれ一長一短はあるが、空海はそれらをこの国に適合させる「編集」が必要だと考えたのだった。
たとえば、唐では天文暦法の管轄部署と陰陽卜占の管轄部署は別である。前者は学術、後者は呪術であった。それが日本では一緒になっている。この混合習合感覚が「日本という編集」なのである。これが最澄にはわかりにくく、空海にはよく見えていた。諸国の関渡津泊を跋渉し、諸国の僧俗貴賎と接触してきたからであったろう。だからそこ空海は、憂国公子の焦燥と短慮を諄々と冷やすこともできたのである。
さて、世紀末の現在というに、八世紀末にもまして二十世紀末の日本はいかにも淀んでいる。その心も荒んでいると思われる。国の為政者にも、家の父親にも、学校の教育者にも、会社のリーダーにも、いずれにも新たな展望も哲学はなく、宗教にもほとんど力がなくなっている。とりわけ宗教界はオウム真理教事件の余波を受けたまま、いまだいっさいの発言を控えたままの現状にある。この気味の悪いほどの沈黙が、玄関法師に身をやつした空海が『秘蔵宝鑰』に勧めた「焦燥の克服」と同種のものであればいいのたが、どうもそんな上等のものでもないようにも見える。いったい、いま密教は何を考えるべきで、何をするべきなのだろうか。私にはそんな解答はないけれど、以下、最近になって思いついていることを綴っておこうと思う。
【2】
空海や密教の思想を、現代のわれわれが負うべきさまざまな課題に近づけて語るということは、一九七〇年代くらいから再三にわたって試みられている。ときには密教ブームなどという言葉もつかわれた。しかし、私が見ているかぎりは、その試みは現代の課題の広がりが多様多彩で、しかもけっこう深刻なわりには、あまり多様でもなく、また深々ともしていなかった。理由はよくわからないが、おそらくは今日の密教者がもともと暢気なのか、それとも怠慢だったからなのだろう。
たとえば、今日では「複雑性」とか「複雑系」という概念が科学の領域や経済社会の領域でさかんにつかわれるようになっているが、ではこのような動向に対して、本来はきわめて高度な複雑性をもっているはずの密教の立場から、今日の複雑なシステムについての理解や共感の声が上っているかといえば、そうとは思えない。
しかし、複雑系の特徴のひとつは、ある系から出た効果がふたたびその系の本体に自己代入的にフィードバックされることによっておこる特徴としてあらわれるのであるが、これは密教思想の一部の特徴とすこぶる近似していたりするのである。すなわち、わかりやすい例でいうなら、空海密教は『十住心論』や『秘蔵宝鑰』がそうであるように、低次の情報編集体験を次々により高次の情報編集体験に自己代入することによって獲得されていくプロセスの自覚にあるのだから、ここには複雑系に似たフィードバック・システムが活用されていると見るべきなのだし、また秘密金剛心とか密厳荘厳心としか名付けえないマンダラ・ステートは、いわば複雑性の極みともいうべきものなのである。が、そのような関心で今日の「複雑さの時代」を凝視しようとしている人々は、残念ながらあまりいないように思われる。
そもそも、このような科学の動向と密教が関係があるかもしれないという判断すら、なかなか成り立っていないように見える。なぜそんなふうになるかというと、密教は古代に成立したもので、その後の発展があったとはいえ、その内実の大半は宗教的なものだから、とうてい科学などと交差するはずがないという頑迷な見方が固定してしまっているからなのだろう。
けれども、たとえばの話、「意識の科学」という一条の光をそこにあててみさえすれば、密教と脳科学はたちまち結びつき、認知科学と六派哲学や唯識論はたちまち交錯し、『即身成仏義』はマーヴィン・ミンスキーの『心の社会』やダニエル・デネットの『志向姿勢の科学』と連携するはずなのである。誰かがちょっと勇気をもって「密教は意識の科学でもあろう」と言いさえすれば、いろいろな事は始まるはずなのだ。
実際にも、このような提案はカリフォルニアに育ったニューエイジ・サイエンスによっていろいろ試みられてきた。それこそ一九七〇年代の頃である。しかし、このような試みにその当時対応した仏教者や仏教研究者は、私の知るかぎりは鎌田茂雄さんと秋月龍治さんくらいのものだった。その後ずいぶんたって、たとえば玉城康四郎さんの『脳幹と解脱』のような試みが世に出たが、私の印象では、それは「ダンマの思惟」としては「速迅の意識」を描いてすばらしいものではあったのだが、科学の言葉を使っておられる部分のすべては、いまひとつ「科学のダンマ」にはなっていないように思われた。いま、仏教者はあらためて、メイナード・スミスの『進化する階層』やジェラルド・エーデルマンの『脳から心へ』などを、クリスチャン・ド・デューブの『生命の塵』やフランシス・クリックの『DNAに魂はあるか』などを、虚心坦懐に読むべきなのだ。ここに思いつくまま挙げた四人のうち三人はノーベル賞科学者であるが、そこに綴られているのは、まさに仏教であり、密教であり、二十一世紀のための思索なのである。
もちろん、いくばくかの同情がないわけでもない。それは、密教学というものが、大村西崖の初期の努力などがあったにもかかわらず、明治このかたいまひとつ高揚できず、それこそ戦後になってからやっと本格的に取り組まれたために、ちょうど密教ブームがおこった一九七〇年代あたりからやっと詳細な細部が日本の密教者の前に立ち表れはじめ、それを凝視すること自体がそれなりに興奮すべきことだったからである。それまではチベット密教の実態すらほとんどつかめていなかったし、ヨーロッパの密教研究の成果も充分に導入されていなかったのである。実際にも、私が吉岡義豊さんに勧められて那須政隆さんを訪れたのはたしか一九七一年の秋であったと思うが、そのとき那須さんは眼を細めて、「あなたはいい時期に密教に直面することになりましたね。密教学はこれからやっと本格的な時代を迎えるのですよ」と言われたものだ。
このような事情もあるので、いちがいに今日の密教状況の情熱の疎密を語ることはできないのだが、しかし仮にも「言語学と密教」というような問題ならば、これこそ空海の言語思想としっかり重なるところなのだから、いまごろはとっくに「密教言語思想体系」あるいは「空海言語哲学」ともいうべきプログラムが巷の識者も覆い尽くし、ソシュールやヴィトゲンシュタインや、あるいはチョムスキーやバフチン以上に論議されるところとなっていてもおかしくなかったのである。とくに井筒俊彦さんが密教に手をさしのべられていれば、それだけでもずいぶん様相は変わったと偲ばれる。空海の「知」をもっと世界に知らせたいと思っている私としては、そこがやはり残念なことである。
【3】
では、なぜ密教思想や空海哲学は現代に赫然として蘇らないのだろうか。あるいはすでに蘇っているのだとするなら、なぜダイナミックな波及力をもたないだろうか。この原因の大半はおそらく今日の仏教者や密教者が負うべきで、日本に数万人もいる密教僧が立ち上がりさえすれば、あっというまに事態は変わるのだと思われる。あるいはたとえば"密教のJリーグ"ともいうべきをつくりさえすれば、事態は大きく変化するかと思われる。しかし、それはまだまだ興りそうもない。それに悪いことに、現在の日本という国は、宗教者の活動や主張が強すぎることをまったく望んでいないという事情もあった。
そうなると、ちょっと別の視点から、密教思想や空海哲学の二十一世紀的な活用を考える必要があるということになる。が、このことは私の気持ちからすれば、実は十四年前に書いた『空海の夢』でそれなりに提案してあったことなのである。それを読んでもらえば、多少は密教思想と空海哲学の「知」の未来化のヒントがどこにあるか、わかってもらえるはずだった。ただし、私の考えも文章も当時はかなり未熟だったから、わかりにくいところも多いにちがいなく、いずれこれらを再編し、さらに説得力のる提案に書き換えるべきなのであろうとも思われる。それこそまさに、私自身の憂国公子にとどまっていてはならないということなのだろう。
それはともかくとして、来たるべき二十一世紀のために、いま私がなんとか事態をまにあわせるべく準備できそうなことは、少なくとも二つの視点から空海密教の特色を明示しておくことではないかと思っている。二つの視点というのは、ひとつは空海密教がとびぬけて優れた「編集の思想」であるということで、もうひとつは、その「編集の思想」は華厳を母体に考えぬかれた「編集の方法」によっていたということである。ここでは、ごく簡単なことだけ書いておく。
空海の「知」は類い稀れな「編集の知」というものである。若い時期はこれを阿刀大足や味酒浄成から学んだであろうが、もっと深くは鄭玄や沈約などの文献から学んだであろう。その驚くべき編集能力はすでに『三教指帰』にたっぷりあらわれている。
このような知の持ち主は、ヨーロッパにも、たとえばベーコンとかヴィーコとかホワイトヘッドとか、あるいはイタリア・ルネッサンスを構築したマルシリオ・フィチーノとかバロックの王者ロバート・フラッドとか、それなりに錚々たる編集知の持ち主がいるのだが、なんといっても八世紀の段階で壮大な編集知を構想したという点では空海は他者との比類のしようがないほどで、それに加えて東洋の知を徹底的に編集してみせたという点で、ナーガールジュナ(龍樹)やヴァスバンドゥ(世親)にもまったく手が出せないものだった。
ただし、当初の空海の編集力をもってしても、気になる手ごわい相手があった。空海にとっての未知の領域が控えていた。それは、ひとつは『大日経』に代表される密教思想である。もうひとつは、華厳の法蔵や澄観が青年空海の前を全速力で進んでいたと見えたことである。空海はこれに追いつき、これを追い越すことを考えた。
空海密教が法蔵や澄観の華厳思想を母体としていることは、誰もが知っていることであるはずなのに、あまり十全に議論されてはいない。私はそのことが気になって『空海の夢』の第二六章に「華厳から密教に出る」というささやかな解読を試みておいたのだが、宮坂宥勝さんと鎌田茂雄さんと井筒俊彦さんをのぞいては、とくに関心を払う人には出会えなかった。しかし、この点がわからないかぎり、空海密教の本質はまったく語れない。とくに空海密教が編集思想であることがわからない。それにはまず、空海が長安にいるときに華厳僧たちがどれほど活躍していたかということを一瞥しておく必要がある。長安の空海の日々は華厳の理解に多くの時間をさいていたのだが、どうもこのことが見えない人が多すぎるからである。
空海が長安に入ったのは三一歳のときだった。西明寺に入ってみると、すでに三十年前からそこにいる日本僧永忠が華厳にやたらに詳しいことに驚いた。聞けば、カシミール僧の般若三蔵という老僧が六年前に『四十華厳』を漢訳したばかりだという。そこで空海は醴泉寺にいた般若三蔵のところに通う。また、宗密というすこぶる鋭利な華厳僧がいて、すでに新たな宗教人間哲学ともいうべき『原人論』を綴ったという。宗密は空海のわずか四歳年上の者だった。空海はこれらの人々の成果を懸命に学習しつつ、その淵源が澄観という華厳の大立者に発していることを知る。
その澄観は六六歳になっていた。のちの華厳宗第四祖である。もともとは五台山清涼寺が本拠であるが、このころは長安の崇福寺に止宿しつづけていた。いろいろ尋ねれば、この澄観の影響指導下にいたのが般若三歳であることもわかってきた。実際にも『四十華厳』漢訳本の巻末には「太原府崇福寺沙門澄観評定」の記載が見える。香象大師澄観に認定してもらったのだった。
このような日々をおくりつつ、空海は澄観から出た宗密が新しい宗教哲学を創造しようとしているのに愕然となり、これに勝る宗教哲学を構想しようとしたはずである。構想の母体は華厳思想におくしかないようにおもわれた。それほど華厳思想はすばらしい出来栄えになっていた。が、その脱出口はどこなのか。どうやら宗密は華厳から禅の方向に転出しようとしているらしい。空海はその方向を採用したいとは思わない。むしろ新たな密教動向に賭けたいと決意する。それこそが恵果の金胎両部のマンダラ密教哲学だった。空海は華厳と密教をまったく新しく統合編集してしまうことに賭けたのである。
すでに華厳宗派は第一祖の杜順と第二祖の智儼の後、第三祖の法蔵がきわめて雄大な構想をつくっていた。ここで華厳思想を要約するのはとうてい不可能であるが、わかりやすい成果をひとつだけあげるとすれば、法蔵は、当時は声聞・縁覚・菩薩の三乗思想にこだわっていた仏教界に対して、華厳別教の一乗思想を確立して"業界思想"を止揚するとともに、そこに「該説門」という思索を吸収する新編集概念を提案することによって、はやくも空観と唯識の両思想を華厳思想に吸収してしまっていたのである。それだけではなかった。法蔵は『探玄記』という著書に、のちに澄観の心をも空海の心をも捉える「十重唯識」(十玄)という卓越した構想を発表し、人間意識のスペクトルの最高段階を「帝網無礙」という境地で言いあらわしていたのである。
すでにおわかりのように、これこそは空海が『即身成仏義』の偈において「重重帝網なるを即身と名づく」と綴った"ルーツ"にほかならない。すなわち空海は、こうした法蔵を頂点とする華厳十玄思想があることを知り、これを密教の方向に軌道展開させながら統合編集しようとしたのであった。二十年ほど前のことになるが、私は『弁顕密二教論』に「密厳華厳」という造語があったことにぶつかって、そうか、空海のルーツは華厳だったのか、と思ったものである。
【4】
二十世紀は、多くのことを発明しながらも、その成果を回収しきれなかった世紀である。戦争や飢餓や疾病が解決できなかったことを言っているのではない。そのような問題はおそらく二十一世紀の半ば近くまで持ち越されるにちがいない。そこまで二十世紀人類の努力は届いてはいない。
そうではなく、この一〇〇年間の二十世紀が到達した英知、たとえば相対性理論や量子力学、分子生物学や精神医学、言語思想や文化人類学などに見られる英知を、どのように一般化し、どのように活用したらいいのか、そのような自分たちが創りあげた思想成果の活用にすら、ほとんど手がまわらなかったのである。もっと端的に言うのなら、われわれは自分たちが創りあげた極上の思想さえ咀嚼できない自己思想の砦にとどまったまま、二十一世紀を迎えるのである。
むろんいくつかの試みはあった。たとえばフランスに興ったディコンストラクション(脱構築)の動向である。またポストモダンの動向である。あるいは脱工業思想や「イデオロギーや知識人は終焉した」という宣言もそうした試みのひとつだった。「歴史の終わり」という観点を持ち出した試みもあった。しかし、これらはおおむね流産していった。なかでは「成長の限界」を認識できたことや環境破壊の脅威を認識できたことが大きな成果であったが、それとても新しいプログラムを組み立てることまでは進めなかった。むしろ明確な英知の形をとることなく勃興したヒッピー運動やエコロジー運動やボランティア運動などが、かえって何かのヒントをもたらしているのかもしれない。
しかし、もうひとつ大きな問題が積み残されている。それは、二十世紀以前の英知をどのように取り扱ったらよいかという問題だ。その最大な成果が宗教や論理や生死の哲学である。これらは現状では、もはや英知ではなく、ただの習慣や記憶になってしまったのだろうか。
以上のことを重ねて言えば、われわれはいま、これらのすべてを統合し、編集する責任をもっているということである。むろん不要なものがあるならば切り捨ててしまってもよいだろう。また、仮設作業や理論構築が半ばのものがあるのならば(これはすいぶんたくさんあるが)、これをどの方向に展開させるかを勇気をもって決定しなければならないだろう。クローン技術や廃棄物処理技術はそのような岐路に立っている。いずれにしても、われわれは自分たちの前に放置された英知と技術のいっさいを検討し、あらためて編集しなければならないはずなのだ。
だが、その方法が見えてはいない。というよりも、それぞれの成果は別々の方法で獲得できたと思いこみすぎているままなのである。
しかしながらよくよく観察してみれば、実は多くの成果の奥には、これらを連携させ、相互に関係させうる共通の方法がひそんでいるはずである。また共有構造もひそんでいるはずである。私はそのような視点で過去と現在の成果を通暁してみる方法を「編集の方法」と呼んでいる。編集とは「別々のものを出会わせる」ということであり、「お互いにひそむ関係を発見する」ということである。
そしてこのとき、空海の方法が忽然と蘇るのだ。空海の編集思想と編集方法は、ひとり古代密教の蔵にしまいこまれたものではなく、二十一世紀の扉を開くものとして、ここに蘇るべきものなのである。おそらく、そのように空海の方法が蘇るには、たとえばソクラテスやプラトンや大乗仏典が開発した「対話の方法」や、玄奘や道元やダンテやヴィーコが発見した「翻案の方法」や、そのほかいろいろの方法が一緒に蘇るはずである。なぜなら、編集は、空海密教がまさにそうであったように、どんな思想や英知をも"即身"させるものであるからだ。