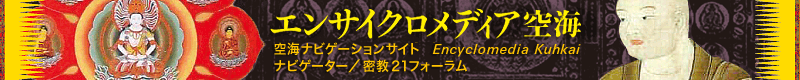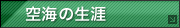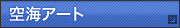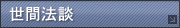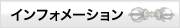齋藤保高(チベット仏教普及協会事務局長)
【前伝期】
チベットへ仏教が最初に伝来したのは、七世紀の中頃だといいます。その当時のチベット(中国側の史料でいう吐蕃)は、英主ソンツェン・ガムポ王のもとで、強大な国に成長していました。唐から迎えた文成公主とネパールから迎えたブリクティーという、二人の王妃が本国から仏像を招来したのが、チベットの仏教の起源だと考えられています。このとき文成公主がもたらした釈迦牟尼像は、「チョヲ・リンポチェ」といい、今でもラサのチョカン寺の本尊として篤く信仰されています。
ソンツェン・ガムポ王は、側近のトゥンミ・サムボータをインドへ派遣し、サンスクリット語を学ばせました。トゥンミ・サムボータは、インドのグプタ文字をもとにチベット文字を考案し、チベット語文法を整理したといいます。これによって、仏教の聖典をチベット語に翻訳する素地ができたといえるでしょう。
またソンツェン・ガムポ王は、十善戒をもとにして、「十六条憲法」を制定しました。日本史に於ける聖徳太子のような役割りを果たした王だったといえるかもしれません。
より本格的に仏教が伝来したのは、八世紀後半のティソン・デツェン王のときです。王は、インドからナーランダ寺の長老シャーンタラクシタを招聘し、その助言で密教成就者パドマサンバヴァも招いて土着の神々を調伏させ、最初の大僧院となるサムイェー寺を建立しました。そこへ優秀な青年たちを集め、シャーンタラクシタが根本説一切有部の比丘戒を授け、チベット人の出家僧侶が初めて誕生したのです。
その当時、チベットが敦煌を領有していたため、禅を中心とする中国系の仏教も、次第にチベットへ広まってきました。しかしその教えは、インド伝来の大乗仏教とは矛盾する点が多かったようです。そこで王は、サムイェー寺で御前問答を行なって決着をつけるように命じ、シャーンタラクシタの弟子であるカマラシーラが中国禅の摩訶衍和尚を論破したといいます。それゆえ、以後のチベット仏教は、教理・実践の両面でインド大乗仏教を範とすることになりました。カマラシーラが説いた『修習次第』は、大乗の止観を実修する指針として、チベット仏教で大変重視されています。
ティソン・デツェン王は仏教を国教と定め、極めて厚く保護しました。それから九世紀前半のティ・レルパチェン王の時代にかけて、経・律・論の三蔵の翻訳が国策として推進されたことは、特に注目すべき史実です。翻訳は、インドから招いた学僧とチベット人の訳経僧がペアになって取り組み、統一された訳語基準に従って厳密に行なわれました。そのため、「チベット大蔵教」収録の経論は、サンスクリット語に還元できるほどの正確な直訳で、今日の仏教学界にも貴重な資料を提供している点は周知のとおりです。
後世、ソンツェン・ガムポ王は観自在菩薩、ティソン・デツェン王は文殊菩薩、ティ・レルパチェン王は金剛手菩薩の化身として崇敬されるようになりました。これらの三菩薩は順に、諸仏の慈悲・智慧・威力の体現で、蓮華部・仏部・金剛部の主尊とされています。
このように王家が施主となって急速に弘通した仏教も、九世紀中頃の王朝分裂によって衰退したといいます。
【後伝期】
しかしやがて、西チベットから仏教復興の動きが活発化しました。その中心となったのが、訳経師のリンチェン・サンポです。リンチェン・サンポは、重要聖典の翻訳を数多く手がけ、『金剛頂経初会』や『秘密集会タントラ』なども訳しています。
十一世紀中頃、西チベットの王家がインド後期密教の総本山ヴィクラマシーラ寺からアティーシャを招き、これが契機となってチベットの仏教は完全に復興を遂げます。アティーシャは『菩提道灯論』を説き、小乗・大乗・密教という三重構造の修行体系を確立しました。この体系を「ラムリム(道次第)」といい、以後のチベット仏教の主潮流となります。
中興祖師アティーシャの教えは、弟子のドムトゥンらに継承されてゆきますが、この宗門をカダム派といいます。カダム派の実践面での特色は、「ラムリム」と「ロジョン(心の修練)」です。後者は、自己中心的な精神状態を大乗仏教の利他心へ転換してゆく秘訣で、インドの聖者シャーンティデーヴァが説いた『入菩薩行論』をもとにしています。思想面では、仏教論理学や中観哲学の学修・研究が、カダム派の系統のサンプ寺で盛んに行なわれました。こうした特色はいずれも、後世のゲルク派に継承されてゆきます。
この時代には、マルパ訳経師のように、インドへ留学に赴くチベット人も数多く出ました。マルパの一番弟子が、密教の聖者として有名なミラレーパです。ミラレーパの弟子にあたるガムポパが創始した宗門を、カギュー派といいます。カギュー派は後に分派しますが、その中ではカルマ派、ドゥク派、ティグン派などが現在でも有力です。カギュー派に伝わる密教としては、「ナーローの六法」などがよく知られています。これは、マルパの師にあたるインドの成就者ナーローパが、『ヘーヴァジュラ・タントラ』、『秘密集会タントラ』、「チャクラサンヴァラ」系の諸タントラの所説をもとにまとめた行法の秘訣です。
もう一つ重要な宗門は、サキャ派です。在家密教行者の氏族宗団から発展し、十二〜十三世紀頃には、サキャ・パンディタなど優れた学僧が輩出するようになりました。そのときチベットは、モンゴル帝国の脅威に直面していましたが、サキャ・パンディタが和平交渉に赴き、モンゴル側を仏教に教化したといいます。これによって、国土がモンゴル騎兵の馬蹄に蹂躙される危機を免れたのみならず、チベット仏教がアジア大陸の広範な地域へ広まる端緒となったのです。
ところでこの時期、インド仏教は急速に衰退への道を辿り、十三世紀初頭にはイスラム教徒の襲来によって、総本山ヴィクラマシーラ寺も破壊されてしまいます。最後の座主シャーキャシュリーバドラは、この法難を逃れてヒマラヤを越え、釈尊以来インドの仏教僧伽が連綿と伝えてきた法灯を、チベットの僧侶たちに託しました。この象徴的な史実からも明らかなとおり、チベットの仏教界に「インド仏教の嫡流」という自負があるのは、決して無根拠の宣伝文句ではありません。
カダム派、カギュー派、サキャ派など、リンチェン・サンポ以降に伝来した密教を自らの教義体系の中心に据えている宗門を、総称してサルマ(新義)派といいます。これに対して、パドマサンバヴァの時代に伝来した密教を中心に据えている宗門を、ニンマ(古義)派といいます。ニンマ派の教義体系は、十四世紀の学僧ロンチェンパによって集大成されました。ニンマ派には「九乗」という独特の教相範釈があり、その頂点に位置づけられるのが「ゾクチェン」です。
【ゲルク派の開宗】
インド仏教の滅亡で法流の伝来が途絶えると、チベットの仏教界では、これまでに受容してきた様々な教えを整理し、教理と実践の体系を再構築しようという動きが盛んになります。これを、主に文献の面から行なったのが、十四世紀の学僧プトゥンです。プトゥンは、仏教史を「大蔵経」の目録とともにまとめ、密教経典を所作・行・瑜伽・無上瑜伽という「四部タントラ」に段階づけて整理しました。これを日本の密教と対比すれば、所作タントラは『蘇悉地経』や様々な雑密経典、行タントラは『大日経』、瑜伽タントラは『金剛頂経初会』や『理趣経』ということになり、無上瑜伽タントラは実践的な伝統としては日本へ伝わっていません。プトゥンは、無上瑜伽タントラの中でも『カーラチャクラ・タントラ』を最高の教えと位置づけ、その多岐に渡る学問体系に注釈を施しました。
このようにして諸聖典の整理が進展した十四世紀後半に、ゲルク派の宗祖ツォンカパ大師が登場します。ツォンカパは、主にサキャ派のレンダワに師事しながら、カダム派やカギュー派の教えも巾広く学修し、プトゥンの弟子たちからも密教の伝授を受けました。また、ウマパという師を介して、文殊菩薩から直接に中観と密教の奥義を授かったといいます。
ツォンカパの主著は、『菩提道次第広論(ラムリム・チェンモ)』です。これは、アティーシャによって確立された「ラムリム」を集大成したもので、三段階の人士の修行を説いています。下品の修行は、来世にも仏法と縁のある境遇を得るためのもので、「十善戒」などが相当します。中品の修行は、輪廻からの解脱を目指すもので、小乗仏教の実践内容にあたります。上品の修行は、一切衆生のために成仏を目指すもので、大乗仏教の実践内容に相当します。しかしこの三者は、一人の修行者が段階的に実践するための位置づけです。上品の最後には、止観についての広大な解説があり、観の内容として中観帰謬論証派の見解を詳細に考察しています。
ツォンカパのもう一つの主著は、『真言道次第広論(ガクリム・チェンモ)』です。これは、「四部タントラ」を順に解説したもので、密教を体系的に学ぶために欠かせない大論書です。その中で、日本密教の中心となる行タントラと瑜伽タントラに関していえば、前者はブッダグヒヤの註釈、後者はブッダグヒヤ、シャーキャミトラ、アーナンダガルバの註釈に基づいて論議を展開しています。このため、善無畏三蔵や不空金剛の解釈に基づく日本密教と、少し異なった側面からの説明になっているかもしれません。特に『金剛頂経初会』は、金剛界品だけでなく四大品に続タントラを加えた広本が所依となっている点で、様々な特色があるように思います。
無上瑜伽タントラに関しては、『秘密集会タントラ』をあらゆる仏法の頂点に位置づけ、それを『チャクラサンヴァラ略タントラ』で補うという行法体系です。この両大法にツォンカパ自身の守護尊である「ヤマーンタカ(大威徳明王)」を加えた「三大本尊」が、ゲルク派密教の核心となっています。プトゥンが最重視した『カーラチャクラ・タントラ』は、後のダライ・ラマ政権の時代になってから、鎮護国家や世界平和など社会的な側面が強調されるようになりました。
この顕密の二大主著の内容を合わせれば、前にアティーシャのときに述べたとおり、小乗・大乗・密教という三重構造の体系になります。これを、一人の修行者が矛盾なく実践するため、チベットでは「外面の所作は小乗、内面の心は大乗、秘密の行は密教」というスタイルが理想的だと考えらえています。つまり、社会的には出家・在家それぞれの立場で戒律を守って役割分担し、精神面では慈悲と菩提心を訓練しつつ空性と縁起の教えに理解を深め、修行の核心としては密教の本尊瑜伽を人知れず実践するということです。
このように、ツォンカパの事績として最も重要なポイントは、八世紀後半から十三世紀初頭にかけてインドから受容した顕教と密教の総合体系を、内容面から深く吟味して明確な形で整理・再構成したことだといえるでしょう。まさにツォンカパという偉大な聖者が出現したからこそ、チベット仏教は、「インド仏教の後継者」としての地位を名実ともに確固たるものとなし得たのです。ツォンカパの事績で外面的に一番目立ったのは、戒律の復興です。ツォンカパと弟子たちが、比丘の具足戒を厳格に守った生活を貫き、真摯に学問と修行に励んでいる姿は、多くの在家信者に深い感銘を与えました。それで、有力な施主が次々と集まるようになり、ツォンカパの宗団は急速に教勢を広げました。これが、ゲルク派の始まりです。アティーシャの伝統を護持するカダム派もゲルク派に合流したので、今日では、ニンマ派、カギュー派、サキャ派、ゲルク派が、チベット仏教の「四大宗派」と呼ばれています。その中でも、ゲルク派が最大の勢力となっており、僧侶の人数では圧倒的多数を占めています。
一四○九年、ツォンカパは、ラサのチョカン寺で「祈願大祭(ムンラム・チェンモ)」の大法要を厳修しました。このとき、本尊の釈迦牟尼像を宝冠などの装身具で荘厳したので、今日拝観できるチョヲ・リンポチェは、無上瑜伽タントラの根本仏たる大持金剛のお姿となっています。これは、釈尊と大持金剛の一心同体性を表現した教えだと解釈できます。
ちょうどその頃、ツォンカパは弟子や施主たちと力を合わせ、ラサ東方の山稜にガンデン寺を建立しました。その少し後に、弟子たちの手で、ラサ近郊の山麓にセラ寺とデプン寺も建立されました。今日この三箇寺は、「ゲルク派三大本山」と並び称されています。これにシガツェのタシールンポ寺を加えれば「四大本山」、東北チベットのクンブム寺とラプラン・タシーキル寺を加えれば「六大本山」となります。それ以外で主なゲルク派の僧院としては、密教の最高学府のギュメー寺とギュトゥー寺が、ラサの市内にあります。また、ラサのポタラ宮の中には、ダライ・ラマ法王直属のナムギェル寺がありました(タシールンポ寺以下は、全てツォンカパ没後の建立ですが、ゲルク派の主要僧院をまとめて紹介するという意味で、ここでは並列的に記載しました)。
【ダライ・ラマ】
ツォンカパのもとには優れた弟子が数多く集まり、その中でも特に傑出していたのが、ギャルツァプ・ジェとケートゥプ・ジェの二大弟子です。ゲルク派の寺院ならばどこでも、ツォンカパ大師と二大弟子の像が、三尊形式で安置されています。それ以外の弟子では、ツォンカパ自身の甥だとも言われているゲドゥン・トゥプパが、特に有名です。彼は後世になってから、「ダライ・ラマ一世」と諡号されています。
晩年のツォンカパは、ガンデン寺で顕密の様々な教えを説き、一四一九年に示寂しました。ツォンカパに後事を託された一番弟子のギャルツァプ・ジェが、長老たちからも推挙されて、第二世ガンデン座主となりました。第三世は、ケートゥプ・ジェです。以後、このガンデン座主の地位は、最も学徳の優れた長老たちの間で師資相承され、今日の第百一世に至っています。ガンデン座主は、宗祖ツォンカパ大師の後継者としてゲルク派を指導する管長職であり、後にダライ・ラマ政権の時代になっても、ゲルク派の管長がガンデン座主である点は何ら変わりありません(ちなみに、第百世ガンデン座主ロサン・ニマ猊下は、チベット仏教普及協会の招聘で二度来日され、「秘密集会」や「チャクラサンヴァラ」の大灌頂をお授けになりました。チベット人社会の民間伝承では、第百世ガンデン座主には、ツォンカパ大師御自身がおなりになると言われています。猊下は昨年九月に示寂され、その際に無上瑜伽タントラの即身成仏の相をお見せになり、インドと欧米の医師や科学者たちもその経過を観察しています。第百世ガンデン座主については、『大法輪』誌二月号に拙稿「チベットの偉大な宗祖の後継者」が掲載されているので、よろしかったら御参照なさってみてください)。
仏教の宗団や寺院に於ける指導者の継承は、一般論として、この師資相承が最もオーソドックスな方法でしょう。しかしチベットでは、他にも色々なやり方があります。氏族宗団の場合、在家行者なら世襲、出家僧なら甥が継承します。そして一番有名なのが、チベット独特の転生活仏制度です。これは、亡くなった前任者の弟子や施主たちが、その転生霊童を探して教育するという方法で、制度としてはカルマ派が最初に始めました。後に、ゲルク派もこれに倣い、ダライ・ラマやパンチェン・ラマを始めとして、転生活仏制度による継承が数多く行なわれるようになりました。そのような中でも、ガンデン座主以下、三大本山各学堂の僧院長、ギュメー寺やギュトゥー寺の僧院長は、いずれも師資相承の原則が守られてきました。それゆえゲルク派では、生まれなどに一切関係なく、誰でも本人の資質と努力次第で、一介の僧侶から大本山の僧院長やガンデン座主にまでなれる機会が開かれていたと言えるでしょう。
ツォンカパ没後のゲルク派は、カルマ派との勢力争いに巻き込まれてしまいます。これは、僧侶どうしの対立というよりも、それぞれの有力施主どうしの争いだと言った方が適切かもしれません。初期ゲルク派の長老たちは、俗事に疎い「仏教一筋」というタイプが多かったようですが、その中でデプン寺の高僧ゲドゥン・ギャツォは、施主層の心をつかんで支持を集めるのに巧みで、教勢の維持・拡大によく貢献したといいます。彼は、ゲドゥン・トゥプパの転生だと言われていたようですが、それは転生活仏制度のもとで積極的に探し出されたわけではありません。しかし彼の没後には、施主層の支持をつなぎとめるためにも、積極的にその転生霊童を探そうという動きになったようです。そうした経緯で迎えられた転生霊童は、スーナム・ギャツォと名付けられ、デプン寺でパンチェン・スーナム・タクパなどの碩学から英才教育を受けました。
一五七七年、スーナム・ギャツォはトゥメト部の首長アルタン・ハーンに招かれ、モンゴル諸部を巡錫しました。この布教は大成功を収め、それ以来モンゴルの仏教界は、ほぼゲルク派一色の様相を呈しています。アルタン・ハーンは、説法を聴聞して信心を深め、スーナム・ギャツォに「ダライ・ラマ(大海の如き師)」という尊称を献じました。これが、ダライ・ラマの始まりです。それで、ツォンカパの直弟子であるゲドゥン・トゥプパがダライ・ラマ一世、その転生と言われたゲドゥン・ギャツォがダライ・ラマ二世と諡号され、スーナム・ギャツォはダライ・ラマ三世とされたのです。以後は、明確に制度化された転生活仏として、先代ダライ・ラマの没後に、側近の弟子たちが懸命に転生霊童を探すようになりました。
このようなわけなので、「転生活仏」という制度は、確かにチベット仏教独特の習慣として世界中で有名ですが、そのときどきの社会的な要請に応じて行なわれてきたにすぎません。チベットの知識人たちも、それが自らの社会の尊重すべき宗教的伝統だと思っているかもしれませんが、仏教の本質的な要素として不可欠なものだとは考えていないはずです。ただ、転生活仏の中でもダライ・ラマに限っていえば、これから述べるように「チベットの政教両面の最高指導者」という立場になった関係で、他の転生活仏と同列に考えることはできません。
【ガンデン・ポタン政権の成立】
ゲルク派とカルマ派の勢力争いは、二代後のダライ・ラマ五世の時代に決着します。一六四二年、東北チベットを勢力圏とするモンゴルのホシュート部の首長グシ・ハーンがチベット全土を平定し、その政治的支配権をダライ・ラマ五世に献上したのです。これにより、「ガンデン・ポタン」と呼ばれるダライ・ラマ政権が誕生しました。この体制は基本的に、今日のチベット亡命政権に至るまで継続しています。それ以来、ダライ・ラマの地位は、ゲルク派という宗派の枠を越え、チベット全体の政教両面の最高指導者となったのです。
政治面では、チベットの国家元首であり、全土を統一したガンデン・ポタン政権の最高指導者という位置づけです。ここでいうチベット全土とは、中央チベット(現在の中国政府がいう「チベット自治区」の大半)、東チベット(「チベット自治区」の東部と四川省の西部、雲南省の一部)、東北チベット(青海省の大半と甘粛省の西部)を合わせた領域です。今日でも、チベット人たちが「自国の領域」と考えているのは、いわゆる「チベット自治区」だけでなく、この三地方の全体です。
宗教面では、前に述べた仏教の四大宗派に民俗宗教のポン教を加えた五つの宗門を統括する最高指導者という位置づけです。この時代、チベット仏教はモンゴル諸部や清朝の篤い帰依を受け、アジア大陸の実に広範な地域へ広まっていました。それゆえ、ダライ・ラマ法王の宗教面での強い影響力は、単にチベットのみならず、この途方もなく広い範囲に及んでいたのです。
一六五九年、ラサのポタラ宮を大規模に拡張する工事がほぼ完了し、ダライ・ラマ五世法王は、デプン寺からポタラ宮へ居を移しました。古代王朝の分裂以来、再びチベット全土の統一政権が打ち立てられたことを、まさに象徴する出来事だといえます。これ以後十八世紀頃までは、「チベット仏教の全盛期」と形容するのにふさわしい時代です。前に述べたように、アジア大陸の広大な範囲にチベット仏教が弘通し、ラサの三大本山には、チベット各地のみならずモンゴル諸部や清朝やヒマラヤ地域などから僧侶が参集し、学問と修行に励んでいました。ガンデン寺は五千五百人、セラ寺は七千七百人、デプン寺は九千九百人の僧侶を擁すると公称されていましたが、実数はそれよりも多かったようです。聖都ラサは、当時のアジア大陸に於ける、宗教と文化の一大中心地だったのです。
【パンチェン・ラマ】
ここで、「ダライ・ラマに次ぐ第二の高僧」とよく言われるパンチェン・ラマについて、少し触れておきましょう。ダライ・ラマとパンチェン・ラマの関係を正しく理解するためには、チベット仏教に於ける師弟関係の重要性を認識する必要があります。もとよりチベットに限らず、仏教全般、中でも密教の法を学修するためには、師の存在が極めて重要です。この点は、恵果阿闍梨と弘法大師の師弟関係からも、明らかだと思います。
チベットの宗教界全体の頂点に君臨するダライ・ラマ法王も、自分自身の師に対しては、仏法僧の三宝を一身に体現する帰依處として恭敬しなければなりません。ダライ・ラマ五世法王の第一の師は、タシールンポ寺のロサン・チューキ・ギェルツェンでした。彼は、以前にダライ・ラマ四世法王の師も務め、「パンチェン(大学僧)」と尊称されていた名僧です。一六六二年、このロサン・チューキ・ギェルツェンが示寂したとき、ダライ・ラマ五世は、恩師に対する追慕の念から、転生霊童を探すように命じました。このようにして、パンチェン・ラマ転生活仏制度が始まり、ロサン・チューキ・ギェルツェンはパンチェン・ラマ一世とされたのです(ただ、チューキ・ギェルツェンはもともとヱンサパという密教聖者の転生と言われており、さらに二生遡るとツォンカパ大師の高弟ケートゥプ・ジェになると考えられていました。それで、ケートゥプ・ジェを「パンチェン・ラマ一世」として諡号し、チューキ・ギェルツェンを四世とする数え方もあります)。パンチェン・ラマは、代々タシールンポ寺を住持することになっています。
これ以降、歴代のダライ・ラマとパンチェン・ラマは、お互いに師となり弟子となって、年長者から年少者へ法を伝えてきました。チベット仏教界でパンチェン・ラマが「ダライ・ラマに次ぐ高僧」というふうに考えられているのは、こうした理由からです。チベットの政教両面の最高指導者は、あくまでダライ・ラマ法王だけであり、パンチェン・ラマがそれと同じような第二位の権能を有しているわけではありません。
現ダライ・ラマ十四世法王と先代パンチェン・ラマ七世は、世代の巡り合わせで年齢が近かったため、師弟として法を伝える間柄ではありませんでした。それで、ダライ・ラマ十四世法王の第一の師は、デプン寺の高僧として名高い先代リン・リンポチェが務めました。そのため、今日のチベット仏教界では、リン・リンポチェも「ダライ・ラマに次ぐ高僧」のように尊敬を集めています。
【今日に至る状況】
前にも述べたように、十八世紀にかけての時代は、チベット仏教の最盛期ともいえます。数多くの優れた学僧が輩出し、ダライ・ラマ七世法王も、特に宗教面で多くの事績を残しています。
しかし十九世紀になると、ダライ・ラマ法王が九世から十二世まで続けて早世するなど、政教両面で停滞状況が見られるようになりました。御存じのとおり、十九世紀は世界規模での激動の時代でしたが、チベットはこの動きに完全に乗り遅れてしまったのです。それまでチベットに繁栄をもたらしていた様々なシステムが急速に機能しなくなている状況に、ほとんど気づかないか、気づいても何も対処できないままに年月が経過してしまいました。
十九世紀末に親政を開始したダライ・ラマ十三世法王は、こうした状況を打開するため、近代化政策を強力に推進しました。それゆえ、歴代ダライ・ラマ法王の中でも、十三世は五世と並んで偉大な名君と称えられています。事実、二十世紀の前半に、チベットは遅ればせながら、近代国家としての一歩を踏み出し始めたのです。
ところが、周囲の状況の変化は、それを遙かに上回る早さで進み、近代国家としてはまだまだ黎明期にあったチベットを、一気に飲み込んでしまうことになります。前に述べた広大なチベット仏教圏の大半が、二十世紀には、宗教自体を否定する共産主義政権の支配下に入ってしまいました。そして第二次世界大戦後、中国の国共内戦に勝利した人民解放軍が、チベットへ侵攻を開始したのです。現ダライ・ラマ十四世法王は、そのときまだ十代でしたが、チベットの朝野をあげての懇願を受けて親政を始めました。そして、中国共産党政府との和平交渉に臨んだのですが、全ては空しい結果に終わってしまいます。それで、一九五九年三月十日に「チベット民族蜂起」が発生し、法王をはじめ十万人近くのチベット人がインドへ亡命することになったのです。法王は、北インドのヒマチャルプラデシュ州ダラムサラを根拠地とし、チベット亡命政権を発足させました。亡命政府は、法王の指導で徹底した民主化を推進し、今日では完全な民主主義の体制が確立されています。
法王の後を追ってチベット本土から脱出した僧侶たちは、北インドのバクサドールという場所に集められ、修行生活を再開しました。ところがそこは、高温多湿で伝染病が蔓延しており、慣れない環境で僧侶たちは次々に倒れてゆきました。インド政府は、南インドのカルナタカ州の広大な土地をチベット人難民に供与する決定を下し、一九七○年代から、ゲルク派四大本山も南インドの亡命チベット人入植地の中に再建されるようになりました。バクサの劣悪な環境を生き抜いた僧侶たちは、開拓民とともにデカン高原の原野を切り開き、一から僧院を築きあげていったのです。カルナタカ州北部のムンゴットには、ガンデン寺とデプン寺が再建されました。今では、堂塔伽藍が軒を競い、かつての聖都ラサを彷彿させるほどの活況を呈しています。同州南部のバイラクッペには、セラ寺やタシールンポ寺が再建されています。その近くのフンスールには、ギュメー寺もあります。
中国支配下のチベット本土で仏教の学修が自由にできないため、現在でも毎年千人単位の青年僧侶や出家希望の若者たちが、命の危険を冒してインドへ亡命して来ます。チベット人の亡命は、決して五十年前の出来事だけではありません。現在進行形で、今この瞬間にも発生し続けている問題です。こうした事実は、意外と知られていません。亡命して来た僧侶や出家希望者の大半は、南インドの三大本山へ入門することになります。それゆえ今日の三大本山は、いずれも五千人を超える規模に膨れあがり、経済的にはとても厳しい状況に直面しています。しかし、本土から新たに亡命して来た僧侶たちが、現在のチベット仏教界の活力を支えているということも、否定できない一面だといえるかもしれません。三大本山(特にデプン寺ゴマン学堂)には、ソ連崩壊後に仏教が復興したモンゴルやロシア領ブリヤート、トゥバ、カルムイクなどからも、留学僧が大勢集まっています。このように、ゲルク派の大本山に関していえば、現在の宗教活動の中心地は、チベット本土から遠く離れた南インドとなっているのです。
しかし、チベット仏教全体の中心地といえば、やはり法王の仮宮殿がある北インドのダラムサラでしょう。ダラムサラの中でも、法王仮宮殿の一帯は「大乗法院(テクチェン・チューリン)」と呼ばれる伽藍になっていて、大本堂(ツクラカン)や時輪堂(トゥーコル・ラカン)などが集まっています。これらは、ラサのチョカン寺のような位置づけです。ツォンカパ大師が一四○九年に始めた「祈願大祭」の大法要も、今ではここで厳修されています。大本堂と法王仮宮殿の間には、ナムギェル寺の僧坊があります。大本堂や時輪堂での法会に出仕しているのは、主にナムギェル寺の僧侶たちです。それらの隣りには、仏教論理大学(ツェンニー・タツァン)があります。これは、学校教育を終えてから出家した僧侶たちのための僧院です。ダラムサラの近郊には、最近になってギュトゥー寺が移転再建され、新しく尼僧院も建立されています。また、在家信者に門戸を開いている仏教論理大学分校や、チベットの宗教文化を保存して紹介する「ノルプ・リンカ」というセンターもあります。亡命政府の官庁街であるカンチェン・キーションには、チベット文献図書館があり、外国人向の仏教教室も開かれています。その隣りにある寺院は、神降ろしの修法で有名なネーチュン寺です。ニンマ派、カギュー派、サキャ派の寺院も、インドやネパールの各地に再建されています。
【真言宗とチベット密教】
最後に個人的な話も交えながら、日本の伝統仏教、特に真言宗とチベット仏教の関連について、少しだけ触れてみましょう。私自身は日本人であり、日本の伝統仏教にも信心を持っています。以前、あくまで一在家信者としてですが、真言宗の教えを僅かばかり学ばせていただいたことがあります。その後チベット仏教の世界へ入っていったのは、決して日本仏教が悪いとか、間違っているなどと思ったからではありません。そうではなく、自分自身に最も合った教えを追求していった結果、チベット仏教、特にツォンカパ大師の教理・実践体系へ辿り着いたということです。
仏教が幾つかの伝統に分かれ、一つの伝統にも様々な宗派が成立していることに対して、批判的な人もいます。しかし、私はそうは思いません。そもそも、お釈迦様が対機説法の善巧方便を巡らしてくださった結果として、後世に多種多様な伝統や宗派が成立したのです。だから、相互の間でたとえ一見矛盾するような部分が見いだされたとしても、単純に一方が正しくて他方が間違っているということではないと思います。ダライ・ラマ法王も、各自が御縁のある教えを広く学び、その中から自分自身に適したものを実践するように勧めておられます。
最近チベット問題がクローズアップされてから、日本の伝統仏教界の多くの皆様が、「同じ仏教徒」という趣旨で、チベットの仏教徒に連帯・支持を表明してくださり、或はこの問題の平和的・人道的解決をアピールしててくださっています。これは、チベット人たちにとって、本当に心強く有難いことだと思います。私も、チベット仏教の世界に身を置く日本人として、こうした日本の伝統仏教界の動きに、心から尊敬と随喜を捧げたいと思います。
これは自分の個人的な感覚ですが、チベット仏教を学修してから日本仏教に再び接したとき、特に真言宗と南都仏教には、一層強い親近感を覚えるようになりました。チベット仏教の特色の一つは「ラムリム」ですが、それに含まれている諸要素の大半は、日本仏教の伝統の中にも見いだすことができます。ただ、「ラムリム」のように一つの大きな体系にまとめられていない点で異なるだけです。「ラムリム」の眼目の一つは、一切衆生のために覚りを求める菩提心を発することです。ツォンカパ大師が「ラムリム」の心髄を読誦用の短い偈頌にまとめた「ユンテン・シルキュルマ」には、次のような一節があります。
我自らが輪廻の苦海へ墜ちたるが如く、
母なる一切衆生も同様なりと観じて、
衆生済度の重荷を背負う、
無上なる菩提心に熟練すべく加持し給え。
日本の伝統仏教をあまり知らずにチベット仏教の門に入った方は、こうした教えを耳にして、とても驚き感動します。そして、「やっぱりチベット仏教は凄いね。本当の大乗仏教の精神が生きている」と言います。もちろんそれは、そのとおりです。でも本当は、これと同じ趣旨の教えが、日本の伝統仏教の中にもたくさんあります。弘法大師も、『三昧耶戒序』で、ほとんど同じことをおっしゃっています。それは考えてみれば当たり前のことで、日本仏教とチベット仏教は、単に「仏教」という点で同じなだけでなく、大乗仏教の伝統を共有しているのです。中でも真言宗の場合、それに加えて、密教の伝統も共有しています。
「ラムリム」の体系に含まれている諸要素で、日本仏教の伝統の中から見いだせないのは、中観帰謬論証派の哲学と無上瑜伽タントラの行法ぐらいです。それも、全然無縁のものというわけではありません。帰謬論証派(プラサーンギカ)の厳密な解釈ということでなければ、中観思想それ自体は、日本の仏教にも存在します。無上瑜伽タントラも、名前だけなら、『十八会指帰』の中にあります。それによれば、ツォンカパ大師が全仏法の頂点に位置づけた『秘密集会』は、「金剛頂経第十五会」に相当します。高野山の酒井真典先生は、『秘密集会』の釈タントラとして重要な『密意解釈』と『金剛鬘』
を、「第十六会」と「第十七会」に関連づけています。現代チベット密教界で事教二相に通暁した高僧として名高いリゾン・リンポチェ猊下(ゲルク派副管長)は、来日時に私とお話しなさった際、「『金剛頂経初会』が、瑜伽タントラと無上瑜伽タントラ両方の根本タントラだ」とおっしゃっていました。これは、『十八会指帰』とほとんど同じ発想だと思います。
弘法大師は、『大日経』と『金剛頂経初会』を併立させる「両部不二」の体系をお説きになる一方で、『十八会指帰』を通じて「広義の金剛頂経」の世界も見据えていらっしゃったのではないでしょうか。だとすれば、それは、ツォンカパ大師が御覧になっていた世界とも重なります。こう考えるのは、「チベット仏教の世界に身を置いた日本人」という私の立場から生じる感慨にすぎないかもしれませんが、当たらずとも遠からずのような気がしてなりません。
ダライ・ラマ法王も、豊山派大本山護国寺を参拝なさったとき、龍猛菩薩像を御覧になって大変喜ばれたといいます。ナーガールジュナを密教の祖師と位置づける発想を、日本とチベットの仏教徒で共有している点から、とても強い親近感を覚えられたようです。このお話を伺ったとき、私は、法王が自分と同じような感じ方をなさっていらっしゃることに、逆に嬉しくなったものです。
(本稿は、平成20年6月9日の密教21フォーラム会員研修に於ける講演内容をもとにして、新たに執筆したものです。)